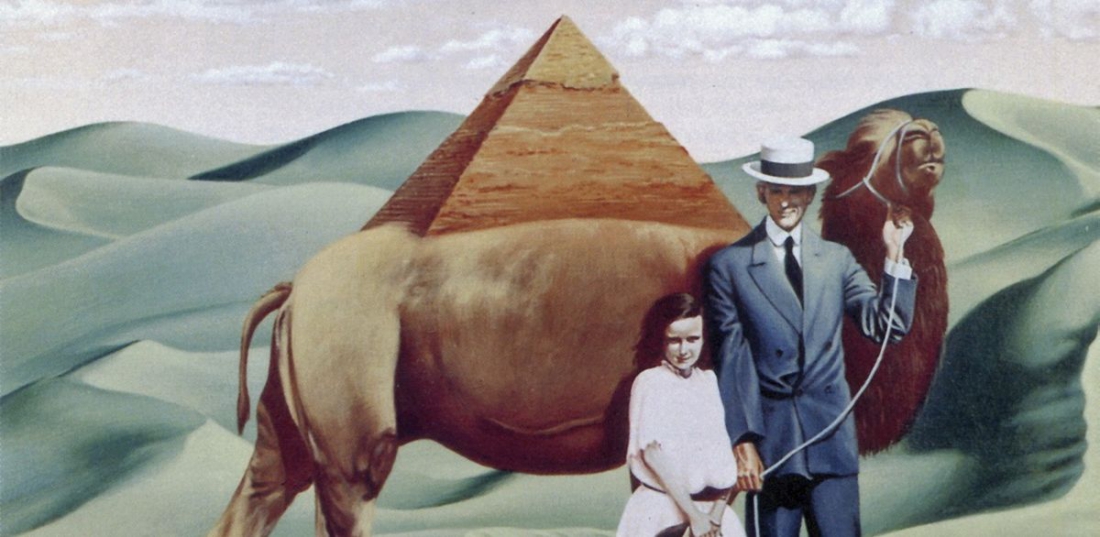「音楽歳時記」 第五十七回 10月3日 登山の日 文・深民淳

10月3日は「登山の日」だそうです。毎度お読みいただいている方々は失笑かと思います。分かりますね、この寒い語呂合わせ。日本アルパインガイド協会が1991(平成3)年に制定し、日本記念日協会が1995(平成7)年に認定したそうです。「登山の日」に行く前に、この日本記念日協会てぇのが毎月、目につくわけですが、ここまでスルーしてきたものの、ちょっと気になったので検索したら、あらら、一般社団法人・日本記念日協会って、けっこうマジな団体じゃないの。記念日登録申請も随時受付ているそうなので、カケレコでも記念日考えて申請してみたらいいんじゃないですか!
で、「登山の日」だね。山だね。山。それこそ山とあるね。う〜ん、寒い感じになってきたね。まぁ、いっぱいありすぎるな。毎月、思いつくのに苦労するのに今月は逆だな。いっぱいありすぎで思いつかない。というわけで、WISHBONE ASH、1973年発表『Wishbone Four』収録の「Ballad Of Beacon」から行きます。Beaconにはかがり火とか狼煙、標識塔という意味があります。
Ballad Of Beacon
歌詞を追っていっても鉄板の山登りの歌なわけですが、この時代のイギリスのロック・バンドがそんなひねりのない曲を歌うわけがない。ましてや前作『Argus』では「Time Was」に始まり「King Will Come」、「Warrior」、「Throw Down The Sword」と時間を昔に戻し中世戦乱トリロジー的曲群をぶち上げたバンドがそんなストレートな歌歌うかね、と思う反面、このアルバムは前作のファンタジー路線から現実路線に戻った印象も強いわけです。オープニングの不満タラタラ、フラストレーション・ソング「So Many Things To Say」からラストの実話ベースの「Rock ’n Roll Widow」至る間にもツアーに出ていたら鉢植えが枯れちゃったみたいな「Sorrel」、お薬頂戴ソング「Doctor」、友情ソング「Everybody Needs A Friend」と身の回りに起きたことや個人的なことが題材となっているわけです。そうすると、これも単純明快、山登りの歌かという気もしますがね。ところが、他に挙げた曲はテーマに沿って明快に歌詞がメッセージを伝えているのに、この「Ballad Of Beacon」に限ってはそのイメージがどこか曖昧。
「Everybody Needs A Friend」も抽象的なテーマではありますが、「Ballad Of Beacon」は『Wishbone Four』の中にあってちょっと雰囲気が異なる。決意を秘めて山に登ろうとする人がいて、君はついてきてくれるかと問いかけがある。山に何をしにいくのでしょうか? 指輪でも捨てに行くのか、というわけで、この曲『指輪物語』の世界が背景にあるのではないか、という気が強くします。
1st から『Argus』まで作品中にファンタジー要素を組み込んだ曲を置き、ミステリアスなムードを演出してきたのは、プログレッシヴ・ロックの時代の真っ只中だったことを鑑みてのことだったと思うのですが、この「Ballad Of Beacon」はWISHBONE ASHのファンタジー路線の流れを汲んだ曲だったように思います。
まぁ、バラードとはいえこのバンドの特徴で、マーティン・ターナーのベースは中音部強めでブリブリ鳴っていますし、スティーヴ・アプトンのバタバタ・ドラムは個性的で流麗なギターとは裏腹な演奏となっているわけですが・・・。
半世紀あまり何も意識せずに聴いてきたアルバムですが、今回、引っ張り出してきて聴き、マジマジと眺めていたら、このアルバムってまさにバンドの転機だったんだなぁ、と実感。まず、アートワーク。この『Wishbone Four』ではじめてバンドのポートレートがフロントに使われています。1st アルバムの端が炭化したウィッシュボーンに似た枝のアップ写真。2nd 『Pilgrimage』のヒプノシス、オーブリー・パウエル撮影による不気味な枝振りの木の向こうに沈む赤い太陽の写真。同じくパウエル撮影、監修ストーム・トーガソンによるマルセイユで撮影された朝日の中に佇む戦士の写真を配した『Argus』ときてこのポートレート・カヴァー。これもヒプノシス・デザインでパウエルが撮影した写真にティンティングを施したものがつかわれており、CDサイズだと今ひとつ伝わりにくいが、オリジナルのLPサイズだと、平凡なポートレート・カヴァーではなく写真選び、着色、フォントの配置全てが計算され尽くした、ヒプノシスらしい前3作と比べても遜色ない仕上がりなのが見て取れます。
WISHBONE ASHは元々、イギリスのプロデューサー、ジョン・ミークの門下生として頭角を現し第1期DEEP PURPLE、3枚のアルバムをプロデュースし有名になったデレク・ローレンスに見出されデビュー。ローレンスは『Argus』までのプロデュースを担当します。『Wishbone Four』はローレンスのプロデュースを離れての最初のアルバムでした。そして、このアルバムの後が『Argus』と並び人気の高い初のライヴ・アルバム『Live Date』。その『Live Date』発表後にギタリスト、テッド・ターナー脱退、HOMEのギタリスト、ローリー・ワイズフィールド加入。1973年から1974年初頭はバンド始まって以来の慌ただしい季節となります。
この時期を時間を追って書くと、まず’73年2月から3月が『Wishbone Four』のレコーディング。デレク・ローレンスを外し、バンドのセルフ・プロデュースでの制作。因みに歌詞は「Rock ’n Roll Widow」がスティーヴ・アプトン作ですが他は全曲マーティン・ターナー作でした。5月にアルバムを発表しこれに伴うイギリス・ツアーが6月に行われ、このツアーの音源を元に『Live Date』が制作されます。プロデューサーは再びデレク・ローレンス。この流れは最初からそういう話になっていたとしか思えませんよね。スタジオ盤制作はローレンスをシャットアウトするけど、ローレンス・プロデュース時代の総決算と言える『Live Date』の制作は任せて円満に関係解消というストーリーが見て取れます。『Live Date』の発売は12月。オリジナル・メンバーによるUSツアーは’74年2月まで行われ、未確認ながら2月後半にはBBCラジオの収録もあったようなので、ここまでがテッド・ターナー在籍時代。
ほとんどリセットに近い大きな変革だったと思います。デビュー以来のプロデューサーを切って、売り物だったツイン・リード・ギターの片割れが交代。背景にあったのは1. ほぼ同じスタートラインに並んでいたギタリスト二人が一人は急激に成長、もう一人は停滞気味。『Live Date』発表当時の日本のファンの認識は、動のアンディ・パウエル、静のテッド・ターナー。この認識がもたれる事自体、既にツイン・リード体制が崩れ始めていた証拠ではないかと思います。2. 『Argus』が’72年イギリス本国の音楽紙のリーダーズ・ポールでベスト・アルバムに選出されるなどイギリス以外での注目度も一気に高まった。特にアルバムを出すごとにツアーを行っていたアメリカでも認知度が高まり、バンドの中にアメリカでブレークしたいという機運が高まった。3. これは2にも関係しますが、1973年のイギリスの音楽シーンを見渡すとハード・ロック、プログレッシヴ・ロックが飽和状態に達しつつあり、バンドとしての変化を考える時期になってきた。
この3要素が絡み合い、恐らくバンドは’73年の段階で、『Live Date』を出した後は、’74年に実際そうしたようにアメリカに活動拠点を移すことを考えていたと思われます。テッド・ターナーは当時、穏便に脱退ということになっていましたが、実際、アメリカ移住に積極的ではなかったにせよ、今、こうして『Wishbone Four』を聴きなおしてみると、ツイン・リード部分がとってつけたかのようで、全体的にはリードとサイドみたいな雰囲気が漂っています。テッド・ターナー作曲面での貢献度は結構高かった人ですが、ここではちょっと浮いちゃった感が漂います。『Wishbone Four』、まとまりは良いけど、突き抜けた感じがなくこじんまりしてしまった要因のひとつにはテッド・ターナーの存在感が薄れてきたというのもあるように思います。こう考えると彼の脱退はほとんどバンド都合の解雇に近い雰囲気もあったのではないかとも思いますね。
ここまで長々と書いてきたように『Wishbone Four』制作の舞台裏はかなりバタバタしていました。バンドは『Argus』の好評を受けツアーのスケールが大きくなった過密スケジュールの中で活動していた最中だったので、『Wishbone Four』制作は明らかに準備不足の中制作が始まったと行っていいでしょう。ローレンスから離れてはっきりしたのは、ハード・ロック・カテゴリーに組み込まれるバンドにしては濃度が濃かったプログレ感はローレンスによる部分が大きかったこと。バンドのセルフ・プロデュースとしては十分健闘した作品ではありましたが、音は仕上げられても、作品を貫くコンセプト作りには長けていなかったこと。重要なポイントだとおもいます。今回取り上げるアメリカ時代の作品がプロデューサーが変わるとサウンドが大きく変化する原因はここにあったように思うからです。
準備不足の中、制作がスタートした『Wishbone Four』バンドの素の部分が色濃く出た作品だったと思います。元々フォーク・ロック的な要素が強かったことは『Argus』でも確認することができますが、『Argus』ではプログレ度の強いハード・ロック展開の曲のパンチが強く、フォーク・ロック要素は陰に隠れたいうか、アクセントみたいな使い方をされていましたが、『Wishbone Four』ではその部分がフィーチュアされています。アメリカでの好評を受け、その巨大マーケットを意識した、ソフト化というのもあったのでしょうが、根本にあったのはメンバーが素の状態で曲を作るとこういうフォーク・ロック的に流れがちな傾向にあったのでしょう。
オリジナルのLPではA面トップに「So Many Things To Say」、B面トップに「Doctor」というWISHBONE ASHのパブリック・イメージに沿ったハードな曲、ラストには野外コンサートの会場で起きた悲劇を歌った「Rock ’n Roll Widow」を置いてバランスをとってはいますが、全体的には完成度の高いフォーク・ロック・アルバム。配置の美が際立つ端正なジャケット・アートワークが全てを物語る、よく出来た小品集となっています。中でも素晴らしいのはアルバム中最長の8分を超えるバラード「Everybody Needs A Friend」でしょう。最初からライヴで演奏することは考えていません。当時のライヴの演奏曲の中に置いたらバランスが間違いなく崩れるタイプの曲です。しかしそのメロディライン、アコースティック・ギター、ピアノ、後半に至ってはメロトロンまで導入したバックの上で舞う叙情的なギター・ソロは限りなく美しく、初期WISHBONE ASHのバラードの中でも屈指の名曲と言って良いかと思います。
Everybody Needs A Friend
この曲、当時、ファンの受けが良かったのではないかと思います。というのもこのテンポと構成をアルバム専用楽曲ではなくライヴでも演奏可能な曲が続くローリー・ワイズフィールド参加第1作『There’s The Rub』に収録されるからです。『There’s The Rub』はアメリカに移住し、制作された最初のアルバムでプロデューサーはEAGLES、JOE WALSH等との仕事で知られるビル・シムジク。レコーディングはエリック・クラプトンの『461 Ocean Boulvard』でも使われたマイアミのCriteria Recording Studioで行われました。カントリー・ロック色が強かったもののトータル・コンセプト・アルバムを発表するなど、イギリスではプログレ・カテゴリーで語られるHOME出身のローリー・ワイズフィールドはアメリカのマーケットでのブレークを果たしたかった当時のWISHBONE ASHにとっては正に適任のギタリストで、オリジナル・アナログ盤における『There’s The Rub』の前半のヴォーカル曲3曲、B面に置かれたフュージョン・ブームを意識したインスト曲「FUBB(Fucked Up Beyond Belief)」ではWISHBONE ASHのセールス・ポイントであるツイン・リード・ギターの可能性を大きく広げる素晴らしいプレイを披露しています。
「Everybody Needs A Friend」の流れを汲むバラード曲はその前半歌ものの3曲目「Persephone」です。テンポとムードは継承しながらも全編エレクトリック主体の演奏に置き換え、哀感漂うギター・ソロをサラのドラマティックに発展させたこの曲はローリー・ワイズフィールド在籍時の人気曲となりました。また、ギリシャ神話に登場する冥界の女王である女神ペルセポネーをテーマにしたこの曲は『Pilgrimage』、『Argus』時代のファンタジー路線にリンクしていたこともファンに強くアピールしました。
Persephone
『There’s The Rub』にはもう1曲、ファンタジーというかイギリスの民間伝承をテーマにした曲があります。イギリス、デヴォン州ダートムーアに伝わる幽霊談キティ・ジェイをテーマにした「Lady Jay」です。WISHBONE ASHというよりワイズフィールドの出身バンドHOMEやFAIRPORT CONVENTIONを思わせる英国マナーに則ったフォーク・ロック。シムジクのサウンドに広がりを持たせた、スタジオ・エフェクトも多用した煌びやかなサウンドを持つアルバムの中にあっては異彩を放つ曲でした。
Lady Jay
アメリカ市場をメインターゲットとした『There’s The Rub』でしたが、全体的には開放感があり明るく突き抜けたサウンドが中心となっていますが、アメリカ的な感じはあまり感じません。アメリカ人のプロデューサーを起用したことにより逆にブリティッシュ感が際立ったような印象すら受けるのです。
結果、『There’s The Rub』は本国イギリスではアルバム・チャートの20位以内に入るヒットを記録しましたが、肝心のアメリカでのチャート・アクションは期待外れの結果に終わります。この結果を受け、バンドとマネージメントはアメリカでのディストリビューションをデビュー以来の関係だったMCAからアトランティックに変更します。1976年制作の『Locked In』はその新たなディストリビューターであるアトランティックと馴染みの深い名プロデューサー、トム・ダウトが手がけます。WISHBONE ASHとしてもアトランティック系の数多くのヒット作を手がけたダウトとの仕事に大きな機体を抱いたのでしょうが、この組み合わせは後にアンディ・パウエルらが自戒を込めて語るように失
敗に終わります。
昔、アンディ・パウエルにインタビューした時に彼はダウトがリヴァーブ、ディレイ等をかけるのを嫌って、レコーディングで使わせてもらえなかったと語っていましたが、実際、この『Locked In』はかなりドライなサウンドで、これまでがホール等のエコーが掛かったかのようなサウンドだったとすれば、いきなり小さなライヴ・ハウスで演奏しているようなサウンドに変化。WISHBONE ASHらしさがかなり削がれてしまったことは否めません。ここまでのブリティッシュ・ロック・バンド然としたミスティなサウンドは影を潜め、THE BAND等に近いサウンドに変化してしまったわけですから、これはやはり向いていないと言わざるを得ません。ツイン・リード・ギターを売りにしており、元々リフで勝負するタイプのバンドでなかったことも災いしたと思います。必然的に単音弾きのリード・パートが多いそのサウンドは、リフで押すバンドに比べて線が細いため、より迫力が削がれてしまったのです。
それでもオープニングの「Rest In Peace」などはいかにもWISHBONE ASH然とした曲で、アンディ・パウエル、ローリー・ワイズフィールドのプレイの特色がはっきりと出ているナンバーに仕上がっています。ただ、その曲想にこうした乾いた音作りは合っていません。でもやはりこの曲は捨てがたい。というわけで、ライヴ・ヴァージョンを探しました。やたらと数が多く、そのクオリティもピンからキリまである彼らのライヴ音源をくまなくチェックして、僕が個人的にこの曲のベスト・ライヴ・ヴァージョンは1990年代後半に4枚組のブックスタイルのボックス・セットとして発表された『Distillation』のディスク4に収録されています。この『Distillation』は2000年に二つに分割され通常仕様で再発されていますので『Distillation 3 & 4』というタイトルで出ているもののCD2にも同内容のものが収録されています。音質的にもしっかりしており何よりもスタジオ版のアレンジをほぼそのまま踏襲しながらもスタジオ版以上の疾走感を持っているところが優れています。カントリー系のギター・プレイにも長けているローリー・ワイズフィールドのかなりトリッキーなピッキングもスリリングで、この曲に関しては『Locked In』収録版ではなくこちらをお薦めします。
『Locked In』はあまりお薦めできませんが、『Argus』とは異なるしっとりとしたソフト&ウェットなWISHBONE ASHが楽しめ、実はフォーク・ロックの隠れ名盤とも言える『Wishbone Four』。アメリカ制覇を目指すもアメリカを意識したら逆に彼らのイギリス人感覚が際立つ結果となった『There’s The Rub』は世間の評価に左右されず是非トライしていだければと思います。
さて今月の1枚は、今月の1曲。キング・クリムゾンがデビュー50周年を迎えたことは皆さんご承知かと思いますが、彼らのレーベルaoDGMの社長でありプロデューサーのデヴィッド・シングルトンが今年の1月から毎週更新でクリムゾンのレア曲や時に未発表曲を彼がその曲のエピソードを語る音声とともに公開していますが、そのKC50もいよいよ終盤に差し掛かり、今週はWeek37を迎えました。このWeek37が個人的に好きな「ConstruKction of Light」のコンプリート・ヴァージョンで、これまで発表されていたヴァージョンではカットされていた歌詞の最後の部分まで入った初公開ヴァージョンということで紹介させていただきます。聴くだけでしたら日本のクリムゾン・ホームページでストリーミング再生できますのでよろしくお願いします。9月20日金曜にデータをウェブ管理者に渡していますので20日から公開されると思いますが、もしまだでしたら何度かトライしていただければと思います。
その「ConstruKction of Light」コンプリート版に寄せたシングルトン氏のコメント訳を掲載しておきますね。
以前他の回でも『The ConstruKction of Light』の再現プロセスについて語りました。パット・マステロットが新たにドラム・パートを録り、ビル・リーフリンのプロダクション・パートナー、ドン・ガンがミキシングをした、という話しです。
もともとこのアルバムは、私が1989年にロバート・フリップと知り合って以来、唯一参加していない新作です。
2000年にアルバムがリリースされた頃、私はシアトルでダウンロード問題に立ち向かい、正気を取り戻そうとしていました。相手は初期のナプスターやmp3.com。それが、ある意味、DGMLIVEというウェブサイトに繋がったとも言えます。
そういうわけで、私自身、『The ConstruKction of Light』というアルバムの原案にあまり馴染みがありませんでした。それはタイトル曲のスタジオ・ヴァージョンについても言えます。
この曲のインスト・パートは、今なお、ライヴ・レパートリーの一部となっていますね。トニー・レヴィンいわく、ここでのスティック・ベース・パートは史上最強だそうです。
新しいスタジオ・ミックスを初めて聴いた時、最後の方で「the man might improvise the construKction of light」という、聞き覚えのない歌詞が耳に入りました。さっそくオリジナル・アルバムをチェックしたのですが、そこにもありません。
2000年に編集作業を行なったロバートとアレックス・マンディが、ヴォーカル・ラインの最後の2行を削除したとのことでした。その当時の決定を重んじて、今回のリイシューでも、『Heaven and Earth』ボックスセットでも、この時のエディットをそのまま使用しています。
しかし、この2行が入っているヴァージョンは、KC50シリーズ向けの、とてもおもしろいアウトテイクです。
なので聴いてみましょう。
完全版スタジオ・レコーディングで
The ConstruKction of Light
【関連記事】
「音楽歳時記」 第五十三回 6月24日 UFOの日・追悼P.レイモンド 文・深民淳
音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。
【関連記事】
「音楽歳時記」 第四十五回 10月23日 電信電話記念日 文・深民淳
音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。
関連カテゴリー
関連CD在庫
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!