「音楽歳時記」 第三十九回 4月17日 恐竜の日 文・深民淳

めっきり春めいてまいりました。桜も前倒しで咲きそうな勢いのようですが、今年も近くの公園の白梅は大変綺麗でした。とはいえまだ3月。寒の戻りもありそうなので皆さん体調を崩さないようご注意ください。さて、4月も思わず体の力が抜ける脱力系の記念日が目白押しですが、今月一番の強引かつ脱力に一発をまずご紹介しましょう。
4月10日駅弁の日です。なんでそうなったかと申しますと、洋数字の「4」と漢数字の「十」を合成すると「弁」の字に見えることから、日本鉄道構内営業中央会が1933年に制定なんだそうです。あ〜、そうと一瞬納得しそうになりましたが、4と十で「弁」だぁ? 見えないでしょ普通。あまりにも強引すぎる感じがします。これだったら同日、ヤマハ発動機が制定した4と10でヨットの日の方がまだ分かる気がします。自分の誕生日、どんな記念日があるかと思えば、この語呂合わせシリーズを拾い始めてから最も強引な一発にぶち当たり、もう原稿書くのやめて寝ちまおうか、とどんよりしたムードに陥っております。
4月17日が恐竜の日となっています。大正12年(1923年)アメリカの動物学者ロイ・チャップマン・アンドルーズがゴビ砂漠へ向けて北京を出発した日に因みに制定されたそうです。チャップマン・アンドルーズ博士の功績は5年間で恐竜の卵の化石を25個発見したことで、世界初の快挙だったそうです。この功績がきっかけとなり、本格的な恐竜研究が始まったのだそうです。太古の生物だったこともあり、なんだか昔から研究されていたかのような錯覚を覚えますが、案外最近の話なんだなぁというのが正直な感想です。まぁ、最近と言ってももうかれこれ100年近く前の話なんですけどね。
恐竜というとタイトルがそのものズバリ『Dinosaur Swamp』。The Flockが頭に浮かびます。米コロンビアから2枚のアルバムを発表し、消滅。数年後に再結成され、マーキュリーから1975年に『Inside Out』を発表しその後再び解散。同じエリアから登場したChicagoが長寿を誇るのに比べ、短命に終わったバンドです。
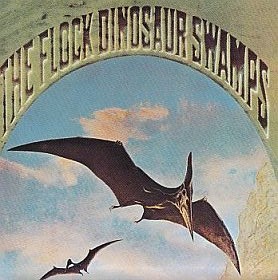
Big Bird
プログレの流れで語られることもありますが、このアルバムはどちらかといえばファンクやジャズからの影響を強く受けたブラス・セクション入りのジャズ・ロック・バンド(要するにブラス・ロックですね)と思ってもらったほうが良いかと思います。元々はガレージ系のラウドなロックをやっていたギター・トリオにブラス・セクションが加わり、ジャズ・ロックにシフトしていった経緯があるそうですが、初期の2作品にはこの後、ジョン・マクラフリンのMahavishnu Orchestraに参加するヴァイオリン奏者ジェリー・グッドマンが参加してことで広く知られています。
ブラス・ロック・バンドしてはかなり雑食性のバンドであったように思います。ブラス・ロック・バンドとしての根本の音楽性はChicagoよりBlood, Sweat & Tearsに近いと思うのですが、デビュー作が’69年、この『Dinosaur Swamp』が’70年発表ということもあり、Blood, Sweat & Tearsの初期作品がそうであったようにスタジオでのギミックを多用し、サイケデリックな雰囲気も醸し出しており、この『Dinosaur Swamp』ではR&B、ジャズからの影響大のジャズ・ロック・サウンドの中に、カントリー・ミュージック、ノスタルジックなミュージカル風ナンバーを取り込むなど一筋縄ではいかない作品となっています。当時、ヨーロッパでも人気を博したのも何となく分かります。当時のヨーロッパだったら立派にプログレの範疇の音です。
最も有名なメンバー、ジェリー・グッドマンは随所で良いプレイを披露してくれますが、決して彼がキーマンという印象ではありません。逆にブカブカと割り込んでくるブラスに肩身が狭そうな感じすら受けます。話の発端が恐竜だったのでこの2ndについて書きましたが、このバンドの真髄はやはり1stにあるかと思います。先に書いたようにガレージ起点のブルース・ベースのラウド・ギター・トリオを母体とするだけあり、1stの方は、ヘヴィなブルース・ロックからブラス・ロックへ変貌をとげる過程がストレートに出ており、同じブラス・ロックでもヘヴィなブルース・ロックにブラスが乗ったイギリスのWallus中にも通じるダークなヘヴィネスを垣間見ることもできますし、ジェリー・グッドマン興味で聴くなら絶対にこちらを推薦します。
『Dinosaur Swamp』、アートワークはQuatermassと並び有名ですが、バンド内の人間関係か力関係が変わったのでしょう。1stに比べるとどこか底が浅い印象を受けます。因みにオリジナル活動時は3枚のアルバムを残し解散しましたが、2004年には1973年再結成時(ジェリー・グッドマンは不参加ながらヴァイオリン奏者は新規で加入)のライヴ音源から『Live In Europe』、2014年にはこれも再結成時のアルバム未収録音源等を集めた『Heaven Bound (The Lost Album) 』が発売されています。この再結成時はオリジナルのFlockのサウンドというよりジェリー・グッドマンが移籍したMahavishnu Orchestraっぽいアプローチが目につくのが面白いですね。
プテラノドンは恐竜と同じ爬虫綱ですが翼竜に属し恐竜ではないのですが、まぁ、タイトルがそうなっていますのでね。引き合いに出しました。同じ翼竜アートワークで引き合いに出したQuatermassも強烈なインパクトを持った一枚ですね。今更、どうこういうこともない鉄板の有名アイテムですが、ギターレス、オルガンでハード・ロックをやったものの中では間違いなく頂点に立つ一枚でしょう。ギターのジャギジャギしたエッヂに欠ける分、ベースのジョン・ガスタフソンがギター、ベース両方の役割を見事に果たしているのです。アルバム『Quatermass』が発表された時代を考えるとかなり斬新でクレバーなアプローチだったと思います。’80年代のヘヴィ・メタル時代以降はいくらでも見られる手法になりますが、この時代にあってはかなり画期的なハード・ドライヴィング・サウンドだったと思います。何でこんなことを書くかといえば、ここひと月以上、ダブル・トリオ期のKing Crimsonの1995年ジャパン・ツアー音源11公演分を仕事なんでずっと聴いていまして。この時期トニー・レヴィンとトレイ・ガンという2人のベーシストがいたという認識をお持ちの方が多いかと思います。実際僕もそういう意識が強かったわけですが、実際にはベースはレヴィン1人で、ギターが3人いたという印象が強いのです。実際、トレイ・ガンはベースではなく、ダブル・トリオ期にはスティック奏者だったのですが、サウンド的には低音部に特化したギターという印象が強いのです。トレイ・ガンがギターとベースの間のギャップを埋めていたという感じなのです。音域的にはベースが受け持つ低音部ながら、ベースの守備範囲を超えた働きみたいな役割を担っていたのです。

Laughtin Tackle
そんなことを改めて認識したもので、仕事の合間に過去印象に残ったベース・サウンドが聴ける作品を引っ張り出して聴いていた中の一枚がQuatermassだったわけです。凄かったですねぇ、ギターの代わりにリフを叩き出し、一方ベースの本分であるルートのキープとグルーヴ保持も同時に行う、かなり異能のベーシストだと思いますね。このQuatermassから発展していくギター入りトリオHard Stuffの2nd『Bolex Dementia』はヘヴィ・ファンクに根ざしたブリティッシュ・ハード・ロックの傑作と思う反面、どこかとっつきにくいというか、リスナー置き去り感みたいなものを聴くたびに感じていたのですが、ジョン・ガスタフソンのベーシストとしての個性に拠るところも大きかったのかな、と思うわけです。曲なんかは結構普遍的でメロディラインなんかはポップな側面もあるわけですよ、ジョン・カン(デュカン)のソロや再結成後のAtomic Roosterなんかにもそのまま通じるポップさがね。でもこの『Bolex Dementia』ではその肌合いがまるで違うわけです。ジョン・ガスタフソン只今、大変気になっております。
さて、話を恐竜に戻しますと、King Crimsonダブル・トリオ期のアルバム『Thrak』にはそのものズバリ「Dinosaur」という曲が収録されています。今回はずっと仕事で聴いていた1995年ジャパン・ツアー音源11公演の中から、仙台サンプラザ公演音源で紹介します。1995年ジャパン・ツアーの最終盤にあたり、地方最終公演となった1995年10月13日収録のライヴ音源です。バンドはこの後東京に戻り、新宿厚生年金会館で日本最終公演を行いそのままアメリカに飛び、同年の北米ツアー2ndレグを行いこの年の活動を終えるのですが、なぜ、仙台公演かといえばこれが音質面・音の分離面で最もグレードが高いと思われるからです。この1995年ジャパン・ツアー音源は基本、サウンドボードから直接DATに録音されたものが元になっているのですが、毎回ほぼ同じ条件で録音されているにも関わらず、音質にバラツキがあるのですが、この仙台は特に分離に優れており、PAから会場に流れるライヴ・ミックスの全体センター寄りサウンドだと今ひとつ分かりにくいビル・ブルフォードとパット・マスティロットの2台のドラムははっきり聴き分けられるようになっていますし、どこか陰の薄い存在だったこの時期のトレイ・ガンの役割も明確に分かります。
「Dinosaur」は1994年に復活したKing Crimsonと同時期音楽シーンの話題をさらっていたThe Beatlesのアンソロジー・プロジェクトの影響を受けたのでしょうか、どことなくThe Beatlesを思わせるポップなメロディラインと中間部のギター・シンセサイザーによる室内楽のようなクラシカルなセクションの対比が印象的なアルバム『Thrak』収録曲の中でも人気の高い曲。この日は前日の大宮公演が荒れた演奏(特に前半)だったこともあり、緊張溢れるタイトな演奏で悪くない出来の日であったと思います。11公演中東京6公演が3月、地方5公演(横浜・名古屋・大阪・大宮・仙台)が4月発売となります。11公演ほぼ同じとかWebでは書かれていますが、何をおっしゃいますやら、毎回聴きどころはありますし、演奏かなり違います。ま、集中して聴いて頂くというのが最低条件にはなりますが、荒れる日もあれば、集中力が極めて高い日もあります。’80年代King Crimsonのコレクターズ・クラブ音源もそうですが、曲者はビル・ブルフォードと意外なことにトニー・レヴィン。歌も歌わなければならないというハンデがある為、エイドリアン・ブリューはあまり無茶しないですが、随所に地雷が仕掛けられているシリーズです。
以前にも別の作品を紹介しましたがBlue Öyster Cultが1980年に発表した作品に『Cultosaurus Erectus』というのがありました。’70年代前半からニューヨーク・アンダーグラウンド・シーンのカルト・バンドとして人気を博し、1976年発表の『Agents Of Fortune 』収録の「(Don’t Fear) The Reaper」が大ヒットし一躍全米規模の人気バンドとなった彼らの安定期に入っていた時代の作品です。初期のどこか闇の部分を感じさせるアンダーグラウンド臭の強いハード・ロックから一転、この時期は完全にFMオリエンテッドと言いますか、初期からの独特の重さは残しながらも、メロディラインは極めて分かり易くポップ、サウンドもタイトなものに変化しています。’70年代後半から’80年代前半にかけてのアメリカン・ハード・ロックの王道かつお手本みたいな作りになっていると言っていいかと思います。
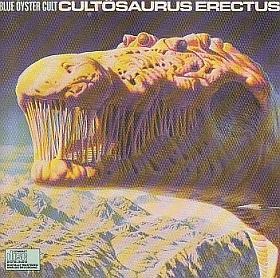
Black Blade
時代から見たグループ分けだとこのアルバムは、彼らにとって2作目のライヴ・アルバムとなった『Some Enchanted Evening』(1978年)に続くスタジオ作『Mirrors』(1979年)、そしてこの『Cultosaurus Erectus』に続く『Fire Of Unknown Origin』(1981年)と繋がる時期の作品で、『Mirrors』、『Fire Of Unknown Origin』もまた『Cultosaurus Erectus』同様、職人芸と言っても過言ではないアメリカン・ハード・ロックの王道を堪能できる作品となっています。この3作を総括した形のライヴ・アルバム『Extraterrestrial Live(通称ETL)』と共にもう少し、ちゃんと聴かれて欲しい作品群なのですが、今ひとつ人気ないんですよねぇ・・・。まぁ、この『Cultosaurus Erectus』と続く『Fire Of Unknown Origin』はアートワークのインパクトという点では彼らの初期作品に引けを取らないインパクトの強いものなんですけどねぇ。
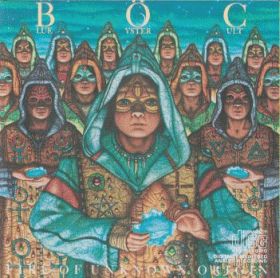
Led Zeppelinはよく恐竜に例えられていました。’70年代末、『In Through The Out Door』を発表するにあたり行われたネブワースでの野外コンサートのブートレッグなんかは実際、恐竜に因んだタイトルがつけられていたものがありました。なんといっても’70年代ロックの最大銘柄であったバンドです。’76年に勃発したパンク・ロック・ムーヴメント、その後に続いたニューウェーヴにとってはオールドウェーヴの象徴みたいなものだったのでしょう。でも、その存在はとてつもなくなく大きく、なるほどそりゃ恐竜ですよね。
そのLed Zeppelinの1972年のLAフォーラム、ロングビーチ・アリーナでのライヴを収録した『How The West Was Won(伝説のライヴ)』が2018年リマスター版で今月、再発されることになっています。通常のCDフォーマットの他、アナログ4枚組やスーパー・デラックス・エディションとして3CD、4LP、2DVDオーディオのセットも用意されています。現行のパッケージでも十分ど迫力のライヴでしたが、2018年リマスター版どうなるか、ちょっと楽しみです。完璧なLed Zeppelinというと語弊があるかもしれませんが、この1972年夏の北米ツアーの後、ロバート・プラントは喉を痛め、ハイトーンの声の出方が明らかに変わりますので、このライヴは貴重な記録だったと思います。正規版では発売されていませんが、この後10月に行われた2度目のジャパン・ツアー、それに付随するオーストラリア・ツアーのブート音源と聴き比べると明らかにロバート・プラントの唱法が変化したことを確認できますし、正規版音源で比べるのであれば、ちょっと時間は開いてしまいますが1973年のUSツアー時のニューヨーク、マディソン・スクエア・ガーデン連続公演のライヴ・ドキュメンタリー映画のサントラ盤『The Song Remains The Same / 永遠の詩(熱狂のライヴ)』と比べると歴然かと思います。結局、プラントの喉のコンディションが元に戻ることはなく、『How The West Was Won』がレコーディングされた1972年夏以前と以後ではことロバート・プラントに関していえばはっきり線引きができるほどの変化があります。ただ、この人が凄かったのは、ハイトーンが出づらくなったらなったなりにそれを補ってあまりある唱法を確立した点でしょう。天賦の才ですっ飛ばすスタイルから、圧倒的な説得力を持った唱法スタイルへと大きな成長を遂げた点は、ロック・ヴォーカリストの最高峰として今も認知されている彼の威厳に満ちたものでした。

Whole Lotta Love
『How The West Was Won』は解散後に発表されたライヴで、オリジナル発売時も大きな話題にはなりましたが、『The Song Remains The Same / 永遠の詩(熱狂のライヴ)』と比べると知名度等でワンランク落ちるような気がします。しかしながら、ロバート・プラントの天賦の才がどれだけ凄かったかを知る上では最強にして最後の記録であり、Led Zeppelinというバンドが、’69年にデビューして一年あまりで世界を席巻した理由が明確に記録された貴重な音楽遺産だったと思います。2018年リマスター、かような観点から大いに期待しているのですが・・・。
さて、今月の1枚ですが、こちらも最新(2017年)リマスターでソロ17作品がSHM-CDフォーマットで3月21日に再発となるロリー・ギャラガー。今回は紙ジャケットではなく、プラケでの再発ですがその分、値段は¥2,000を切っており、手頃な価格帯と言って良いかと思います。まだ全部聴いてはいないのですが、全体的に分離は良くなっていると思いますが、その分、多少、デジタル臭い仕上がりになっている印象を受けました。特に初期のアナログ盤時代ポリドールから出ていた作品やライヴ3作品『Live In Europe』、『Live In Ireland』、『Stage Struck』は特にギターとベースがグシャっとくっついていて、そのくっつきぐあいが押しの強さになっていた感がありますが、今回の2017年リマスターはかなり、それぞれの楽器がくっきりと聴こえるようになっています。よって、これまでのアナログ盤、BMG/CAPO時代のリマスター音源のある種乱暴な一体感が好きだった人には嫌われるかもねぇ、といった印象を受けました。
その中からご紹介するのは、ロリー・ギャラガーが最もハード・ロックに寄っていた時期のライヴ・アルバム『Stage Struck』です。晩年のアナログ・オリジナル盤がCAPOから出ていた時代の枯れたブルース・サウンドや初期のアンプのオーヴァードライヴそのままサウンドとは異なりやたらとギラついたトレブリーかつエッヂの立ったサウンドを叩き出していた時代。編成はトリオで、ベースは彼のソロ・キャリアをずっと支えてきたジェリー・マカヴォイは変わりませんが、ドラムが元Tear Gas、Sensational Alex Harvey Bandでこの直後にMichael Schenker Groupに加入するテッド・マッケンナだったこともあり、ロリー・ギャラガー史上最も馬力のあるパワー・トリオだった時代のライヴです。
アナログ盤時代から演奏がパワフルかつ歪みまくっているので全体がかぶりまくり、かなりカオス状態のサウンドになっており、BMG/CAPO時代のリマスターでもそのグシャグシャ感はあんまり解消されていなかったのですが、今回は分離面ではかなり健闘してるのですが、その分本来のギターの音が若干損なわれた感があります。とはいえ、これまではグシャっとしてイマイチはっきりしなかったベースラインとかはかなりくっきりと浮かび上がっており、興味深く聴くことができました。演奏はとにかく、ロリー・ギャラガーってこんなに派手だったか、と思うくらいに徹頭徹尾ハード・ドライヴィング・サウンド。オープニングの「Sin Kicker」から全開モードですが、スタジオ・ヴァージョンを軽く蹴散らした「Wayward Child」の壮絶爆走ヴァージョンに思わず血管が切れそうになりますし、泣きのメロディラインを持ちながらでもドライヴィング・ハード・ロックという、誰にでもかける曲ではないロリー・ギャラガーらしい名曲「Shadow Play」等聴きどころ多数です。ロリー・ギャラガーというアーティストに地味なイメージを抱いている方にぜひ聴いていただきたいライヴ・アルバムです。
Shadow Play
関連カテゴリー
第三十九回 4月17日 恐竜の日
-
QUATERMASS / QUATERMASS
キーボード・トリオ編成のハード・ロック・グループ、レインボーがカバーした「Black Sheep Of The Family」収録の70年作、オルガンの響きがこれぞブリティッシュ!
後にSUN TREADERを経てBRAND Xへと加入することとなるPete Robinson、HARD STUFF、ROXY MUSICなどで活躍するJohn Gustafson、STRAPPS、GILLANへと参加するMick Underwoodによるキーボード・トリオ。Harvestレーベルからの70年作。その内容はハード・ロックを基本にクラシックやジャズなどの手法も使い分けるPete Robinsonのオルガンをメインに据えたヘヴィー・ロックの名作であり、オルガンのほかにピアノやハープシコードなどで巧みに表情を変え、楽曲によってはストリングスも導入したシンフォニック・ロック的な音楽性も聴かせます。
-
デジパック仕様、Peter Robinson自身による5.1 SURROUND SOUNDミックス音源を収録したDVDをプラスしたCD+DVDの2枚組、NTSC方式、リージョンフリー
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!






























































































