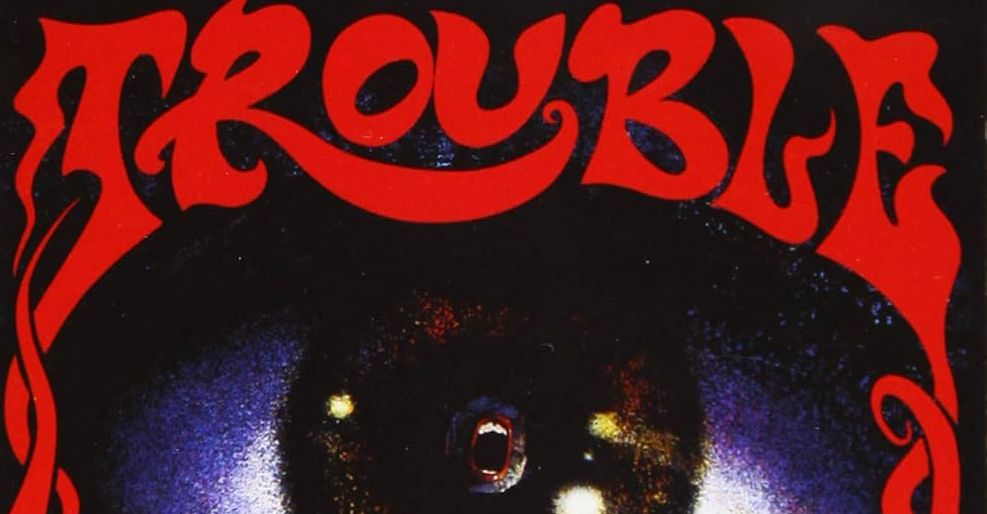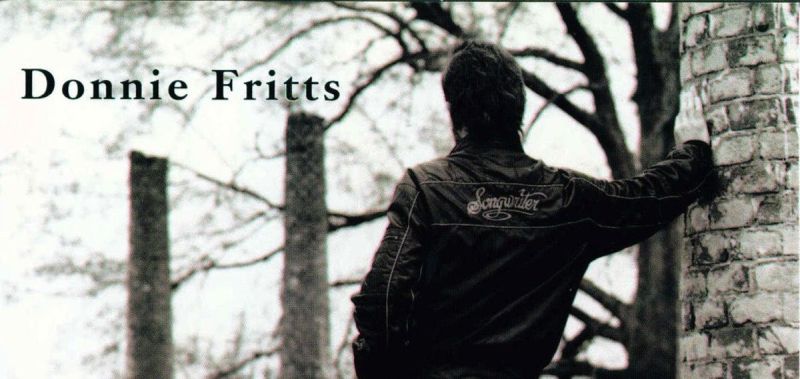「音楽歳時記」 第五十一回 4月8日 タイヤの日 文・深民淳

4月8日はタイヤの日だそうです。日本自動車タイヤ協会が、春の全国交通安全運動が行われる4月のタイヤがふたつくっついたみたいな8日を記念日としたんだそうです。2000年に制定された新しい記念日なので馴染みはあんまりなさそうですがね。因みにその前日、4月7日はタイヤゲージの日なんだってさ。タイヤゲージってタイヤの空気圧測るやつね。タイヤゲージを製造している旭産業が制定したそうです。完全に被せてきた感じですが、会社としては正しいやり方だと思います。しかし、その記念日誰が知ってんだよ、という疑問はありますが・・・。
ロック・バンドで成功して、金儲けていい車乗りたい!ってそんなステレオタイプの連中ばかりじゃ、今更ないだろうと思いつつも、やはり、タイヤの日となると、車・ロックと連想が繋がっちまいます。発想が貧困と言われそうですが、良いんだよ、あながち間違いではないんだから。
では、タイヤが付いているもの、付いていたであろうもので行って見たいと思います。まずは、自動車の国アメリカを支えたデトロイトの名を冠したMitch Ryder & The Detroit Wheels。結成は1964年ということですから明らかに第一次ブリティッシュ・インヴェイジョンの影響で盛り上がりを見せたビート系サウンドのご当地版として登場したのでしょうが、アメリカン・ハード・ロックの流れの中では見逃せないバンドでしょう。このミッチ・ライダーとかやはりアメリカの工業地帯五大湖周辺都市シカゴから出てきたThe Shadow Of Knightが60年代半ばに活躍していなかったらイギー・ポップのThe StoogesやAerosmith、KISSといったバンドは生まれていたのかなぁ、と正直思います。そのアグレッシヴなサウンドは音質面はともあれ、まさにアメリカのハード・ロック・サウンドのオリジンと言っても過言ではないでしょう。
SundazedレーベルがリリースしたThe Shadow Of Knightのライヴ・アルバムを聴いていて、再びMitch Ryder & The Detroit Wheelsにたどり着いちゃったわけですが、彼らの2ndアルバム『Breakout…!!!』(1966年)好きですねぇ。特に「Good Golly Miss Molly 」とメドレーになっている「Devil With A Blue Dress On」が大好き。「青いドレスを着た悪魔」ってくらいですからセクシー系のオネェちゃんのことを歌った曲なんだってことは容易に想像つきますが、日本人の僕にはDevilがデブに聞こえてしまうため、「青いドレスを着たデブ」と全く反対方向に行ってしまった空耳曲に聴こえます。おまけにこのMitch Ryder版ではそうでもないのですが、この「Devil With A Blue Dress On〜Good Golly Miss Molly」をそのままライヴでカヴァーしたブルース・スプリングスティーンではイントロのコーラス・パートの一番の歌い出しが「Fee,fee,fi,fi,fo,fo,fum」とまぁ、感嘆詞がそのまま音になったみたいな歌い出し、日本語にすると「お〜、お〜、こりゃ」と向こうからやってくるセクシーなオネェちゃんに思わず声が出るみたいな始まり方になっているのですが、ここがねぇ、スプリングスティーン・ヴァージョン、僕には「爺ィ、婆ァ、ボー、ボー、ボー」と聴こえてしまうわけです。「青いドレスを着たデブ」ときて「爺ィ、婆ァ、ボー、ボー、ボー」ですからもう完全に笑いのツボに直球勝負となります。スプリングスティーン版は70年代末に行われた反原発イベント・コンサート『No Nukes』に収録されています。ハナから脱線しましたが、続けます。Mitch Ryder & The Detroit Wheelsは短命に終わりましたが、その後も1971年にはDetroitというバンド名で活躍した時期もありました。Detroitはミッチ・ライダー入りのアルバムを1枚発表していますが、ライダー抜きでも活動していたようですね。オリジナルThe Detroit Wheelsのツイン・リードの片割れはジム・マッカーティ(もう1人のギタリストの名はウェブ等でご確認ください。ちょっとカタカナ表記はヤバイお名前でして・・・)、そうです、Cactusのジム・マッカーティ。DetroitのヴォーカルだったのがやはりCactusのヴォーカリスト、ラスティ・ディ。ついでにこのDetroitのギターは後にLynyrd Skynyrdに参加するスティーヴ・ゲインズとルー・リード、アリス・クーパーのバックバンドで活躍と言いますか、プロデューサー、ボブ・エズリン人脈のスティーヴ・ハンター。ギタリストの輩出スタイルからするとアメリカ版The Yardbirdsといった趣もありますね。で、ミッチ・ライダーです。ミッチ・ライダーの方も、1969年にはスティーヴ・クロッパーをプロデューサーに迎え、ブッカー・T&ザ・MG’sをバックに制作した『The Detroit-Memphis Experiment』なる燻し銀の名盤もありますが、ここでは1978年発表の『How I Spent My Vacation』を強く押したいと思います。

アメリカの音楽シーンはFMロック全盛の1978年にしては、全体、Rawな作りで、流行りになんか迎合せんもんね、というロックンロール・オリジネーターのプライド全開。引き攣るくらい猪突猛進のThe Detroit Wheels時代のサウンドに比べるとタメが効いたファンキーなサウンドに変化、真夜中ムードのバラードもありと彼なりの時代との決着のつけ方はありますが、このサウンドの引力は半端なし。アメリカン・ハード・ロック好きにとっても60年台ロックンロール・マニアにとっても微妙にインフィールドから外れた微妙な立ち位置にある作品ではありますが、アメリカのオーセンティックなロックが好きという方はぜひ一度体験していただきたい作品です。アーティストとしてのスタイルもその個性も異なり、もちろんそのサウンドにも共通点はないのですが、ルー・リードにおける『Transformer』に近い説得力を感じます。また特に有名ミュージシャンの参加もなく、バックはずっと一緒にやっていた自身のバンドなんですが、このバンドがまたいい演奏するんだ。「青いドレスを着たデブ」を発端にして久々に聴き通しましたが、思わず聴きこんでしまいました。無駄が一切ないんだよなぁ、このアルバム・・・。
Freezin’ In Hell
さて、タイヤといえばホイール。って、なんだそりゃなんですが、ホイールでパッと浮かぶのはCreamとかになっちゃいますが、本日頭に浮かんだのは「Wheels Of Fortune」。アメリカの視聴者参加型クイズ番組は「Wheel Of Fortune」。「Wheels Of Fortune」はThe Doobie Brothersの1976年発表6thアルバム『Takin’ It To The Streets』のオープニング・トラックです。「Wheels Of Fortune」というフレーズはタイヤとの関連はちと薄く、多少強引ではありますが間違ってはいないということで。『Takin’ It To The Streets』はトム・ジョンストン、パトリック・シモンズ時代とマイケル・マクドナルド時代の分岐点に当たる作品です。トム・ジョンストンは前作『Stanpede』発表と前後して病気療養のためバンドを離れ、本作で復帰。次作『Livin’ On The Fault Line』のレコーディングにも参加しますが、彼が書いた曲は収録されず、そのまま脱退してしまいます。実際にはこの『Takin’ It To The Streets』でもジョンストンの曲は「Turn It Loose」1曲しか収録されておらず、アルバムのほとんどがシモンズとマクドナルド作ということもあり、『Stanpede』までバンドの顔であったジョンストン色はだいぶ薄れてしまっているのですが。
マイケル・マクドナルドの参加は『Stanpede』発表後のツアーにジョンストンが病気による入院で参加できなくなり、ギターはSteely Danから移籍してきたジェフ・スカンク・バクスターが正式参加していたため何とかツイン・ギター体制を維持できたものの、サウンドが薄くなることとヴォーカル・ハーモニー面での補強兼ねたものだったわけです。それまでメインのヒット曲はジョンソン作、シモンズは豪快ロック路線というよりもオーセンティック・アメリカン・サウンド、通好みのギター曲担当みたいな住み分けがあったのが『Stanpede』のひとつ前の『What Were Once Vices Are Now Habits』に収録された「Black Water」がシングルとして大ヒットしたことで作曲面でもジョンストンと対等になってきたところでのジョンストン休養。バンドの看板となったことでStanpedeツアーでシモンズの才能が一気に開花したという点も見逃せません。
『Takin’ It To The Streets』に続くジョンストンは参加しただけに終わる『Livin’ On The Fault Line』のAOR路線にシフトしたアルバムでもシモンズは活躍しますが、シングル・ヒットとして目立つのはマクドナルド楽曲の方で以降、バンドの中心メンバーとしての比重はマクドナルの方に傾いて行きます。『Takin’ It To The Streets』はライヴ・アルバムを最後に解散するオリジナルDoobie Brothers期にあって最もシモンズ色が強くでた作品であり、70年代前半のアメリカを代表したギター・バンドDoobiesの最後の輝きを見せた作品だったと思うのです。アルバムからのシングルは「Takin’ It To The Street」、「Wheels Of Fortune」、「It keeps You Runnin’」の3枚で内2曲がマクドナルド楽曲ですから、既にマクドナルドの方が目立っているのですが、それでもこのアルバム、キモはシモンズ楽曲だったと思います。
「Wheels Of Fortune」はアルバムのオープニングを飾るナンバーで、ギターの華麗なカッティングが印象的な楽曲。ジョンストンのオーヴァードライヴが掛かった豪快なリフとは異なり、カラッとしていて、薄っすらコーラス・エフェクトが掛かったサウンドと切り返しの仕掛けと目の覚めるようなキメ・フレーズが印象的なナンバー。このカラリとしたカッティングは、やはりアルバムの中でも印象的な「8th Avenue Shuffle」遺憾無く発揮されます。病気上がりでまだ本調子とは言えないものの、自分が引っ張ってきたバンドというプライドがまだこの時にはジョンストンにあったんでしょうね、軽快なシャッフル・ナンバーでありながら、軽く流れず、サウンドの重心は低めだけど疾走感があるDoobies固有のグルーヴ感がしっかり残っている部分にはジョンストンの存在が大きかったと思います。このアルバム最大の聴きものはシモンズとバクスターの共作である「Rio」かと思います。その名の通りサンバのリズムを取り入れた、マクドナルド楽曲とは明らかに異なるAOR感覚が光る軽快なナンバーです。ロックというよりフュージョンのスタイルに近いリズム・パターンと複雑なギター・アンサンブルの妙技は鍵盤楽器で曲作りをする人間には作り出せない独特のグルーヴがあり聴かせます。途中ゲスト参加のマリア・マルダーが歌というよりほとんどセリフのような「(Do You) Wanna Take A Ride?」という一言が妙に趣のある声で挿入されるシーンも聴きどころのひとつになっています。
作品自体を有名にしたのはマクドナルドの書いたヒット曲だったのかもしれませんが、それでもまだこの作品はギター・バンドDoobiesの魅力が色濃く残った作品であったと思います。
加えて、プロデュースを担当したテッド・テンプルマンにとっても重要な作品だったと個人的には思っています。あの独特の空間処理とコンプレッサー・ワーク、定位設定の妙技・・・テンプルマン・プロデュースの勝ちパターンを確立したのはこの作品だったと思うのです。
Wheels Of Fortune
B.B.キング、フレディー・キングと共にブルースの世界の3大キングの一角、アルバート・キング 。ブルース界の王様の1人ですから何たってガタイが立派。写真見ていると手もごっついですねぇ。グローブみたいな手です。左利きでフェンダーのストラトキャスター弾いている写真なんかはジミ・ヘンドリックス同様、右利き用のギターを逆さまにして使っています。B.B.キングは愛器ギブソンES-345に「ルシール」と名付けましたが、左利きの彼は反対に持ってもシェイプが変わらないギブソン・フライングVを使用することも多く、B.B.に対抗して「ルーシー」と名付けたという逸話も残されています。

曲としては「Sky is Cryin’」「Born Under A Bad Sign」、元はトミー・マクレナンがカントリー・ブルース・スタイルで演奏していた「Crosscut Saw
をファンキーなアレンジしたヴァージョンなどはロック・ファンにも広く知られています。特にそのごっつい手を活かしたパワフルで粘り気のあるチョーキング・スタイルはクラプトン、スティヴィー・レイヴォーンを始めブルースをプレイするロック・ギタリストはほとんど直接・間接を問わず影響を受けたと言っても過言ではないでしょう。スタックス・レーベル時代の1970年には全曲エルビス・プレスリーの代表曲でまとめた『Blues For Elvis: King Does The King’s Thing』なるアルバムを発表していますが、見事な俺様流アレンジで、あまりに堂々と無茶アレンジをやっているため、元の曲がどんなだったか一瞬分からなくなるくらいの暴れっぷり。普段、ブルースに親しみのないロック耳のリスナーに方にも十分お楽しみいただけるファンク系ブルースの怪作でした。
タイヤがらみでご紹介するのは『Blues For Elvis: King Does The King’s Thing』同様スタックス時代の1974年に発表された『I Wanna Get Funky』収録の「Flat Tire」です。まず、ジャケット写真が良いですねぇ。スタジオ・レコーディング中の写真で、ここでは「ルーシー」ではなくストラトキャスターを逆さまに持ってタバコの煙をブワーッと吐き出した瞬間といった感じですが、要するにそういう音が詰まっております。一見しただけでどんな音楽やっているのかが丸分かりという、大変優れたアートワークだと思います。『I Wanna Get Funky』と名付けた割には、ま、確かにファンキーではありますが、ロック耳にも大変心地よい、どちらかというとゆるめのテンポでどっしり聴かせるタイプの曲の方が多い優れた作品で、先に挙げた十八番のひとつ「Crosscut Saw」のファンク度増し増しの再演なども収録されており、巷ではスタックス時代の名盤のひとつに数えられているわけですが、その中にあって、「Flat Tire」はお茶目といいますか、ちょっと外した感じの一曲、アルバムの良いアクセントになっています。
元はかなりいなたい感じのベース・リフが全体を引っ張るファンク・ブルースだったのでしょうが、アレンジ段階でやらかしてしまった感強く、ホーンをドーンと入れて、女性コーラス隊もフィーチュアして行きましょうみたいなプレゼンをされ、当の本人も「良きに計らえ」って感じで気にもせずアレンジャーが調子こいて書き上げたイケイケ・アレンジにそのまま乗っかったというところなんでしょう。そのいなたいファンク・ブルースの後ろで鳴るホーンやら女性コーラスがこの当時のR&Bの流行をそのまま取り入れました、最近のR&Bヒット曲の美味しいところをバレない程度にパクって繋げてみました的な浮いたアレンジ。そのアレンジとキング本人のプレイが妙にかけ離れているところが逆に耳に残る。なんかチグハグなんだけど一周回って結果オーライみたいな雰囲気にそそられる仕上がりとなっています。おそらくレコーディング現場では「師匠、そこはもう少し細かくカッティングなされたほうが、ファンキーな感じが出ると思われますが・・・と進言されても本人、意に介さずいつも通りの唯我独尊カッティングで押し通したが故にこの迷曲が生まれたのではないかという妄想が頭の中に渦巻く、どう聴いても聴き流すの無理といった聴く者を強引に巻き込むフックを持ったナンバーなわけです。
因みにこの「Flat Tire」、1978年にトマト・レーベルから発表した『New Orleans Heat』で再演されているのですが、こちらは元々のスタイルの小編成バンドによる演奏で、いなたいファンク・ブルース感全開ヴァージョン。本人任せでやるとこういうアレンジなります、といった感じの仕上がりになっています。この『New Orleans Heat』版聴いて思ったのは、スタックスってアーティストのイメージ管理とかプロデュースがしっかりしていたんだなぁ、ということ。パッとスタジオ入って思うがままに作った感じの『New Orleans Heat』とは作品の方向性が全く違うことがよく分かります。
因みに1986年にスタックスが出したベスト盤『Best Of Albert King』はジャケット写真が反転しており右利きになっております。発売するまで誰も気が付かなかったってことんなんでしょうけど、なんだかねぇ。
Flat Tire
今月の1枚はGood Godが1972年にアトランティックから発表した唯一作『Good God』です。フィラデルフィア出身のジャズ・ロック・バンドです。CDはFlowed Gemから出ておりカケレコでも販売しています。このアルバムを一枚残しただけで消えた謎の多いバンドです。アルバム一枚で消えたバンドなんて大したことないじゃないと言われそうですが、ギター、キーボード、サックス共に水準以上のテクニックを持った優れたプレイヤー揃いで、フランク・ザッパの人気曲「King Kong」、ジョン・マクラフリンの「Dragon Song」のカヴァーも収録されています。ザッパのカヴァーをやっているところからも分かるように、サックス・プレイヤーがいるバンドではありますが、ブラス・ロック的な雰囲気は皆無に近く、そのサウンドはフランク・ザッパの硬質なインスト曲、僅かにメル・コリンズ在籍時のKing Crimson、Gentle Giantなどのテイストを感じることのできるサウンドで、カケレコ商品案内にあるようにアメリカというよりイギリスのジャズ・ロック寄りのサウンドが魅力のバンドです。ギター、キーボード、サックス共に水準以上と先に書きましたが、インプロヴィゼーションの引き出しも豊富で、アルバムを通して全6曲中5曲が5分以上の長尺曲ですが、演奏がダレる場面は皆無で、最後まで緊張感ある演奏が楽しめます。「King Kong」も良いのですが、ジョン・マクラフリンの「Dragon Song」がカヴァーが個人的には気に入っています。途中のギター・ソロがかなり秀逸で、マクラフリンとは違い、ジャズ/フュージョン系というよりロック・フィールドに位置付けられる硬質でロックな熱量を存分に感じさせるプレイは好感が持てます。このギタリスト、ジーノ・スパークル(本名:Larry Cardarelli)は検索しても他の作品への参加が出てこなかったのですが、この時代のギタリストしてはかなりの腕前だっただけに残念ですね。また、ヴォーカル入りナンバーである2曲目の「Galorna Gavorna」も個性的でSmall Circle Of FriendsミーツGentle Giantといった不思議な感触を持った曲に仕上がっている点もこのバンドの特異な個性を物語っています。
メンバーがキャプテン・ビーフハートの熱烈なファンで、このGood Godというバンド名もキャプテン・ビーフハートに付けてもらったという真偽のほどがはっきりしない逸話が残されていますが、ここまで出てきたきたキーワードに引っかかりを覚える方は聴く価値のある発掘作品だと思います。キャプテン・ビーフハートにバンドの名付け親になってもらおうとしたということで、イマイチ内容がうまく伝わらないアートワークの奇妙な絵もキャプテン・ビーフハートの手によるものかと思ったのですが、それは違ったみたいですね。
ともあれ、アートワークが今ひとつそそられなかったこともあり、大したバンドではないだろうと思っていましたが、聴いてびっくり! これかなり良いですよ。では、また!
Dragon Song
【関連記事】
「音楽歳時記」 第四十五回 10月23日 電信電話記念日 文・深民淳
音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。
関連カテゴリー
関連CD在庫
-
DOOBIE BROTHERS / TALKIN’ IT TO THE STREETS
76年作
-
紙ジャケット仕様、SHM-CD、09年デジタル・リマスター、内袋付仕様、定価2500
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!