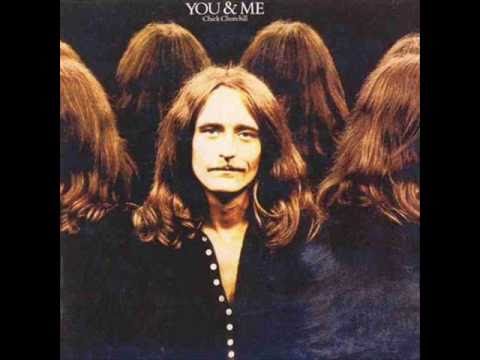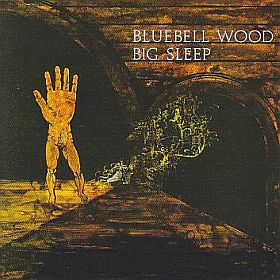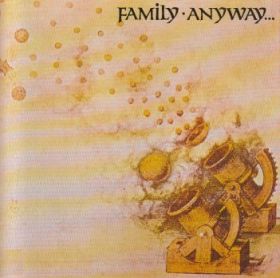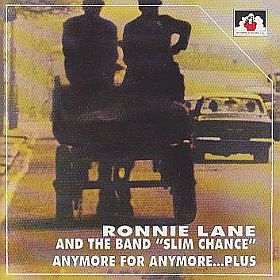「音楽歳時記」 第二十ニ回 11月 感謝祭・七面鳥の受難 文・深民淳

11月は去年やらなかった感謝祭というのがあります。サンクスギヴィング・デイ。アメリカでは家族・一族が集いスタッフィングを詰めた七面鳥のローストをグレイヴィー・ソース、クランベリー・ソースでいただくという、アメリカ全体が食事会という日です。いい加減なこと書きやがって、と思われるかもしれませんが、あながち間違っていません。本当にそうだし。
この感謝祭、アメリカでは11月の第四木曜日となっており、アメリカ人この週は週末にかけてほとんど仕事しません。といいますか、音楽業界はほとんど働いていません。しかも、この後すぐにクリスマス休暇が来ますので我々日本人にとっては結構、迷惑な時期と言っても良いでしょう。
またこの感謝祭の週は一年中で最もアメリカ国内移動が面倒な時期かもしれません。空港、道路どこも恐ろしく混み合います。ある種、日本の盆休みに近いところもあるように思いますが、スケールはもっと大きいように思います。
元々は、1620年、イギリスからマサチューセッツ州プリマス植民地に入植したピルグリム・ファーザーズが彼の地にたどり着いた冬の厳しさから多くの死者を出し、危機的状況にあった時、翌春、アメリカ先住民ワンパノアグ族がトウモロコシなどアメリカ大陸に合った農作物の栽培知識を授け、これにより1621年の秋は多くの収穫を得ることができピルグリム・ファーザーズらは栽培知識を授けてくれたワンパノアグ族を招いて神への感謝を捧げ食事を共にしたことを起源としていると言われていますが、異説も多々あります。マサーチューセッツ植民地の統治者ウィンスロップがアメリカ先住民であるインディアンとの間に戦争や虐殺といった暗く血塗られた歴史しかないため、明るい話を広めるため作り上げたという説。15世紀末にコロンブスがアメリカに到達した際持ち込んだインフルエンザ菌を始めとするアメリカ大陸には存在していなかった病原菌によりニューイングランド近辺に居住していたインディアンの90%は1620年までに病死していた説もあり、ピルグリム・ファーザーズたちは病死したインディアンの住処や日用品を使うことで生き延びたという説もあります。また、インディアンにとっては先祖の生存のための知識や土地がヨーロッパからの移民たちの手により奪われた、大量虐殺の始まりの日という認識もあり、実際、ワンパノアグ族を始めとするニューイングランドのインディアン部族が集まった「ニューイングランド・アメリカインディアン連合」はこの感謝祭にぶつけて「全米哀悼の日」として抗議デモを続けている事実もあります。
単純に七面鳥焼いて食うだけの日ではないということですね。確かに、先住民に対する感謝があったのになぜインディアンの大量虐殺という歴史的な事実があったのか、とこの感謝祭の由来を聞くたびに思います。ただ、こうした由来にまつわる様々な異説は蔑ろにできないにせよ、今日での感謝祭は実に平和な家族イベントとなっています。
まぁ、逆に考えれば七面鳥にとっては受難以外何者でもなく、アメリカではこれとクリスマスがセットで来ちゃうものですかから、喰われる方にとってはたまったものではありません。ともあれ、七面鳥=ターキー由来のバンドといえばまずはこれかなと。WILD TURKEY。JETHRO TULLを辞めたというか追い出されたベーシスト、グレン・コーニックが元EYES OF BLUEのゲイリー・ピックフォード・ホプキンス、元PETE BROWN & PIBLOKTO!のジョン・ウェザースらと結成したバンドです。TULL流れで来ているところからもハード・ロック、プログレの系統で語られることの多いバンドですが、実際は落とし所が見つけにくかったりします。全編、ほぼ一発録り(このツンのめるグルーヴをパート毎に録っていたのであれば逆に凄いですね)のサウンドは最後までどこか不安定なノリに終始し、バンドの個性というより、メンバーの個性がそのままサウンドに反映されちゃったかのような、こちらもどこか半端な音楽性に終始しています。こう書くとなんか面白味のないバンドのように思えるのですが、カケレコでCD買っている人なら解っていただけると思いますが、こうしたどこか煮え切らないバンドの方が面白いし、新鮮味があるわけです。
本当に妙なバンドです。ゲイリー・ピックフォード・ホプキンスのいかにも英国人といった淡々としたヴォーカル(というより、特徴のない声ではないのですがどこか捉えどころがない)。トゥイーク・ルイスのあんまりトーンのこととか考えてはいないけれど、妙に聴くものを引きつけるギター・プレイ。焦点が合っているのか否か、いまひとつはっきりしないサウンドにも関わらず、ひとり思い切り輪郭がはっきりしているベース(一応、この人のバンドってことになってますからね。親方力には多少欠けている感がありますが・・・)とか、名手、ジョン・ウェザースを起用しながらグタグタ寸前のサウンド・メイクとか突っ込みどころ満載なのですが、これが全部逆に捨てがたい魅力となってまして・・・。グレン・コーニックがJETHRO TULLのメンバーだったこともありクリサリス・レーベルから2枚のアルバムを発表したほか、発掘音源CDとして客席録音によるライヴ『Final Performance』、シングル、ライヴ。レア・トラックス構成されたコンピ盤『Rarest Turkey』、再結成盤などがありますが、ここではやはり2枚のオリジナル・アルバムを薦めます。デビュー作でのグタ寸前のサウンドの反省を踏まえ、多少ちんまりとしてしまったけど、良く纏まったロック・ヴォーカル・アルバムといった作りの2nd『Turkey』(1972年)のほうが作品としての安定感はありますが、やはり1st『Battle Hymn』から聴いていただきたい。本当に突っ込みどころ満載です。でも聴き終えると「こういうのも良いよね」と思っていただけるかと。大体、比べるバンドがほとんど見当たらないくらいクセのあるロック・トラックが2曲続いた後に「Dulwitch Fox」などという妙にのどかなフォーク・ソングが出てくるとは誰も想像できないでしょうし、後半の「あんた、逆にそういう歌メロ良く考えついたね」と感心してしまう、妙なメロディを持った曲の連発があったり(で、それが妙に頭に残ったりするわけだ)と、聴いたことない方でしたらかなり楽しいチェレンジになるかと思います。
Dulwitch Fox
WILD TURKEY一式をつらつら聴いていたところ、今回もどこに特徴があるのかよく判らなかったゲイリー・ピックフォード・ホプキンスにはまってしまいました。というわけで次はこれ。なんですが、もしかすると前に一度紹介した可能性がありますが、私、3カ月以前は滝なのですいません。TEN YEARS AFTERのキーボード奏者チック・チャーチルが1973年に発表したソロ・アルバム『You And Me』です。中学生当時ROLLING STONE日本語版というのがありまして、そこのアルバム・レビュー(オリジナルROLLING STONE掲載のレビューの翻訳だった記憶がありますが)でボロカス書かれていたもので、ずっとダメなアルバムという先入観を持ったまま、21世紀になってしまい、発表から四半世紀以上を経てCD化されてから聴いたわけですが、良かったのよ、これが。もう、全部中途半端。聴くほうは「あぁ、ここもう少し磨けば突き抜けた名曲になるのに!」と歯がゆく思っても、やっているほうは「これが気持ち良いっしょ!」みたいにサラリと躱される感覚。全編、言葉そのままのニッチ・ポップ!コージー・パウエルは参加しているし、バーニー・マースデンもいる、でもハード・ロックというより良くできたロック・ヴォーカル・アルバムといった作りで、こういうところにゲイリー・ピックフォード・ホプキンスを当てるともう無敵状態という他ありません。一等賞は取れないけど良い歌メロ満載の残念珠玉作として私は愛聴しております。
Come And Join Me
1970年にPegasusレーベルから唯一のアルバムを出して消えたBIG SLEEPもゲイリー・ピックフォード・ホプキンスがらみでは外せません。『Bluebell Wood』は彼らの唯一のアルバムではありますが、メンバー構成から見れば、ゲイリー・ピックフォード・ホプキンスが参加していたEYES OF BLUEの実質的な3rdアルバムとも取れる作品です。EYES OF BLUEが持っていたビート系サウンドは後退。R&B色は根底に残してはいるものの、時代の影響から幽玄フォーク調、オルガン、ピアノ入り耽美的ナンバーが増え、初期プログレの名盤の一枚も数えられている作品ですが、ここでもピックフォード・ホプキンス、いい仕事をしています。幽玄フォークや耽美ナンバーにピックフォード・ホプキンスの声を被せると虚ろさ加減が半端なくリアルになる!1970年発表のプログレが発展期に入ったあたりの作品ですから、めくるめく展開とかは期待できないのですが、先月紹介したMANの『Back Into the Future』にも参加していたフィル・ライアンのキーボード・プレイはこのころからすでに非凡な才を発揮していますし、部分的に導入されたストリングスもいいアクセントとなっており、全編を通してだれることなく聴き通せる優れものとなっています。EYES OF BLUE時代からメロディ・センスは定評があったわけですが、その優れたセンスは本作でも遺憾なく発揮されているといって良いでしょう。
Bluebell Wood
感謝祭の七面鳥からゲイリー・ピックフォード・ホプキンスという派手な飛び方をしてしまいましたが、話を元の感謝祭に戻すと、コロンブスが持ち込んだ病原菌やウイルスが元で17世紀までにはニューイングランド近辺の先住民たちの90%は病死という話を引用しました。ここでふと私の頭の中に浮かんだのが、ピルグリム・ファーザーたちはその先住民であるインディアンの住処を使うことで最初の冬を乗り越えた、という部分。ニューイングランドあたりの冬は厳しそうなのだが、東海岸に住んでいたインディアンたちも西のインディアンみたいにあの独特のテントのような住居に住んでいたのか?という疑問。そもそも、あのインディアンの住居はなんと言うのだろうとなりまして。ググりました。「え〜! あれってWIG WAMって言うんだ!」ということでした。今月は妙に綺麗に納まりました。次はそれです。
そのものズバリのWIG WAMが浮かぶ前に私、ワンストップしちゃいまして、まずはそっちから。画像検索かければ容易に出てくると思いますが、SWEETがインディアンの格好で写っているプロモ写真あるじゃないですか。そういえばあったよね、「Wig Wam Bam」って曲、と繋がっちまったわけです。そうです。Chinnichapです。マイク・チャップマンとニッキー・チンのソングライティング+プロデュース・チームは’70年代のUKシングル・チャートを席巻していました。ミッキー・モストのRAKレーベルを中心にスージー・クアトロ、SMOKIE、MUD等’70年代前半のシングル・チャートの常連として数々のヒットを連発し、’70年代半ばには、マイク・チャップマンはアメリカに移住し、BLONDIE、THE KNACKで成功を収め、1979年にはDREAMLANDレーベルを創設しました。
Chinnichapはイギリスでヒットを連発していた時期に彼らの手による曲の総称として使われた言葉で、やっかみ半分、羨望半分でガキ向けPOPの代名詞みたいな感じで使われていました。SWEETはこのChinnichap全盛時代に、彼らの書いた曲&プロデュースで数多くのヒット・シングルを量産しており、「Wig Wam Bam」もそんなヒット曲のひとつです。この時期のヒットとしては「Little Willy」、「Blockbuster」なんかもあります。元々DERAM NOVAからアルバムを出していたELASTIC BANDにいたアンディ・スコットをはじめとしてそこそこのバンドに在籍していたメンバーが結成したバンドで、ちゃんと演奏できるバンドだったため、デビュー当時のChinnichapヒットだった「Funny Funny」や「Co-Co」なんかは飴でコーティングしたみたいなPOPソングで、メンバーもやっていて小っ恥ずかしかったのではないかと思ってしまいます。ただ、この「Wig Wam Bam」のヒットあたりになるとグラム・ロック全盛期で、SWEETもこの流れにうまく乗ったこともあり、曲調が次第にハードになっていきます。この後、バンドのオリジナル「Fox on The Run」がヒットしたことでChinnichapから距離を置くようになり、全盛期を迎えるわけですが、「Fox on The Run」直前、Chinnichap後期のヒットにはかっちりとタイトな中にも独特の沈殿感といいましょうか、妙な重さがあって結構気に入っています。
Wig Wam Bam
さて肝心のWIG WAMですが、2001年デビューのノルウェイ産ハード・ロック・バンドの方ではなく、’60年代末から活躍しているフィンランドのプログレ/ポップ・バンドのほうです。北欧を代表するプログレ・バンドという側面と、英VIRGINレーベルから世界に向け発信されたニッチなポップ・ロック・バンドという面を併せ持っています。
フィンランドのアンダーグラウンド・シーンを代表するバンドとして日本でも早い時期から聴かれていたバンドで、元々は’60年代、R&Bとブルースに傾倒していたBLUES SECTIONが分裂し、一方がこのWIG WAM、もうひとつがこれも当時の北欧ロック・シーンを代表したTASAVALLAN PRESIDENTTIになりました。1968年にニッケ・ニカモ、マッツ・ハルデン、ロニー・オスターベルグによって結成されたWIG WAMにイギリス人ジム・ペンブロークとプログレ期WIG WAMの方向性を決定付けたキーボード奏者ユッカ・グスタフソンが加入し、アルバム『Hard n’ Horny』を発表。翌年、ギターのニカモ、ベースのハルデンが脱退し、ギターは結局、この後長い間ゲストでつなぐ時代が続きますが、ベースにはフィンランドを代表するコンポーザー、マルチ・プレイヤーとなるペッカ・ポーヨラが加入。カンタベリー・テイストとアメリカのTHE BANDに代表されるようなオーセンティックなロック・サウンドが同居する『Tombstone Valentine』(1970)、1970年代初期のオルガン・プログレの名作『Fairyport』、トータル・コンセプト・アルバムの白眉と言っても過言ではない傑作『Being』(1974年)と順調に作品を発表していきますが初のライヴ・アルバムとなった『Live Music From The Twilight Zone』(1974年)を最後にグスタフソン、ポーヨラが相次いで脱退。ペンブローク主導のポップ路線に方向転換し、英VIRGINを通じて世界発売された1975年の『Nuclear Nightclub』以降は北欧の10CC称される、どこか屈折感のあるポップとプログレのうまく嵌まり込んだサウンドを標榜するバンドへと変化していきます。
プログレ時代の代表作といえばやはり4thアルバム『Being』ということになるのでしょう。ユッカ・グスタフソン主導で制作された『Being』は、クラシカル・テイストとジャズ・ロックが高次元で融合を果たした完成度の高い作品で、WIG WAMのディスコグラフィの中にあっても一枚だけ浮いている感もありますが、不穏なムードから始まる導入部、高い演奏能力にものいわせてフルスロットルで展開していくジャズ・ロック的パート、ペッカ・ポーヨラ作でマイク・オールドフィールドの目に止まったことで後に英VIRGINを通じて世界に発信されることになる『The Mathematician’s Air Display』(1977年、原題は『Keesojen Lehto』)にも収録される「Hands Straighten The Water』(原題は「Kadet Suoristavat Veden」)の原曲が収められていたり聴きどころが多い充実した作品に仕上がっています。ただ、ここで紹介したいのはその『Being』の一つ前の彼らにとって初のLP2枚組作となった『Fairyport』です。初期CARAVANやSOFT MACHINEに通じるオルガン主体の楽曲、牧歌的でフォークテイストに満ちているものの、どこか屈折していている小品構成された作品で、後半にはライヴ・マテリアルも収録されています。過去何度か再発されていますので、ボーナス・トラック等収録曲数の違うヴァージョンが存在しますが、ここでは日本盤紙ジャケットに使われたリマスター・ヴァージョンを前提に書かせてもらっています。
やはり聴きどころはオープニングの「Losing Hold」とこの時期は専任ギタリストがいなかったためゲストとして招いたユッカ・トローネンのギター・ソロが炸裂するロック・ジャム曲「Rave-Up For The Roadies」でしょう。特に「Losing Hold」はオルガン・プログレ好きで、未聴でしたら是非と薦めたいスピード、テンション共にかなり高めの名曲です。グスタフソンのオルガンも指回転しまくりの活躍ですが、ここに絡んでくるポーヨラのベースが凄い! かなりトリッキーなオルガンのメロディに事も無げにユニゾンかましたり、やたらと隙間を埋めた細かくかつ目眩く展開していくベースには唖然となります。追加収録としてこの「Losing Hold」のライヴ・ヴァージョンが収録されていますが、こちらは後半が自国の偉大な作曲家シベリウスの代表作の一つである「Finlandia」に繋がっていく興味深いヴァージョンで、グスタフソンのオルガン、ポーヨラのベース共にスタジオ録音以上の暴れっぷりを見せており、聴く価値十分の圧巻のライヴ・テイクとなっています。
Losing Hold
こうした圧巻のライヴ・トラックを聴いてしまうと、ライヴ・アルバムの方に興味がいってしまうのですが、『Being』の直後に発売されたオフィシャル・ライヴ・アルバム『Live Music From The Twilight Zone』は『Being』までのWIG WAMというより、その後のポップなサウンドのWIG WAMへの橋渡し的な作品となっており、どちらかというとゆったりとした曲調のナンバーが多く、THE BEATLESの「Let it Be」、ジョン・レノンの「Imagine」のカヴァーなんかも収録されており、圧倒的な爆発力を見せつける、WIG WAMのもう一つの姿は残念ながら封印されてしまっています。ジャズ・ロック/プログレ度の高いWIG WAMが聴きたいという方には2000年頃に発売された2枚組レア・トラック集『Fresh Garbage-Rarities 1969-1977』を薦めます。
最後に今月の1枚ですが、今年もいい感じの夕暮れが楽しめる季節になりました。そんな時間帯に聴きたくなった曲が収録されている作品を2つ紹介しておきたいと思います。まずはFAMILYの4thアルバムでオリジナルは片面がライヴ、もう片面がスタジオ録音楽曲で構成された『Anyway』です。一説によれば新曲をライヴで演奏したものを集めて新作とする予定が、レコーディング状態に難があり、ライヴとスタジオ録音の合体作となったとも言われている作品です。ライヴの方はロンドンの南にあるクロイドンのフェアフィールド・ホールで1970年7月26日に収録。スタジオ録音はオリンピック・スタジオで行われています。このスタジオ録音パートの中の「Normans」この時期聴きたくなります。2代目ベーシスト、ジョン・ウェイダーのフォーク、C&Wタッチのヴァイオリンとポリ・パーマーのピアノの紡ぎだすメロディにほっこりするインスト曲で、イギリスのカントリーハウスの茶色をベースにした落ち着いた情景が目に浮かぶ心弾むナンバーです。
Normans
もう1曲は、これ自体、秋の夕暮れのため音楽と言って良い、RONNIE LANE’S SLIM CHANCEが1974年にGMレーベルから発表した『Anymore For Anymore』収録の「The Poacher」。ストリングスと管楽器を加えたノスタルジックなメロディが愛らしい小品ですが、何度見ても良いアートワークだなぁ、と思う本作のジャケットを見ながら聴いていると、この黄昏の世界に引き込まれていくような感覚を覚えます。今日はこのまま『Anymore For Anymore』を聴きながら過ごしたいと思います。
The Poacher
関連カテゴリー
音楽歳時記 11月 感謝祭・七面鳥の受難
-
BIG SLEEP / BLUEBELL WOOD
EYES OF BLUEの後身、リリシズムいっぱいの極上英国ポップ!71年作
EYES OF BLUEのメンバーそのままに71年にリリースされた唯一作。EYES OF BLUE時代の格調高い英国ポップに、プログレ、スワンプなどの要素を加えた、いかにも70年代初期の薫り漂う極上英国ポップ。叙情的なメロディー、クラシカルなストリング、哀愁のオルガンが絶妙なアンサンブルを奏でる1曲目は、70年代英国ロック・ファン必聴の名曲。もう少し品のあるジャケットであれば、評価も違っていたでしょう。完成度としては文句無しの傑作。
-
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
小さい圧痕あり
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!