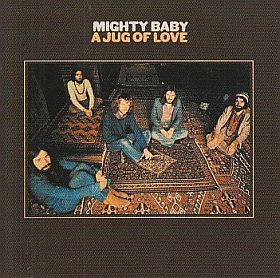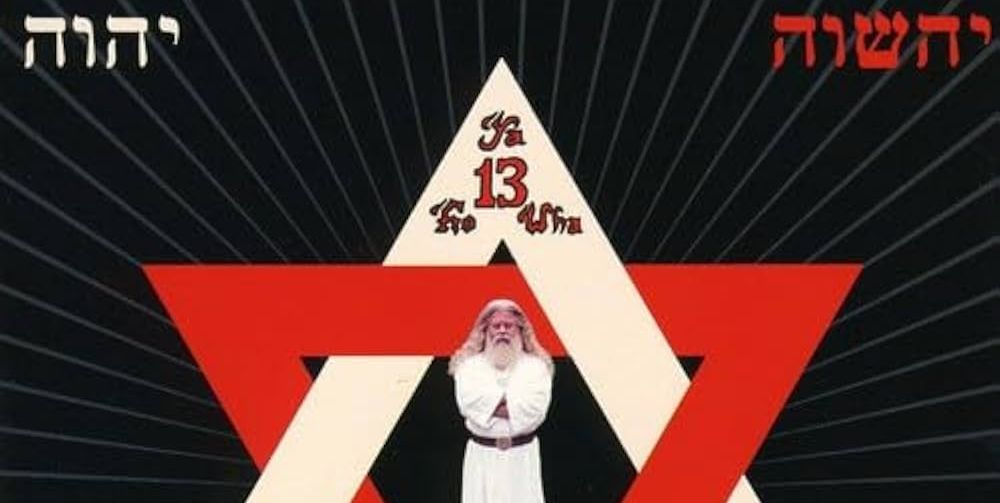「音楽歳時記」 第三十七回 関係ないけどバカヤローの日 文・深民淳

早いもので3年が経ちました。最初は2月ヴァレンタイン・デイからスタートしたように記憶していますが、もう既に何を書いたかは霧の彼方です。霧といえばThe Spotnicksが定番なんでしょうが(年寄りにとってはね)僕の場合はカナダのMashmakhanが頭に浮かびます。「霧の中の二人/As The Years Go By」ですね。本国カナダはもとより、アメリカでもTop40ヒットとなり、日本でも大ヒットしました。The Spotnicksも寒いトーンが印象的でしたが、こちらもリヴァーブがかかったオルガンのトーンが寒いです。当時、この曲はシングルとして大ヒットし、来日もしていますが、ヒットが続かず一発屋のイメージが強いバンドなのですが、アートワークも超寒そうな2ndアルバム『The Family』(1971年)はオルガン入りジャズ・ロックとしてはかなり出来が良く、一発屋で片付けてしまうには惜しい好盤でした。「霧の中の二人/As The Years Go By」が収録された1stと『The Family』の2枚を2in1にしたCDが’90年代の終わりに出ており、中古で良く見かけます。ちなみにドラムのジェリー・マーサーはMashmakhan解散後April Wineのメンバーとなります。
As The Years Go By
寒いという以外、2月とは関係ない話でしたが、変わった記念日はないかと探すと、2月28日ビスケットの日というのがありました。1855年にビスケットの製法を記した文書「パン・ビスコイト製法書」が当時の水戸藩に伝わったことを記念し1980年に全国ビスケット協会が制定。ビスケットの語源であるラテン語の「ビス・コクトス」意味が「二度焼かれたもの」であったことから「二度」の2と「焼かれる」で8の語呂合わせで決まったそうです。2月の語呂合わせ系では他にも2月9日「ふくの日(フグの日)」、2月10日「ニットの日」などがあります。
この2月28日はバカヤローの日でもあります。なんだそりゃ、という感じですが、1952年(昭和28年)当時の首相、吉田茂が衆議院予算委員会で社会党の西村栄一議員との質疑応答中、西村議員の質問に対し吉田首相が「無礼じゃないか!」と発言。これに対し西村議員が「何が無礼か! 答弁できないないのか君は」と応酬。これに激昂した吉田首相が「馬鹿野郎!」といったことから内閣不信任案が提出され可決したことで3月14日に衆議院が解散。歴史的にも有名な「バカヤロー解散」の発端となった答弁が行われた日ということで知られています。
まぁ、世の中バカヤローなことは多く、思い切り期待してCDとか買ってバカヤローと叫びたくなる経験はみなさんお持ちでしょうが、わざわざここであれがバカヤローだ、いやこれがバカヤローって話はいくらでもできますが、そんな殺伐とした原稿書いてもしょうがないしねぇ・・・と思っていたところに白谷潔弘くんが監修しシンコー・ミュージックから発売された「ブルース・ロック・アンソロジー:ブリティッシュ編」を送ってきてくれまして。本自体は昨年の夏には出ていたようですが、本人が著者贈呈分を一冊送ってくれたようです。いやぁ、白谷くん!遂にやったねぇ。凄い本だよ、これ! 資料としても読み物としても最高峰に位置する驚異的な一冊だ。うれしかったなぁ! 本当にどうもありがとう。あんまり凄いので、送ってもらったけど、もう一冊金出して買うよ。こういう素晴らしい内容を持ったアンソロジー本は売れて欲しいし、是非、アメリカ編やヨーロッパ編と続刊が出て欲しいしね。

白谷くんはブルース、R&Bオリエンテッドのロックの書き手としては当世、第一人者だと僕は思っています。彼の仕事で最初に凄いなぁと思ったのは、キーフ・ハートレーの自叙伝「ブリックヤード・ブルース」の巻末に資料として掲載されていた、ブリティッシュ・ブルース・ロック系アーティスト、レーベルの作品リストでした。当時、僕はマイク・ヴァーノンのブルー・ホライズン・レーベル(CBS、ポリドール配給時代)から発売されたアルバムをオリジナルでコンプリートしようとしていて、CBS、ポリドールから発売されていたブルー・ホライズン作品は8割がた把握してはいたものの、後期のポリドール配給になってからのリストで幾つか不明なものがあり、結構難儀していたのですが、「ブリックヤード・ブルース」巻末の資料で一気に解決。原盤番号まできっちり明記されていたのでめでたくコンプリートすることができたのでした。
今回の「ブルース・ロック・アンソロジー:ブリティッシュ編」はこの時のリストのアーティスト・バイオ、ディスク・レビュー付き版といった趣きなのですが、質・量ともに凄い! ブリティッシュ・ブルース・ロック系のサウンドを堪能する上では是非一冊手許に置いておきたい優れものとして強く推したいと思います。
というわけで今回はこの「ブルース・ロック・アンソロジー:ブリティッシュ編」掲載アーティストからいくつか拾っていきたいと思います。まずはTruth。Themがらみのバンドです。Themはメンバー・チェンジの多かったバンドで、ご存知のように後にTrader Horn、ソロで活躍するジャッキー・マコーリー、Camelを結成するピーター・バーデンス、Tasteのドラマーとなるジョン・ウイルソンといった後に有名になるメンバーが入れ替わり立ち替わり参加。Thin Lizzy初期のギタリスト、エリック・ベルも一時関係があったと言われています。まぁ、Themのメンバーで最も有名なのはヴァン・モリソンなわけですがね。1966年のUSツアー後バンド活動は停滞し、ヴァン・モリソン、アラン・ヘンダーソンはアイルランドのベルファーストで細々と活動を続けるものの、モリソンがソロに転身。USツアー時のメンバーに新ヴォーカリスト、ケン・マクドウェルを加えキャピトル参加のタワー・レーベル(Pink Floydの初期作品もアメリカではここから出ていましたね)作品を発表しますが、成功を収めるには至らず、1968年には消滅状態となります。Them解散時のメンバー、マクドウェルらを中心にシカゴに拠点を移して結成されたのがTruthでした。
Themというとヴァン・モリソンの強烈に男臭いR&Bタイプのヴォーカルをフィーチュアしたアグレッシヴなサウンドを誰もが想起すると思いますが、マクドウェル参加後の後期Themは当時のアメリカのトレンドを取り込み、サイケデリック・サウンド路線に変化していました。Truthもその延長線上にあり、実際、後期Themのナンバーの焼き直し等が収められており、ブルース、R&Bというよりも、浮遊感が魅力のサイケデリック・サウンドとなっています。
サイケデリックと言ってもスタイルは様々で、欧米ではファズ・ギターが暴れまくるガレージ・ロック・タイプのものが人気ですが、Truthはもう少しメローな雰囲気のどこかジャム・バンド・スタイルにも通じるテイストを持っていました。そのメロディアスでどこかフォギーなメロディ・ラインはLoveのブライアン・マクリーンが作った曲にもちょっと似た、ムーディな曲もあり、軽くダウナーな音楽性はかなり完成度が高いと思います。アメリカのバンドがこういうサウンドを作ると、どよーんとした雰囲気になりがちなのですが、このTruthは演奏がどこまでも律儀。ジャム・バンド的な延々と繰り返されるベース・ラインの上で展開されるソロも淀みなく、いかにも英国的なサイケデリック・サウンドが堪能できます。長めの曲とか聴くと初期Camelのアーカイヴ・ライヴ等に収録されているインスト曲やManのインスト・パートに通じるものもあります。シタールが飛び交うラーガ・ロック・スタイルの曲もやっぱり端正な作りで英国然としたそのサウンドはブリティッシュ・ロック好きにはかなりアピールするのではないかと思いますね。
Castles In The Sand
サイケデリックといえば、Mighty Babyのマーティン・ストーンも個人的は外せません。Rolling Stonesがやったヤツより個人的なはるかに好きな「Harlem Shuffle」をレコーディングしたブリティッシュ・ビート系名バンド、The Actionの後期メンバーとして加入。その後The Actionは時代の流れを汲みMighty Babyへと発展していきます。これも前出のTruth同様、アメリカ西海岸のゆったりと流れるサイケデリック・サウンドの影響を受け、独特のダウナー感を持った黎明期プログレ・サウンドは今も人気が高く、アナログ・コレクターにとって本作の英Head原盤は高嶺の花となっています。僕は’80年代の初頭に西新宿で入手しました。その頃から既にレア盤として知られていましたが、その時はまだ1万円以内で買えました。今じゃ夢見たいな話ですが・・。1stアルバムに於けるMighty Babyのサウンドは、例えばEyes Of Blueといったビート系からサイケデリックの洗礼を受けプログレっぽいサウンドに変化していったバンドと近いものがありますが、Mighty Babyがそうした当時はいくらでもあったバンドと趣を異にしている点は圧倒的な地下室感、アンダーグラウンド感覚だったように思います。虚ろな空気感とでも言いましょうか。この感覚はマーティン・ストーンが持ち込んだものとみて間違いないでしょう。Mighty Babyは1st同様、Headレーベルから2ndを出す予定でしたが、レーベル閉鎖に伴い、契約が宙に浮き、業界の知り合いのアーティストたちのバック・バンドを担当し、何とかバンドを存続させることになります。前回の犬ものでカケレコの佐藤さんが僕の印象に残る犬ものはこれです、と原稿受け取りの返信メールであげてくれたアンディ・ロバーツの『Home Grown』、シェラ・マクドナルド『Album』を始め、The Actionのヴォーカルだったレグ・キング、キース・クリスマス、ゲイリー・ファー、ロビン・スコット(その後、Mと名乗りテクノ・ポップ屈指の大ヒット「Pop Music」を放ちます)らのレコーディングに参加。その後1971年にストーン旧知のマイク・ヴァーノンのブルー・ホライゾンから2ndアルバム『Jug Of Love』を発表します。英国のGrateful Deadとも評されるこの2ndアルバムもブルー・ホライゾンがCBSから配給を移したポリドールのサポート体制が弱く、オリジナルはレアな作品となってしまいます。
1stがプログレ・ファンにも広く知られる作品だったこともあり、このアルバムもリイシューとしては注目を集めましたが、大体のプログレ系リスナーは1曲めを試聴して「何だ、カントリー・ロックじゃん」と早々に撤退してしまいます。ま、英国版デッドと言われたくらいですから、その傾向はあるわけですが、単にカントリー・ロックでは済まされない虚ろな美しさを秘め、このバンド固有のサウンドとコーラスの美しさと淀みなく不思議な透明感を持つ演奏が印象的な楽曲が連なっていることが意外と知られていないのは残念に思います。
で、マーティン・ストーンなわけですが、ここで紹介したいのは1969年に彼がセッション参加したアルバム『Southern Comfort』です。黒人ブルースメンと英国のロック・アーティストが共演する’60年代後半から’70年台前半にかけブームとなったブルース・ジャムの括りに入る一枚で、印象的にはFleetwood Macの『Blues Jam At Chess』の緩めヴァージョンといった印象です。メインの黒人ブルースメンがブルース・ハーピスト(ハーモニカ)のビッグ・ウォルター(ウォルター・シェイキー・ホートン)、バックをジェローム・アーノルド(b、Butterfield Blues Band)、ジェシー・ルイス(ds、Otis Rush Band)、ギターにストーンという編成で企画もの感ありありのブルース・セッションで、全体のテンションは決して高くないのですが、最後の1曲「Neti Neti」が凄い。それまでのブルースのりを全部チャラにする11分越えのサイケデリック・ロック・トリップ! この作品のオリジナルもMighty Babyのオリジナル盤同様かなりのレア盤で、僕はかなりアホな金額出してオリジナル盤を購入しました。Mighty Baby関連アイテムというだけで。買って帰って家で聴いていて、どんどん顔が引き攣っていったのですが、最後の「Neti Neti」で思い切り満足という脅威のサイケ・インスト曲でした。名前は有名ですが、なんとなくギタリストとしてのイメージが掴みにくく、うまいんだか下手なんだかもわからない人ですが、これは彼が残した最強の怪演だと思います。買った当時はCDなんぞになっていませんでしたが、あまりのインパクトに自分でCDRに落とし込み「凄いから聴いてみ!」と友人に配りまくっておりました。現在ではしっかりCD化されています。爆音サイケ・ロック・インストに笑いながら浸りたいという方には自信を持ってお薦めします。
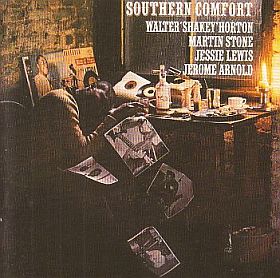
Neti Neti
マーティン・ストーンは音楽だけでなく古書のディーラーとしても知られており、オカルト関連の書籍も扱っていたことから、一時期、ジミー・ペイジとも繋がりあり、これもシンコー・ミュージックから発売されている「レッド・ツェッペリン・オーラル・ヒストリー」の中にその当時のエピソードが掲載されています。そこに掲載された証言とか読む限りはかなり変わった人だったみたいですね。
白谷くんの本をまぁ、よくここまで頑張ったと感心しながらパラパラやっております。お、ロング・ジョン・ボルドリー。この人も作品数多いですね。UA時代のR&Bシンガー、バリバリのボールドリーには当然のことながら燃えますが、ここでは’70年代に入りワーナー・ブラザーズからリリースされた2枚のアルバムを紹介したいと思います。1970年に彼のマネージャーだったビリー・ギャフが催したクリスマス・パーティでボールドリーはロッド・スチュワートとエルトン・ジョンと再会。二人ともボールドリーのバンドに短期間、在籍していたことがあり、再会を喜び、これを機にロッドの進言もあり、ワーナー・ブラザーズとの契約が成立。オリジナルLPの片面ずつをロッドとエルトンがそれぞれプロデュースするという豪華なスタイルのアルバムが生まれます。
まずは1971年発表の『It Ain’t Easy』。冒頭のブギウギ・ピアノの伴奏に合わせたトーキング・ブルース「Conditional Discharge」からバックの演奏が思い切りローリングするブギー・チューン「Don’t Try To Lay No Boogie Woogie On The King Of Rock & Roll」に切れ目なしで繋がる流れは、ロッド・スチュワートの初期ソロ作品、The Facesなんかが好きな方には堪らない展開。久々に聴き直して思わず「おぉ!かっちょええ!」と大興奮しちまいました。アルバム・タイトル曲はロン・デイヴィス作の名曲でデヴィッド・ボウイも『Ziggy Stardust』で取り上げているあの曲です。スタジオ録音なんですが、さすが’60年代からクラブ・シーンでブイブイ言わせてきたベテランだけあって、リスナーの掴み方がうまい! じんわりと沁みるちょっと鼻にかかった塩辛い声質もこの人固有の華があり、アップテンポからバラードまできっちり聴かせます。バックもエルトンを筆頭に、Hookfootのメンバー等DJM、ロケット・レーベル系ミュージシャンがきっちりとサポート。その中でも後にGMレーベルでレーベルメイトとなるレスリー・ダンカンの参加は光ります。最近、CBS、GM時代の作品が軒並みリイシューされ、再評価が進んでいる彼女のソロはどちらかというとしっとり系のヴォーカル・アルバムですが、ここでは軽快なロックン・ロールのバックで嬉々としておきゃん(死語だな)なバック・ヴォーカルをぶち込む、ソロとは違った魅力が堪能できる点も押さえておきたいポイントかと思います。

It Ain’t Easy
続く1972年の『Everything Stop For Tea』もエルトン、ロッドがプロデュースを担当。今回のバックはHookfootからデイヴィー・ジョンストン、ナイジェル・オルソンを中心とした黄金期のエルトン・ジョン・バンドが担当。アルバム前半がエルトンがプロデュース、後半をロッドが担当というスタイルです。全体の作りは前作の良いノリを継承しつつも、こちらの方は若干、スワンプ、ニューオリンズ色が強目といった印象です。ちなみに8曲めの「Mother Ain’t Dead」ではロッド・スチュワートの弾くマンドリンというのも聴くことができます。いやぁ、久々に聴きましたが、これどちらも良いですねぇ。思い切りハマりました。今回紹介の2作はどちらももちろんCD化されています。これより前の諸作品もCD化さているのですが僕は持っていなくて、LPで所有しているため、気になるのでこの週末にでも引っ張り出して聴こうと思います。
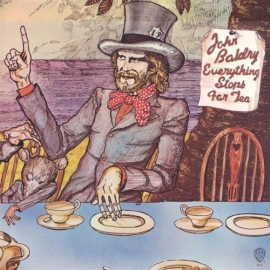
Mother Ain’t Dead
続いては、先に英ブルー・ホライゾンのCBS、ポリドール時代のアルバムをコンプリートしたと書きましたが、そのブルー・ホライゾンのLP群の中で個人的に最も好きな作品を紹介したいと思います。ダスター・ベネットの2ndアルバム『Bright Lights』です。彼のプレイスタイルはワンマン・バンド形式で、ギターを弾きながら足でバス・ドラム、シンバル等を操作しブルースを演奏します。ブルー・ホライゾンからリリースした3枚のアルバムの中では、1968年デビュー作でFleetwood Macのメンバーがレコーディングに参加した『Smiling Like I’m Happy』がジャケットも含め最も有名ですが、この2ndアルバムはレーベル・オーナーでありプロデューサーのマイク・ヴァーノンが多忙でスタジオ録音に立ち会う時間が十分に取れないという理由からライヴ録音となった背景があります。多分に妥協の産物という側面はあるのですが、それを引いてもあまりあるめちゃくちゃ良い雰囲気のライヴ盤に仕上がっており、好感が持てる内容になっています。ゲストにはThe Yardbirdsの初代ギタリストでベネットとは学生時代からの友人だった、トップ・トッパム、6弦ベースでアルバム・クレジットではピーター・ブルーと変名を使っているピーター・グリーンらが参加しています。また、デビュー作にも参加していたベネットの妻であるステラ・サットンもヴォーカルで参加。変声寸前の個性的なヴォーカルも微笑ましくかつ、ライヴの良いアクセントになっています。派手なエレクトリック・ブルースではなく、小さなクラブでのアコースティック・メインのライヴ演奏ですが、その熱量たるや大ホールでのエレクトリック・パフォーマンスに引けを取らない熱さで聴く者を圧倒します。書いてあることを読む限りなんか地味そうなライヴに思えるでしょうが、アコースティック・ギターとはいえ、ピックアップをつけて、小さなアンプを思い切りオーヴァードライヴさせて音出しをし、録音のほうも歪みぎみなため気持ち良いグルーヴ感を満喫できる一枚となっています。ブルー・ホライゾン時代のベネットの作品は『The Complete Blue Horizon Sessions』としてまとめられCD化が済んでおり、この『Bright Lights』もその中に含まれています。ダスター・ベネットはコンピレーションや未発表音源集が多数発表されており、どれも質が高いものではありますが、これから聴こうという方にはこのブルー・ホライゾン時代の全曲集をお薦めしたいですね。

今月の1枚はGroup 87。マーク・アイシャムとフランク・ザッパのバンドで活躍したパトリック・オハーンが結成したフュージョン・バンドで1980年この唯一作を発表しました。海外では一度CD化されていたのですが、買い逃し、なかなか見つからなかったのですが、ソニー・ミュージックのクロスオーバー&フュージョン1000シリーズの1枚として去年の11月に国内発売されました。マーク・アイシャムは最近では映画音楽方面で大御所感を醸し出していますが、僕は彼が’76年に参加していたジャズ・ピアニスト、アート・ランディの『Rubisa Patrol』が好きで、そのマーク・アイシャムのバンドで当時、フランク・ザッパのバンドにどえらいドラム叩く奴がいると話題になっていたテリー・ボジオが参加していたこともあり、当時購入しよく聴いていました。久々に聴いてみると、ジャズ・フュージョンの世界もやはりニューウェーヴ全盛の影響を少なからず受けていたのでしょうね、思い切り’80年代の音で、当時の聴感とはちょっと異なる印象を受けたのですが、楽しく聴かせてもらいました。当時のザッパのインスト・パートにプログレ・テイストをまぶしたかのようなサウンドです。どちらかといえば硬派なインスト・フュージョンですね。ボジオのドラミングが叩きまくりではなく、タイトに締まったトーンでグルーヴをキープする感じは後にMissing Personsを思わせるものになっています。
Moving Sidewalks
関連カテゴリー
第三十七回 関係ないけどバカヤローの日
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!