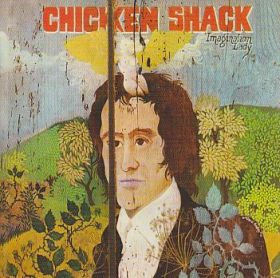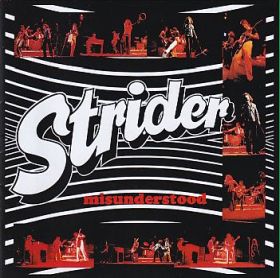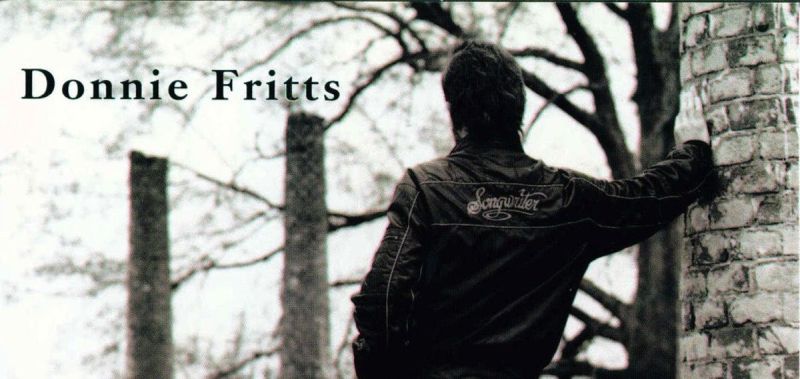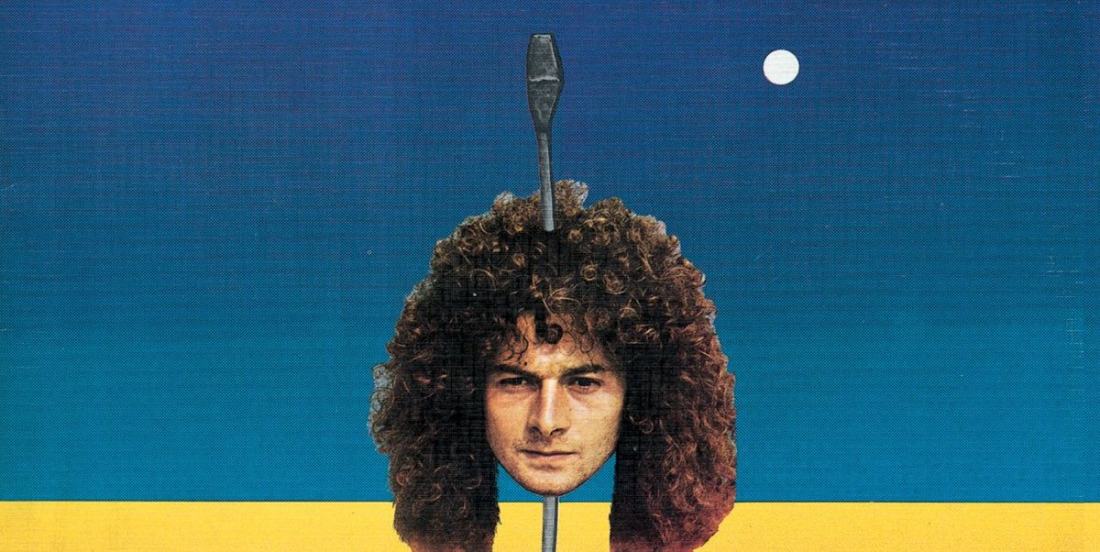「音楽歳時記」 第十三回 節分とハード・ロック 文・深民淳

「季節を分ける」ので節分。まぁ、誰でも知っていますよね。旧暦で言えばここから春が始まるわけですが、今の暦では立春と言われてもこれから冬がピークを迎えようとしているわけですから、なんだかピンと来ません。
節分行事と言えば、真っ先に思い浮かぶのが「豆まき」でしょう。宇多天皇時代に鞍馬山の鬼が都に降りてきて町を荒らすのを何とか阻止せんと祈祷をして鬼の穴を封じ、三石三升の炒り豆で鬼の目をつぶし難を逃れたという故事が今も続いているのだそうです。何となく会社でもやっていますが、年末の大掃除の時とかに「なんでこんなところに豆が落ちてんだ!」てな感じで会議室の隅の方に豆が転がっていたりして、衛生面でも問題ありそうな事態が毎度発生していたりして、豆まきは事後処理が問題多いような気がします。
毎回、バタバタとしたまま気がつけば2年目に突入してしまい、去年の暮れの一瞬、凪を迎えた数日間には「あぁ、そうだ。2年目に入るからバナーも変えたいよねぇ」とか思いつつも、ひたすら作業に明け暮れた去年の仕事でほとんど事故現場のようになってしまった自分の部屋を何とかものを崩さず歩けるようにするだけで精一杯で、気がつけば締め切りという体たらく…。話を大盛りにし過ぎなんじゃないかという方もいらっしゃるかと思いますが、今の自分の部屋の状況は、世の母親と奥さんは100%怒る壮絶なカオス状態。どのくらい凄いか写真撮って掲載してもらおうかと、一瞬思いましたが、それは恥以外何者でもないのでやめました。
さて、年明け早々締め切りに追われていたこともあり、月の半ばでありながら、既に第3週になっていることを完全に失念。てっきり来週かと思っていたので、そろそろネタを選ばないと思っていたので、まだ何も考えていなかった状態でして、時間も迫っていますので、年末にレコード、CDの部分的な整理をした際に積み上げられたCDの塔、入りきらなくなったレコードを暫定的に収めていた棚を動かし、奥の方にしまわれっぱなしだったCD、レコードを引っ張りだし移動させたものからいくつか紹介していきたいと思います。
今回、奥の方から引っ張りだしてきたのは主に、イギリス系のハード・ロック。脈略はあまりないし、テーマとどう関連しているのかが今ひとつ不明ですが、豆を投げるにはそれなりの力が必要。力と言えばやはりそこから導きだされる音楽形態はハード・ロック。と苦しい言い訳で今回はハード・ロック特集とさせていただきます。
まず、秋くらいから久々に聴きたいとずっと思っていたBEDLAM。故コージー・パウエルと元PROCOL HARUMのデイヴ・ボール(ロビン・トロワーの後任として参加。アルバム『Live With Edmonton Symphony Orchestra』に参加。アルバム『Grand Hotel』制作時に脱退。故にアートワークに写っているミック・グラバムの写真は顔だけすげ替えで体はデイヴ・ボールのものと言われている。残念ながら昨年4月に死去)、デイヴの兄弟デニス(ベース)、フランク・アイエロ(いまひとつ読みに自信なし。英語表記はFrank Aiello)の4人で結成され1973年夏にクリサリスから唯一のアルバム『Bedlam』を発表し解散したバンドです。
‘70年代英国産ハード・ロックとしてはコージー・パウエル、PROCOL HARUMのデイヴ・ボールが在籍していたことで知名度は高いし、人気もあるものの、現在では手軽に入手可能なのは2012年にエンジェル・エアー・レーベルが発売した『Live At Command 1973』くらいで、2000年代初めに立て続けに発売されたアルバム『Bedlam』、『Live In London 1973』等は軒並み廃盤となり高値がついています。2000年代初めには先の2枚の他、アンソロジー作や、BEDLAMの前身となったBIG BERTHA(COZY POWELL’S BIG BERTHA)の1970年12月のドイツ、ハンブルグ公演の発掘音源など立て続けに発表されたのですが、それももう十数年前のこととなり、以降、正規のリイシューはなくちょっと残念な状態が続いています。
ことの発端はエンジェル・エアーから発売された『Live At Command 1973』(ちなみにこれもブートレグCDで2000年代初めには流通していました)をつい買ってしまったことだったわけですが、買った瞬間は「なんだよ、ブートで出ている音源じゃん!」とがっかりしたのですが、久々に聴くと安定感のあるリズム・セクション、結構歌えるヴォーカル、そしてHUMBLE PIE時代のクレム・クレムソンにも通じる生固い引っ掛かりのあるデイヴ・ボールのブルージーなギターの絶妙な案配が気持ちよく、オリジナルのLPはすぐに取り出せたものの、CD群が奥の方にしまわれていたため、年末にようやく発掘の運びとなりました。
『Live At Command 1973』はいかにもラジオ音源といった感じの抜けの悪さは気になるものの惨いというレベルではなく、バンドのポテンシャルはきちんと伝わる1枚となっています。さて、CD群を見つけ出したかった最大の理由は、BEDLAMの前身となったBIG BERTHAのライヴ盤が聴きたかったからなのですが、これもクラブでレヴォックスのテープレコーダーで録音されたもの故、音質的には若干難がありますが、ハード・ロック時代を迎えた’70年代初頭に出たパワー・トリオとしては豪快磊落、とてつもなくパワフルな演奏が堪能できる一方、ほとんどの曲がカバーやブルース・クラシックで構成されており、抜きん出た個性という面では若干ランクが下がる印象でした。ただ、後にBEDLAMのアルバムにも収録され、元々のバンド名となっていた「Beast」はこの時には既に演奏されており、コージー・パウエルがJEFF BECK GROUPに参加していなかったら、BIG BARTHA、BEDLAMの運命ももう少し違うものになっていたのではないかと思います。結局、コージーがジェフ・ベックとの活動を始めたので、プロジェクトは宙に浮いた形となり、1972年後半に再度メンバーは合流を果たし、BIG BARTHA時代の弱点だったヴォーカル面を専任ヴォーカル獲得で強化したのですが、音楽性の基盤は既にBIG BARTHAで作り上げたものがほぼそのままだったため、アルバムが発表された1973年にはどことなく遅れてきたバンド感があったことは否めなかったというところでしょうか。
とはいえ、40年以上も経過して’70年代ブリティッシュ・ハード・ロックという大きなくくりで見た時にはこの堂々としたパワー・トリップぶりはかなり美味しい体験となることは間違いないと思います。BIG BARTHA、アルバム本体そしてCD化の際同時期に出ていた『Live In London 1973』(『Live At Command 1973』より若干音質は上で曲数も多い)の3枚は再発を望むと同時に、中古でも探す価値は大いにあると思います。
また、デイヴ・ボールはPROCOL HARUM脱退直後にロング・ジョン・ボルドリーと活動を共にしています。ボルドリーは’60年代から活躍していたR&B、ブルース・ベースのシンガーですが’70年台に入り再評価の機運が高まり、ワーナー、GMから立て続けにアルバムを発表します。ワーナーからの2枚『It Ain’t Easy』、『Everything Stop At Tea』は共にスワンプ・ムード満載のローリング系ブルース・ロックの好盤となっていますが、特に『Everything Stop At Tea』のほうは親交の深かったエルトン・ジョンとロッド・スチュワートが制作に深く関わった作品でもあり、今ならまだ新品でも購入可能ですし、FACESとか好きな方には強くお薦めします。
やっていることは凄いのに発表時期が少し遅かった、というのはこのBEDLAMに限らず色々な例はあるのですが、CHICKEN SHACKの『Imagination Lady』もそんなアルバムではないでしょうか? FLEETWOOD MACと並び英国のブルース・ロック・シーンをリードしたCHICKEN SHACKもブルー・ホライズン後期の『ACCEPT CHICKEN SHACK』あたりからハード・ロック路線へのシフト・チェンジが始まっており、デラムへ移籍した後の『UNLUCKY BOY』ではかなりヘヴィなブルース・ロック・バンドへと変貌を遂げているのですが、この『Imagination Lady』はスタン・ウェッブ版CREAMともいえるパワー・トリオによるハード・ロック・スタイルを打ち出しています。英国のブルース系ギタリストにとっては目標のひとつであったCREAMのようなパワー・トリオ。アイデアは良かったと思いますし、ベースに元TOE FAT後にCARMEN、JETHRO TULLで歴史と印象両方で強いインパクトを残したジョン・グラスコックスを配した目の付け所は秀逸だったものの、時代がもう、そういうものは過去の遺物に成り始めた時期だったこともあり、大きな成功は収めることができなかったのですが、これも今聴くと思わずにんまりする豪快なパワー・トリップぶりが堪能できます。
何より掴みの1曲目が強力! 3コードのファスト・ブルースですが、ベースは思わず指が攣りそうになるような細かいリフを徹頭徹尾貫き通し、ドラムは2バス踏みまくり、多少大げさに評するならCREAMの「Cross Roads」に匹敵する名演だと思っています。また、このアルバム、多分、クラブ興行の1ステージをなぞった形の一種の疑似ライヴ・アルバム風の作りになっている点も興味深いです。そういう設定故、ドラム・ソロはありますし、最後にみんな演奏しているドン・ニックスの「Goin’Down」が全体のバランスをあえて崩すような形で収録されていますが、これも考えれば一種のアンコールのようなものだと思えば納得がいくわけです。「Goin’Down」収録というのはスタン・ウェッブの中では同時期に活動していたもうひとつのパワー・トリオ、BECK, BOGERT & APPICEへの対抗意識というのもあったのではとも思いますね。
STRIDERも微妙な時期に出てきたバンドのひとつです。サイケデリック・ブームの終わり頃にひっそりとデビューしたSAMSON(NWOBHMのほうではなく1969年デビューのほうです)のメンバーだったキーボード奏者イアン・キューリー(SAMSONではヴォーカリスト)らが結成したハード・ロック・バンドで、’73年にGMレーベルよりアルバム『Exposed』でデビューします。GMはロッド・スチュワートを擁したマネージメント会社が経営に関与していたため、プロモーションがしっかりしており、当時、メディアでもかなり取り上げられ、注目を集めました。1st発表後、ヴォーカル面の強化を図るため、専任ヴォーカリスト、ロブ・エリオット(その昔、SECOND HANDに在籍)を加入させパワーアップして発表したのが2ndで名作の呼び声高い『Misunderstood』です。1974年発表、ちょうど、BAD COMPANYが世に出た年でハード・ロックのスタイルもタイトでソリッドなものへと変貌を遂げる時期に出てきたバンドだけあって、よくまとまっている作風には大いに好感が持てますし、ハード・ロック然としたドライヴ感も損なわれておらず’70年代前半のブリティッシュ・ハード・ロックはこういうスタイルが主流であったという好例として聴いておきたい1枚となっています。実際、カケレコでも完全に定番商品となっているようですね。未聴の方はこの機会に是非! ちなみに、音源がないので何ともいえないのですが、BABE RUTHを脱退したジェニー・ハーンが分裂寸前のSTRIDERに加入していたらしいのですが、そこは聴いてみたいですね。
STRIDERは健闘したものの大きな成功は収めることが出来ず、『Misunderstood』を最後に解散してしまいますが、イアン・キューリーはその後ガース・ワット・ロイらとよりポップでニッチなRIMEYを結成。RIMEY(これも結構良いです。からっとしたハード・ポップといった感じでしょうかね)解散後、’80年代に一世を風靡したポール・ヤングのバックバンドの主要メンバーとして活躍します。
どうも今回はあまり多く紹介できなくて申し訳ない、というわけで年末のハード・ロック集中的に聴きまくりの成果が10%ほどしか反映されていないのは悔しいので、次回もこのまま強引にハード・ロックをテーマとしたいと思います。年末に実施したのはSTRAYを全部ちゃんと聴く、STRAY DOGと関連アイテムをまとめて聴く、TASTE、STUD、AXIS POINT等TASTE由来のアイテムをきちんと聴き直す等結構集中して聴きまくった上、アメリカものもまとめて聴いたので次もハード系で行きます。鬼ですね。ほら、テーマと繋がった(どこが?)
さて、最後に今月の1枚ですが、昨年末のハード・ロック三昧の中で、聴きながら個人的に初めて聴いて最も衝撃を受けたメジャーにならなかったハード・ロック作品は何だっただろうか?と考えている時に頭に最初に浮かんだ作品がこれ! JERICHO(エリコ)です。1972年英A&Mから発表されたイスラエル出身のハード・ロック・バンド。確かカケレコでも売っていたと思います。スピード感溢れるリフの妙、ドラマティックに盛り上げていくミッドテンポ楽曲の重量感溢れるプレイの妙。どこをとっても高品質のハード・ロック・サウンドが楽しめます! 1曲目の「Ethiopia」凄いですよ! これぞハード・ロックの醍醐味といえる強力なファスト・チューンです!
関連カテゴリー
節分とハード・ロック
-
STRIDER / MISUNDERSTOOD
74年作2nd、重厚さととめどない哀愁に満ちた英ハード・ロックの大名作
英ハード・ロックの名グループ、74年作2nd。英ハード・ロックの名作1stに続き、こちら2ndもずばり名作!元SECOND HANDのRob Elliott(Vo)、英ロック界の名ドラマーTony Brockが新加入。ヌケの良いハイトーンヴォイスとズシリと重いリズム隊により、サウンドはさらにエッジと厚みを増しています。スリリングかつ粘りのあるギター、英国らしい叙情性溢れるピアノ&キーボードは1stから変わらず魅力的。ハード・ロック・ファン必聴!名作です!
-
盤質:無傷/小傷
状態:良好
若干スレあり
-
STRIDER / EXPOSED
73年リリース、腰が抜けるほどに格好良すぎる英ハードの名作!
英ハード・ロック・グループ、73年作の1st。エッジの立ったキレ味抜群のギター、リズミックで叙情性溢れるピアノ、力強いシャウト・ヴォーカル、コシのあるリズム。これは文句なしに格好良いです。ピアノが美しく響く引きの部分から、左チャンネルにギターがテンション溢れるフレーズで切れ込んでくるのを合図に全パートが一体となって畳みかけ、シャウト・ヴォーカルが仁王立つ。鳥肌ものの格好良さ。圧倒的な存在感です。ハード・ロック・ファン必聴の名作。
-
JERICHO / JERICHO
イスラエルを代表するハード・ロック・グループ、72年作、本場英国の名作群にも引けを取らないハード・ロック史上に残るべき傑作!
イスラエル出身、60年代に後半に活躍したCHURCHILLSを前身に、JERICHO JONESと改名してイギリスに渡ってアルバムをリリースした後、さらにバンド名を短くJERICHOと改名。72年にリリースしたイスラエルが誇るヘヴィ・プログレ/ハードの逸品。エッジのたったトーンでスピーディーに畳みかけるギター・リフが引っ張るアグレッシヴなサウンドが持ち味。痺れるキメのリズム・チェンジなど、自由自在のアンサンブルはさすがイスラエル・ハードNo1グループ。炸裂するシャウト・ヴォーカルも素晴らしい。英国のハード・ロック名作にも一歩も引けを取らないハード・ロック史上に残る傑作。
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!