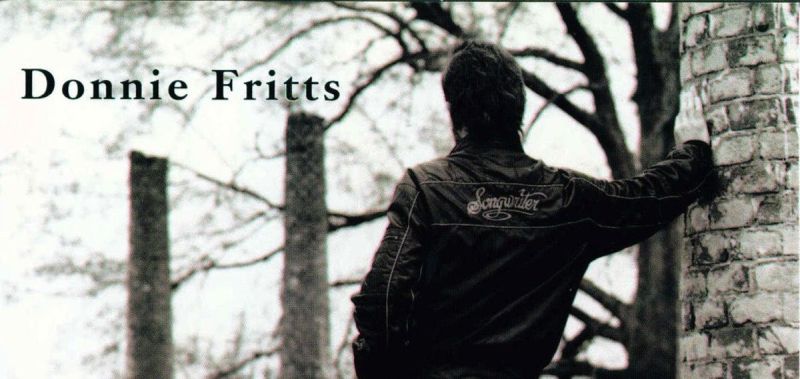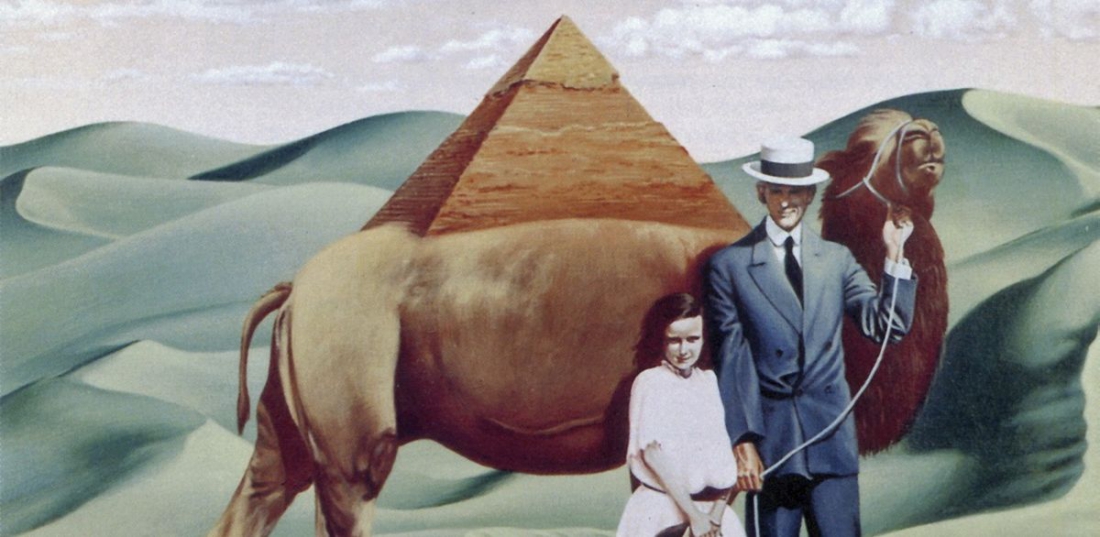「音楽歳時記」 第二十七回 4月 やっぱり花見でしょうか? 文・深民淳

いつものごとくギリギリのスケジュールで書いております。この時期は毎年そうですが、春めいてきたなぁ、と思った翌日がほとんど真冬日だったり、天候面では概ね良好ながら寒暖差は激しく、その寒暖差のせいもあるのか気分も上がったり下がったり。なんだか落ち着かない日々が続きます。そんな時期ですので今年も全国の桜の開花予想をあちらこちらで眼にしたり、耳にしたりするようになりました。僕なんかは毎年のごとくで「ふ〜ん」と聞き流していますが、開花予想をTVの天気予報で見ると気もそぞろって方も多いかと思います。
うちの犬のボンゾくんの週末の長い散歩コースに紅梅・白梅が両方植えられているところがあり、2月から3月にかけて見頃を迎えます。紅梅・白梅は同時に咲くのではなくそれぞれ微妙に開花時期がずれるのですが、それでも2週間くらいは紅・白両方が楽しめる期間があり、毎年楽しみにしています。梅の花も桜に劣らず美しく、だいたい枝振りがさぁ、ロジャー・ディーンの世界で描かれている樹木みたいで良いじゃん!と思うのですが、梅見で日本中狂乱!というのはなんでないのだろう? と、しばし考え、自分の馬鹿さ加減に気づく。
それは、寒いからでしょ。熱燗も10分で冷酒になってしまう気温の中、それでも完全防寒で楽しく盛り上ろう、ってそりゃ無理。やっぱり花見は桜である、と。
無難にまとめちゃったねぇ。でも実際には梅と桜の時期の寒暖差はそんな劇的に違うのかよと正直思います。確かに日中の気温は梅の季節と比べれば暖かく、だからこそ桜が開花するわけです。でも夜桜の下で盛り上がる花見客って、ほとんど防寒対策万全、熱燗は13分以内飲まないと冷酒だよ〜!程度の違い。実際、夜はまだ十分に寒い。日中の日差しは強くなっても地面はまだ温まっていないため1日のうちの寒暖差はまだまだ大きい時期です。それでも都内の花見スポットでは夜半まで狂乱の宴が繰り広げられているわけです。なんでなんだろう?
古の昔から日本人の遺伝子の中に埋め込まれたスイッチがOnになっちゃうんでしょうね。海の民もいれば山の民もいる、日本にも様々な生活基盤があるにせよ、古くから農耕を主とした生業にしてきた日本人にとってこの時期は一年を賄う生活の糧を得るための本格的な作業の始まり。生活の暦の上ではまさに新しい一年の始まり、気温はそう変わらなくても、もはや冬は終わり春である、と。心の持ち方が違うのでしょう。桜はその象徴のようなものであり、梅は冬のモノトーンの世界に彩りを添え、春が近いことを知らせる「萌」(きざし)なのでしょう。というわけで、今回は花にまつわる作品を取り上げてまいります。
以前1973年の日本公演のライヴ・アルバム『Twin Peaks』を取り上げたことがあるMOUNTAINのオフィシャル・リリースとして初のライヴ音源を収録した作品が3作目にあたる『Flowers Of Evil』(1971年)でした。前年に発表した『Nantucket Sleighride』のヒットを受け登り調子の中発表された作品でした。『Nantucket Sleighride』収録の表題曲は世界十大小説のひとつにも数えられているハーマン・メルヴィルの『白鯨』(因みに現在も使われている原題は米国版由来の『Moby-Dick; or The White Whale』ですが最初はWhiteがなかったそうで。故ジョン・ボーナムのドラム・ソロでお馴染み、LED ZEPPELINの「Moby Dick」はここから)でこれが「Mississippi Queen」、「Theme For An Imaginary Western」と並ぶ代表曲となり、大きな注目を集める中のリリースとなりました。
Flowers Of Evil
日本の邦題は『マウンテン・ライヴ悪の華』原題・邦題からシャルル・ピエール・ボードレールの詩集『悪の華』(因みにボードレールはフランス人なので原題は『Les Fleurs du mal』)を想起させるが、前作でメルヴィル『白鯨』を曲のモチーフとしたことで、思わぬ反響があったことからここでも文学的なキーワードを配置したといったイメージで、ボードレールとの因果関係は薄いように思います。実際、タイトル曲はベトナム戦争における従軍した兵士たちの麻薬禍について歌われたもの。ただ麻薬がもたらす退廃的なイメージはどこかリンクしているかも。しかし、よく考えると初っ端から花じゃなくて麻薬はないよなぁ。
このアルバム、後に再結成はするものの、オリジナルMOUNTAINのスタジオ録音入り作品としては最後の作品となります。『Nantucket Sleighride』がヒットしたため大きな期待がかかったものの、チャート的には前作には及ばずに終わっています。内容を追っていくとオリジナルのアナログはA面が1971年9月NYレコード・プラント・スタジオ録音のマテリアル、B面が1971年6月27日NYフィルモア・イーストでのライヴ録音となっており、両面合わせた収録時間が50分越え、特にB面のライヴは29分弱という当時のLPとしては異例の長尺収録となっていました。『Nantucket Sleighride』のヒットにより彼らのライヴに対する期待感が大きかったという点は影響しているのでしょうが、その後最初の解散が起きることを考えるとバンド内の事情みたいなものも関係していたのかもしれません。今ふと頭に浮かびましたが、この作りってフェリックス・パパラルディが関わっていたCREAMの『Goodbye』とA面、B面の構成が反対ですが同じ作りだねぇ。意味深ですねぇ。
さて、スタジオ録音のほうは良い曲はあるんですよ、CREAMのプロデューサーとして活躍したパパラルディがリフ一発のインパクトを徹底的に磨き上げたリフ職人としての名人芸はここでも遺憾なく発揮されていますが、どこか後ろ向きというか、前作に収録されていた曲がバックに見えてしまう点がちょっと苦しい。両方聴くと、これはあれ、みたいなものがすぐに判ってしまうのが難点。ただ、スタジオ録音ならではの凝った作りの「Pride And Passion」や日本のFRIED EGGがメイン・リフをそのまま「Rollin’ Down The Broadway」で流用した「Crossroader」(タイトルはCREAMの「Crossroad」を想起させるしリフは同じく「Politician」を分解再構成したみたいな曲ですが)など印象的な曲はありますが、前作を越え突き抜けたという印象は正直ないというのが正味のところです。
ライヴのほうは29分弱もあるのにトラック的にはたったの2曲。ラストに鉄板の人気曲「Mississippi Queen」のライヴが収録されているものの、うち約25分は「Dream Sequence」と題されたメドレー形式のナンバー。内容を明記しておくと「Guitar Solo ~ Roll Over Beethoven ~ Dreams Of Milk And Honey ~ Variations ~ Swan Theme」となっており、全体の6〜7割がインプロヴィゼーションというおよそ普遍性には欠けた内容ながら、インプロヴィゼーションにおけるパパラルディの差配のうまさを再発見しました。
ことのきっかけは1月くらいにWEST, BRUCE & LAINGがマイ・ブームとなり、ネットで聴けるライヴ音源を次々と聴きまくったのですが、このバンド、出来が悪い日のライヴはすべった日のCREAMを遥かに凌ぐグダグダぶり。リズム・セクションの足並みが全く揃わず、レスリー・ウエスト途方に暮れるというライヴが結構ありまして。この原因は何処かと考えるとやはりジャック・ブルースのように思います。コーキー・レイングのドラムは手数も多く豪快なのですが、一方でかなり荒っぽい側面もある人で要するにこの特性を活かすためにはコントロールが必要なわけです。ジャック・ブルース、コントロールしないんだよね。根っからの俺様体質と言いましょうか、とにかく押しが強く、レイングもそこに真っ向から向かっていくので、リズム・セクションのグルーヴ自体が怪しくなるし、ギタリストに気持ち良く弾かせてやろうという配慮がまったく見受けられない事態となります。こうなるとウエストも手癖、指癖で無難に弾いて終わるという聴きどころがつかめない演奏で、なんじゃこりゃ、というライヴが結構ありました。
それらと比較するとパパラルディはレイングのみならず全体のコントロールが本当に巧み! インプロヴィゼーションを展開させる場面では必ずベースが一種、テーマのようなフレーズを提示してまずドラムを安定させる、リズムが安定したところでウエストを焚きつけるべく、その時のキー、コード内でリズム・セクションが煽り山場をしっかりと作り出す。メドレーの最後に「Swan Theme」という曲のパートがあります。このリフはスタジオ面に収録されている「One Last Cold Kiss」の後半に使われるリフなのですが、曲の歌詞がつがいの白鳥の一羽が猟師に撃たれ死んでしまうという内容から「Swan Theme」というタイトルになったのですが、「Variations」から「Swan Theme」に至る一連の流れは淀みなく、このバンドの特性を端的に提示しており聞いておく価値ある名演だと思います。昔から長ったらしいインプロヴィゼーションで華がないとか言われておりますが、僕はしっかり花咲かしていると思いますよ。
え〜、花の話でした。GRATEFUL DEADに「Sugar Magnolia」という曲があります。マグノリアは日本で言うところのモクレンです。春の訪れとともに香り立つ白い花は東京でもよく目にします。さて、「Sugar Magnolia」、このオリジナルは1970年発表の『American Beauty』に収録されていました。DEADというと、よく耳にする歌声は、ヘニャヘニャの鼻歌みたいなジェリー・ガルシアが歌っている曲が多いのですが、これはもう一人のギター&ヴォーカル、ボブ・ウィアーが書いた曲なので、彼が歌っています。ジェリーに比べるとこちらはもうチョイ声が低く、ちょっとモゴモゴ感ありといった感じです。
高校生の時初めて買ったDEADのライヴ・アルバム『Europe ‘72』にも収録されており、よく聴きました。まぁ、実際はあの白地に虹とワーク・ブーツ、頭にソフト・クリームくっつけているガキンチョのイラストのインパクトが強烈でLP3枚組という値の張る商品でしたが衝動買いしました。最初はよく分からなかったですね、何が面白いんだか。当時、日本のはちみつぱいが好きで、彼らの音楽がDEADからの影響大という話を伝え聞き、それもあって買ったのですが、最初は全然いいと思わなかったです。それでも高い金出して買ったアルバムということで聴き続けるうちにまずこの曲が好きなり、一個きっかけができると後は簡単。今でもドカドカ出るライヴ・シリーズ(現在はDave’s Picksシリーズが年間4作品発売)やボックス・セット(DEADのボックスはどれも凝った作りでパッケージ見ているだけで楽しいですよ、興味があったら一度彼らのオフィシャルHP覗いてみてください)にも入れ食い状態で食いつくコテコテのファンとなり現在に至っています。
Sugar Magnolia
曲自体はとりわけ目立った特徴があるわけではない、一聴した限り開放感溢れるオーセンティックなアメリカン・ロック。でも何度か聴いているうちに妙に頭に残り、いつの間にか好きになっている、そんな感じの曲です。DEADこういう曲多いですね。因みにこの「Sugar Magnolia」、最も知られているDEADナンバーの一つにも数えられており、ジェリー・ガルシアが亡くなり、DEADの活動が停止するまでコンスタントに続けられたツアーの定番ナンバーとして親しまれてきました。
普段プログレとか聴いている人たちからは捉えどころがないバンドという印象なのでしょうが、風の中に舞う羽のよう、と形容されたジェリー・ガルシアの音符が湧き出してくるかのような淀みないギター・ソロ、そしてその澄み切ったトーンは結構刺さると思うのですが。
アメリカン・ロックから遠いところにいる人たちからDEAD聴いてみたい、と聞かれる時、僕は1975年発表の『Blues For Allah』を薦めています。赤いローブを纏った骸骨がヴァイオリンを弾いている緻密なイラストのアートワークはきっとどこかで一度は目にしていると思います。僕自身、高校時代にYESやPINK FLOYDを聴くのと同じ感覚で楽しんでいました。機会があればアルバム冒頭の「Help On The Way/Slipknot!」から「Franklin’s Tower」へ至る流れはかなりインパクト強いと思います。曲自体はこんこんと湧きだす泉のごとく流れていき、強烈なフックやまさかの転調とは無縁なんですがね。
Help On The Way/Slipknot!
また、花つながりではこの『Blues For Allah』に続いて発表された『From The Mars Hotel』にも「Scarlet Begonias」という曲があります。ベゴニアも花屋さんとかでよく見かける日本でもポピュラーな花ですね。タイトル通り、真紅、薄紫、黄色など鮮やかな色彩で咲き誇る花です。
さっきから桜で何かなかったかなぁ、と考えていますが、なかなか思いつきません。桜の木だったらGENESISが1978年に発表した『…And Then There Were Three…』収録の「Scenes From A Night’s Dream」の歌詞の中に、桜の木を切ったジョージ・ワシントンの話が出てきたなぁ、と。この曲、元々は1900年代初頭にアメリカの新聞に連載されていたウインザー・マッケイ作のコミックのエピソードを歌ったもの。日本でも1976か77年にパルコ出版から連載をコンパイルした立派な本が出て、当時とあのレトロ・モダンな美しい絵が素晴らしく衝動買いした記憶があります。う〜ん、あんまり関係ないねぇ。桜の花はCherry Blossom…あ〜、なんか歌詞に出てきたのあったなぁ、なんだっけと考えていて、ようやく思い出したのがこれ。THE TUBES、1981年発表『The Completion Backward Principle』、そうです、あの青バックに白いT字型のパイプ(チューブ)が浮いているアートワークのやつです。この中の「Sushi Girl」の中に出てきたなぁ、Cherry Blossom…。従来の危ないイメージを脱ぎ捨て、明るくポップなAORハード・ポップ路線に鞍替えした最初のアルバムに入っていた曲。作りは悪くないし、曲も元々、メロディとかはしっかりしたバンドだったのでソリッドなハード・ポップになっても、その特性は十分活かされていましたが、なにもTHE TUBESがこれやらなくても良いじゃん!と当時は思いましたね。これ書いていて聴きなおしてみたら、良い感じに聴こえたわけですが、この「Sushi Girl」はやはり、今聴いても日本人の僕には座っていてムズムズする感覚があります。だいたい「桜の花とごはん」って歌詞はなんなんでしょうかね。
Scenes From A Night’s Dream
Sushi Girl
アカシアも春の花なんですよね。THE EAGLESの『One Of These Nights』の「Hollywood Waltz」では冒頭「春にはアカシアが咲いて…」と歌われています。
バラはどうだろう? これは色とりどりですね。白はキャット・スティーヴンス、黒はTHINLIZZY、赤はTHE WINGS『Red Rose Speedway』他多数。黄色はHERON。この間の来日時にも演奏されていました。それで思い出したのが、THE BLUE ROSE。1971年にアメリカのEPICからアルバム1枚出したきりだと思います。青いバラは当時は作り出せないと言われていたと思うのですが、今はあるみたいですねぇ。よく知らないけど。で、そのTHE BLUE ROSEなんですが、このバンド自体はご存知なくても、彼らの代表曲とその中心人物の名前には覚えがあるのではないかと思います。THE BLUE ROSEの代表曲のタイトルは「My Impersonal Life」。1971年に発表されたアルバム『The Blue Rose』にももちろん収録されていますが、同年、THEREE DOG NIGHTがアルバム『Harmony』でこの曲を取り上げています。『Harmony』は「An Old Fashioned Love Song」、「Never Been To Spain」の2大ヒット曲が収録された作品で、その前年に発表し「Joy To The World」のメガ・ヒットを生んだ『Naturally』と共にTHEREE DOG NIGHT全盛期を作り上げた作品でしたが、このアルバムに「My Impersonal Life」は収録されています。「Never Been To Spain」と「An Old Fashioned Love Song」に挟まれる形で。この曲の作者はテリー・ファーロング。あ、分かった、という方もいるでしょう。THE GRASS ROOTSのギタリストだった人です。THE BLUE ROSEはそのファーロングのバンドだったわけです。結局、これ一枚で短命に終わってしまったようですが、曲は今も結構鮮明に覚えています。THEREE DOG NIGHTヴァージョンだと歪んだオルガンのイントロから始まる、重厚ながらこの当時のヒット・ポップスらしいメロディがしっかり立った好楽曲でした。
My Impersonal Life
My Impersonal Life(Thee Dog Night)
今月の1枚はREDBONEで行こうかと。REDBONEは’60年代末にネイティヴ・アメリカンとメキシコの血を引くパットとロリーのヴェガス兄弟を中心に結成されたバンドで1970年発表(1969年説もあり)のアルバム『Redbone』でデビュー。R&B、カントリー、ケイジャン、ロック、ファンクが混じり合ったサウンドで人気を博したバンドでした。当時のプロモやライヴ写真などを見るとインディアンの衣装や羽根飾りをつけ、ネイティヴ・アメリカンの血が入ったバンドであることを前面に打ち出していました。コンスタントにアルバムを発表していましたが、1973年に発表した5作目のアルバム『Wovoka』からシングル・カットされた「Come And Get Your Love」が全米チャート5位まで上昇するビッグ・ヒットとなり一躍有名になりました。なんだかのほほんとしたとぼけた味わいのポップ・ロックで最初は変な曲と思いつつも何回か聴くうちにはまってしまう不思議な魅力を秘めたナンバーでした。この「Come And Get Your Love」をメインにしたベスト盤、その曲が収録されたオリジナル・アルバム『Wovoka』、最近再発された1stアルバムは比較的容易に入手可能だったのですが、その他のアルバムが結構手に入りにくく、探していましたが、この度、1970年の『Potlatch』、1971年のロック・アルバムとしてはこれが一番と個人的には思っている『Message From A Drum』、ちょっと飛んで1977年EPICからRCAに移籍して発表された『Cycles』の3枚がワンパッケージに収められたCDがめでたく発売の運びとなりましたので、紹介させていただきました。

Come And Get Your Love
関連カテゴリー
「音楽歳時記」 第二十七回 4月 やっぱり花見でしょうか?
-
GENESIS / AND THEN THERE WERE THREE
80年代へと繋がるポップ・センスが発揮され始めた78年作、ヒットチューン「Follow You Follow Me」収録
KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1978年に発表された9枚目のスタジオ・アルバム『そして3人が残った』は、ギタリストSteve Hackettが脱退しPhil Collins、Mike Rutherford、Tony Banksの3人編成となったGENESISの初めてのスタジオ・アルバム。新たなギタリストは加入せず、Mike Rutherfordがギタリストも兼任(ライブではギタリストDaryl Stuermerがサポート)するスタイルとなっています。収録曲数が増加(11曲)し、各曲の演奏時間がコンパクトにまとめられていることからも分かる通り、プログレッシヴ・ロックの成分を残しながらポップ化に向けて舵を切ったアルバムと言えるでしょう。本作は全英アルバム・チャートに32週チャート・イン(最高3位)する好記録を打ち立て、また、シングル・カットされた「フォロー・ユー・フォロー・ミー」は全英シングル・チャート7位に輝きました。
-
GRATEFUL DEAD / AMERICAN BEAUTY
ガルシアの原点であるルーツ・ミュージック路線に回帰したカントリー・ロック永遠の名作、70年発表
70年発表のスタジオ5作目。グレイトフル・デッドと言うと、長尺のギター・ソロをフィーチャーしたサイケデリック・ロックというイメージですが、本作で聴けるのは、美しすぎるメロディとハーモニー、しなやかで哀愁溢れるアンサンブルが印象的なアメリカン・フォーク・ロック。1曲目「BOX OF RAIN」が奇跡のように素晴らしく、憂いのある美しすぎるメロディ、心に染みるコーラス、メロディアスなギターは、何度聴いても感動的。NEIL YOUNG、CSN&Yあたりのフォーク・ロックのファン、WILCOなどの90年代以降オルタナ・カントリーのファンも間違い無く気に入るでしょう。アメリカン・ロック永遠の名作。
-
定価1700+税
盤質:傷あり
状態:良好
帯無
帯無、黄ばみあり、トレーに黄ばみあり
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!