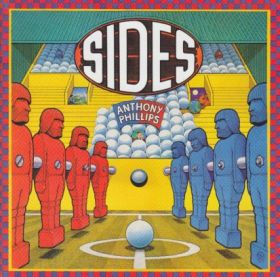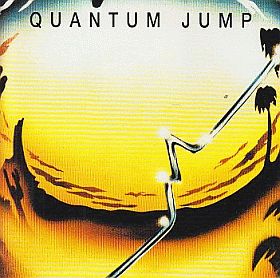「音楽歳時記」 第五十六回 9月16日 マッチの日 文・深民淳

遅れまして申し訳ありません。2週間遅れました。夏風邪をひき体調を崩したのが原因です。締め切り前までに3600字。CAFÉ JACQUESの1stまで書いておりましたが、そこで倒れました。復調後続きを書いたものですが、書き出し等倒れる前のものを修正せずそのままにしてあります。よって、イントロ部分の時制の一致が怪しくなっておりますが、ご了承ください。
この原稿を書いている時点では台風10号上陸中。飛行機・鉄道は軒並み欠航・運休だらけ。関東エリアからはまだ大分遠くにいますが、大型台風のためその影響はあり、いきなりドシャ降りになったと思ったら一時間後には晴天、気がつくとまた雨がという目紛しい天候に閉口しております。まぁ、暦の上では既に夏真っ盛りとは言えない時期なのですが、実際に体感上は8月のほうがヘヴィな印象が強く、まぁ、この暑さは我慢するしかないよね、と思うんですが、今年は湿度がえらいことになっているような気がします。統計上は過去の平均から大きく逸脱していることはないのでしょうが、今年は肌寒かった7月前半から一転、蒸し焼きオーブン状態。これはかなりこたえました。冷凍肉がいきなりオーブンに放り込まれたかのような印象です。音楽聴くのすらかったるい、脱力モードに突入しております。
しかし、暑さというのは音楽ソフトの売り上げに影響を及ぼすものなのでしょうか?
さて、9月16日『マッチの日』というのがあります。数字見た限り語呂合わせではないので読んでみると、1948年(昭和23年)それまで配給制だったマッチの自由販売が解禁されたのを記念しているそうです。戦後の物資が不足していた時代、マッチも配給制だったんですねぇ。皆さんが一般的に知っている箱の側面(ブックタイプのやつは表か裏に帯状についているやすり部分)で擦って点火するマッチは安全マッチと呼ばれていますがこれは1879年(明治12年)から国内で製造されるようになり、品質が高かったこともあり、かなり大量に輸出されたそうです。大昔、雑誌か何かの記事で読んで記憶が曖昧なんですが、マッチって店や商品の販促目的で作られたものが多く、様々なデザインのものがあり、コレクタブルなのですが、ヴィンテージのマッチ・コレクターの話として、海外で売られたり、配られたりしたデザインが魅力的なマッチの多くが実はメイド・イン・ジャパンだったというのがありました。
さて、マッチ・デザインのアートワーク、結構あったように思いますが、ぱっと思いついたのはBRONCOの3rdアルバム『Smoking Mixture』、ボブ・ジェームス&アール・クルーの『One On One』。『バナナの日』の回で作品について書かなくても普通、最初に出てくるというか、バナナのアートワークでは最も有名なVELVET UNDERGROUNDの1stをすっ飛ばした前科者なので、このマッチに関しても、普通誰でも思いつくのはそれでしょ、というのを飛ばしているように思えてなりません。なんかもっと普遍的なものがあったように思えてなりませんが、浮かびません。
さて、マッチで思い出した曲はこれでした。と言いますか、あの効果音が鮮明に頭の中で鳴りました。CAFÉ JACQUESの1st『Round The Back』の収録曲、「Farewell My Lovely」です。この曲タイトルはレイモンド・チャンドラー作の私立探偵フィリップ・マーロウを主人公としたシリーズで最も有名な『さらば愛しき女よ』の原題でもあります。映画化もされていますね。曲自体、フィルム・ノワール、ホードボイルド・ディテクティヴ・ストーリーの世界を彷彿とさせるもので、この曲のイントロ部分で効果音として(タバコを吸うために)マッチを擦って火をつける音が収録されています。曲タイトルから受ける印象でホードボイルドっぽい雰囲気なんだろうというのは容易に想像がつきますし、それだったら小道具としてはタバコやウイスキーというのもすぐに浮かんでくるので、イントロの演奏をバックに何かの摩擦音と勢いよく何かが燃え上がる音はマッチを擦ってタバコに火をつける音と判るのですが、無音状態でマッチをする音から曲がスタートするのではなく、音楽バックで流れる効果音をそれらしく聴かせるのは結構難しい作業です。でもこの曲における効果音、良い音で録られています。曲の背景を知らなくてもすぐにマッチを擦る音と判ります。まぁ、僕の個人的な意見ではありますが、この『Round The Back』の真髄がよく出た場面だと思います。アルバム全体、無駄がなく一音一音が吟味されたプロ仕様のブリティッシュ・ロックという印象です。効果音のマッチ擦る音にもプロの拘りを感じます。
Farewell My Lovely
CAFÉ JACQUESはスコットランド、エジンバラの出身で1977年に1stアルバム『Round The Back』を発表する時点では3人組になっていましたが初期は7人編成のバンドだったそうです。デビュー時のメンバーはクリス・トンプソン(vo、g)、ピーター・べイチ(kbds、violin、accordion、後にPENGUIN CAFÉ ORCHESTRAに加入)、マイク・オグルツリー(ds、vo、黒人メンバー。後にFICTION FACTORYに加入、SIMPLE MINDS『New GoldDream(81-82-83-84)』に参加)。デビュー作『Round The Back』はプロデューサーにルパート・ハイン、ベースにジョンG.ペリー、ジェフリー・リチャードソン(viola、flute、clarinet、CARAVAN1973年『For Girls Who Grow Plump In The Night』から1980年『The Album』までのメンバー。CARAVANの後はPENGUIN CAFÉ ORCHESTRAに加入)、フィル・コリンズ(GENESIS、BRAND X。本作にはパーカッションで4曲参加。『Round The Back』の英国盤初期プレスには彼が参加している旨が明記されたステッカーが貼ってあった。そのステッカーは一定の効果があったと思う。僕は全然知らないバンドだったけどリリースされた直後にフィル・コリンズに惹かれて購入したわけだし・・・)
今見ても十分魅力的な錚々たるメンバーが参加していますね。サウンドの傾向はプログレッシヴ・ロック通過型で後にAORに集約されていくキーボード主体のポップなプログレ・タイプ。クリス・トンプソンの塩辛声のヴォーカルを活かした、ポップでメロディアスなんだけど浮ついたところがない燻し銀の楽曲が光ります。
プロデューサーのルパート・ハインは緻密でクールな音作りでハワード・ジョーンズ、ボブ・ゲルドフ、ケヴィン・エアーズ、FIXX、THOMPSON TWINS、RUSH、SAGA、スティヴィー・ニックスらのプロデューサーとして一世を風靡する存在となりますが、この時期はパープル・レーベルから2枚のソロ・アルバムを発表した後、ベースで参加のジョンG.ペリーとQUANTUM JUMPを結成し活動していた時期で前年の1976年に1st、CAFÉ JACQUESのプロデュースを担当した1977年に2nd『Barracuda』を発表する時期。プロデューサーとしては’70年代前半に所属していたパープル・レーベル時代に同レーベルと契約したイヴォンヌ・エリマンの2ndアルバム『Food Of Love』(1973年)あたりからスタートし、’74年にJONESYの3rd『Growing』、ケヴィン・エアーズの『The Confessions Of Dr. Dream And Other Stories / 夢博士の告白』、ジョンG.ペリー『Sunset Wading』(1975年)、『Seabird』(1976年)、デイヴ・グリーンスレイド『Cactus Choir』(1976年)、NOVA『Blink』を手がけこちらのほうも軌道に乗り始めた時期でした。因みにCAFÉ JACQUESデビューと同じ1977年の他のプロデュース作としてはアリスタ・レーベルと契約を交わしポップな作風を模索していたアンソニー・フリップスのPrivate Parts & Piecesを除いたソロ第2作『Wise After The Event』(また翌’78年発表の『Sides』もハイン・プロデュース)でした。
さて、このCAFÉ JACQUESプログレ時代通過型バンドなので、演奏能力は極めて高く、この時代を代表したプログレ・バンドの大御所群に引けを取らない演奏力を持っているのですが、まずそこに耳が行かない。全体を通してビターな味わいが魅力の通好みのメロディラインがまずしっかりと頭に残るよう作られている。それを実現している背景にあるのはレコーディング技術が発展してきた’70年代後半にあっても驚異的なサウンド・エンジニアリング! まぁ、気持ち良いくらい音抜けが良いわけです。定位とかも完璧。こうしたスタジオ・レコーディングのポテンシャルを最大限に活かしたプロデュースがなされている点がまず感動しますね。
バンドの演奏能力も十分に高いのですが、それを最大限に活かして余りあるプロデュースが作品のスケールを大きなものにしていると思います。曲の展開の中で先に書いたようにメロディラインにリスナーを惹きつけたい時にはそこに自然と耳が行くように、それが終わりインスト・パートに入ると、映像でカメラがすっと引きの画に移り変わるようにリスナーを誘導していくわけです。まさにプロデュース=演出ですね。
歌っている内容も男女間や人間関係の苦いドラマみたいな雰囲気のものが多く短編小説ロックといった趣があるのですが、ハインのプロデュースは本作の成功に大きく貢献していると思います。
このアルバムで一番有名な曲は2曲目の「Ain’t No Love In The Heart Of The City」。全米制覇前のWHITESNAKEがカヴァーしライヴでも人気に高い曲として知られていた名曲です。ビターなアンチ・ラヴ・ソングで先に挙げた「Farewell My Lovely」同様、ハードボイルドな世界観を持った曲でした。この2曲に挟まれた「Sands Of Singapore」も素晴らしい仕上がりです。リリカルなピアノ・イントロから展開されるサウンドはシンフォニック・ロック・サウンドと言っても過言ではないくらい重厚ですが、このバンドが打ち出そうとしたビターなポップ感は全く揺るぎません。この1stアルバムは大ヒットしたわけではありませんが、日本でも当時、ロックからシティ・ポップへ変貌を遂げていったムーンライダースをはじめとする日本のバンド群にも大きな影響を与えました。
Ain’t No Love In The Heart Of The City
CAFÉ JACQUESは翌’87年に2ndアルバム『International』を発表します。プロデュースはやはりルパート・ハイン。と言いますか前作のサポート・チームはそっくりそのまま参加という作品でした。アナログ時代はUK・ヨーロッパ盤とアメリカ盤でエンディングの曲が違うと騒がれていましたが2001年に国内CD化の際に両方の収録曲が合体。UK盤を原本としてそこにUS盤のラスト曲「International」とアルバム未収録曲「Ease Up」がボーナス・トラックとして追加されました。この後2010年にEsotericからも出ているのですがそっちのほうはUK盤仕様で追加収録がないようです。内容のほうは1stアルバムで打ち出したサウンドを継承していますが、ミッドテンポ中心だった1stに比べ、アップテンポの曲が増え、押しが強くなった感を受けるのと、若干コマーシャル化傾向に傾いた印象を受けます。
まず話題となったのはオープニングの「Boulevard Of Broken Dreams」。歌詞はデスペラートな雰囲気で1stで築き上げたハードボイルド・ポップ路線を継承したオリジナルかと一瞬思いますが、これは1933年にアル・ダビン作詞・ハリー・ウォーレン作曲で作られた曲で元々は1934年のミュージカル映画『ムーラン・ルージュ』の劇中歌。敗者のバラードといったビターな歌詞が歴代のアーティストたちを引きつけたのでしょう、ビング・クロスビー、トニー・ベネットらが歌い、このCAFE JACQUESと同時代のカヴァーとしてはマリアンヌ・フェイスフルが1987年発表の『Strange Weather』で取り上げています。’90年代に入ってからはダイアナ・クラールもカヴァーしていますね。このCAFE JACQUESヴァージョンの「Boulevard Of Broken Dreams」はメロディがオリジナルとだいぶ異なっており、歌詞を追っていかないと同じ曲とは思えない様変わりを見せています。彼らがこの曲を取り上げた理由はその歌詞にあったと思います。決してハッピーな世界ではなくどこか斜に構えたはぐれ者の世界。多分にハードボイルド的でありそれ自体、短編小説のような世界を描き出してきたバンドですから、このアル・ダビンが描いた歌詞の世界に惹かれた理由は良く分かります。オリジナルの歌詞はインターネットで簡単に検索できますので、興味を持った方は是非チェックしてみてください。演奏能力も極めて高いバンドでしたが、歌詞の方も独特のねじれ方が心に沁みますし、何よりもクリス・トンプソンの塩辛い声がこの歌詞世界にぴったりとハマっているのが最高です。
Boulevard Of Broken Dreams(~3:08)
CAFE JACQUESは2011年にクリス・トンプソンが中心となり再結成アルバムを発表していますが、残念ながら筆者は未聴。ただ、’70年代に彼らが残した2枚のアルバムは甲乙つけがたい出来で40年以上に渡り愛聴しています。トータルで考えれば1stの方が完成度が高いと思うのですが、『International』には先の「Boulevard Of Broken Dreams」のようにヴィンテージ楽曲をまるで自分たちの曲ようにカヴァーしてみせる強かさと1stでは少なかったアップテンポで畳み掛けるタイプの「Can’t Stand Still」、「International」、よりポップ度が高くなってはいるけどメロディが頭に残る「Waiting」、彼らのレパートリーの中では珍しいドリーミー・ポップ「Station Of
Dream」などの出来が良く、失ったものもあるけど得たものも多い結果になっています。ハインのプロデュースは1stのようにあっちこっちにスイッチを仕掛けた細かい演出からアルバム・トータルでバンドの個性を打ち出すスタイルに変化していますが、これもまた
好プロデュースと言ってよいでしょう。
まぁ、そういうわけで「マッチの日」からCAFE JACQUESに行って、今更ながらルパート・ハインのプロデュース凄いなぁ、という感じになってしまったのでこのまま話を進めます。
‘70年代に彼が手掛けた作品は先にご紹介しましたが、次はアンソニー・フィリップス。イギリスはアリスタ(他のヨーロッパ各国はヴァーティゴ、アメリカはパスポート)から出た2nd『Wise After The Event』、3rd『Sides』の2作がルパート・ハイン・プロデュース作です。まずは1978年発表の『Wise After The Event』から。バックグラウンドしては、まずこの時期フィリップスが在籍していたGENESISが金の稼げるバンドになっていました、というのが前提にあり、脱退した中心人物ピーター・ゲイブリエルのソロは勿論のこと、フィル・コリンズが参加したBRAND Xやスティーヴ・ハケットのソロもビジネス的に成功。アンソニー・フィリップスもほとんど自主制作でGENESISの出版会社名義で出したソロ・アルバムがカルト・ヒットとなっていたこともあり、ソロで行けるんじゃないかということでアリスタが手を挙げたわけです。でもメジャーから出す以上地味なフォーク・アルバムになっては困るので、その保険も兼ねてルパート・ハインをプロデューサーに起用ということになります。
どちらかというとエレクトリック系プログレ流れのアーティストとの相性が良かったハインですが、彼の名を広めたパープル・レーベルからの1stアルバム『Pick Up The Bone』はアコースティック主体でストリングスも効果的に配した作品で資質的には問題がなかったのですが、いざ制作を開始したら結構大変な作業だったのではないかと思います。と言いますのもEthotericから2016年に出た3CD+DVDAのデラックス・エディションのCD2にこのアルバム用のデモが収められているのですが、それ、フィリップスがポップ路線とは別に始めた『Private Parts & Pieces』シリーズと区別がつけ難いものがほとんどだったからです。印象的なギター・パートは多く、ポップな側面もよく聴けば多々あるのですが、第一印象は地味。多分、ルパート・ハインと組まなければ1stソロ『The Geese & The Ghost』より地味な作品となってしまった可能性もあったと思います。
『Wise After The Event』におけるルパート・ハインのプロデュースは、CAFE JACQUESとは異なり、スタジオ・エンジニアリングの知識と経験を総動員して、用意された楽曲を広がりのある音像に発展させ、ポップな側面を際立たせるエンジニア戦略とデモを一聴して理解したであろうベースラインへの無頓着ぶりとリズム面の弱さを克服するため、ベースには当然のようにこの時代のハインの右腕で歌ものバックにも強いジョン・G・ペリー、ドラムにマイケル・ジャイルズを起用しレコーディングを敢行します。音作りの基本は12弦ギターを多用するフィリップスのギターの共鳴の多いサウンドを活かしながらも耳障りな高音部を抑えふくよかで広がりのあるアコースティック・サウンドを確立。デモではルート移動くらいしかなかったベース・パートは時にヴォーカル・メロディに時にはギターに寄り添い単調になりがちな曲調に躍動感を与えるプレイを全体に配置。全体の曲想からかなり勿体無い使い方ではあるものの、ジャイルズの参加も光り、フィルインやオカズの入れ方にあの独特な叩き方を聴くことが出来きます。
『Wise After The Event』はGENESISファンを中心に手堅いセールスを記録するものの、その結果はアリスタが満足するレベルまでは達しなかったものの、やはりメジャーからの発売ということもあり、アンソニー・フィリップスは『The Geese & The Ghost』以上の反響に手応えを感じ、レーベルの要望を受け入れるのと同時に、才能あるギタリストではあったけれども性格的にバンド活動が苦手で家で作曲することを好んだフィリップスももう一度バンド・サウンドを追求してみようか、と意欲を見せます。引きこもりの中で生み出された小品を発表する『Private Parts & Pieces』シリーズを始めたこともあり、それとは別に表舞台でも、と考えた結果が1979年発表の『Sides』だったように思います。『Wise After The Event』と『Sides』の最大の違いは『Sides』ではヴォーカリストを起用したこと。線が細く、淡々と歌うフィリップスのヴォーカルもそれはそれで味があるのですが、『Sides』ではギタリスト、キーボード奏者に専念する形で、リード・ヴォーカルを取った曲は1曲のみ。アルバムではラルフ・バーナスコーンとデール・ニューマンを起用します。バーナスコーンはフィリップスの古くから友人でSirの称号を持っている人物らしいので、恐らくフィリップも通っていた名門パブリック・スクール、チャーター・ハウス時代からの付き合いかと思われます。ベースとドラムは『Wise After The Event』同様、ジョン・G・ペリーとマイケル・ジャイルズ、ゲストとしてメル・コリンズとBRAND Xのモーリス・パートが参加という陣容で『Sides』は制作されました。
レーベルが望んだポップ指向、バンド・サウンド、エレクトリック・サウンドの要求を受けた1st Halfも良いのですがやはり、今このアルバムをあえて聴くのであれば、オリジナル・アナログのB面に当たる2nd Halfにこそアンソニー・フィリップスらしさがあるのではないかと思います。2nd HalfはANTHONY PHILLIPS’ GENESISと行った趣が全体に立ち込めているからです。2nd Half 1曲目はインストのキーボード・シンフォニック・ロック「Sisters of Remindum」この曲は次作『1984』への布石となったナンバー。続く「Bleak House」もピアノを主体としたキーボード曲ながらこちらはヴォーカル入りクラシカルなメロディラインはアルバム中最高の美旋律を湛えています。アナログでは終盤にあたる「Magdalen」と「Nightmare」はさながらアンソニー・フィリップスによる『侵入/Trespass』再訪といったサウンド。これもメロディラインが美しい「Magdalen」は如何にもフィリップスらしいアコースティック・ギターのクラシカルなアルペジオがバンド・サウンドに乗ると一気に初期GENESISの世界が再現され、展開の激しい「Nightmare」の中間部のギター・プレイは「White Mountain」を彷彿とさせます。バックを受け持つのがジョン・G・ペリーとマイケル・ジャイルズですから正に盤石のGENESIS REVISITEDと言って良いでしょう。場面がコロコロ変わる「Nightmare」では異能のドラマー、マイケル・ジャイルズの本領発揮の場面もしっかりと確認できます。バンド活動には不向きでアコースティック中心の世界に引っ越したアンソニー・フィリップでしたが、GENESISの成功を見るにつけ、もう一度やってみたいという欲求はあったのでしょう。ハインがジョン・G・ペリーを連れてきて、旧交のあったマイケル・ジャイルズが参加してくれたこともあり自分史上最高にポップな楽曲を揃えた1st Halfの反対をあえて突っ走った2nd Half。フィリップス作品のアートワークを数多く手掛けたピーター・クロスの描いたイギリス人が大好きなテーブル・サッカー・ゲームに引っ掛けアナログではA面、B面ではなく、1st Half、2nd Halfとしたのでしょうが、もうひとつ、ハーフ毎に戦略を変えるという意味もあったのでしょう。
Nightmare
こういう作品の作りになるとルパート・ハインのプロデュースは冴えまくります。まずポップな1st Halfは正に彼のホームグラウンドのようなもの。およそこれまでのフィリップスからは想像もつかない疾走感溢れる屈折ポップ・ロック「Um & Aargh」、アコースティック・ラヴ・バラード「I Want Your Love」、浮遊感が面白い「Lucy Will」、メル・コリンズもサックスで参加しているファンク・ロック「Side Door」、Genesisの「Follow You Follow Me」とレゲェが合体したかのような「Holly Deadlock」を全曲こうあるべきスタイルにきっちりと当てはめていきます。しかし彼の本領が発揮されるのは2nd Half。戦略を180度変えているので、前半と後半はほぼ水と油。でもそれをシームレスで聞かせるのです。特に現行CDはそのまま進んでいきますから尚更なんですが違和感はありません。終盤のGENESIS REVISITED部分など、このアルバムがオリジナル発売された1年前にGENESISは『…And Then There Were Three…』を発表しており、フィリップスが在籍していた頃のGENESISはこの時点では既に遠い昔になっていたわけですが、そこも違和感ありません。これこそプロデュースの勝利だと思いますね。ところでこの段で「Holly Deadlock」がGenesisの「Follow You Follow Me」みたいと書きましたが、それってギターのエフェクトのかかり方なのですが、これフィリップスが曲書いた時点でそういう音にしようと思ったのか、ハインがレコーディング中に出したアイデアなのか、気になります。このアルバムもEsotericから3CD+DVDAのデラックス・エディションが発売されており、CD2にはデモやオルタナ・テイクが集められているのですが、そこには「Holly Deadlock」のデモはないのです。
Holly Deadlock
ポップになったアンソニー・フィリップスというイメージが強く付いて回る『Sides』ですがここに書いたように特に終盤はGNESIS度が高い作品となっています。そういったプログレ度の高い曲の別テイクや2016年版アルバム・ニュー・ミックス、5.1chサラウンド・ミックスを追加したEsotericの3CD+DVDAのデラックス・エディションは『Sides』はポップ・アルバムという固定観念をお持ちの方に強くお薦めします。
ルパート・ハイン・プロデュースというテーマで進めてきましたが、彼自身も優れたキーボード・プレイヤー。CAFE JACQUESやアンソニー・フィリップスをプロデュースしていた時期に存在した自身のバンド、QUANTUM JUMPもまた魅力的なバンドでした。結成は1973年だそうで、スタジオ・ミュージシャンが集まったセッション・バンドとしてスタート。ちょうどハインがパープル・レーベルからの2ndソロ・アルバム『Unfonished Picture』をリリースした時期です。メンバーはハイン、ベースにはジョン・G・ペリー、ドラムに元PEDDLERSのトレヴァー・モライス、ギターにマーク・ワーナーというカルテット編成でした。テクニシャン揃いで1976年発表の1stアルバム『QUANTUM JUMP』は痛快なファンク/フュージョン・ロックを披露。特に強烈な早口言葉をフィーチュアした「Lone Ranger」は話題となりラジオを中心にかかりまくりますが、歌詞の一部に麻薬や同性愛についての言及(ほぼ言いがかりに近い解釈)があると指摘され放送禁止となりせっかく上向いた状況も一気に萎んでしまいます。血湧き肉躍るといった表現がぴったりくる強烈なファンク・ロック・サウンドは今聴いても十分刺激的なのですが、レーベル契約を得るために長い時間が掛かったにも関わらず、ほとんど言いがかりに近い中傷でバンドの未来が閉ざされたと感じたギタリストのマーク・ワーナーはキャット・スティーヴンスのツアー・ギタリストのオファーを受けてのを機にバンドを脱退。トリオとなったQUANTUM JUMPは1976年末にCARAVAN等で活躍していたジェフリー・リチャードソンのサポートを得て2ndアルバム『Barracuda』を制作。翌’77年に発表された同作は、前のめりのファンク・サウンドの肝だったワーナーを欠いた編成となっていたため、フュージョン・タッチのサウンドは継承されたものの、そのサウンドはゆったりとしたミステリアスなものに変化します。このアルバムも素晴らしい仕上がりでしたがセールスは伸びず、バンドは’77年終わりに解散。しかし、2年後の1979年中傷受け放送禁止となったはずの「Lone Ranger」がまさかのリヴァイヴァルとなり最終的は全英チャート5位まで上昇するヒットなります。BBC「Top Of The Pops」出演を打診されたQUANTUM JUMPはTV出演のため急遽再集結します。このヒットに合わせ、1st、2ndの主要曲を曲によってはパートの差し替えを行いリミックスしたコンピレーション・アルバム『Mixing』を発表しています。
Lone Ranger
QUANTUM JUMPのCDに関しては2014年にEsotericから出たものをお薦めします。1st『QUANTUM JUMP』にはシングルB面曲の他、アルバム『Mixing』に収録された1stからのリミックス・ヴァージョン4曲が追加収録されており、『Barracuda』に至っては2CDにエクスパンドされ、こちらにはアルバム未収録曲、『Mixing』に収録のリミックス・ヴァージョンに加え、BBCイン・コンサート出演時のライヴが追加マテリアルとして収録されています。このBBCイン・コンサートがまさに鬼! 唖然とするくらいにテンションが高くテクニカルなサウンドを堪能できる優れものとなっています。
なんかぐったりしたと思ったら、もう9000字超えてるじゃん! 今月の1枚はさらっといきます。今年の暑さの中、涼を求めて聴いた1枚です。CAROL OF HARVEST、2008年、まさかの2ndアルバム『Ty I Ja』です。1978年発表の1stアルバムは女性ヴォーカル入りプログレを愛好する皆様には大変有名です。カケレコではダークなRENAISSANCEと表現されています。わはは!確かにそうだ。間違っていない。オリジナルは透明感溢れる女性ヴォーカルとフォーク・タッチのプログレ・サウンドの融合が魅力でしたが、『Ty I Ja』もその流れはしっかり継承しています。テクノロジーの進化で透明感がさらに増した印象。女性ヴォーカルの傾向もオリジナルを引き継いでいるのですが、30年も後に出たアルバムなので同じ人じゃないと思いますが、CAROL OF HARVESTのイメージを壊すことはありません。大変涼しい作品です。歌が英語じゃないのも部屋の中に冷気のように漂うサウンドの一因となっているかと思いますが、女性ヴォーカルのメロディもギターの爪弾きも美しく今年の夏は大変重宝しました。3分前半の短い曲ですが3曲目の「W Objeciach Twych」は今年の夏もっとも再生回数が多い曲となりました。では、また来月。来月は遅刻しません。
W Objeciach Twych
【関連記事】
「音楽歳時記」 第五十三回 6月24日 UFOの日・追悼P.レイモンド 文・深民淳
音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。
【関連記事】
「音楽歳時記」 第四十五回 10月23日 電信電話記念日 文・深民淳
音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。
関連カテゴリー
関連CD在庫
-
ANTHONY PHILLIPS / WISE AFTER THE EVENT
元GENESISのギタリストによる78年2nd、メルヘンチックで温かみ溢れる好盤、マイケル・ジャイルズ/メル・コリンズ/ジョン・G・ペリーらが参加、ルパート・ハインのプロデュース
元GENESISのギタリスト、Anthony Phillipsによる78年作、ソロ2枚目。Rupert Hineがプロデュースを担当、ゲストに元KING CRIMSONのMichael Giles(DRUMS)、Mel Collins(SAX)、元CARAVANのJohn G.Perryを迎えて制作されています。内容は初期GENESISを彷彿させる繊細なギター・アルペジオが印象的なヴォーカル・アルバム。Peter Crossのアルバム・ジャケットの如く、メルヘンチックな世界観を楽しむことが出来ます。タメの効いたリズム、ジェントリーなヴォーカルの裏で様々な表情を見せるギター・アルペジオが美しく響く幻想的なアンサンブル。優しいメロディーを奏でるサックスも素晴らしい。Michael Gilesもクリムゾン時代の存在感と比べると大人しいですが、「Pulling Faces」ではアグレッシヴな叩きっぷりを堪能出来ます。ヴォーカルにフォーカスしている分、彼のメロディー・メイカーとしての才能がより浮彫になっています。プログレッシヴ・ロック・ファンのみならず、メロウな英フォークが好きな方にもおすすめです。
-
ANTHONY PHILLIPS / SIDES
初代ジェネシスのギタリスト、79年作の4thソロ、マイケル・ジャイルズ(Dr)、ジョン・G・ペリー(B)参加
初代ジェネシスのギタリスト、79年作の4thソロ。ルパート・ハインのプロデュースで、1曲目「Um & Aargh」からヒネリの効きつつもキャッチーなメロディとアレンジが光まくっていて躍動感いっぱい。マイケル・ジャイルス(Dr)、ジョン・G・ペリー(B)という名手2人の参加も特筆で、全体をシャープに引き締めるキレのあるリズム隊も聴きどころです。特にアルバムのラストを飾る「Nightmare」はジェネシスを彷彿させるプログレッシヴなナンバーで、マイケル・ジャイルスの手数多くもふくよかなドラミングが冴え渡っています。スピーディーに畳み掛けるパートでのドラムは、あのクリムゾン1stでのスティックさばきを彷彿させます。アンソニー・フィリップスの数あるソロ作の中でもプログレッシヴ・ロック寄りの作品で、代表作と言える名作です。
-
2枚組、DISC2にはアルバム収録曲のオルタネイトverなど12曲を収録
盤質:傷あり
状態:良好
1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!