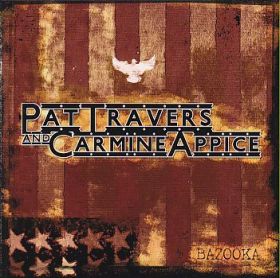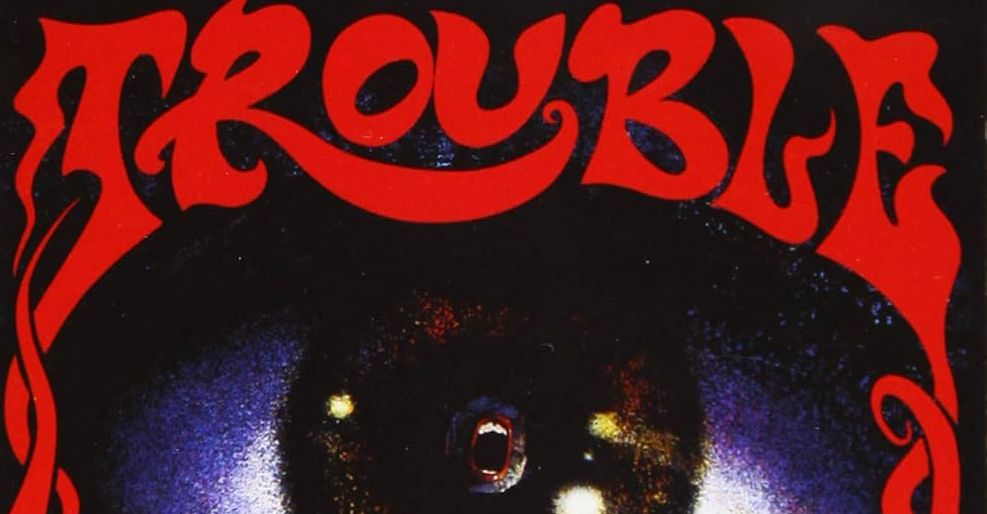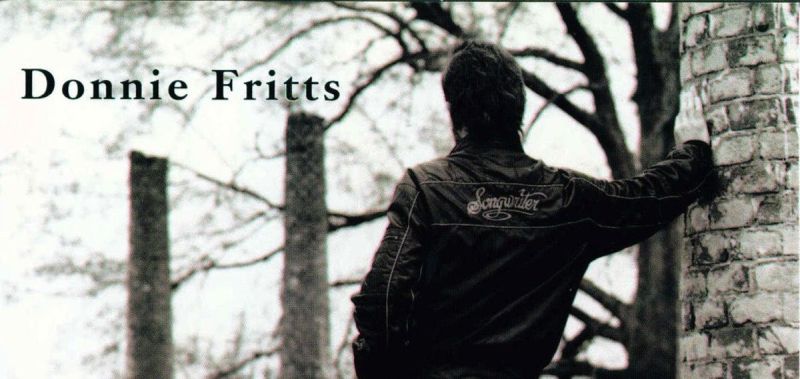「音楽歳時記」 第四十一回 6月6日 カエルの日 文・深民淳

6月も妙な記念日が目白押しです。小学生の時、6月になると虫歯予防デイだか虫歯予防週間だか忘れましたが、歯磨き体操というけったいなものがあり、朝礼の時朝礼台の上で担当教諭が巨大な歯の模型と歯ブラシを持って曲に合わせ歯磨きの仕方を教えるというものだったのですが、その歯の模型が気色悪かったことを思い出します。歯茎のピンク色が毒々しくてねぇ。全国的にそれがあったかどうか分かりませんが、昭和の時代に小学生だった方は思い当たる節があるかと思います。現在は6月4日から10日まで歯の衛生週間として続いているそうですが、歯磨き体操、今もあるのかなぁ? へんてこな曲だった印象です。
6月4日はまた虫の日でもあるそうです。日本昆虫クラブが提唱しているそうですが、う〜ん、虫はパスだなぁ。
6月6日にはカエルの日というのもあります。あれ?6月6日・・・「6月6日に雨ザァザァ降ってきて、三角定規にヒビ入って・・・」って絵描き歌あったよなぁ。あの歌なんて言うんだっけ?(「かわいいコックさん」でした)え〜、話戻します。カエルの日は「かえる友の会」という団体が1998年(平成)に提唱したそうで、カエルの鳴き声にちなんだ語呂合わせからきているそうなんですが、カエル色々ありますねぇ。最初に頭に浮かんだのはバンドとかではなく、映画です。『マグノリア』です。トム・クルーズですね。映画終盤大量のカエルが空から降ってくるシーンが頭に浮かびました。あれ、ファフロッキーズという現象だそうで、旧約聖書にも記されている現象なのですが、原因は諸説あり、今も解明されていないみたいです。
さて、最近、あんたの挙げる例は変化球ばかりというご指摘を受けていますが、やっぱり普通すぐに出てこないものが頭に浮かんでしまいました。カエルだとEthel The Frog。ハル出身で地元では早くから活動していましたがNWOBHMムーヴメントの中、Iron Maidenらと共にEMIからデビューしたバンドです。メジャー・シーンに最初に登場したのは今となっては伝説のNWOBHMコンピレーション・アルバムとなっている1980年発表の『Metal For Muthus』だったかと記憶しています。Iron Maiden、Samson、Angelwitch、Praying MantisといったNWOBHMシーンを牽引したバンドと共に「Fight Back」が収録されていました。Samson、Angelwitch、Praying MantisといったバンドはEMIではなく他のレーベルから作品を発表しますが、このEthel The Frogは同年EMIからアルバム『Ethel The Frog』、シングル「Eleanor Rigby」でデビューします。今のロック・ファンにしてみれば、凡庸に聴こえてしまうのかもしれませんが、デビュー当時のIron Maidenなどはパンク・ムーヴメントを通過した若いミュージシャンならではの疾走感・刹那感を持った前のめりのリフで押しまくるヘヴィ・メタル・サウンドが当時は新鮮に聴こえました。Ethel The Frogはどうだったかというと、このバンドも、’70年代のハード・ロック・バンドとは一線を画した疾走感と押しの強いリフを持った曲もありましたが、もう少しロックン・ロール寄りでアメリカのハード・ロックから影響なんでしょうか、ヴォーカルのコーラス・パートなどは爽快感溢れるものになっていました。その最たるものがシングル・カットされた「Eleanor Rigby」。The Beatlesのクラシカル・テイスト溢れるヒット曲のカヴァー・ヴァージョンです。バックのハードでちょっとダークな演奏とエコー深めのヴォーカルに特徴があるミスティなアレンジに仕上がっており、単体で聴くとヘヴィ・メタルというより’70年代アメリカのFMオリエンテッドなポップ・ハード系に近いサウンドに聴こえ、他のアルバム収録曲とのバランスが、ちと悪いような印象を受けます。ある種の営業戦略みたいなものがあったのでしょうが、これが逆にバンドの印象を散漫なものにしてしまった感もあります。唯一のアルバムは’90年代の終わりにCD化されているのですが、即市場から消えたこともあり、今となってはプレミアがついてしまっているのもちょっと痛いですね。
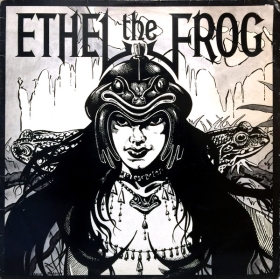
Eleanor Rigby
先に挙げたNWOBHMのコンピレーション『Metal For Muthus』にはもうひとつカエルがらみのバンドが収録されていました。Toad The Wet Sprocketです。アメリカにも同名のバンドがありますが、こちらはコテコテのメタル・バンド。ベッドフォード出身でNWOBHM然とした疾走感を身上としたバンドだったようです。ようですって、なんだよという話なんですが、このバンド、シングル残しただけで消えたバンドなので今ひとつ全貌が見えにくいわけです。バンド名は恐らく’70年代に放映されていたモンティ・パイソンに登場したギャング蛙のアニメーションから採ったものと思われます。
Toadはどちらかというとガマ・ガエルなのですが、スイスの名ハード・ロック・バンドの名前でもあります。CreamからLed Zepplinに繋がっていくブリティッシュ・ハード・ロックからの影響をもろに受けたそのサウンドは今聴いても新鮮というか、オリジナル活動当時は日本に紹介されていなかったため、後付けで認知されたバンドですが、ヨーロッパ・アンダーグラウンド・ロック史を語る上では重要なバンドと言っていいでしょう。

このToad、スイスのバーゼルで結成されるわけですが、オリジナル・メンバーの経歴が立派! リズム・セクション、ワーナー・フローリッヒ(b)、コジモ・ランピス(ds)は共にスイス・サイケデリック/エクスペリメンタル・バンド、Brainticketのレコーディングに参加しています。アルバムがドイツのベラフォン・レーベルから発表されていることもあり、ドイツのバンドとする資料もありますが、活動拠点はスイスだったようですし、設立メンバーのJoel Vandroogenbroeckはベルギー人ですので、多国籍バンドというべきなのでしょう。日本は島国なので今ひとつイメージが湧きませんが、ヨーロッパは地続きですから、日本で言えば県またぎみたいな感覚のバンドはいくらでもあったわけです。ふたりは2ndアルバム『Cottonwoodhill』のリズム・セクションとして参加していますが、このアルバムもToadの1stアルバムも同じ1971年に発売されているところを見るとセッション参加みたいな感じだったのかもしれません。実際、Brainticketはメンバーが流動的でしたしね。ついでにWikiで見るとToadの結成は’70年という表記がありますので、多分にスポット参加だったのではないかと思います。
このふたりと創生期のHawkwindに在籍していたギタリスト、ヴィック・ヴァージートが出会いToadは結成されます。Hawkwindもデビュー前はブルース、フォーク色の強い音楽性だったのが1970年にLibertyからデビューする頃にはBrainticket同様、サイケデリック/エクスペリメンタル色が強くなっていき、これを良しとしなかったVicは袂を別ちToad結成へと向かいます。で、Hawkwindのほうはデイヴ・ブロックとヒュー・ロイド・ラングトンというギター二人体制でデビューする形になります。
3人ともサイケデリック/エクスペリメンタルのカオスの中にいたものの、本心はハード・ロックがやりたいという気持ちが強かったのでしょうToadはスイスというハード・ロックの世界では決して中心とは言えないエリアで活動をしていたものの、そのポテンシャルは高く、ミュージシャンとしてのスキルも圧倒的に高かったこともあり、当時、Deep Purple、Black Sabbath、Budgieなどを手がけブリティッシュ・ハード・ロック系のプロデューサー、エンジニアとしては飛ぶ鳥を落とす勢いだったマーティン・バーチに見出され、ロンドンのDe Lane Leaスタジオでアルバムを制作します。恐らくプロダクション・サイドの働きかけがあったのでしょう、レコーディングにはリード・ヴォーカリストとしてベンジャミン・イエガーが参加し1stアルバム『Toad』はカルテット編成でレコーディングされます。イエガー参加は1stアルバムのみですが、彼は後にベースのフローリッヒと共にIslandに参加します。ギーガーの絵画をアートワークに配し、ヨーロピアン・プログレッシヴ・ロックの名盤として今なお人気が高いお馴染みのあのバンドです。
Cotton Wood Hill
『Toad』はCream、Led Zeppelin、Deep Purpleといった当時トップクラスのブリティッシュ・ハード・ロック、そしてジミ・ヘンドリックスからの影響をストレートに打ち出したハード・ロックが堪能できる名作となりました。影響を受けて、そこを目指すことは誰でもできることですが、このバンドが凄かったのは、その影響下にあり、オリジナルと同等、もしくはそれ以上のミュージシャンとしてのスキルを持っていたことでしょう。曲の中で目まぐるしく変化するリズム・パターン、豪快にドライヴするギター、リフ・ワークの引き出しの多さ、どれを取ってもこの時代のトップクラスと言っても過言ではないでしょう。今調べたら、カケレコでもしっかり特集ページがありますね。こちらもご参照ください。
【関連記事】
スイスの名ハード・ロック・バンドTOADの1st『TOAD』と2nd『Tomorrow Blue』を特集!
スイス屈指というか、ユーロが誇るハード・ロック・バンドTOADの1st、2ndを特集!
スタジオ・アルバム3作はどれも優れた作品ですし、CD時代になって発売された発掘ライヴ・アルバムも聴くに値する良品だと思います。筆者はCD化される前、’80年代前半に中古のアナログで入手したのですが、この頃には既にコレクターズ市場でも幻の超弩級ハード・ロック・バンドとして認識されており、5桁を越すプレミアがついていました。それだけの金額支払っても、買って良かった。スゲェなぁと思ったくらいですから、ハード・ロック好きなら死ぬまでに聴いたほうが良いバンドのひとつでしょう。
もう少し書かせてもらうと、ここのベースのフローリッヒは明らかにジャック・ブルースの流れを引いています。そこまで細かいノート詰め込まなくても良いだろうと聴いていて思う点もよく似ています。筆者、フローリッヒがこのToadの後参加したIslandを聴くたびに、良いアルバムだと思うけど、いやぁ、音が詰まり過ぎていて、通して聴くとぐったりするなぁ、と思ってしまうのですが、この印象の最大要因ってフローリッヒにあったのかもしれないですね。
さて、最近取り上げたばかりですが、ロリー・ギャラガーには「Bullfrog Blues」という名曲・名演があります。オリジナルは1928年デルタ・ブルース・アーティスト、ウイリアム・ハリスが吹き込んだアコースティック・ブルースでロリー・ギャラガーが取り上げる前はCanned Heatがカヴァーしたヴァージョンが有名でした。ロリー・ギャラガーのヴァージョンはTasteを解散させソロに転じて3作目にして初のソロ・ライヴ・アルバムとなった『Live In Europe』に収録されています。Taste時代は熱く弾けるブルース・ロックが身上でしたが、ソロに転じてた初期は1971年という時代の風の中、ソロならではの多様性を打ち出そうとし、基本、デビューからブレのないブルース・オリエンテッドな音楽性ながらアコースティック路線に舵を切ったり、直球勝負のTasteのサウンドから意図的に離れていこうとしていた時期で、特に2ndアルバム『Deuce』は彼の全作品中最も内省的な内容を持った作品だったと思います。『Live In Europe』はそんなこれからどこへ向かおうと思案の時期にあったギャラガーが、再びブルース直球勝負に出て、ソロ・アーティストとしてのアイデンティティを確立した記念すべき作品だったと思います。
筆者がこのアルバムを買ったのは1973年の頭、冬の時期でした。当時レコードを購入していたレコード店のバイトの大学生に「え?それ買うの、地味だよ」と腐されながらも、音楽誌等で好意的なレビューや紹介記事が掲載されていたのに影響を受け買いました。初めて聴いた日から今日に至るまでこのアルバムが地味だと思ったことは一度もありません。それまでLed Zeppelin、Deep Purpleといった典型的ブリティッシュ・ハード・ロックやプログレッシヴ・ロックに入れ込んでその手のものしか聴いていなかった筆者の耳にも新鮮でしたね。最初に気に入ったのはその「Bullfrog Blues」、そしてオープニングの「Messin’ With The Kid」、「Laundromat」でした。「Laundromat」はデビュー・アルバムのオープニング曲で彼の自作ですが、「Bullfrog Blues」と「Messin’ With The Kid」は猛烈にオリジナルを聴いてみたいという欲求にかられました。
Bullfrog Blues
ロックを聴き始めて4年くらい経っていたわけですが、まぁ、ガキだったし、大した見聞もなかった頃ですから、音楽を楽しむという無限の世界に足を踏み入れたものの、その広さを知ろうともせず自分の足元ばかり見ていたら、このアルバムに「顔上げて見な、色んなものが見えるから」と教えられた、そんな感じでしたね。筆者にとっても開眼の一枚だったわけです。ブルースやR&B、ソウルといった黒人音楽も楽しめるようになったきっかけは間違いなくこのアルバムでしたし、「Bullfrog Blues」や「Messin’ With The Kid」は特にそうしたageの気分に火をつけたナンバーでした。
肝心の「Bullfrog Blues」はそのオリジナルを聴くことができたのは随分と後のことでしたが、ジュニア・ウェルズがやっている「Messin’ With The Kid」はバディ・ガイとのコンビで1972年に発表した『Buddy Guy & Junior Wells Play The Blues』を輸入盤店で見つけ買いました。初めての黒人ブルース体験はこのアルバムでした。ロリー・ギャラガー・ヴァージョンの火の出るようなハードな演奏とは違い、なんと説明すれば良いかなぁ・・・。あぁ、そうだ。「タモリ倶楽部」のオープニング曲を聴くと今もこのアルバムの「Messin’ With The Kid」を思い出します。ロリー・ギャラガーとバディ・ガイ&ジュニア・ウェルズ、アレンジは全く異なるのですが、ロリー・ギャラガー、アレンジを大幅に変えても曲のコアな部分、肝はしっかりと押さえており、黒人ブルースには完全に素人だった筆者もすんなりとその世界に馴染むことが出来ました。それを考えると非凡な才能を持ったアーティストでしたね、ロリー・ギャラガーって。もう音源や映像作品でしか彼の音楽に触れることが出来ないことを改めて寂しく思いました。
ハード・ロック寄りになってしまいましたが、フォーク・ロック系にも良いカエルものがあります。Southern Comfortの『Frog City』です。元々はFairport Conventionを脱退しソロとなったイアン・マシューズのバック・バンドとして1969年にスタートし、イアン・マシューズと3枚のアルバムを制作し、1971年発表の『Later That Same Year』を最後に独立。同年発表されたバンドとしてのデビュー作なのですが、このバンドで圧倒的に有名なのはヒプノシスのティー・カップ・ジャケットが印象的な2ndアルバム『Southern Comfort』なのですが、この『Frog City』も良い出来です。カエルもので纏めているのでなんですが、これに関しては味はあるのですがヘタウマっぽいカエル・ジャケットが若干損をしているようにも思います。
Good Lord D.C.
アメリカン・ロックを標榜し、カントリー・テイストも取り入れたかなり高レベルのフォーク・ロック・バンドで、ラップ・スティール・ギターも取り入れアメリカナイズされたフォーク・ロック・サウンドにCSN&Yにも通じる流麗なコーラス・ワークが映える好作品です。
ただ、やっぱりイギリス人が作ったアルバムなんですよねぇ。アメリカのこの手のバンドって、そのミュージシャンの根幹の部分にフォークやカントリーの遺産や歴史がプレ・インストールされているというのあるのでしょうが、当たり前のように備わっているものだから、その扱いがどこかぞんざいというか雑なところがあるように思います。で、そのどこか雑な作りがイギリス人ミュージシャンを引きつけ、同時に悔しがらせる訳です。逆にイギリス人はそうした音楽に対する強い憧憬みたいなものがあるため、ぞんざいに扱わず掌に乗せ大切に愛でるようにサウンドを作りあげる傾向があるように思うのです。その差がやっぱりこの作品にも色濃く出ているのです。作りが繊細なんですよ。ダイナミックにやっているつもりでもどこか繊細。見える景色がロッキー山脈ドーンにならず、どこか箱庭的な風景、そんな感じなのです。そしてそのちんまり感がアメリカ人には作り上げることのできない魅力となっているわけです。秀逸ジャケットの2nd、そしてクラシカル・テイストとほんのりアシッド感も加わったフォーク・ロック、誤解を恐れず書いちゃえば、とことん分かりやすくなったIncredible String Bandといった趣のバンドの中心人物アンドリュー・レイのソロ・アルバム『Magician』も含め聴いていただきたいと思います。
とはいえ、筆者実はCDを見たことがない3rdアルバム『Stir Don’t Shake』がいちばん好きなんですよね。これCD化されていないよね? 個人的にはこのアルバム、イギリス人が作ったフォーク・ロック作品の中ではかなり秀逸な作品だと思うのですが・・・。
今月の一枚はハード・ロックに寄ったついでにもう一枚。パット・トラヴァースが昔から好きでして、特にツイン・リードの相方に名手、パット・スロール、ベースにピーター“マーズ”カウリング(英国プログレの名バンド、名盤『Lady Lake』を残したGnidrolog出身。このPat Travers Band時代のプレイは今日に至るまでのハード・ロック・ベーシストの中でも間違いなくトップクラスに位置するバカ・テク・ベーシスト)が在籍した時代は特に好きだったのですが、2000年代に入ってからリリースされたPat Travers Power Trioあたりからなんとなく昔の名前で出ていますみたいな雰囲気が強くなってご無沙汰していました。先日、某チェーンの中古盤コーナーでTravers & Appiceが2005年に発表したスタジオ・アルバム『Bazooka』を発見。聴いたことなかったので結構高いなぁ、と思いつつも購入。ベースをトニー・フランクリンが弾いている曲もあり、なんだかジョン・サイクスのBlue Murderのギタリスト違いみたいなところにも興味があったのですが・・・。Travers & Appiceはオリジナルに特化したアルバムもありますがこの『Bazooka』は二人が過去にやっていた有名曲のセルフ・カヴァーが中心の作品で、パットラ流れの曲は「Snortin’ Whiskey」、「Boom Boom」、「Crash & Burn」、カーマイン・アピス流れの曲はCactus時代の「Evil」、BB&Aの「Superstitious」、「Livin’ Alone」、これになぜかAerosmithの「Last Child」なんかが取り上げられており、それらはまぁ、そこそこ楽しく聴けたのですが、惹かれたのはそこではなく「Disappear」という曲でした。これがパット・トラヴァースらしくない曲でして、雰囲気的にはHawkwindなんかに近いドライヴ感を持ったナンバーで醒めた感じで歌われるヴォーカルのメロディラインはどこかラーガ・ロック的というかインドっぽい印象を受けるというものでして。深めのディレイがかかったギターや4弦ベースでフレットを押さえて出す最低音Fの爆走ストレート8グルーヴが意表をついており思い切りはまりました。当時クラブ・ツアーは集客力あったらしいですが、CDのほうはあまり話題にならず、現在では探すのが一苦労となっているみたいですが個人的に燃える部分もあったので紹介させていただきました。それでは!
Disappear
関連カテゴリー
第四十一回 6月6日 カエルの日
-
RORY GALLAGHER(ROLLY GALLEGHER) / LIVE ! IN EUROPE
ソロ通算3作目、72年発表の傑作ライヴ・アルバム
-
TOAD / TOAD
スイス屈指のハード・ロック・グループ、71年の傑作デビュー作!
スイス屈指のハード・ロック・バンドによる71年のデビュー作。ドイツのサイケデリック・ロック・バンドBRAINTICKETで活動していたベースのWerner FrohlichとドラムのCosimo Lampisを軸に、英サイケ/スペース・ロック・バンドHAWKWINDで活動していたギターのVittorio ‘Vic’ Vergeatが参加してスイスはバーゼルにて70年に結成。ヴォーカルには後にISLANDでも活躍するBenjamin “Beni” Jaegerを起用して制作されたのがこの71年1stアルバム。凶暴に歪んだギターがヘヴィに刻むリフを中心に、ジャック・ブルースばりに暴れまわるベースと、ジョン・ボーナムの重さとジンジャー・ベイカーの手数を合わせたようなドラムが重戦車の如く畳み掛けるアンサンブルは凄まじい音圧。ツェッペリンの重量感、パープルのスピード感とキレ、サバスの凶暴さが合わさった聴き手をなぎ倒さんばかりのハード・ロックをプレイします。ロッド・スチュワートやピーター・フレンチばりのしわがれヴォーカルも魅力的で、アコースティックなパートで聴かせる叙情性もまた一級品。これはスイスのみならずユーロが誇る、と言っても過言ではないハード・ロック傑作!
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!