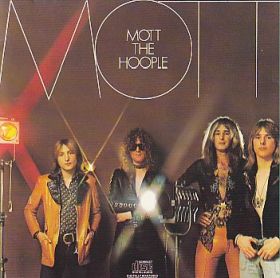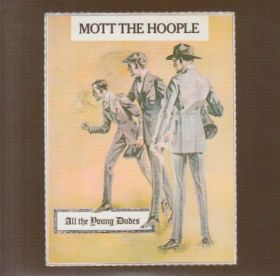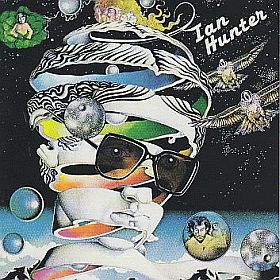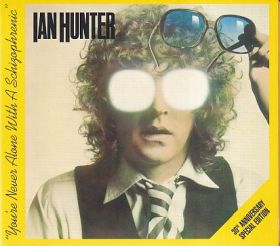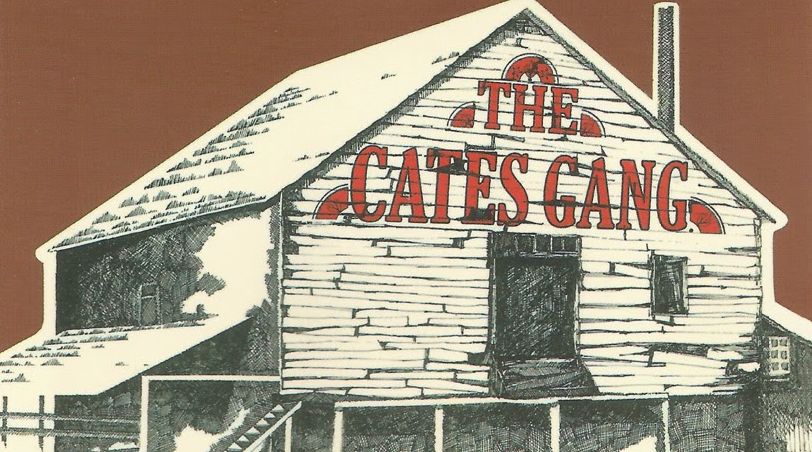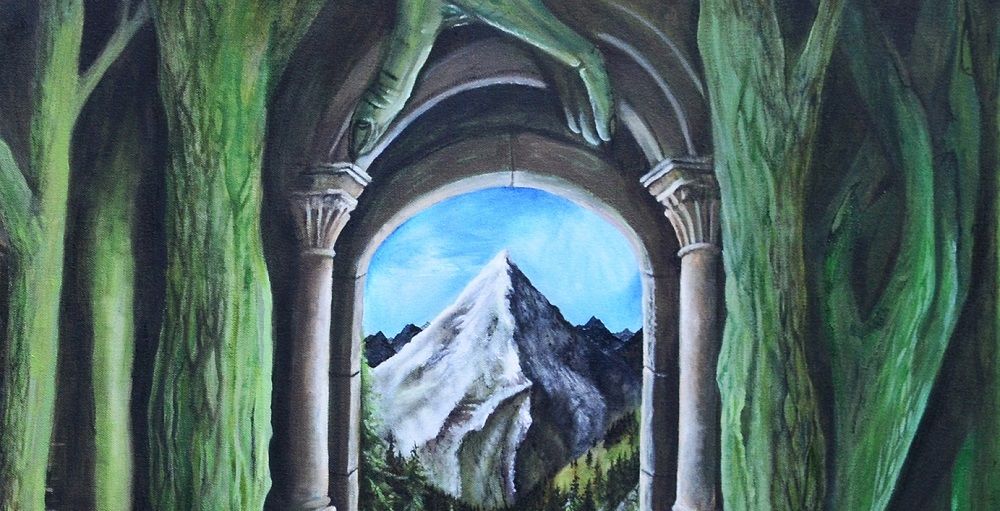「音楽歳時記」 第二十回 9月 妙な記念日山盛り~またも番外編 文・深民淳

2度目の9月を迎えました。前年は確か中秋の名月ネタだったような気がしていますが、定かではありません。そんなもの、読み返せばいいだろうと言われそうですが、締め切り直前故、その時間すら今は惜しい。そういう状況です。
記念日カレンダーを見ながら何か膨らませそうなネタはないかと探していますが、イマイチ、ピンとくるものが見つからなくて困っています。
とはいえ、変な記念日いっぱいありますね。9月1日はいきなりこじつけ以外何者でもない「くいの日」、「キウイの日」がダブルであります。翌2日はありそうだな、と思っていたらやっぱり「靴の日」がありました。もうひとつ予想していた9月9日「九九の日」はありませんでしたが。
どこぞの業界が無理やり作ったんだろうなと思う記念日もあります。9月14日「メンズ・バレンタインデー」、「セプテンバー・バレンタイン」。何を贈れば良いのでしょうか? 食べ物関係で行くと9月6日これは解りやすく「黒豆の日」、「黒牛・黒豚の日」、9月18日「かいわれ大根の日」(なんで?)、9月25日「即席ラーメンの日」(ではこの日、僕は古井戸「インスタント・ラーメン」を聴くことにします)、9月29日「洋菓子の日」兼「ふぐの日」、そしてこれは何故だかよく理解できない9月30日「くるみの日」というのもあります。
9月9日にはちょっと我が目を疑いましたが「男色の日」なんていうのもありました。菊の節句であることからだそうですが、なんで菊の節句となどと突っ込まないでいただきたい。大人なら分かるでしょう。自分で書いていてちょっとイラッときました。
様々な記念日がある中で、個人的にピンときたのが、9月11日「公衆電話の日」。電話に引っかかってしまいました。なんかここ数日、理由ははっきりしないのですが、10CCの『How Dare You』がすごく聴きたいモードに入っていたのですが、仕事が無茶苦茶な状況でそれが叶わず、漸く原稿書きに突入したので今、聴きながら書いています。『How Dare You』は10CCの4作目にあたる作品で、名作の誉れ高くロック・クラシックとなっている「I’m Not In Love」が収録されている『Original Soundtrack』に続き1975年に発表されました。4人のオリジナル・メンバー最後の作品で、本作発表後、ゴドレー&クリーム組は脱退しデュオで活動を開始。10CCはスチュワート&グールドマンが継承していく分岐点的アルバムになりました。
このアルバムに惹かれる理由は、各音の配置の妙にあります。元々は音圧が高く、ぎっちりと詰まった音作りを好みますが、時々、反動で考え抜かれた音の配置がなされ、隙間をうまく使った音作りが無性に聴きたくなる時があります。こう書くと、「?」となる人も多いかと。前作収録の「I’m Not In Love」などは音のレイヤーの化け物のようなマルチトラック・レコーディングの粋を集めたかのような曲でしたし、ギズモトロンを多用し音を埋めていくゴドレー&クリームがまだ在籍していた本作も隙間をびっちり埋めたサウンドがそこかしこに存在しています。ただ、そのパートが終わって特に歌モノのバックになった瞬間の音の配置が見事。ほとんど手入れの行き届いた庭園を見ているような、思わず絶句する職人技が堪能できます。
職人技で、もう1枚。現在発売中のレコード・コレクターズ誌は各社、夏から秋口にかけAOR誕生40周年を記念し’70~’80年代にかけてのAOR名作群を廉価盤シリーズとして再発するのを受け、AOR特集がメイン・コンテンツとなっています。アメリカのAORに関してはエリア、系統ごとにかなりのヴォリュームの作品レビューが掲載されており、後々資料として役立ちそうな気合の入った特集です。
この企画実現の原動力となったのは、7月に発売されたソニー・レコーズのAOR CITY 100(7月に前半50作品、8月に後半50作品というスケジュールです)シリーズだと思うのですが、この前半部分で発売されたもののオーストラリア人アーティストいうこともありRC誌にレビューが載らなかったジョン・ファーラーを紹介させてください。ファーラーは1960年代初頭にオーストラリアのメルボルンで結成されたTHE STRANGERSにTHE MUSTANGSから1964年に移籍。このTHE STRANGERSはオーストラリアのTHE SHADOWSと評されるギター・インスト・バンドでした。その後1970年まで同バンドに在籍後、イギリスへと渡りTHE SHADOWSのハンク・マーヴィン、ブルース・ウェルチとMARVIN, WELCH, FARRARを結成します。HARVESTレーベルほどではありませんが、EMI傘下のレーベルとしてはアナログ・マニアからコレクターズ・レーベルとして認識されているREGAL ZONOPHONEから『MARVIN, WELCH, FARRAR』、『SECOND OPINION』と2枚のアルバムを発表しました。世界中に衝撃を与えたCROSBY, STILLS & NASHの成功を受け、その英国版を目指したハーモニー重視のフォーク・ロック・サウンドだったのですが、元がTHE SHADOWSですから確かに方向性はそうだったのでしょうが、いかにも英国然とした、突き抜けなくてカラッと晴れないフォーク・ロックになっており、メンバーの割に大きな注目を集めることなく終わってしまうのですが、今聴くと紅茶の国のフォーク・ロックとしては超秀逸な逸品です。乱暴な言い方すれば、MOODY BLUESに接近したCS&Nといった感じでしょうか。
ま、そんな活動を展開していたのですが、彼を知らない人に紹介する際はこちらの方がてっとり早いでしょう。オーストラリア出身ということもあり、ファーラーはオリヴィア・ニュートン・ジョン(以下ONJ)の世界デビューに大きく関与しています。元々、クリフ・リチャードの秘蔵っ子として、ONJはクリスやTHE SHADOWSファミリーのバックアップを受け大きくなっていくのですが、その中でファーラーも多くの曲をONJに提供しています。有名な曲としては「Have You Never Been Mellow(そよ風の誘惑)」、「Hopelessly Devoted To You」「Magic」、ジョン・トラヴォルタとのデュエット曲「You’re The One That I Want」などがあります。要するにメインライター、プロデューサーの一人だったわけです。その彼が1980年11月に発表したのがこの『John Farrar』。時代的にはAOR全盛時代の作品なので今聴くとピカピカ眩しすぎる感もありますが、収録曲はどれも秀逸。特にこの作品制作と前後してONJの大ヒット作『Physical』(1981年)にコンポーザー、プロデューサーとして関わったこともあり、半数以上の収録曲を作曲(トム・スノーとの共作もあり)ONJはアルバム『John Farrar』収録の「Recovery」、「Falling」をカヴァーしています。バラード「Falling」にほうは有名ですが、ここではやはり「Recovery」を推したいところです。このコード進行と構成はなかなか思いつくものではないと、今回の再発を機に聴き直してその思いを新たにしました。

Recovery
最近、こうした再発や企画ものに影響を受け、長いこと聴いていなかったものを改めて聴き直す機会が増えているのですが、聴かない間に勝手に作り上げられていたイメージが思い切り崩れ、目から鱗状態になることが多々有ります。次に紹介するDOWN ‘N’ OUTZもそんな体験のひとつでした。
DEF LEPPARDのジョー・エリオットとはフォノグラム時代からの付き合いで、1993年から約10年にわたりアーティスト担当をしていたこともあり、今もことあるごとにメールでやりとりしています。DEF LEPPARDのほうは今も活発な活動を展開しており、8月上旬から北米ツアーが始まり秋まで続くことになっています。
そんな彼から7月の初めくらいにメールで「THE ROLLING STONESの紙ジャケットCD探しているんだけど、見つからないヤツがあるんだよね」ってことでズラッとリストが送られてきました。要するに見つけてくれよ〜!ってことなんですが、リストを見ていくとですね。なるほど見つからないワケだ。だって、紙ジャケット化されていないんだもの。何といっても天下のSTONES、過去何回も紙ジャケット発売されていますし、そのアイテム数も半端ないこともあり、ジョーもなんでもかんでも紙ジャケットになっていると思うのはいたしかたないところなんですが、発売されていないものもあるのです。逆に考えるとそれ以外は持っていることになり、相変わらず拘って集めているなぁ、と妙に感心してしまいました。
ただ、ジョーのリスト中、『Love You Live』は紙ジャケット化されているのですが、検索かけてみるとあら〜、高いんだねぇ。プレミアついているんだ、これ。というわけで、持っているけど聴かんねぇ、という方は速やかにカケレコに送っちゃってください。高く買ってくれます。きっと。
現在、ジョーはTHE ROLLING STONES萌えモードに入っているようなので、うちにあった紙ジャケットBOXを8月頭の彼の誕生日プレゼントとして送ってあげたのですが、ことの他喜んでくれて速攻、御礼メールが来たのですが、それを見てびっくり! 7月の終わりになんと娘が生まれたとのこと。(ちなみに2人目。息子がひとり既にいます)彼、僕より一歳年下なので今年、57歳なんですが、ふと考えると娘が成人する時には70歳台後半ですからねぇ・・・やるなぁ、おっさんと妙に感心してしまいました。
ここ数ヶ月、ジョー・エリオットと頻繁に連絡取っている理由は手前味噌で申し訳ないのですが、9月に彼がサイドプロジェクトとしてやっているDOWN ‘N’ OUTZの作品群を最新作となる2014年のライヴDVD+CDを含め一挙4作品9月末に発売することになり、そのマスターやらアートワークの手配等のやりとりを本人と直接やっているからなのです。
2014年末のシェフィールドでのライヴは今年発売の新作なのですが、他3枚はとっくに海外は発売されており、最初の2枚はもう、手に入りにくくなっているし、本来、2014年ライヴも去年発売されるはずで、店舗に送る注文書は去年出ていたのですが、新作が遅れたことでどえらい延期となっていた、担当者としては頭痛の種的アイテムだったワケですが漸く発売の目処が立ちました。
DOWN ‘N’ OUTZはジョー・エリオットが敬愛してやまないMOTT THE HOOPLE、イアン・ハンターのトリビュート・プロジェクトです。ジョー・エリオットが関わったトリビュート・プロジェクトはこのDOWN ‘N’ OUTZの前に、CYBERNAUTSというデイヴィッド・ボウイがZIGGY STARDUST、ALADIN SANEだった頃の楽曲を取り上げたプロジェクトがあり、フォノグラム時代しっかり担当させられ、ツアーも行ったので覚えている方も多いのではないかと思います。もともと、ボウイの’70年代初期のバックバンド、SPIDERS FROM MARSのリズム・セクションだったトレヴァー・ボールダー(b)、ウッディ・ウッドマンジー(ds)と知り合ったことでスタートしたCYBERNAUTSはジョーが同じくDEF LEPPARDのフィル・コリンを巻き込んだことで一気に具体化し、アルバムを制作し、日本ツアーもやってしまったのですが、今考えるとこのプロジェクトはジョー・エリオットが何が何でもボウイやりたいという衝動一発が原動力で、DEF LEPPARD型デイヴィッド・ボウイの解釈は楽しかったのですが、いまいちコクが足りなかったような印象もありました。
まぁ、彼のグラム・ロックを愛するが故の止めようのない衝動の発露であり一種のガス抜きみたいなものという認識で、次はないだろうと思っていたのですが、2009年10月に今度はQUIREBOYSのメンバーを巻き込んでDOWN ‘N’ OUTZとしてロンドンのロックのメッカ、ハマースミス・アポロで興行をぶちかますという、二度目の大爆発に至ったのであります。
先にも書いたようにDOWN ‘N’ OUTZ はMOTT THE HOOPLEとイアン・ハンターへのオマージュを込めたバンドだったわけですが、CYBERNAUTSとの大きな違いは、CYBERNAUTSがデイヴィッド・ボウイの鉄板有名曲中心だったのに対し、DOWN ‘N’ OUTZはMOTT THE HOOPLEとイアン・ハンターの数多い楽曲の中でも決して有名曲とは言えないものをレパートリーとしているし、最後の「Good Times」なんて曲、MOTT/ハンターがらみの曲であったか?と思って聴いてみればなんとTHE EASYBEATSの曲だったり。MOTT THE HOOPLEとイアン・ハンター・トリビュートというスタイルをとっているものの、実はロックン・ローラー、ジョー・エリオットを形作ったものを伝える自伝的プロジェクトと言えるのかもしれません。今を遡ること45年前、12歳にして一丁前のロック小僧としてならし、毎日ラジオにかじりついていたエリオット少年はラジオ・ルクセンブルグが今週の1枚として流したMOTT THE HOOPLEの「Downtown」を聴いて以来、今日までずっと聴き続けてきたのです。グラム・ロック命の男で、ボウイもT. REXもROXY MUSICも大好きなんですが、MOTT THE HOOPLEとイアン・ハンター一党への傾倒は彼のグラム・ロック愛の中でも群を抜いていると思います。ちなみにジョーのMOTT THE HOOPLE初体験となった「Downtown」はMOUNTAINの「Long Red」(実際彼らもカヴァーしています。『Wildlife』に収録)のスタジオ・ヴァージョンにバブルガムのエッセンスを振りかけたかのようなポップでキャッチーなナンバー。1980年くらいに発売されたコンピレーション『Two Miles From Heaven』に収録されています。シングル発売時のB面は「Home」でした。
ジョーは今、STONESモードのようですが、僕はDOWN ‘N’ OUTZの発売準備をしている関係もあり、MOTT/ハンター・モードにどっぷりはまっています。そんなわけで今回はMOTT/ハンターがらみの作品をDOWN ‘N’ OUTZの最新作『THE FURTHER LIVE ADVENTURES OF DOWN ‘N’ OUTZ』(2014年12月20日ジョーの出身地、シェフィールドのクラブ、ザ・コーポレーションにて収録)のソング・オーダーに合わせ紹介していきましょう。
オープニングはMOTT/ハンターとは無関係のエルトン・ジョン1973年発表の『Goodbye Yellow Brick Road』冒頭のメドレー「Funeral For Friend ~ Love Lies Bleeding」。ジョー・エリオットお気に入りの曲です。ジョーがキーボードを弾く姿を観ることができるのですが、ま、今回のテーマからは外れているので飛ばします。ドラマティックに始まった後を受け、一気に全開モードに持っていくナンバーとして選ばれているのがBLITISH LIONSの「One More Chance To Run」。MOTT THE HOOPLEからイアン・ハンターが脱退し、MOTTとなりそこにMEDICINE HEADのジョン・フィドラーが加わったのがこのBLITISH LIONS。イギリスの音楽シーンがパンクからニューウェイヴへと移行していく、オールドウェイヴ・ロッカーにとっては冬の時代だった1978年に発表された1stアルバムのオープニングを飾っていた曲です。DOWN ‘N’ OUTZ版はずっしりと重量感がある演奏となっていますが、オリジナルはニューウェイヴ全盛ということもあり、その後登場してくるTHE CARSとかにも通じるハード・ロックとニューウェイヴの真ん中に位置するかなり個性的なサウンドとなっています。B級扱いされていますが、MOTTの後身ならではR&R感覚は今聴いても新鮮です。カケレコでもプッシュされていますしね。
One More Chance To Run
そういえば、このBRITISH LIONS、CD化された時にジョー、本気で喜んでいたことをよく覚えています。MOTTフリークだった彼はオリジナルLP発売時に即入手して何度も繰り返し聴いたようで、手軽にCDで聴けるようになったことが本当に嬉しかったみたいです。
「Rock And Roll Queen」は1969年発表のMOTT THE HOOPLEのデビュー作に収められていた曲であり、デイヴィッド・ボウイのサポートを受けCBSに移籍しブレークを果たしたのを受け、それまで在籍していた英ISLAND(アメリカはATLANTIC)が1972年に組んだ初期のコンピレーションのタイトルにもなった曲。1969年作品にしてはタイトにまとめられているし、この時代のハード・ロックとしてはかなりモダンなんですが、オリジナルは音がかなりこもり気味。その音質が初期MOTT THE HOOPLEの独特の雰囲気を醸し出していたのもまた事実。DOWN ‘N’ OUTZヴァージョンはまるでジョーの持ち歌なんじゃないかと思える堂々の歌いっぷり。オリジナルもDOWN ‘N’ OUTZ版もどちらも心躍ります。カッコいい曲だよね。
Rock And Roll Queen
続いて登場するのは、MOTT THE HOOPLEの代表作として今も高い人気を誇る『MOTT』(1973年)からの2曲。「Drivin’ Sister」と「Whizz Kidd」。「Drivin’ ~」はMOTTのライヴでも定番曲。典型的なSexソング。重要なのは後者の「Whizz Kidd」。とっつきにくいヴォーカルとどこか甘酸っぱいサビのメロディの対比が印象的でこの時代のイアン・ハンターがどれだけ輝いていた存在だったかの絶好のサンプルだと思います。突き放すような歌い方、ぽろっと字余り気味に最後に一行付け加えられたかのようなサビの締め方に少年時代のジョーは身をよじるくらいに感動したんでしょうね。後にスターになる彼の唱法にも大きな影響を与えた曲だと思います。DOWN ‘N’ OUTZ聴いていて嬉しくなるのは、ちょっとご無沙汰していた曲の良さを思いっきり再認識させてくれるところです。
Drivin’ Sister
Whizz Kidd
続く「Storm」も僕にとっては再認識ナンバー。元はMOTTに改名してからの1976年作『Shouting And Pointing』収録ナンバー。イアン・ハンター脱退後は聴いてはいたけどそれほど熱心だったわけでもなく、流していた感じでほとんど曲も覚えていなかったのですが、ジョーが歌っているのを聴いて「良い曲じゃん!」ってことでオリジナルを引っ張り出して聴いたら、かなり良かったですね。ハード・ロックとバッド・ボーイ・R&Rの中間の良いところに位置する好盤でした。BRITISH LIONSに好感を持っている方なら同じように楽しめると思います。DOWN ‘N’ OUTZのライヴでは2曲飛ばした9曲目でそのアルバム・タイトル曲「Shouting And Pointing」も演奏しています。
Storm
「Storm」に続くのはイアン・ハンター、1976年発表の3rdソロのタイトル曲「Overnight Angel」。弾けたイメージのCBS時代のMOTT THE HOOPLEを脱退後のハンターのソロはどこか内省的なイメージが強く、特にこの前の『All American Alien Boy』が取っ付きにくい印象だったため、このアルバムも印象に残っていなかったんですが、レイドバックとは異なる不思議なゆったり感と気だるい感覚を醸し出すDOWN ‘N’ OUTZヴァージョンを聴いて、オリジナルを繙けば、ずっと聴いてなくてすいません、と思わず反省の弁が口をつく優れもの。ジョー・エリオットくん、こちらの凝り固まった頭をどんどんほぐして忘れていた良いものを次々に耳に届けてくれています。次は1972年発表、MOTT THE HOOPLEの出世作『All The Young Dudes』からの有名なナンバー「One Of The Boys」。さすがにこれは皆さんご存じでしょう。
Overnight Angel
One Of The Boys
9曲目はさっきも書いた「Shouting And Pointing」。で、10曲目。「Sea Diver」。一瞬どのアルバムに入っていたか考えてしまいましたが、そうか『All The Young Dudes』のLPの最後の曲だ、と思い出したのは良いのだけど、これも中学生時代に聴いた時の感動をすっかり忘れていました。美しいピアノ・バラードでこの当時のランディ・ニューマンあたりにインスパイアされハンターはこの曲書いたのだろうな、と推測できるのですがオリジナルの最後のほうで鳴っている燻んだ色合いのスリングスの音色が絶品ですね。
Sea Diver
11曲目は「The Journey」。これもすっかり忘れていました。1971年末に英アイランドから出た4thアルバム『Brain Capers』収録曲です。この曲に大きな衝撃を受けたのが今回、DOWN ‘N’ OUTZとジョー・エリオットを取り上げるきっかけだったのですが、詳しいことは後で書かせていただくとして、先に進みます。12曲目にイアン・ハンターの1stソロ収録でこの人の曲としては珍しい、ウォーキング・テンポのブルース・ナンバー「Who Do You Love」を挟み、DOWN ‘N’ OUTZのライヴはクライマックスを迎えます。クライマックスはMOTT THE HOOPLEの1974年当時のライヴでもクライマックス、集まった観客が最高にエキサイトする場面で演奏されていた2曲1974年発表の『THE HOOPLE』から「Crash Street Kidds」そこから間髪入れずに「Violence」へと続いていきます。ストリート・ギャングの抗争をテーマとした「Crash Street Kidds」、下層階級の少年のやり場のないフラストレーションを題材にした「Violence」。共にCBS時代のMOTT THE HOOPLEがどうしてあれほどまでにティーンエイジャーの支持を集めていたのかがわかる熱く、怒りに満ち溢れたナンバー。少年時代のジョーもイアン・ハンターのアジテーターぶりに大きく心動かされてきたのでしょう。彼にとっては絶対外せない上にこれ2曲はセットになっていないと、という思いがあったのでしょう。MOTT THE HOOPLEのオリジナルのほうで、この部分を体験したい方は『Live: 30th Anniversary Edition』のディスク1で聴くことができます。『Live: 30th Anniversary Edition』はもともと1枚ものとして発売されていた『Live』の発売30周年を記念してCD2枚組にエクスパンドされたものですが、今から入手するなら絶対にこっちをお勧めします。
The Journey
Who Do You Love
Crash Street Kidds
Violence
DOWN ‘N’ OUTZライヴ、最後の締めは「England Rocks」。元歌はイアン・ハンターの『You’re Never Alone With Schizophrenic』収録曲で元々は「Cleveland Rocks」というタイトルでした。オハイオ州クリーヴランドはニューヨークやLAに比べ鈍臭い田舎町という印象を持たれていましたが、ハンターはMOTT THE HOOPLE時代から変わらず熱狂的に受け入れてくれるクリーヴランドが気に入っており、クリーヴランドへの敬意を込めてこの曲を発表しました。クリーヴランドの人々もこの曲が贈られたことに感謝を示し、地元のFM局WMMSでは発売当時、毎週金曜日の午後6時にこの「Cleveland Rocks」をオンエアーした他、クリーヴランド・ベースのスポーツ・チームも勝利の歌としてこの曲を率先して取り上げたという経緯があります。ハンターは後に歌詞の「クリーヴランド」部分を「England」に変えたヴァージョンを発表。こちらのほうは『The Singles Collection 1975-1983』を始めとするいくつかのコンピレーションに収録されています。DOWN ‘N’ OUTZが取り上げたのは、後から変更された「England」ヴァージョンということになります。サビの下降音階がアルバム『MOTT』の冒頭に収録されている「All The Way From Memphis」のピアノの旋律によく似ておりいかにもハンターらしい曲と言えるでしょう。
England Rocks
アンコールは後にAC/DCのプロデューサーとして名を成す、ハリー・ヴァンダとジョージ・ヤングが在籍したオーストラリアのビート・バンド、THE EASYBEATSのナンバー「Good Times」。1968年発表の『Vigil』に収録されていたナンバーです。BEE GEESと並びヨーロッパ、アメリカで大きな成功をバンドで特に有名なのは1966年のヒット曲「Friday On My Mind」。故ゲイリー・ムーア、ピーター・フランプトンをはじめ多くのアーティストにカヴァーされています。フリーク・ビート・マニアにも愛される名バンドです。この「Good Times」が収録された『Vigil』の頃になるとロック・バンドっぽく変化を遂げ、AC/DCサウンドにバブルガム・ポップの要素を加えたかのようなサウンドは当時ありがちといえばそれまででしょうが、ラジオにかじりついてヒット・ポップスにどっぷりはまっていたエリオット少年の心を鷲掴みにするには十分なインパクトがあったのでしょう。ジョーは想像して楽しむというのが多い人なので、きっと子供の頃、この曲を聴きながら、「僕がロック・スターになったら、アンコールでこの曲をやるんだ。誰もが楽しめる曲だからきっと盛り上がる」とか絶対想像していたと思います。ま、普通の人はそれで終わりなんですが、ジョーはDEF LEPPARDにしろこのDOWN ‘N’ OUTZにしろそれを実現させちゃったところが凄いんですけどね。
Good Times
さて、最後に今月の1枚。先に後で詳しくと書いた、MOTT THE HOOPLEの『Brain Capers』です。おそらく最も売れなかったMOTT THE HOOPLEのアルバムではないかと思います。チャート的にも惨敗していますしね。アートワークもなんだかイケてないパーティの案内みたいでイマイチな感じだし、どこか投げやりな雰囲気も漂っています。英国盤オリジナルLPは妙な傷がついているものも多いのですが、実は、どういう基準でつけられていたのかは判らないのですが、このアルバム発売当時アートワークにある黒いマスクが実際付けられていて、ゴムの部分がホッチキス止めされていたため、その圧痕で傷になったものもあったようです。今となっては完品のものはほとんど見ませんが、昔複数回売られているのを見ましたし、実際手元に持っています。

普通のファンにとってはCBS時代になってもライヴでは演奏されていた「Sweet Angeline」と冒頭の「Death May Be Your Santa Claus」くらいしか馴染みがない作品でしょうし、僕も第一印象地味ということもあり率先して聴くことはなく今日まで来てしまった作品でした。しかし、DOWN ‘N’ OUTZ版の「The Journey」を聴いてちょっと衝撃! 日に日に状況が悪くなっていくバンドが出口を求めてもがくかのようなやるせない空気が流れるこのバラード、今までどこを聴いていたのかと猛反省する最近の一番の衝撃でした。そこを起点に『Brain Capers』を聴き直していくと、その他大勢のブリティッシュではあってもアメリカ・ツアーも行っていたこともあり、イアン・ハンターが元々影響受けていたボブ・ディランはもちろん、ランディ・ニューマンやR&B系アーティストからの新たな影響も入ってきて、バンドは停滞し重苦しい雰囲気はあっても反面音楽性は広がりをみせ始めた時期だったことが解ります。そうでなくては「The Journey」な曲がポンと出てくることはないだろうと。
実際、MOTT THE HOOPLEはこのアルバムを最後にデイヴィッド・ボウイのバックアップを受けCBSに移籍し『All The Young Dudes』を発表し一気にブレイクしていくのですが、『All The Young Dudes』と『Brain Capers』がそんな劇的に違うのかと言われれば、光の当たり方が違うだけという印象も強くします。「The Journey」のような曲はわずかな光しかあたらなかった故に陰影がより濃く出た曲で、苦難の時代故に生み出すことのできた曲という気が強くしています。
音楽の聴き方は人によって大きく違うのは当たり前でしょうが、ジョー・エリオットの好きなバンドやアーティストの全てを受け入れ、咀嚼し自分の音楽表現に反映していくその姿から色々と学ばせてもらいました。確実にMOTT THE HOOPLE やイアン・ハンターの作品の聴き方は変わりましたし、この大きなヒントは他のアーティストを聴く上でも重要なものになっていくように思います。
関連カテゴリー
音楽歳時記 9月 妙な記念日山盛り~またも番外編
-
-
-
MOTT THE HOOPLE / MOTT
ロックン・ロール・バンドとしての魅力を発揮したセルフ・プロデュース作、73年作6th
デヴィッド・ボウイがプロデュースした前作『ALL THE YOUNG DUDES すべての若き野郎ども』により、一躍人気を獲得したモット・ザ・フープル。グラムバンドとして成功しても、「自分たちはロックンロールバンドだ!」と自負していていた彼らは、73年6thの本作をセルフプロデュース。ワイルドで妖しいイアン・ハンターのヴォーカルがグラムロックの華やかさを漂わせつつ、サウンドはギターを前面に出したストレートなロックンロールになっています。オープニング「All The Way From Memphis」から、キャッチーなロックンロールナンバーで、軽快なピアノのイントロから始まり、いったんトーンダウンすると、イアン・ハンターのヴォーカルとハードなギターが絡みながらじわじわ聴かせていき、テンポアップしたギターを合図にサビへ突入。コーラスも加わりキャッチーなメロディ−で一気に盛り上がり、間奏ではグルーヴィーなサックスが滑り込んで一段と盛り上げます。エネルギッシュなロックンロールバンドとしての魅力が十二分に発揮された傑作。
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!