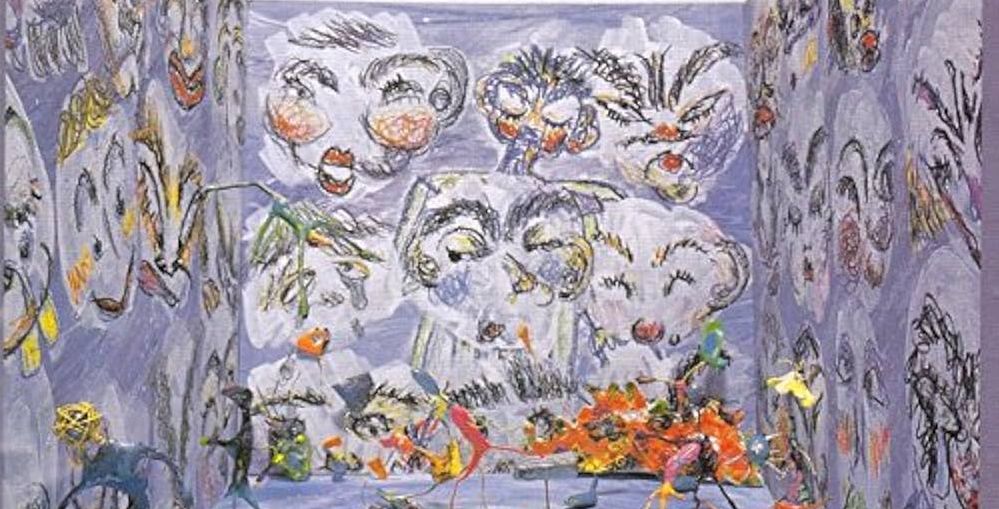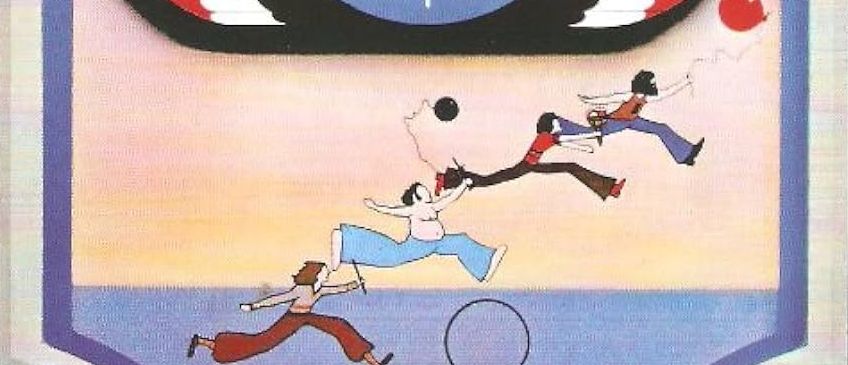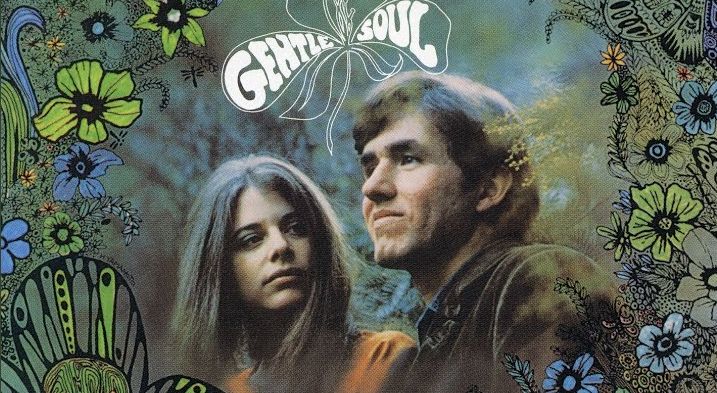「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ 60年目のユ・ウ・ウ・ツ篇」 第四十六回 高齢者にとっての〈二つのPT〉【後篇】 どうしてこんなに1980年代を想い出すんだろう。
2010年12月8日 | カテゴリー:-
タグ:

今月リリースされたばかりの、スティーヴン・ウィルソン選曲編集の4CD箱『STEVEN WILSON PRESENTS:INTRIGUE – PROGRESSIVE SOUNDS IN UK ALTERNATIVE MUSIC 1979-1989』が、なかなか感慨深い。

直訳すれば《UKオルタナ・ロックにおけるプログレ》、要するに「プログレ的なコンセプチュアルな思考や野心が1977年以降に突然消滅してしまったわけではないことを、1980年代のロックに懐疑的な人びとに知ってもらうため」に、彼が「野心的でストレンジでスリリング」と思う58曲を収録した、まるで学生の卒論タイトルのようなコンピ盤だ。
とりあえず収録アーティストを一部並べてみる。
WIRE。MAGAZINE。XTC。GANG OF FOUR。JOHN FOXX。WIRE。SIMPLE MINDS。THIS HEAT。GARY NUMAN。JAPAN。BILL NELSON’S RED NOISE。NEW MUSIC。SWELL MAPS。THE SPECIALS。ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK。JOY DIVISION。NEW ORDER。THE STRANGLERS。PIL。THE DURUTTI COLUMN。ECHO & THE BUNNYMEN。THOMAS DOLBY。KATE BUSH。THE CURE。PETER HAMILL。SCOTT WALKER。COCTEAU TWINS。THIS MOTAL COIL。TEARS FOR FEARS。A CERTAIN RATIO。IN CAMERA。MOMUS。THE SISTERS OF MERCY。THE ART OF NOISE。DEAD CAN DANCE。DAVID SYLVIAN。DALIS CAR。ROBERT FRIPP AND THE LEAGUE OF GENTLEMEN。TEARS FOR FEARS。PROPAGANDA。THE ASSOCIATESなど。
うわあ。どうしよう。そもそも目茶目茶かっこいいぞ。
なんかもうデジャ・ヴの洪水で、太平洋の彼方まで流されそうだ。
だって知人が経営するカフェバー(←死語)や服屋に頼まれて何度も作ったBGM用カセット群と、「ほぼ」同じプレイリストだもの。あとDANCE SOCIETYやTHE CREATURES、THE MONOCHROME SETなんかも入れたけど。当時の私はね。
ちなみにSWは、大人の事情で今回収録できなかった楽曲名までライナーに記載している。PREFAB SPROUTにRANDOM HOLDにTALK TALKにVIRGINIA ASTLEYにTHE BLUE NILEときた。おー。どんだけヴィニール・ジャンキーなんだあんたは。

数10倍の熾烈な競争倍率を毎月勝ち抜き、2P見開き原稿を6ヶ月連続掲載させて初めて『ロッキング・オン』誌のレギュラー執筆者になった1980年当時は、まだ予備校生だった私。採用されるためにはとにかく他人と違う原稿を書くしかないわけで、➊あえて軽薄な文体を採用する、➋世間一般と同じ理屈で褒めない・けなさない、➌独自のエビデンスとボキャブラリーを確立する、➍自分を切り売りする、❺現在で言うところの炎上上等――なんてことを常に意識していた。そして最も手っ取り早いのが、❻他人が書かないアーティストを書く。素材選びは大事です。
とにかく70年代物の需要が壊滅的な世の中だったから、当時の『RO』で人気はクラッシュにPILにXTCにジャムにストラングラーズ。ボウイにデビシル。ストーンズにさよならレノン。おおロック(失笑)。そんな同じ土俵で争っても不毛なのでロキシーを橋頭保に、馬鹿にして誰も手を出しそうにない新ジャンルの、ニュー・ロマンティックスや英シンセ系ニューウェイヴを「あえて」選んだ。
ヴィサージとかデュラン×2とかクラシックス・ヌーヴォーとかアダム&ジ・アンツとか、渋谷陽一社長や松村雄策さんからは「グラム・ロックの偽物聴いてどうする?」と説教されたけれど、世界観そのものは嫌いじゃないし、頭でっかちのROとはおもいきり無縁のダンスフロアと最新英盤12インチシングルが主力メディアという機動性と能動性が、新鮮だった。髪を切り、当時まだ流行り始めのDCブランドを着て、的なフリップの『エクスポージャー』第二の青春デビューを笑えない「若気の至り」も含め。
だってニューウェイヴ・ディスコ(←死語)じゃ、PILの“ディス・イズ・ノット・ラヴソング”やスジバンの“呪文”やキャプテン・センシブルの“ハッピー・トーク”やブルーベルズやチャイナ・クライシスで皆、盛大に踊ってるんだよ? とてもフルアルバムを出せそうにない有象無象の新人たちのシングルを漁り、仲間内で面白がるためだけに青田刈りするんだよ?
すると必然的にエレポップやゴス、90年代に前代未聞のモラトリアム・ポップ〈渋谷系〉を開花させちゃうネオアコもその誕生から書き倒したわけで、その頃読者だった高校生の小山田圭吾は「軽薄な原稿書きやがって」と私を心底嫌っていた――とのちに本人から告白されるってどうよ。
各種シンセやらシーケンサーやらヴォコーダーやらドラムマシンやら新楽器の登場で、いわゆる70年代ロックの大前提だった〈卓越した楽器演奏力〉がなくても楽曲が作れるようになり、これまでなら陽の目を見ることは決してなかった感性一発の新鮮なロックが続々と登場したのだから、面白くないはずがない。未熟であるがゆえの粗暴なアンサンブルのストイックさが胸を打つポスト・パンクなバンドたちも、後を絶たず。チープでも短絡的でも勘違いでもアルバム一枚もたなくても、全然赦せた。
平日の早朝28時にNHKのBSプレミアムで繰り返し再放送されてる『MUST BE UKTV』は、有名アーティストのみならず80年代英シングル・チャートにちょっとでもかすった連中を、十把一絡げで目撃することができる。正直、7割方は笑うしかない。偽ユーリズミックスとか偽スタイル・カウンシルとか偽デペッシュ・モードとか、もう腐るほど大量発生していたのがよくわかる。
そんなおもいきり玉石混淆だったけども、ポップだったり斬新だったり実験的だったりで、弛緩してたロック村がとりあえず一気に活性化した感があったのだ。素人の台頭、もっと言うと、我々リスナーの大逆襲に他ならない。
かつてジョン・ウェットンは「25歳以上の楽器をちゃんと弾けるミュージシャンが英国の音楽紙には絶対載らなかった1976年以降は、一巻の終わりかと思った」と嘆き、キース・エマーソンは「ドラム・マシーンやシーケンサーの出現でそれこそ誰でもレコードを作れるようになった80年代は、ミニマリストの時代」と諦観していた。たしかにパンク/ニューウェイヴ勃興以降が受難の時代と化した彼らは不幸だったが、ありとあらゆる〈新しい音楽〉の瞬間最大風速を体感できた私は幸運だったとつくづく思う。
「野心的でストレンジでスリリング」だと思ったから、私も推した。「新しい音をとにかく早く見つけて沢山聴かなきゃ」的な強迫観念に苛まれはしたが、いろんな未知なものが堰を切ったように溢れてくるドキュメントをリアルタイムで共有できるなんて、〈60~70年代ロック追体験世代〉の身には何しろ初めての経験だ。乗っからない奴がどうかしてる。たぶん同じように面白がった(に違いない)SWの部屋の床が、聴き漁ったレコードの重みで抜けた(らしい)話がまた、素敵じゃないか。
さすが私とたった五歳違い。

ポーキュパイン・ツリーは、いくら聴いても胸躍らないから面白い。
と前回書いた。録音された全ての音に敬意を表して際立たせるSWの〈リミックスの流儀〉そのままに、準備万端考え抜かれた〈理詰め〉のPTワールドでは、どんな破綻も偶然も起こらない。無類の隙のなさが生む強靭なストイシズムが、聴く者をひたすら圧倒する。だけど、どの音もすべからくはっきりしっかりくっきり聴こえるから、実はバンド感は希薄だったりする。しかもあんなにハードでインダストリアルなのに、クール。
つまりPTとは、あくまでもSWにとっての〈机上の理想論〉バンドに他ならない。この天然物に固執しない感覚は、やはり思春期にあの80年代を原体験したからこそだ。マインド的にもメソッド的にも彼自身が、PTのみならずNO-MANやブラックフィールドなどとにかく演りたい音楽のフォルダでいっぱいのデスクトップでいられることも含めて。
友人の特撮おたくの編集者によれば、かつて我々が観ていた昭和の『仮面ライダー』と平成以降の『仮面ライダー』は、同じ『仮面ライダー』でも物語的互換性は皆無の同音異義作品で、だからこそ旧態依然としたお約束事に縛られることなく次のフェーズに楽に移行できたらしい。一方、平成以降も昭和のウルトラ兄弟的世界観をどうしても捨てられない『ウルトラマン』は、果てしない無限ループの末にシュリンクしてしまった。
人材不足と演奏力の呪縛から解放され自由な発想が陽の目を見た1980年代を、主観的に過ごしたSWのような人材がいただけでも、ウルトラマンの悲劇だけは免れたのかもしれない。プログレって。
よくよく考えたら、本気でポール・ヤングの線を狙ってたジャコ・ジャクジクも、そのポール・ヤングやリサ・スタンスフィールドのバックで叩いてたギャヴィン・ハリスンも、燃え尽きたエコバニやアズカメを看取ったジェレミー・ステイシーも、シアトルでクリムゾンを追体験しながらゴスの洗礼を受けてインダストリアル・ロック全般に走ったビル・リーフリンも皆、ポスト70年代ロックを至近距離で体験してきた人材だったりする。
また、exカジャ・グー・グーのニック・ベッグスやスパンダー・バレエのゲイリー・ケンプを、スティーヴ・ハケットやニック・メイスンズ・ソーサーフル・オブ・シークレッツの現場で見つけると、何十年ぶりかに逢った旧友に思えるから不思議だ。「識者」たちから馬鹿にされてたもんなあお互い。
90年代が開幕するやいなや、「何も生まれなかった十年」と英米でも酷評され続けた80年代だけれど、捨てたものではないのだ。
たとえばヒューマン・リーグにヘヴン17、キャバレー・ヴォルテールやABCやトンプソン・ツインズらを輩出した英シェフィールドだって、カンタベリーみたいに〈シェフィールド・ロック〉とか〈シェフ系〉とか命名されてもいいのではないか。
ないないない。
ポーキュパイン・ツリーというかスティーヴン・ウィルソンのアイディアやサウンド・デザインとその独特なダイナミズムに、とてもティアーズ・フォー・フィアーズっぽさを感じるのは、たぶんこうした音楽的思春期事情のせいだ。そして音楽的には異なるけれど、底なしの好奇心を見事に具現化させた、ナイーヴな上に几帳面であるゆえの人並外れた〈辻褄合わせ〉癖を、TFTとPTは共有している。主観をマウントしてしまうその驚異の客観力こそが、ヴィンテージをしっかり踏まえたモダン・ロックとしての両者を成立させた張本人なのである。
そういう意味では、〈80年代的なもの〉こそ実はヴィンテージとモダンの懸け橋だったのかも、と思うとなんだか感慨深い。
だから、内省的なのにスタジアム・ロックな『ソングス・フロム・ザ・ビッグ・チェアー』も、偏執的ポップの『シーズ・オブ・ラヴ』も、そして昨年リリースされた18年ぶりの新作『ザ・ティッピング・ポイント』も、TFTからSWが5.1サラウンド・ミックスを任せられ続けてるのは、至極当然なのだ。同じ沼のムジナだもの。
ただしスティーヴン・ウィルソンもローランド・オーザバルも、ギターを自分で弾きたがるのは控えた方がいいと思う。
とはいえPTのきんきんする音色は耳鳴りを誘発するので、あんまり聴き続けると身体的にしんどい。そんな私にありがたい存在が、〈もう一つのPT〉ザ・パイナップル・シーフだったりする。

ポーキュパインほど緻密でも万能でもない代わりに人力度が高い、変拍子アンサンブルに絡むブルース・ソードの躍る物憂げヴォーカルが、聴けば聴くほど病みつきになるのだ。意外に。まさに灯台下暗しの、〈唄物プログレ〉もしくは〈ヴォーカル・オリエンテッド・プログレ〉。
ソードが優秀なのはライヴに適したそんな特性を的確に自覚している点で、ギャヴィン・ハリスンが正式加入した2016年以降、『YOUR WILDNESS』→『WHERE WE STOOD』に『デソリューション』→『ライヴ!~Dissolution Tour 2018~(HOLD OUR FIRE)』と、スタジオ新作の翌年には必ずそのライヴ盤を制作してきた。2020年に『VERSIONS OF THE TRUTH』のツアーをコロナ禍で自粛した際も、無観客スタジオ・ライヴ盤『NOTHING BUT THE TRUTH』を翌年出しちゃうのだから、徹底している。
それほど彼らの物憂げな疾走感溢れる人力アンサンブルは、ライヴがよく似合うのだ。

そもそもはポーキュパインのアルバム『スチューピッド・ドリーム』をリリースするため、英《Snapper Music》傘下に1999年設立させたレーベル《Kscope》に、SW自身がスカウティングしたのがパイナップル・シーフだ。「ポーキュパインのソフィスティケイト版」と言っちゃうと身も蓋もないが、二大モダン・プログレ・バンド〈二つのPT〉の一翼としてレーベルの顔を担ってきた。2009年の『ジ・インシデント』以降、ポーキュパインがずーっと開店休業したのも大きい。
そして「僕のレーベルだったはずなのに、シーフ以外はくそバンドばっか勝手に集めやがるから縁を切ります」と、怒れるSWに三行半を一方的に突きつけられた2016年以降は、《Kscope》も絶対的エースとしてシーフを力入れまくりで売りに出た。とはいえ、体育館で行なうバレーボールとグラウンドで行なうバレーボールぐらい、似て非なる両者なんだけどもね。

ところがSW+ハリスン+リチャード・バルビエリのトリオ編成で昨年再起動したポーキュパイン・ツリーの、実に13年ぶりの新作『クロージャー/コンティニュエイション』が、「SWにしては」おもいきりフィジカルなロック・アルバムだったのには驚いた。しかも9月から北米、10月に中南米を挟んで欧州ツアーまで敢行したのだから、絵に描いたようなバンド・オン・ザ・ランじゃないか。
《辞めるか続けるか》という最終通告みたいなタイトルも含め、異色ずくめの新作だ。コリン・エドウィンの〈場違いなフレットレス〉が聴けなくなったのは残念だが、SW一人の遠大なる妄想バンドではないポーキュパイン・ツリーが、30年目にしてやっと実現した感がある。

これまで一人でほぼ全曲書いてたSWが、今回は10年前からハリスンと二人でちょこちょこジャム・セッション(!)する中で作り続けてきたマテリアルだという。しかもハリスンのドラムから生まれるアイディアにベースで対応しながらの共作だから、画期的だ。だからなのか、一曲の中で小節の長さが変化し続ける〈変拍子の連続ドラマ〉みたいなのやら、〈変拍子のかくれんぼ〉みたいな実は数学的展開のバラードやら、どの楽曲も「まずドラムありき」の痕跡があからさまで面白い。
バルビエリに関しては、あくまでもジャムとは別工程で「彼らしいサウンドメイク」を施すのが課せられた職務だったようで、見事なバンド内適材適所ではある。なお、やたらスリリングなギターを聴かせるのはゲストの、高齢プログレッシャーズにとっては、〈#元オアシス&ブラック・クロウズ〉より〈#ジェレミー・ステイシーの双子の兄〉で馴染み深いであろうポール・ステイシーです。ほら、達者なひとに任せた方がいい。
そういう意味では相変わらず理路整然とデザインされてはいるものの、とにかく求心的で性急なバンド・アンサンブルを過去最高の人力度で実現したポーキュパインだ。じゃあなぜSWはこの13年間、魅力的なこのマテリアルを温存してきたのだろう。
さあ。それは知らん。
ただひとつ言えるのは、冒頭で書いた《UKオルタナ・ロックにおけるプログレ4CD箱》収録曲たちの、いま聴いても耳が切れそうな表現衝動のフリーキーさを、この新作がおもいきり共有しているということ。1980年代とともに10代の思春期を迎えたSWの最初で最後のオトシマエが、この(たぶん)ラスト・ポーキュパイン・ツリーなのかもしれない。
内省的なダイナミズムといい、もってまわったリリシズムといい、几帳面なフレキシビリティーといい、やはりこの男は永遠の〈服を着た1980年代〉なのである。

偶然にもほぼ同時期のリリースとなったパイナップル・シーフの新作は、「NO MORE映画泥棒」の新キャラにしか見えないレコードロイド(←勝手に命名しといた)らが整列する『GIVE IT BACK』。2020年のレコード・ストア・デイ限定赤盤12”シングル“Uncovering The Tracks”同様の、ギャヴィン・ハリスン加入以前の楽曲のリメイク・リモデル集で、〈唄う変拍子ロック〉っぷりはますます加速している。根本的にメロディアスだしメランコリックだし――狙ってこれを演ってたのなら、すごい。
ところがおそらく「天然」だから、ブルース・ソードはすごくない。
かつてアルバム『SOMEONE HERE IS MISSING』のアートワークを憧れのストーム・トーガソンに手掛けてもらったときの、子供のようなはしゃぎようが象徴的だろう。ウィルソンの5歳下ならではの能天気さも、影響しているかもしれない。
他にも、シーフでメロトロンを導入した際の「イエスでリック・ウェイクマンがメロトロンを使ったときは最新の楽器と見られたけど、いま僕が絶対使いたいと思って使うと、ヴィンテージな楽器と思われるから面白いよ」発言――実は物事の本質を突いてるのに、残念ながら本人は気づいてなかったフシがある。しかし、だから素敵なのだ。
『GIVE IT BACK』と『クロージャー/コンティニュエイション』。期せずして二つのPTの最新作は共に、バンド・アンサンブルならではの息遣いを超至近距離で感じられる能動的なアルバムだった。〈天然物〉と〈養殖物〉および〈自然〉と〈人工〉という、シーフとツリーの違いを超越した着地点の一致は偶然、ではなく必然と思いたい。
すると、新作に尋常じゃない影響を及ぼしているハリスンの存在が、嫌でも際立つ。彼のドラムに触発されてウィルソンは新曲を作ったわけだし、ソードの〈唄うプログレ〉が成立するのも彼の変拍子あってこそだ。そもそも楽団クリムゾンの三人太鼓があれだけ機能したのも彼が理論的に統率したからであり、《ギャヴィン・ハリスン》という優秀なリズムアプリ争奪戦はますます激化するに違いない。

とはいえDL「させていただく」ために三顧の礼を尽くすのは、人の世の常だ。両PT共ドラムのミックス権をハリスンに委ねてるし、他のメンバーよりも共作クレジットも多く明らかに優遇している。他のセッション仕事でも必ずドラム・ミックスはハリスン自身だから、これはトリセツの1頁目に赤字で明記されてると見た。
もちろん、DL主も気を遣った分だけアプリをフル活用してて微笑ましい。
ツリーのライヴDVD+2CD『ARRIVING SOMEWHERE…』に特典映像としてわざわざ収録されたのは、その名もずばり“Cymbal Song”。のちに楽団クリムゾンのライヴで披露する「俺のパーカッション芸に酔いしれなよ」曲“バンシー・レッグス・ベル・ハッスル”の元祖みたいなもので、多種多様なシンバル音だけで聴かせる自意識高めの楽曲だ。全てのシンバルを叩くハリスンの手許をマルチアングルで同時に観せるのだから、これはこれで可笑しい。
シーフも負けていない。スタジオ・ライヴ盤『NOTHING BUT THE TRUTH』の限定箱に収録されてる映像版のメニュー画面には、《DRUM CAM ON/OFF》という見慣れぬ表示が。はい。起動させればご想像通り、ドラムを叩くハリスンの映像が画面左上に1/4弱大のサイズでずーっと映り続けるのであった。
ブレイキン観るよりはるかに愉しめましたけどね私は。

第一回「ジョン・ウェットンはなぜ<いいひと>だったのか?」はコチラ!
第ニ回 「尼崎に<あしたのイエス>を見た、か? ~2017・4・21イエス・フィーチュアリング・ジョン・アンダーソン、トレヴァー・ラビン、リック・ウェイクマン(苦笑)@あましんアルカイックホールのライヴ評みたいなもの」はコチラ!
第三回「ロバート・フリップ卿の“英雄夢語り”」はコチラ!
第四回「第四回 これは我々が本当に望んだロジャー・ウォーターズなのか? -二つのピンク・フロイド、その後【前篇】-」はコチラ!
第五回「ギルモアくんとマンザネラちゃん -二つのピンク・フロイド、その後【後篇】ー」はコチラ!
第六回「お箸で食べるイタリアン・プログレ ―24年前に邂逅していた(らしい)バンコにごめんなさい」はコチラ!
第七回「誰も知らない〈1987年のロジャー・ウォーターズ〉 ーーこのときライヴ・アルバムをリリースしていればなぁぁぁ」はコチラ!
第八回「瓢箪からジャッコ -『ライヴ・イン・ウィーン』と『LIVE IN CHICAGO』から見えた〈キング・クリムゾンの新風景〉」はコチラ!
第九回「坂上忍になれなかったフィル・コリンズ。」はコチラ!
第十回「禊(みそぎ)のロバート・フリップ ーー噂の27枚組BOX『セイラーズ・テール 1970-1972』の正しい聴き方」はコチラ!
第十一回「ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)前篇 --BOXを聴く前にブライアン・フェリーをおさらいしよう」 はコチラ!
第十二回 「ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)後篇 --BOXを聴いて再認識する〈ポップ・アートとしてのロキシー・ミュージック〉」はコチラ!
第十三回 「今日もどこかでヒプノシス」はコチラ!
第十四回 「ピーター・バンクスはなぜ、再評価されないのか --〈星を旅する予言者〉の六回忌にあたって」はコチラ!
第十五回 「悪いひとじゃないんだけどねぇ……(遠い目) ―― ビル・ブルフォードへのラブレターを『シームズ・ライク・ア・ライフタイム・アゴー 1977-1980』BOXに添えて」はコチラ!
第十六回 「グレッグ・レイク哀歌(エレジー)」はコチラ!
第十七回 「クリス・スクワイアとトレヴァー・ホーン -イエスの〈新作〉『FLY FROM HERE -RETURN TRIP』に想うこと- 前篇:スクワイアの巻」はコチラ!
第十八回 「クリス・スクワイアとトレヴァー・ホーン -イエスの〈新作〉『FLY FROM HERE-RETURN TRIP』に想うこと- 後篇:空を飛べたのはホーンの巻」はコチラ!
第十九回「どうしてジョン・ウェットンを好きになってしまったんだろう(三回忌カケレコスペシャルversion)」はコチラ!
第二十回「どうしてゴードン・ハスケルは不当評価されたのだろう ー前篇:幻の1995年インタヴュー発掘、ついでに8人クリムゾン来日公演評も。」はコチラ!
第二十一回「どうしてゴードン・ハスケルは不当評価されたのだろう -後篇:幻の1995年インタヴューを発掘したら、めぐる因果は糸車の〈酒の肴ロック〉」はコチラ!
第二十二回「鍵盤は気楽な稼業ときたもんだ--あるTKの一生、に50周年イエス来日公演評を添えて」はコチラ!
第二十三回「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう(by ビリー・シャーウッド)」はコチラ!
第二十四回「荒野の三詩人-誰かリチャード・パーマー=ジェイムズを知らないか-」はコチラ!
第二十五回「会議は踊る、プログレも踊る-リチャード・パーマー=ジェイムズを探して-」はコチラ!
第二十六回「我が心のキース・エマーソン & THE BEST ~1990年の追憶~」はコチラ!
第二十七回:「『ザ・リコンストラクション・オブ・ライト』は、キング・クリムゾンの立派な「新作」である。 プログレ「箱男」通信【KC『ヘヴン&アース』箱】号①」はコチラ!
第二十八回:「《The ProjeKcts》の大食いはいとおかし。 プログレ「箱男」通信【KC『ヘヴン&アース』箱】号②」はコチラ!
第二十九回:「ロバート・フリップの〈夢破れて山河あり〉物語 プログレ「箱男」通信【KC『ヘヴン&アース』箱】号➌」はコチラ!
第三十回:「封印された〈車道楽プログレ〉ー『レイター・イヤーズ 1987-2019』箱から漏れた、ピンク・フロイドVHS『道(MICHI)』」はコチラ!
第三十一回:「どうしてプロレスを好きになってしまったんだろう。へ?」はコチラ!
第三十二回:「LEVINは何しに日本へ? の巻」はコチラ!
第三十三回:「どうして日本人はキング・クリムゾンを唄いたがるのだろう -雑談三部作・完結編-」はコチラ!
第三十四回:「コロナの記憶:どうしてビル・リーフリンを忘れられないのだろう トーヤ&フリップ「夫婦善哉」への道」はコチラ!
第三十五回:「キル・ビル/ビル・ブル 極私的「60歳からのプログレッシヴ・ロック」論」はコチラ!
第三十六回:「イエスCD+DVD34枚組『ユニオン30ライヴ』boxは、20世紀からの玉手箱か?」はコチラ!
第三十七回:「ジャコ・ジャクジクが〈ポール・ヤング〉に憧れた日 1980年代に遺したJAKKO青春の蹉跌シングルズを徹底追跡してみた。」はコチラ!
第三十八回:「「妄想」は荒野をめざす 『キング・クリムゾンー至高の音宇宙を求めて』40年目の読書感想文」はコチラ!
第三十九回:「ニーナ・ハーゲンは最強の〈ジャーマン・プログレ〉である。」はコチラ!
第四十回:「とあるキャメルの「不幸」」はコチラ!
第四十一回:「まずは、さよならキング・クリムゾン。」はコチラ!
第四十二回:「(第41回からの)日曜日のお昼ごはん。【前篇】ロバート・フリップと渡辺明」はコチラ!
第四十三回:「(第41回からの)日曜日のお昼ごはん。【後篇】トーヤと伊奈めぐみ」はコチラ!
第四十四回:「(第41回からの)高齢者にとっての〈二つのPT〉【前篇】ウドーちゃん祭りでポーキュパイン・ツリーを観た。」はコチラ!
第四十五回:「高齢者にとっての〈二つのPT〉 【中篇】スティーヴン・ウィルソン「息苦しさ」の美学」はコチラ!
STEVEN WILSONの在庫
-
STEVEN WILSON / INSURGENTES
ミキシングの名手としても知られるPORCUPINE TREEのリーダー、08年ソロ作
-
盤質:傷あり
状態:良好
スリップケース無し、盤に指紋跡あり、ケースにスレあり
-
-
STEVEN WILSON / RAVEN THAT REFUSED TO SING AND OTHER STORIES
PORCUPINE TREEの中心人物、プログレ名盤の数々を手がける名ミキサーとしても活躍する英ミュージシャン、13年作。アラン・パーソンズのプロデュース。
-
デジパック仕様、直輸入盤(帯付仕様)、定価2300+税
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
帯裏にシールが貼ってあります
-
STEVEN WILSON / 4 1/2
PORCUPINE TREEの中心人物、往年のプログレ名盤の数々を手がけるミキサーとしても活躍する英ミュージシャン、16年作
-
デジパック仕様、スリップケース付き仕様、ボーナス・トラック1曲、定価2700+税
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
盤に汚れあり、帯に折れあり
-
-
-
PORCUPINE TREEの在庫
PINEAPPLE THIEFの在庫
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!