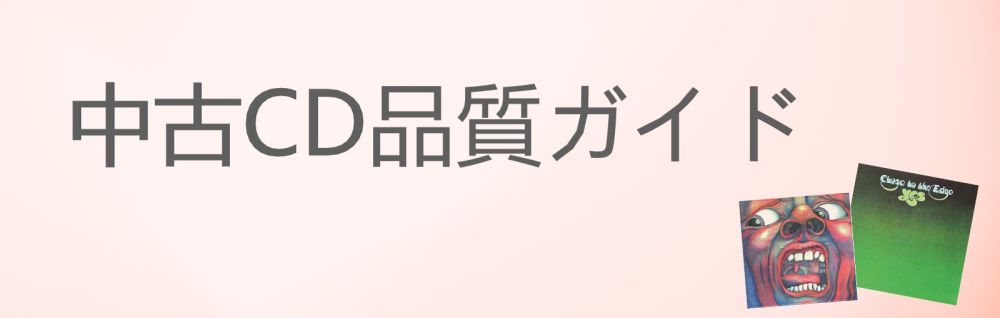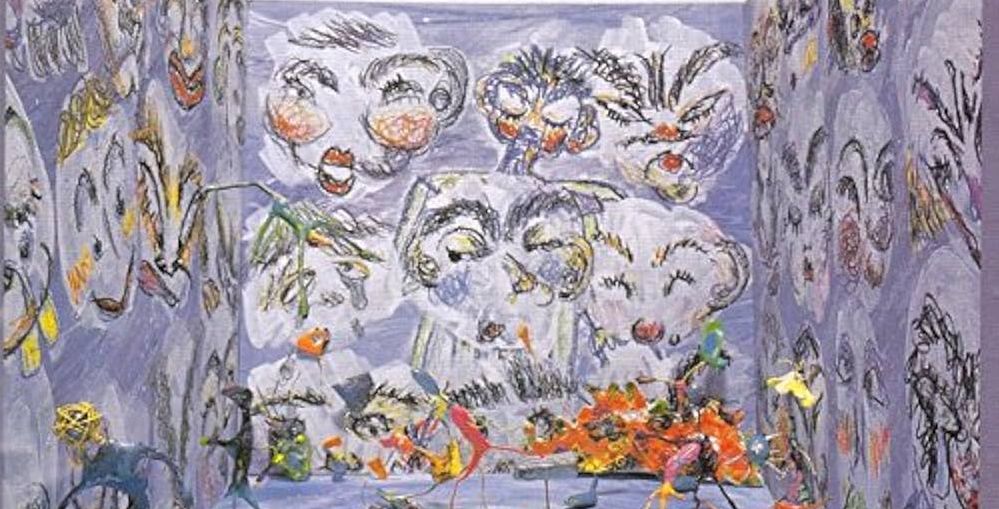「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ」 第二十一回: どうしてゴードン・ハスケルは不当評価されたのだろう -後篇:幻の1995年インタヴューを発掘したら、めぐる因果は糸車の〈酒の肴ロック〉 文・市川哲史
2019年3月9日 | カテゴリー:どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ 市川哲史,ライターコラム
タグ:

第二十一回: どうしてゴードン・ハスケルは不当評価されたのだろう -後篇:幻の1995年インタヴューを発掘したら、めぐる因果は糸車の〈酒の肴ロック〉

たったひとりでロバート・フリップに立ち向かった男、ゴードン・ハスケル物語の続きである。どれだけ需要があるのか不安だが、気にしない。だってキング・クリムゾンに対して、世界で唯一ネガティヴなOBなのだから。

ハスケル1990年発表の3rdアルバム『ハンブルドン・ヒル』と1992年の4thアルバム『ドライヴ・ユー・クレイジー』が、1995年盛夏にMSIから日本発売されることとなり、ライナーノーツを書く際に実現した電話インタヴューのテープ起こし原稿が、唐突に実家で発見された。この自家製アーカイヴ――当時のハスケルのインタヴューなんてきっと貴重なので、24年ぶりの原稿化だ。
ハスケル同様、過小評価されまくったOBにデヴィッド・クロスがいる。毎晩毎晩ライヴでウェットン&ビルブルの轟音絨毯爆撃に翻弄されたあげく、心が折れちゃった可哀相なひとだ。脱退後もミュージシャン活動はぱっとせず学校の先生に身をやつしてたし、『USA』でヴァイオリンをエディ・ジョブソンにオーヴァー・ダブされた惨劇も、『紅伝説』で唄はエイドリアン・ブリュー、ベースはトニー・レヴィンに差し替えられたハスケルと同じ匂いがする。

それでも1997年の5thソロ・アルバム『EXILES』が“突破口”、2015年のフリップとの連名アルバム『スターレス・スターライト』は“スターレス”がおもいきりモチーフのクロスのクリムゾン依存体質に較べ、〈赤の他人〉を貫き続けたハスケルの、なんと潔いことか。
しかし、フリップへの恨みをまだまだ抑えきれなかった1995年当時のハスケルも、それはそれで微笑ましいのである。では後篇、いきます。
ハスケル クリムゾンに一時期在籍してはいたけれど、僕自身としては残念ながら何の印象も感銘も受けなかったというのが、現実なんだ。クリムゾンを崇拝する評論家たちが何と言おうと、僕の人生の中では何の転機にもならなかったのさ。
市川 あなたが在籍したクリムゾン唯一のアルバム『リザード』は、キース・ティペットら英国ジャズ系ミュージシャンたちの参加が最大の個性と捉えられてますが、当事者としてはどうですかね。
ハスケル まだFDLに在籍していた頃に、米国人ソングライターが書いた最高のマテリアルを、いわゆる本物のジャズ・ミュージシャンたちがプレイするのを目の当たりにしてたから、彼らに対して強い関心はなかったよ。
市川 あらら。一方、イエスというよそのバンドの顔であるジョン・アンダーソンに、“ルーパート王子のめざめ”を唄われてしまいました。庇を貸して母屋を取られたというか。
ハスケル でもあの楽曲の制作には、個人的な事情からまったく関わることができなかったから、思ってもみなかった出来事だったねあれは。
市川 なんですか〈個人的な事情〉って。
ハスケル ……僕とアンディ(・マッカロック)は当時、レコーディングしていた作品にまったく興味を持つことなく演奏していただけだからな。でもロバートとピートだって、自分たちが求めているものが何かわからないまま、スタジオ作業に明け暮れてただけとしか思えなかったし(失笑)。
市川 結局、1971年1月からのツアー用リハ中に脱退しちゃったんでしたっけ。
ハスケル リハが始まってまもなく、“21馬鹿”のグレッグ(・レイク)のキーが僕には高過ぎるから、「下げてほしい」とロバートに頼んだのさ。すると彼の答えは、「ヴォーカルは加工するから大丈夫」。さすがに頭に来たから、「ステージに上がるつもりはないし、自分が確信持てない楽曲は唄いたくない」と言い放って、スタジオを出ていった。
市川 うわ。フリップたちの反応はどうでした。
ハスケル その場に居合わせたピート(・シンフィールド)とメル(・コリンズ)は、お通夜のように黙ってた。ロバートは――「それでも印税はもらえるからな、ゴード」の一言だけだったよ。
市川 それ、『紅伝説』であなたの唄やベースが差し替えられた伏線としか思えませんわ。あのときツアーが中止になったことを相当、彼は根に持ってましたから。
ハスケル そうだろうね。
市川 あなたにとってのクリムゾンとは、〈フリップとの確執〉がすべてだったような。
ハスケル 簡潔に言えば――イエスだよ。僕もいまなら、ロバートと対等に付き合うことができるだろう。もちろん音楽的意見が合うわけじゃなくて、力関係の問題だよ? ビジネスとか物事の是非とか倫理観とかだ。いまでもロバートは、当時の僕を「単なるセッション・メンバーだった」と言ってるよね……彼にとって僕は〈一家の恥〉みたいな存在だったから。
市川 そこまで言わんでも。
ハスケル 『リザード』の楽曲を唄ってるうちに、僕は自分を偽ってるのがしみじみわかった。あのままクリムゾンに残っていれば、儲かっていたとも思う。でも僕は、違う意味で自分が豊かになれる道を選んだんだ。クリムゾンは酷い悪夢だった……が、自分のどこが間違っているかをはっきりと教えてくれた。だから、神が与えた試練のようなものさ。神よ感謝します、ロバートよ感謝します。
市川 いまや達観しております。でも脱退直後のあなたに、なにがしかの音楽的方向性は見えていたんでしょうか。
ハスケル キング・クリムゾンに参加し、おまけに脱退してしまったような愚か者の僕が、どの面下げて音楽的指針なんて言える? 当時の僕は愛によって突き動かされていたけれど、それは僕のロング・アンド・ワインディング・ロード人生にしか関わりないことだ。僕は60年代を終わらせたくなかった。しかし終わりは呆気なく訪れ、そしてゴミみたいな80年代へと続き、現在の混乱に至るわけさ。
とお先真っ暗だったはずのハスケルは、クリムゾンを脱退したばかりの1971年に、それこそ彼が大好きなアトランティック・レコードから2ndソロ・アルバム『歳時記』を速攻でリリースできた。あら。
同郷ジョン・ウェットンを介して旧知の仲だったモーガル・スラッシュの元マネージャー、ジョン・ミラーからアトランティック・レコード創設者にしてレイ・チャールズやアレサ・フランクリンを売った、アーメット・アーティガン――のちに2007年12月10日開催の、レッド・ツェッペリン一夜限りの再結成《復活の日》で追悼された、あのひとがロンドンに滞在中と聞き、超内省的なハスケルが自らを積極的に売り込んだ。御前試合というか、アコギで6曲披露したらしい。するとアーティガンは心底ハスケルを気に入り、契約を交わしたばかりか個人的な借金まで肩代わりしてくれたのだ。
天国から地獄へそして天国へ、とは数奇な人生である。
プロデュースはハスケルの希望が叶い、当時アトランティックのハウス・プロデューサーだったアリフ・マーディン。アレサやダニー・ハサウェイ、後にはホール&オーツやビー・ジーズといった白人ソウル/ディスコ村で全米を席捲した、その筋の花形職人だ。
参加メンバーは、ウェットン、マッカロック、exモーグル・スラッシュのビル・アトキンソン、そして【ダウランズ】を手伝ったときに知り合い、当時フィールズを結成したばかりのアラン・バリーに、レア・バードのデイヴ・カフィネティときた。そういえばこの見事な〈渋プログレ〉人脈っぷりが、西新宿界隈でこのLPを2~3万円の高値で取引させたんだった。ハスケルはクリムゾンだし、誤解するのも無理ないが。
同じくマーティン・プロデュースの、米SSWを代表するダニー・オキーフ73年の名盤『そよ風の伝説……』のプロト・タイプ的な質感を誇る、AOR系60年代フォーク・ロックとでも言えばいいだろうか。ロンドン・セッションで録られた素材をNYに持ち帰り、ヤング・ラスカルズのデヴィッド・スピノザのリズム・ギターやニール・ローゼンガーデンのピアノ、でもってコーラスやホーンを重ねたことで〈英国的でもあり米国的でもあり〉、しかも見事に〈プログレとは似ても似つかぬもの〉を完成させたマーディンは、正しい。
要は〈キング・クリムゾン的なもの〉を期待する方が悪いのだ。
クリムゾンでもSSWでもない、とにかくノー・センスな気色悪い〈森の木人(ぼくじん)〉ジャケの独自性がより混乱を招いた気もするが、ハスケル本人も嫌だったようだから忘れよう。
それでもおそろしく聴きやすいサウンドとは裏腹の、実はシビアな歌詞が感慨深い。
もう1曲目の“ノー・ミーニング”から、〈意味のないことを僕は唄うよ/でも世界は何事も起こらないじゃない/たわいもないことを僕は唄うよ/きみの気が休まるように〉とか、〈どろどろした闇からやっとリザードが這い出てきたよ〉とか、明らかにクリムゾン全否定だもの。
とにかく絶対的なものはないことをシニカルに唄い続けるハスケルの姿勢と、ある意味浮世離れしたサウンドの乖離ぐあいを愉しむのが、『歳時記』の正しい聴き方なのだろうと思う。だって『IT IS AND IT IS NOT』なのだから。
ハスケル じゃあ記憶を掘り起こそう(苦笑)。内容的には地球規模の環境の行方を憂えた、メッセージ色の濃いアルバムだった。つまり、「手遅れになる前に何とかしよう」タイプの内容なんだけど、誰も耳を傾けはしなかったね。この作品の重要性が認識されるには、20年早かったのさ。
市川 でも歌詞といい音といいジャケといい、それは非常に伝わりづらかったですよ。
ハスケル 僕が精神的に安定していればもっとわかりやすく作れただろうし、もっと必死で働きかけただろうと思う。アトランティックの社長(=アーメット・アーティガン)は僕のことを、「ニール・ヤングよりビッグになる」と言った……僕はその後、レーベルを裏切って失踪してしまったんだけど……すべては成りゆきなのさ……。
天国から地獄へそして天国へでも地獄が、とはやはり数奇な人生である。
『歳時記』をリリースした1972年の11月、マウンテンとウィッシュボーン・アッシュをお供にハスケルは、ロンドンのレインボー・シアター(!)で初めてのソロ・ライヴを実現させた。しかもそのままスタクリッジとオーディエンスと共に全英ツアーまで廻ったのに、本人言うところの〈失踪〉をかましてしまったのだ。
結局、ハスケルは自分自身の抱える〈駄目駄目コンプレックス〉に苛まれ、アトランティックから逃亡。次に彼が姿を見せたのは1973年で、FDL時代の僚友ブライン・ハワースの清々しい初ソロ・アルバム『レット・ザ・デイズ・ゴー・バイ』へのゲスト参加だった。メル・コリンズやラビット、ジョン・ポーターにアラン・スペナーといった私が個人的に好きな連中揃いだが、1976年に組まれたハワースのライヴ・バンドにもハスケルは参加していた。旧友としか仕事できないほど、神経衰弱の渦中だったのかもしれない。
ところが僅か2ヶ月でハワースから独立した三人――ハスケル&加藤ヒロシ&ジム・ラッセルで1977年に突如バンドを組むのだ。【JOE】である。遺した作品は英GTOからシングル“How Can I Resist c/w Sweet Annabelle”一枚と、日本のテイチクからの《グラフィティ・ハウス・バンド》の変名で発表したオールディーズの企画盤『いかすぜジャック~ツイスト決定盤』と数少ないが、ある種のリハビリだったに違いない。
例の“イミテーション・ゴールド”を含む山口百恵ロンドン録音盤『ゴールデン・フライト』に、加藤プロデュースの線からハスケルがベーシストとして参加したのも、同じ1977年の8月になる。私は小学生高学年のとき彼女のファンクラブに入った会員番号二桁の男なのでむしろ運命を感じたが、きっと少数派なんだと思う。
ハスケル J.J.ケールの線の、愛があるバンドさ。
市川 そこですかやはり。
ハスケル 僕はそもそも、白人の音楽よりもブラック・ミュージックに愛の存在を感じていた。僕は宗教の厳しい戒律の下で育てられたからどうしようもなく内向的な人間にならざるを得なかったけれど、そこから抜け出して初めてそういった曲を知り、触れ合うことができた。スタックスやモータウンのリズムは、聴いてるだけで「自分は黒人なのかもしれない」と思えるほど、僕に合っていた。つまり白人っぽくなかったんだよ。
市川 極端なひとだったんですねぇ。
ハスケル でもやがて気づいたよ。白人/黒人というより、僕は半分米国人じゃないかと思うほどの米国贔屓だということに。いつだって米国人が新ジャンルを作り出して、英国人がその後を追っているだけと思ってるから。
市川 そうですかぁ? ブルースからこれだけ多彩なロックを生み出せた英国人は、日本人から見ればリスペクトの対象でしたけどね。昔から。
ハスケル その考えには、申し訳ないけどとても賛同できない(←きっぱり)。
市川 あなたはそうでしょうなぁ。ちなみに山口百恵の印象はどうでした。
ハスケル 美人だったし歌唱力もあったね(愛想笑)。
しかしこの直後から、ハスケルは我々プログレッシャーズの前から完全に姿を消してしまった。インタヴューの事前に送られてきた本人直筆FAX《ハスケル空白の15年間》によると、以下の通りになる。なおこの頃はまだ地球規模で、ネットもメールもまったく一般化してなかったのだった。ああ懐かしい。
同年。RCAでレコーディング。学習。
1982年。ニューヨークのCBSで、ソングライターとして活動。学習。
1984年。ソロ・ライヴ開始。学習。
1987年。〈彼女〉と出逢い、別れた後〈アーティスト〉になる。
1989~1995年。精力的にツアー。発展。成長。訓練。そして、完成。
〈訓練〉とか〈学習〉とか、奇しくもフリップ用語が並ぶのは、何かの因縁なのか。
前述したJOEの解散後、ロンドン市内のクラブやパブでラウンジ・トリオ――要は箱バンみたいなもんで細々と演奏していた際に、運良くクリフ・リチャードのバック・バンドの一員になれて12週間の世界ツアーを廻る。
すると突如、RCAレコードとソロ契約を結ぶことができたのだ。これは前篇で触れた、1968年にFDLをバックにハスケル曲の“Lazy Life”を【クオンティン・E・クロップイエガー】名義で唄い、南アフリカで大ヒットさせたビル・キンパー(=ビル・フォレスト)がなんと、RCAの重役になってたおかげだったりする。
ああ、ビルの恩返し。
そのキンパーのプロデュースで1979年、8年ぶりに制作された3rdソロ・アルバムが『SERVE AT ROOM TEMPERATURE(室温が最適)』。ハスケル同様クリフ・リチャードのバック経験者たちが主に参加しているが、パシフィック・イアドラム、ディープ・フィーリング、ブラックフット・スー、ケヴィン・エアーズなどおそろしく渋い前科を誇る実力者揃いではあった。内容的にも前作『歳時記』の世界観がさらに孤高になったような、いわゆる〈ジョン・マーティン〉化が進行したような作品だ。
しかしアルバムがリリースされることなく全10曲中7曲が、79年に“People Don’t Care/Silhouettes”、80年に“I Need Your Love So Much/Living in the Attic”と“Castles in the Sky/My Baby”、そして81年に“Whisky/5-10-15”のシングル4枚に分割して、かろうじてリリースされるにとどまった。ニューウェイヴとダンス・ミュージックと産業ロックとAORが全盛の当時のシーンと百億光年は離れた作品だから、仕方ないけども不幸だった。
もちろんシングル群は商業的に全滅した。ただ最後のシングルのカップリング曲“5-10-15”はアルバム未収録の新曲で、しかも全っ然似つかわしくないディスコ・ナンバーだから、却って痛々しかったのである。
なおこの幻の3rdアルバムは1997年に日本のエヴァンジェル・レコードより、邦題『サード』としてようやく発掘リリースされた。にしてもこの国内盤は全収録曲に日本語タイトルがなぜか一切付けられておらず、いちいち英字表記しなければならないのが面倒くさい、と思ってるのは私だけだろうか。
結局のところRCAとの契約もアルバム一枚で終わり、新しいディールにも恵まれないまま、北欧のバーを始め欧州中をギターの流しで10年近く廻り続けていたようだ。まさにディシプリンの旅、なのだ。
ハスケル 偶然だよ(苦笑)。だけど「失われた15年」と言われても、僕は一度も引退したつもりはないのさ。そこには書かなかったが、1987年にはポール・マッカートニーのソング・コンテストで2位になったし、1989年には(正式な)3rdアルバム『ハンブルドン・ヒル』をレコーディングして、翌90年にリリースした。
市川 レコードで、でしたよね。CDリリースは1992年だったと記憶してます。
ハスケル うん。で僕のサウンドは次第にヴォーカル色が強まり、その1992年に次の(実質的な4thアルバム)『ドライヴ・ユー・クレイジー』を作ったいまでは、『ハンブルドン・ヒル』の頃とはまったく違うものになったけどね。
市川 たしかにあなたは、90年代の開幕に伴ってやっと外に向かった感があります。
ハスケル いま思うとロバートは、ある一点で正しかったよ。
市川 えらく限定的な物言いですなぁ。
ハスケル 〈訓練〉。もしも僕が1970年の時点で訓練を受けていれば、もっと楽な人生をを過ごすことができたかもしれない。でも楽な人生をおくれている人間なんて、ほとんどいないよ。いたとしても、退屈で傲慢で鈍重で冷酷で信じられないほど不実だと思うね。たとえばサッチャーなんかは、そういう人間の一人さ。アドルフ・ヒトラーも同じ。訓練それ自体はファシストお気に入りの常套手段だが、個人の精神的成長や努力と結びついたときには真の効果が現れる。でもサッチャーは、僕が知っていた英国をぶち壊してしまった。知性なんかないのに、あるようなフリをしているだけなんだよ。
市川 わはは。
ハスケル 彼女は教育を受けた阿呆なのさ。単なる。現代社会にはそんな奴らがうようよしているんだ――そんな〈裸の王様〉シンドロームに、僕は立ち向かうのさ。
このインタヴューを行なったときの〈1995年のゴードン・ハスケル〉は、まさに遅れてきた49歳のパンクスだったのだ。
19年ぶりに発表されたソロ・アルバム『ハンブルドン・ヒル』は、ハスケル自身が〈スピリチュアル・アルバム〉と語ってる通り、ようやく訪れた自らの精神的安定の下に唄った作品だ。フラットだからこそ彼本来の、実はフリップに負けないシニカルな自分が顔を覗かせ始めたと言える。ただし音楽的には、全11曲中8曲を共同プロデュースしたトニー・アーノルドが弾くスライド・ギターが全編でフィーチュアされた、AOR系バンド・サウンドだ。若干のムード・プログレ風味はご愛敬か。
「マーケティング担当者が求めてたものとは違ったみたいだけどね(苦笑)」。
それでも収録曲の“オールモスト・サーテンリー”が、南アフリカではチャート1位を獲得した。なぜいつも彼の曲は、南アフリカ限定で歓迎されるのかしら。
その次の、実質5枚目は原題の『IT’S JUST A PLOT TO DRIVE YOU CRAZY』が示すように、全編ほぼ一人弾き語りの新曲プリプロ集――いわゆるデモ・トラックス・アルバムだった。
「それでも僕の成長が一応、表れたイノセントなアルバムではあると思うんだけどな」。
このモラモラした言い方が、当時のハスケルの表現性が独特のセンシティヴィティーに立脚してるのを、如実に物語っている。録音場所のクレジットが〈Room with a View/景色のいい部屋〉というのがまた、腹わたが煮えくり返るほど似合ってるではないか。
思うにゴードン・ハスケルというひとは、極度の万年モラトリアム青年だったんだと思う。要はコンプレックスの反動で、60年代後期のフラワー・ムーヴメントのまさに渦中で趣味に育まれ過ぎたたひと、だ。その殺気まみれの能天気さが彼を米国音楽に向かわせたのだろうし、モラトリアムの「モ」の字もないエゴ対エゴの無制限衝突集団であるクリムゾンで、生ける屍と化したのも無理からぬ話だった。
たしかに復活後のソロ2作には、ふっきれたモラ男の潔さが見えた。しかしよぉーく聴いてると、「僕はちっとも悪くない、世界がみんな悪いんだ」的なスタンスは、やはりモラトリアムの発展形だ。よくも悪くもそういうひとなのである。
失礼な言い方だが、踏みつけられた路傍の名もない花的なハスケルに、私が妙なシンパシーを感じてきた最大の理由かもしれない。
さてその後のハスケルにも少しだけ、触れておく。
市川 すっかり〈闘うSSW〉路線なんですね。
ハスケル ああ。マーク・ノップラーとヴァン・モリソンと、J.J.ケールのマネージャーも褒めてくれた。内容の濃さと質の高さには自信があるよ。もっとも音楽ビジネスはまた別の話だから、「売れる」という保証はないんだけど(苦笑)。
インタヴュー当時、既に完成させていたらしい新作の『IN THE CACTI KINGDOM(サボテンの王国)』話まで持ち出して、〈第二のゴードン・ハスケル〉人生をことさらアピールする彼だった。前年1994年には、英ヴォイスプリント・レーベル企画のスタジオ・ライヴ・アルバム・シリーズ《VOICEPRINT RADIO SESSIONS》第1弾として、『GORDON HASKELL』もリリースしており、旺盛な表現欲とともに精力的に活動していた。
まさに、〈25年目にしてナイーヴ男、起つ!〉だったんだと思う。
結局『サボテン王国』はリリースされなかったが、ハスケルは積極的に音楽し続けて現在に至る。おそろしくかいつまんで書いとくと――。
❻BUTTERFLY IN CHINA(1996年)

おそらく『サボテン』ほど直接的ではないが、社会をシニカルに眺める姿勢はまさに『ドライヴ・ユー・クレイジー』の後継機的アルバム。ちなみに収録曲の“More Yin Than Yang”は、もしかしたら『歳時記』のリヴェンジかも。70年代のハスケルは陰と陽にやたら惹かれており、本当は『歳時記』のジャケを〈陰陽魚太極図〉にしたかったものの、当時の糞みたいな広報担当によりノーセンスな森の木人ジャケにされてしまった。私が見ても、あのジャケのせいでセールス2000枚は損してるはずだ。つまりこの楽曲は“More It Is And It Isn’t”なのである。たぶん。
❼ALL IN THE SCHEME OF THINGS(2000年)

ジャケだけ見ると、なぜか昭和B級アートの匂いが充満してて可笑しい。exプリテンダーズでポール・マッカートニーを復活させたロビー・マッキントッシュの参加が、ハスケル式AORに彩りを加えた。“エリナー・リグビー”のカヴァーもそうだが、オリジナル曲の“ユー・キャント・ホールド・ア・グッド・マン・ダウン”とか“プレイング・サイフォン”とか、ファンキーなパブ・ロック色が滲み始める。
❽ⓐLOOK OUT(2001年)→❽ⓑHARRY’S BAR(2002年)

マッキントッシュのみならず、マッカートニーのツアー・バンドにおけるマッキントッシュの相棒でexアヴェレイジ・ホワイト・バンドのヘイミッシュ・スチュアートも、本作から加わった。全英2位ヒット・シングル曲“How Wonderful You Are”で、本作も英2位・仏30位・独38位・蘭24位・ポーランド5位・フィンランド7位の大ベストセラー・アルバムとなった。そしてハスケルは、知る人ぞ知るEU圏を代表する英国SSWとなった。あーめでたい。
そして売れた途端に弱小インディペンデント・レーベルから❽ⓐを買い上げ、タイトルとジャケだけ変えて❽ⓑを新装リリースしたワーナー・ブラザーズは、恥ずかしい。
❾SHADOWS ON THE WALL(2002年)

マッキントッシュが一部プロデュースを担ったこともあってか、ジャジーでブルース色が濃い目に。英国では44位と❽ⓑから大きく順位を下げたが、ポーランドとフィンランドでは各8位と18位を記録した。
❿THE LADY WANTS TO KNOW(2004年)
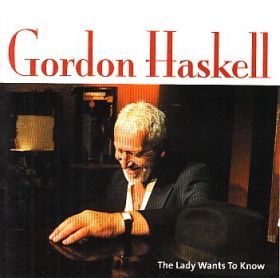
ようやく世間的に認知されたことが、やっとハスケルの双肩からありとあらゆる煩悩を下ろさせたのか、まさに本人がどうしても演りたかったんだろうマイケル・フランクスのカヴァー・アルバム。楽曲によってはジャジーでファンクネスで、かなり恰好いいパブ・ロックを聴かせる。今度はヘイミッシュ・スチュアートがプロデュースと監修を務めたせいか、印象的にはスタイリッシュですらある。
今回も14位とポーランドでは商業的成功が継続しており、2005年にポーランドの女優カーシャ・スクシェネツカ(Kasia Skrzynecka)嬢とのデュエット・シングル“All in the Scheme of Things”、2008年にはライヴ盤『GORDON HASKELL W SZCZECINIE LIVE!』がポーランド限定で発表されてるから、立派なスーパースターだ。
まさかのポーランド万歳。
⓫ONE DAY SOON(2010年)

♪誰だって天国には行きたいけど、いますぐ逝きたい奴はいない――2006年リリースの3曲入りCDシングル“Everybody Wants to Go to Heaven”は、アルバム未収録ながらハスケル・スタイルを確立した記念碑的な楽曲だと思う。〈バーでスコッチ舐めながら〉が似合うパブ・ロック的AORで、エルヴィス・コステロを想い出す機会が増えてきた。しかも数あるハスケル作品の中で初めて、恰好よいジャケだったし。なので翌2007年にドーセットからギリシャのスコペロス島に家族と移住し、いよいよ自分のペースで音楽に向かうようになったのも、わかる。
で、再びアルバム未収録の2008年発表シングル“Take My Breath Away”を経てリリースされたのがこの『ONE DAY SOON』で、洒脱さが増してスマートですらあった。しかも唄われている内容は、マハトマ・ガンジーやらトマス・ジェファーソンやらキング牧師の言葉に触発された自分の政治信条だったりする。パブの常連客の間で毎晩繰り返される政治談議という名の、まさに酒の肴に他ならない。
これぞパブ・ロックの真髄だ。
そして現時点での最新作――デビュー50周年記念シングル“I’m Letting Everybody Know”をリリースした翌2016年末に帰英したハスケルは、相変わらず自分の趣くままに今日もどこかで演奏しているはずである。たぶん。
正直、私は〈21世紀のゴードン・ハスケル〉に詳しくない。1995年にインタヴューして以降は、リリースされたアイテム群を聴いてきただけに過ぎない。だから私の妄想的なハスケル観はもしかしたら的外れかもしれないが、「こうであってほしい」と私に思わせるだけの、リアルに等身大な作品群なのだ。
とはいえ、最もリアルだったのは1991年発表のフリップ夫人、トーヤ・ウィルコックスのソロ・アルバム『オフェリアズ・シャドウ』の幕開けを飾るタイトル曲のイントロで、ハスケルがキーボードを弾いてたという〈嘘みたいな事実〉。同じ年の12月に、トーヤ夫が彼の唄とベースを差し替えた『紅伝説』がリリースされたなんて。
ねえ?
プログレって奥深い。

第一回「ジョン・ウェットンはなぜ<いいひと>だったのか?」はコチラ!
第ニ回 「尼崎に<あしたのイエス>を見た、か? ~2017・4・21イエス・フィーチュアリング・ジョン・アンダーソン、トレヴァー・ラビン、リック・ウェイクマン(苦笑)@あましんアルカイックホールのライヴ評みたいなもの」はコチラ!
第三回「ロバート・フリップ卿の“英雄夢語り”」はコチラ!
第四回「第四回 これは我々が本当に望んだロジャー・ウォーターズなのか? -二つのピンク・フロイド、その後【前篇】-」はコチラ!
第五回「ギルモアくんとマンザネラちゃん -二つのピンク・フロイド、その後【後篇】ー」はコチラ!
第六回「お箸で食べるイタリアン・プログレ ―24年前に邂逅していた(らしい)バンコにごめんなさい」はコチラ!
第七回「誰も知らない〈1987年のロジャー・ウォーターズ〉 ーーこのときライヴ・アルバムをリリースしていればなぁぁぁ」はコチラ!
第八回「瓢箪からジャッコ -『ライヴ・イン・ウィーン』と『LIVE IN CHICAGO』から見えた〈キング・クリムゾンの新風景〉」はコチラ!
第九回「坂上忍になれなかったフィル・コリンズ。」はコチラ!
第十回「禊(みそぎ)のロバート・フリップ ーー噂の27枚組BOX『セイラーズ・テール 1970-1972』の正しい聴き方」はコチラ!
第十一回「ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)前篇 --BOXを聴く前にブライアン・フェリーをおさらいしよう」 はコチラ!
第十二回 「ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)後篇 --BOXを聴いて再認識する〈ポップ・アートとしてのロキシー・ミュージック〉」はコチラ!
第十三回 「今日もどこかでヒプノシス」はコチラ!
第十四回 「ピーター・バンクスはなぜ、再評価されないのか --〈星を旅する予言者〉の六回忌にあたって」はコチラ!
第十五回 「悪いひとじゃないんだけどねぇ……(遠い目) ―― ビル・ブルフォードへのラブレターを『シームズ・ライク・ア・ライフタイム・アゴー 1977-1980』BOXに添えて」はコチラ!
第十六回 「グレッグ・レイク哀歌(エレジー)」はコチラ!
第十七回 「クリス・スクワイアとトレヴァー・ホーン -イエスの〈新作〉『FLY FROM HERE -RETURN TRIP』に想うこと- 前篇:スクワイアの巻」はコチラ!
第十八回 「クリス・スクワイアとトレヴァー・ホーン -イエスの〈新作〉『FLY FROM HERE-RETURN TRIP』に想うこと- 後篇:空を飛べたのはホーンの巻」はコチラ!
第十九回「どうしてジョン・ウェットンを好きになってしまったんだろう(三回忌カケレコスペシャルversion)」はコチラ!
第二十回「どうしてゴードン・ハスケルは不当評価されたのだろう ー前篇:幻の1995年インタヴュー発掘、ついでに8人クリムゾン来日公演評も。」はコチラ!
KING CRIMSONの在庫
-
KING CRIMSON / CONSTRUKCTION OF LIGHT
よりヘヴィにより理知的に深化を遂げた00sクリムゾン第一弾、2000年リリース
-
KING CRIMSON / HAPPY WITH WHAT YOU HAVE TO BE HAPPY WITH
02年リリース、「The Power To Believe」の予告編的ミニアルバム、全10曲
-
-
-
KING CRIMSON / SHOGANAI
02年作
-
KING CRIMSON / ELEKTRIK: LIVE IN APAN 2003
ロバート・フリップ/エイドリアン・ブリュー/トレイ・ガン/パット・マステロットによる03年東京公演を収録、全12曲
-
KING CRIMSON / POWER TO BELIEVE
「ヌーヴォ・メタル」を標榜した03年作
-
紙ジャケット仕様、初回プレス限定ステッカー・ブックレット付仕様、デジタル・リマスター、定価2415
盤質:傷あり
状態:良好
帯無
帯無、若干スレ・軽微な汚れあり
-
-
-
KING CRIMSON / LIVE IN ARGENTINA 1994
全35曲、ダブル・トリオ時代の歴史的パフォーマンスを捉えた映像作品
-
CLUB47(KING CRIMSON COLLECTORS CLUB)
デジパック仕様、DVDオーディオ2枚組、NTSC方式、リージョンフリー、スリップケース・ブックレット付仕様(画像はスリップケースです)
盤質:傷あり
状態:並
1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、スリップケースに圧痕あり
-
-
KING CRIMSON / IN THE COURT OF THE CRIMSON KING
69年発表、ロック・シーンの流れを変えた歴史的デビュー作!
ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1969年に発表されたデビュー・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』は、プログレッシヴ・ロックのスタート地点となった大名盤であり、プログレッシヴ・ロックを聴くならまずはこのアルバムからと断言できる作品です。メンバーはギタリストRobert Fripp、ベース・ヴォーカリストGreg Lake、ドラマーMichael Giles、管楽器に加えて鍵盤楽器(メロトロン)も担当するIan McDonald、そして作詞家Peter Sinfieldという布陣。「21世紀のスキッツォイド・マン」のオープニングから緊張感のある変拍子アンサンブルやユニゾン・フレーズが畳み掛け、「風に語りて」では牧歌的でありながら浮世離れした音世界を構築。“混沌こそ我が墓碑銘”の一節があまりに有名な「エピタフ (墓碑銘)」と、同じくリリックの幻想美に酔いしれる「ムーンチャイルド」を経て、メロトロンの洪水に溺れるシンフォニックな最終曲「クリムゾン・キングの宮殿」へ。“THE BEATLESの『Abbey Road』をチャート・トップから陥落させた”というエピソードの真偽はともかくとして、プログレッシヴ・ロック時代の幕開けを告げる衝撃的な作品であることは間違いありません。『クリムゾン・キングの宮殿』に触れずにプログレッシヴ・ロックを語ることは、まず不可能でしょう。
-
紙ジャケット仕様、HDCD、デジタル・リマスター、ブックレット・ステッカー付仕様、定価2500+税
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
若干圧痕あり
-
-
KING CRIMSON / IN THE WAKE OF POSEIDON
衝撃的デビュー作「クリムゾン・キングの宮殿」の構成を踏襲した70年2nd、前作に匹敵する重厚さドラマ性に加えジャズ系ミュージシャンを起用し新機軸も打ち出した一枚
ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1970年に発表されたセカンド・アルバム『ポセイドンのめざめ』は、デビュー・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』の延長上に位置する作品となっています。『クリムゾン・キングの宮殿』発表後、ギタリストRobert Frippと作詞家Peter Sinfieldを除く3名が脱退を表明するも、諸事情によりGreg LakeとMichael Gilesは引き続き本作のレコーディングに参加。新たにKING CRIMSONに参加したのは、ピアニストKeith Tippett、管楽器奏者Mel Collins、ベーシストPeter Giles(Michael Gilesの実弟)、そしてヴォーカリストGorden Haskell。その結果、本作には8名ものミュージシャンの名前がクレジットされることになりました。音楽的にはデビュー・アルバムと同一線上で捉えることも可能ではありますが、例えばKeith Tippettのジャズ・ピアノをフィーチャーした「キャット・フード」、あるいは、ホルスト作曲の組曲「惑星(火星、戦争をもたらす者)」を思わせるリズムとカオティックなメロトロンが凄まじい相乗効果を生む「デヴィルズ・トライアングル」など、新たな試みも行われています。なお本作の後、Greg LakeはEMERSON, LAKE & PALMERとして再デビュー、そしてMichael GilesとPeter Gilesの兄弟はすでにKING CRIMSONを脱退していたIan McDonaldと共にMcDONALD AND GILESを結成します。
-
KING CRIMSON / LIZARD
70年3rd、表題曲にはYESのジョン・アンダーソンが参加
ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。セカンド・アルバム『ポセイドンのめざめ』を最後に、Greg Lake、Michael Giles、Peter Gilesが脱退。1970年に発表されたサード・アルバム『リザード』は、『ポセイドンのめざめ』に参加していたベース・ヴォーカリストGorden Haskellと管楽器奏者Mel Collinsが正式加入、さらにドラマーAndy McCullochを迎え入れ制作されました。ゲスト・ミュージシャンは、過去作にも参加のジャズ・ピアニストKeith Tippettがバンドメイト(コルネット奏者Mark Charigとトロンボーン奏者Nick Evens)を引き連れ参加している他、オーボエ奏者Robin Miller、さらにYESのヴォーカリストJon Andersonが、表題組曲「リザード」の「ルーパート王子のめざめ」で歌声を響かせています。本作は、Keith Tippettが持ち込んだフリー・ジャズのエッセンスがグループに新たな息吹を注ぎ込んだ作品であり、特に「インドア・ゲイムズ」や「ハッピー・ファミリー」におけるインプロヴィゼーションなどで、その影響をはっきりと聴き取ることができるでしょう。一方で、フルートが舞う「水の精」ではこれまでのKING CRIMSONらしい牧歌性も披露。ラストには20分を超える表題組曲「リザード」が控えます。フリー・ジャズへの接近を通じて、後のKING CRIMSONサウンドの重要なポイントとなる即興色を拡張した傑作です。
-
30TH ANNIVERSARY EDITION、デジタル・リマスター
盤質:傷あり
状態:並
カビあり
-
-
KING CRIMSON / LARKS’ TONGUES IN ASPIC
フリップ以外のメンバーを一新して制作された73年作5th、圧倒的な緊張感とダイナミズムが支配する大傑作!
ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。4thアルバム『アイランズ』を発表後に解散したKING CRIMSONですが、Robert Frippは新たなメンバーを探しKING CRIMSONを再始動。グループの最高傑作と名高い1972年の5thアルバム『太陽と戦慄』を世に送り出しました。メンバーはギタリストRobert Frippに加えて、ベース・ヴォーカリストJohn Wetton、ドラマーBill Bruford、パーカッション奏者Jamie Muir、ヴァイオリン奏者David Crossという布陣。本作は、確かな技巧を持ったミュージシャンたちによる最高品質の実験音楽作品であり、1曲目の「太陽と戦慄 パートI」と最終曲「太陽と戦慄 パートII」に象徴される、即興演奏を重視したメタリックなプログレッシヴ・ロックの大傑作となっています。また、2つの先鋭的な楽曲に挟まれた中盤の楽曲たちも素晴らしく、John Wettonのヴォーカルが冴えわたる「土曜日の本」や、最初期のKING CRIMSONサウンドが頭をよぎる「放浪者」、 ヘヴィーなギターとスキャットから始まる「イージー・マネー」 、Jamie Muirの話し太鼓(西アフリカの伝統的な太鼓の奏法)を曲名に冠した「トーキング・ドラム」と、どの楽曲も強烈な個性を持っています。ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックを聴くうえで、避けて通れない名盤です。
-
紙ジャケット仕様、40周年記念エディション、HQCD+DVD-AUDIOの2枚組、K2HDマスタリング、ブックレット・内袋・復刻巻帯付仕様、DVD-AUDIOはNTSC方式・リージョンフリー、定価4500+税
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
盤に内袋の跡あり
-
-
KING CRIMSON / RED
フリップ、ウェットン、ブルーフォードの三人が尋常ならざる緊張感の中で生み出したクリムゾンを代表する傑作、74年作7th
ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。6thアルバム『暗黒の世界』後にヴァイオリン奏者David Crossが脱退。3人体制となったKING CRIMSONは、1974年に7thアルバム『レッド』をリリースしました。メンバーは、ギタリストRobert Fripp、ベース・ヴォーカリストJohn Wetton、ドラマーBill Brufordという布陣。ゲストには、ソプラノ・サックス奏者Mel Collins、アルト・サックス奏者Ian Mcdonald、ヴァイオリン奏者David Cross、コルネット奏者Mark Charig、オーボエ奏者Robin Millerという旧メンバーあるいは過去作にもゲスト参加の経験を持つミュージシャンたちが迎えられています。その内容は、アルバムのオープニングを飾る「Red」から破壊的なギター・サウンドとアグレッシヴなリズム・セクションに驚愕する傑作。KING CRIMSON作品の中で最も素晴らしいバラード曲との呼び声も高い「堕落天使」、初期のKING CRIMSONサウンドをヘヴィーに再構築したような「再び赤い悪夢」、インプロヴィゼーションのライブ録音楽曲「神の導き」、抒情的なヴォーカルが印象的な前半部とギターやサックスが暴れまわる後半部から成る長尺曲「スターレス」と、全曲がプログレッシブ・ロック史に残る名曲です。本作のリリースをもって、KING CRIMSONは再び解散することとなりました。裏ジャケットに使われている、レッド・ゾーンに振り切れた音量メーターが、本作の狂暴な音楽性と当時のグループの状況を示唆しています。
-
ロバート・フリップによる89年リマスター、ファミリーツリー付き仕様、定価2233+税
盤質:傷あり
状態:
帯有
若干スレあり、カビあり
-
ロバート・フリップによる89年リマスター、ファミリーツリー付き仕様、定価2233+税
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
若干折れ・側面部に若干色褪せあり、ケースに若干スレあり
-
40TH ANNIVERSARY SERIES、デジパック仕様、スリップケース・ブックレット付仕様、CD+DVDの2枚組、ボーナストラック3曲、DVDはNTSC方式・リージョンフリー
盤質:無傷/小傷
状態:良好
スリップケースに若干圧痕あり
-
-
KING CRIMSON / STARLESS AND BIBLE BLACK
精緻にしてヴァイオレンス!ライヴ音源とスタジオ音源に巧みな編集を施した74年作7th、クリムゾン史上の難曲「FRACTURE」収録
ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。5thアルバム『太陽と戦慄』に続いて1974年にリリースされた6thアルバム『暗黒の世界』は、スタジオ・レコーディングとライブ・レコーディング(73年録音)が混在する変則的な作品となっています。収録曲順に見ていくと、「偉大なる詐欺師」と「人々の嘆き」は完全なスタジオ・レコーディング。「隠し事」はライヴ・レコーディングで、「夜を支配する人」はライヴ・レコーディングの冒頭から途中でスタジオ・レコーディングに切り替わります。「トリオ」はライブ・レコーディングで、「詭弁家」はライブ・レコーディングに後からスタジオ・ヴォーカルをかぶせた楽曲。「暗黒の世界」と「突破口」はライブ・レコーディングとなっています。前作『太陽と戦慄』でパーカッション奏者Jamie Muirが脱退したため、本作のメンバーはギタリストRobert Fripp、ベース・ヴォーカリストJohn Wetton、ドラマーBill Bruford、ヴァイオリン奏者David Crossという布陣。内容的には、初期の強烈なKING CRIMSONサウンドに回帰したようなスタジオ楽曲と、インプロヴィゼーションで聴かせるライブ楽曲に分かれています。本作を発表後にDavid Crossが脱退し3人体制となったKING CRIMSONは、次作『レッド』の制作に取り掛かります。
-
30TH ANNIVERSARY EDITION、デジタル・リマスター
盤質:無傷/小傷
状態:良好
-
-
KING CRIMSON / A YOUNG PERSON’S GUIDE TO KING CRIMSON
75年発表、のちに日本のみで期間限定CD化された幻のベスト・アルバム、全15曲
-
廃盤希少、2枚組、ファミリーツリー付き仕様、定価3786+税
盤質:傷あり
状態:並
帯無
帯無、若干カビあり
-
-
KING CRIMSON / USA
75年リリース、『RED』発表前の爆発的パフォーマンスを収録した名ライブ盤!
75年発表のライブ・アルバム。「RED」発表前の74年に録音されており、当時のラインナップはRobert Fripp(g)、John Wetton(b、vo)、 Bill Bruford(ds)、David Cross(vln、key)の4人編成。アルバム中3曲でEddie Jobson(vln、key)のパートがダビングされています。鮮やかなヴァイオリンの旋律を切り刻むメタリックなギター・リフ、グイグイとウネリを生み出して暴走するリズム隊。この時期ならではのパワフル且つ緊迫感溢れる即興演奏に終始圧倒されっぱなし。代表的名曲「21st Century Schizoid Man」では原曲のサックス部分をヴァイオリンで再現しており、よりヒステリックな爆発力を楽しむことが出来ます。沸点目掛けて上り詰めるRED期クリムゾンの凄さを体験出来る名ライブ盤。
-
紙ジャケット仕様、24bitリマスター、HDCD、3曲追加収録、ブックレット・歌詞対訳付仕様、定価2200+税
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
スレあり
-
-
KING CRIMSON / THREE OF A PERFECT PAIR
フリップ/ブリュー/レヴィン/ブルーフォードによる80sクリムゾンの最終幕を飾る84年作
ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1984年に発表された10thアルバム『スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペアー』は、8thアルバム『ディシプリン』と9thアルバム『ビート』と同一メンバーにて制作されました。メンバーは、ギタリストRobert Fripp、ギター・ヴォーカリストAdrian Brew、ベーシストTony Levin、そしてドラマーBill Brufordという布陣。本作は、KING CRIMSONのスタジオ・アルバムの中ではあまり目立たない存在かもしれません。その理由は、契約履行のために作ったアルバムという印象が強いことや、Adrian Brewのポップ・センスに寄せた出来になっていることなどが挙げられるでしょう。確かにアルバム前半には分かりやすいヴォーカル・ナンバーが収録され聴き手を困惑させるかもしれませんが、後半ではKING CRIMSON版インダストリアル・ロックとでも名付けたくなるようなインストゥルメンタルが配置されています。もちろんインプロヴィゼーションもフィーチャーされており、最終楽曲のタイトルは、なんと「太陽と戦慄 パートIII」。Robert Fripp本人も本作に対してはポジティブな感想を持っていないようですが、8thアルバム『ディシプリン』からの一連の流れを知る意味で、チェックしておきたいアルバムでしょう。
-
紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック5曲、ブックレット・ステッカー・内袋付仕様、定価2625
盤質:傷あり
状態:良好
帯無
帯無、若干汚れ・若干圧痕・軽微な色褪せあり
-
-
KING CRIMSON / VROOOM
90sクリムゾンの第1弾アルバム、94年作
ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1980年代に『ディシプリン』『ビート』『スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペアー』を発表し活動を休止したKING CRIMSONの次なるリリースは、94年のミニアルバム『ヴルーム』。この時期のKING CRIMSONは
ギタリストRobert FrippとAdrian Brew、ベーシストTrey GunnとTony Levin、ドラマーPat MastelottoとBill Brufordという布陣から「ダブルトリオ期」と呼ばれています。本作は、95年のフル・アルバム『スラック』へのウォーミング・アップのような意味合いの作品であり、事実6曲中4曲がアルバム用にリミックスされ『スラック』にも収録されています。内容は、7thアルバム『レッド』に通じるヘヴィーな楽曲を中心としており、KING CRIMSONの進化はまだまだ続くと確信させられる出来栄えです。-
紙ジャケット仕様、初回プレス限定ステッカー付仕様、デジタル・リマスター、定価2300+税
盤質:無傷/小傷
状態:並
帯無
帯無、軽微なカビあり
-
-
KING CRIMSON / THRAK
10年の沈黙を破り再始動したクリムゾンが放った95年作!
ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1980年代に『ディシプリン』『ビート』『スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペアー』を発表し活動を休止したKING CRIMSONは、94年に久々の新作となるミニアルバム『ヴルーム』を送り出し、翌95年には『ヴルーム』の楽曲を含むフル・アルバム『スラック』を発表しました。この時期のKING CRIMSONはギタリストRobert FrippとAdrian Brew、ベーシストTrey GunnとTony Levin、ドラマーPat MastelottoとBill Brufordという布陣から「ダブルトリオ期」と呼ばれています。内容は、冒頭の「ヴルーム」を聴いただけで7thアルバム『レッド』の衝撃がよみがえるような、強烈なヘヴィー・プログレッシヴ・ロックとなっています。Robert Frippは、新たなKING CRIMSONの音楽性を「ヌーヴォ・メタル (Nuovo Metal)」と標榜しました。
-
紙ジャケット仕様、HDCD、デジタル・リマスター、定価2345
盤質:傷あり
状態:良好
帯無
帯無、側面部に色褪せあり
-
盤質:傷あり
状態:良好
スリップケースに角潰れあり
-
KING CRIMSON / THRAKATTAK
95年ツアーのライヴ音源より、インプロヴィゼーション・パートのみを編集した96年作
-
DGM96042(DISCIPLINE GLOBAL MOBILE)
デジパック仕様、ブックレット・ポスター付き仕様
盤質:全面に多数傷
状態:
盤に曇りあり、小さい破れあり
-
KING CRIMSON / ABSENT LOVERS
84年7月モントリオールで行なわれた第4期のラスト・ライヴを収録。
-
紙ジャケット仕様、2枚組、デジタル・リマスター、定価3675
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
帯中央部分に軽微な色褪せあり、初回プレス限定の「THE COLLECTORS KING CRIMSON SAMPLER VOL.3」(5曲入り)付属
-
-
-
KING CRIMSON / GREAT DECEIVER 2 LIVE 1973-1974
73-74年期のライヴ音源集
-
紙ジャケット仕様、2枚組、デジタル・リマスター、定価3500+税
盤質:傷あり
状態:並
帯有
帯中央部分に色褪せあり、カビあり、盤に軽微な曇りあり
-
GORDON HASKELLの在庫
-
GORDON HASKELL / SAIL IN MY BOAT
初期キング・クリムゾンに在籍した英フォーク・シンガー、クリムゾン加入以前にリリースした69年作
69年発表の1stソロ。キング・クリムゾン「リザード」への参加で有名ですが、本作で聴けるのはクリムゾンの面影など微塵も感じない英SSW然としたサウンド。決してうまくはないが味のあるヴォーカルと和やかなメロディーに心温まります。弦楽器、ピアノ、フルートによる洗練されたアレンジが印象的。
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!