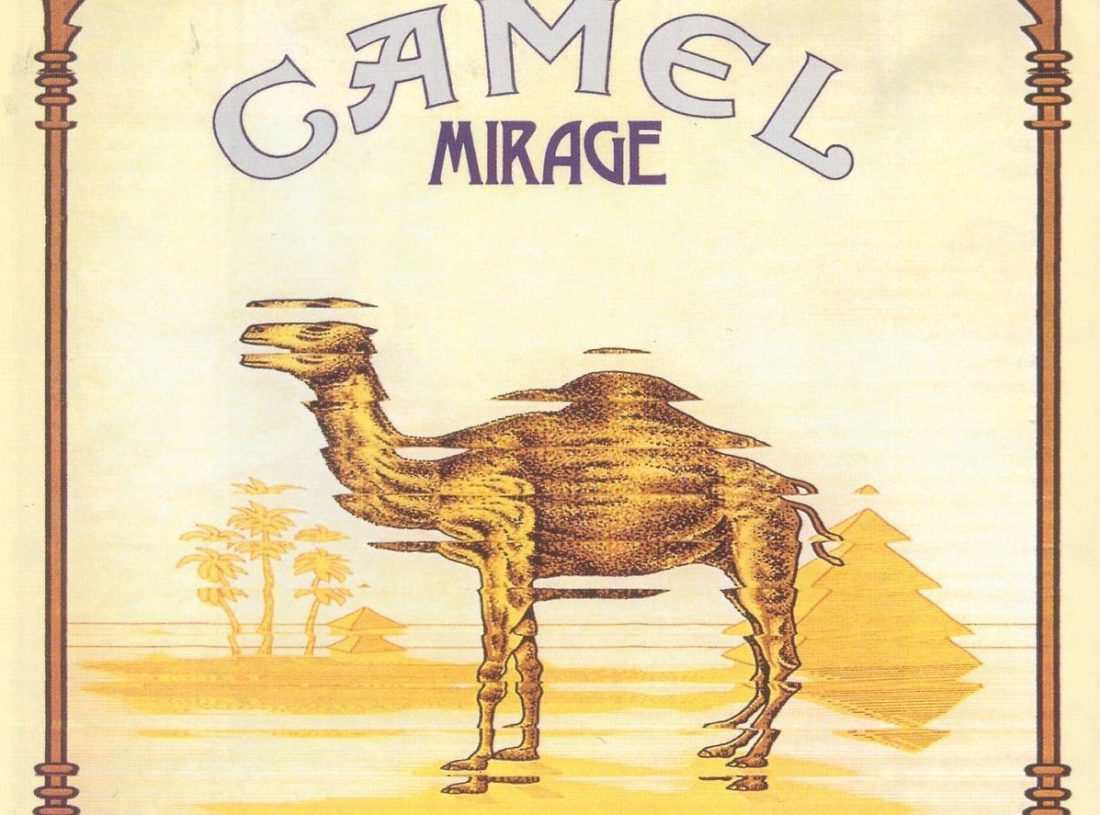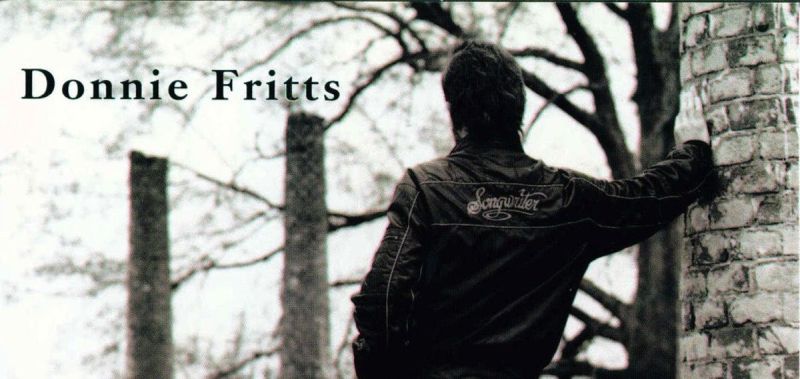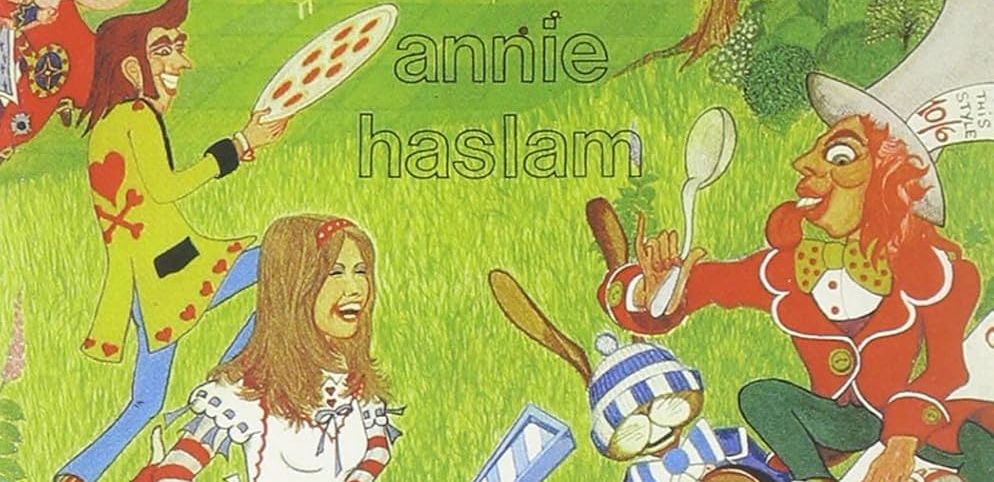「音楽歳時記」 第三十回 再び山の日、さらばグレッグ・オールマン 文・深民淳

昨年の夏前に小野瀬雅生ショウを紹介させていただいた際にちらっと書いた、大学時代の知人、安西史孝氏のことを皆さま憶えていらっしゃるでしょうか?
憶えているわけないよねぇ、そんなこといきなり言われて、憶えてる〜って言われる方が怖いです。
さて、この安西くん、日本で最初にフェアライトを導入するなど、日本の鍵盤系面倒な機材史(無論、そんなものがあればの話ですがね)に残る偉人としてその名を残しておりますが、もっとわかりやすく言ってしまえば、日本のプログレ、フュージョン史にその名を残すCROSSWINDのキーボード奏者として活躍しておりました。CROSSWINDは後にRCサクセションでも活躍するギタリスト、小川銀次を中心としたプログレとハード・フュージョンを見事に融合させた剛腕バンドでした。解散後も小川氏は様々なバンドで活動していましたが2015年8月2日に癌により58歳という若さで亡くなってしまいました。
今回、そのCROSSWINDの未発表ライヴ音源を『LIVE Ⅱ CROSSWIND 〔“Eternal Days”〕』と題しCD化するプロジェクトが始まっており、現在クラウドファンディングで出資者を募集しています。詳しくは、
https://www.muevo.jp/campaigns/1253
をご覧ください。幻に終わった4thアルバム収録予定だった曲のライヴ・ヴァージョンも収められるようでカケレコ・ユーザーの皆さんでしたら興味ある方が多いのではないかと思い紹介させていただきます。本日で締め切りまで46日となっていますが、達成度48%となっており、多分、達成してこのプロジェクトは実現すると思いますが、少しでも引っかかるものがありましたら、一度ウェブ・ページの方を覗いていただければと思います。
それでは今月も行かせていただきます。まずは、当の本人もあっ!とびっくりのトピックがありましたので、ここだけの話ってことでよろしくで・・・。
クラシック・ロック再発関連も既に行くところまで行ってしまった感があり、最近はFM放送音源は勿論、会場での隠し録り音源を元にしたブートレグ由来のものまでオフィシャルとして商品化されています。オフィシャル・ブートレグ増えましたよね。HUMBLE PIEもCD3枚組のオフィシャル・ブート・ボックスを発売しました。4音源が収録されており、1972年9月22日のシカゴ、1973年5月の東京公演、1974年5月18日のロンドン郊外のフットボール・グラウンド野外公演、同’74年のレインボー・シアター公演を収めています。
どれも過去にブートで出たことのある音源で、レインボー・シアターの音源はここでは音だけですが、映像もあります。また、’74年の野外公演はメイン・アクトにTHE WHOが出演したフェスティヴァルに出演した時のもので過去にブートとして発売されたパッケージには同日出演したTHE WHO、BAD COMPANYと一緒にまとめられたものもありました。まぁ、推奨はしませんが、どの音源もWEB検索に自信のある方でしたら実は無料で聴けちゃったりします。
ここ日本ではHUMBLE PIEにとって唯一のジャパン・ツアーとなった1973年5月の来日時、渋谷公会堂公演が収録されているのが話題になっているかと思いますが、この音源、実は良く知っています。写真を見ていただきましょう。


このスコッチの120分カセット・テープがこの音源のマスター・カセットです。マスターからコピーしたとかそういうのではなく、正真正銘のマスターです。録音機材は当時流行ったSONYのカッパ・サイズ(新書版変形サイズで光文社が出していたカッパ・ブックス)に近いナショナル(現パナソニック)製のモノラル・テープレコーダーを使用、マイクは本体にビルトインされていたものが使われました。スコッチの120分テープはラジオのエアチェックが録音されていたものの使い回しでテレコの録音ヘッドが若干傾いていたためオリジナル・マスターでは左チャンネル側のエアチェックされた番組の音が完全に消去されておらずわずかに残っています。
今回のCDに使用されたのは、2000年代の初頭にDATによるテープ・トレードをやっていた時にイギリスのトレーダーとDAT交換する際に一度DATにコピーし、元々モノだったのでしっかりと録音された右チャンネルの音源を左チャンネルに貼り直し作業をして出したものが元になっています。昔、友人とかに結構コピーしてあげたのでオリジナル・カセットをそのままコピーした演奏や観客ノイズが静かめになると日本人のアナウンサーが喋っている声や音楽等がうっすら聴こえるヴァージョンもどこかに存在しているはずです。
貼り直しをしたヴァージョンは昔、ブートCD化されたことは知っていました。多分これが元になっているかと思います。今回、そのオフィシャル・ブート・ヴァージョンを聴きましたが、オリジナルと比べると少しジャリジャリした印象でした。元々モノのカセット録音なので音質の差と言っても微々たるものですがオリジナルはもう少しふくらみのある音なんですがね。さて、公演の思い出ですが、印象としてはスティーヴ・マリオット・ショウといった印象が強く、演奏中けっこう唾を吐くのですがその量がけっこう多く、水みたいだなぁ、というのを記憶しています。それとグレッグ・リドレーのベースの持ち方ね。ストラップかけていますが、ほぼ縦にしており、どこかウッド・ベースを弾くようなスタイルがカッコよかったなぁ、と。BLACKBERRIESもちゃんと一緒に来日していたし、いいコンサートでしたね。この1973年5月はBECK, BOGERT & APPICE公演、TEN YEARS AFTERの2度目の来日公演なんかもありましたが、やはり、このHUMBLE PIEが一番印象に残っております。(次点として武道館でみんなが紙テープ代わりにトイレット・ペーパー投げまくるのでムッとしていたアルヴィン・リーというのを挙げておきます)というわけで、今回はネタをブッ込んでみました。ちなみに、録音者は僕ではありません。友人です。でも、これを録音したテレコ借りて他のバンドの公演結構録音していたから知っているんだよね。テープはその当時から借りっぱなし状態になっていたわけです。
さて、本題に入ろうという感じなんですが、去年の12月くらいから追悼ものが多く、なんだかなぁ、と思っていたらグレッグ・オールマンまでいなくなってしまいました。個人的にはかなりショックです。ユニバーサル時代にキャプリコーン・レーベルも担当していたし、2000年代に入ってから、ウォーレン・ヘインズ、デレク・トラックスのツイン・リード体制で復活を果たしたTHE ALLMAN BROTHERS BANDの『Hittin’ The Note』(2003年)も担当したので馴染みが深かったし、何よりも復活後はライヴ音源をCDRですが公演ごとに出しており、いつの間にかその年の公演をまとめた巨大なボックスを出すようになり、毎年楽しみにしていたこともあり、今大きな脱力感を感じています。
デュエイン・オールマン存命中のオリジナルALLMAN BROS.も勿論素晴らしいと思っていますし、大好きなんですが、僕はヘインズ&トラックスの21世紀ALLMAN BROS.がすごく好きです。2003年から2014年までとてつもない数の公演を聴き続けてきて、デレク・トラックスというギタリストの成長ぶりをほぼリアルタイムで体験できたし、バンド全体の調子がいいときは恐ろしくテンションの高い演奏を展開するくせに、調子悪いと笑うくらいボロボロの演奏もあったり、とにかく毎年聴くのが楽しみだったのです。2014年に毎年恒例のニューヨーク、ビーコン・シアター連続公演を3月7日からスタートさせたものの、スケジュール後半の3月22日公演後、グレッグ・オールマンの体調不良で残りのビーコン・シアター公演をキャンセルしたため、10月に仕切り直しとして、10月21日から28日まで6公演を行い長い歴史に幕を下ろしたのですが、グレッグの体調が良くなればまたカムバックしてくるだろうと思っていたんですけどね・・・。残念ながらその機会は永遠になくなってしまいました。
で、本題です。以前取り上げているのですが再び、山の日を取り上げます。山の日の説明についてはバックナンバーを参照して頂ければと思います。(「第十九回 8月 山の日もできちゃいました」 )
ALLMAN BROS.の山といえば、やはり「Mountain Jam」かと。1971年10月29日にオートバイ事故で他界したデュエイン・オールマンが残したスタジオ録音曲に彼の死後録音されたナンバー、デュアン存命時にフィルモア・イーストでライヴ・レコーディングされたその「Mountain Jam」で構成された1972年発表の4thアルバム『Eat A Peach』に端を発します。
「Mountain Jam」の曲名の由来は、およそ34分にも及ぶジャム・セッション曲である同曲の最初の部分でドノヴァンの「There Is A Mountain / 霧のマウンテン」のメロディが主題としてギターで演奏されているところからきています。ドノヴァンのオリジナル・ヴァージョンは1967年にシングルとして発表され、アメリカではビルボード・チャート11位、イギリスでは8位まで上昇するヒット曲となり後に『Donovan Greatest Hits』(1969年)に収録された他、1968年発表の『Donovan In Concert』にもライヴ・ヴァージョンが収録されています。フルートとパーカッションのバッキングが印象的なこのライヴ・ヴァージョンがALLMAN BROS.のジャム・セッション・ヴァージョンのオリジンになっているように思いますね。まず『Eat A Peach』と「Mountain Jam」をとことん楽しむ上でこの『Donovan In Concert』収録のライヴ・ヴァージョンも是非聴いてみていただきたいと思います。ライヴ・アルバム全体に漂う平和でスコーンと抜けた空気感が、デュエイン・オールマンをはじめとするメンバーに愛され、「Mountain Jam」の主題として選ばれたんだろうな、と僕は思います。ドノヴァンの作品の中ではどちらかというと不人気な作品で、ヒット曲も取り上げてはいるものの、ベスト・ヒット・ライヴというより雰囲気重視みたいなところがあるので、不人気もいたしかたないように思いますが、この空気感はフラワー・ムーヴメント期のドキュメントとしても貴重ですし、なにより全体に漂うこの時代ならではの空気感はかなり良い感じです。
ALLMAN BROS.の「Mountain Jam」に戻りましょう。この『Eat A Peach』収録のオリジナル・ヴァージョンはGRATEFUL DEADと並び元祖ジャム・バンドともいえるALLMAN BROS.の真骨頂を堪能できる至福の名演なのですが、『Eat A Peach』を中学生の時に最初に買った時は全然ピンと来ませんでした。その前に某新宿のロック喫茶で大音量で聴いた『At Fillmore East』の押しが強く男性的なパフォーマンスに比べどこか抜けた感じがあり、しかもドラムやベース・ソロが挟み込まれている点がなんだか2枚組にするための時間稼ぎみたいな印象が強く、最初の頃はスタジオ・レコーディング曲ばかり聴いていたのですが、当時は少ない小遣いをやりくりしてLPを買っていましたから、勿体無い気持ちが先に立ち繰り返し聴くようになり次第にはまっていった次第です。GRATEFUL DEADの『Live 1972』もそうだったのですが、面と向かわず、聴き流すような感じで流していた時に体全体がグルーヴに乗っかったような、妙に気持ちの良い瞬間があり、一度そういう感覚を味わうと印象はガラリと変わるもので・・・。『At Fillmore East』とは質感が異なる暖かい気の流れのような浮遊感がとにかく気持ち良く、「Mountain Jam」開始の定番の合図であるティンパニーの連打が聴こえてくるだけで気分が高揚するようになってしまったわけです。この『Eat A Peach』収録のオリジナル・ヴァージョンはジャム・バンドの入門編としても広くお勧めします。
Mountain Jam(Studio ver.)
まぁ、’70年代から’80年代はこのオリジナル・ヴァージョン一本被りだったわけですが,’90年代に入ると『Live At Lulow Garage 1970』が発表されます。『Eat A Peach』収録テイクよりも古く、『Eat A Peach』収録テイク以降の定番ティンパニーのイントロなし、全体の浮遊感もまだ低空飛行で型と構成は既に出来上がっているものの、全体的にもっさりした印象。特にベースとドラムのリズム・セクションが細かく前ノリ、後ノリ自在にグルーヴを変化させる「Mountain Jam」の肝とも言える部分がまだ発展途上。しかしながらこの『Live At Lulow Garage 1970』ヴァージョンは収録時間が44分という超エクステンディット・ヴァージョンなのが魅力でした。
次に発掘音源として登場したのが、再結成ALLMAN BROS.が1990年代を過ごしたEPICレーベルから2003年に発表された『Live At The Atlanta International Pop Festival July 3 & 5 1970』。かのアトランタ・ポップ・フェス出演時のライヴ音源でこれも『Eat A Peach』版より前の録音でした。2ヴァージョン収録されており、こちらはティンパニーのイントロから始まるタイプで、かなり『Eat A Peach』版に近い形になってきています。
デュエイン・オールマンの死後「Mountain Jam」はどうなったかといえば、『Eat A Peach』版の印象が強いものでツイン・ギターじゃないと、という印象がありますが、ギタリストディッキー・ベッツひとりとなった『Eat A Peach』以降も決して封印されたわけではなくチャック・リーヴェルが加入しグレッグのオルガンとリーヴェルのエレクトリック・ピアノというツイン・キーボード体制になった時期には2台のキーボード、ギターとキーボードの対比に形を変えた「Mountain Jam」が演奏されています。バンドのウェブ・ショップで販売されていた(日本の輸入版店でも見かけたので今でも入手可能かも)アーカイヴ・ライヴ・シリーズの第4集『Nassau Coliseum, Uniondale, NY 5/1/73』でこの時期の「Mountain Jam」を聴くことができます。貴重なヴァージョンといえばそうなのでしょうが、やはりこの時期のキーボード主体型の「Mountain Jam」はちょっと違うかな、という感じです。

ALLMAN BROS.の歴史については今更説明するまでもないと思いますが、アルバム『Brothers And Sisters』以降は作品発表の間隔が長くなり、グレッグがソロとしても活動を活発化させるなど、ALLMAN BROS.の魅力の一つとなっていた結束力の強さが弱まり、一度解散。その後、再結成し、古巣キャプリコーンからアリスタにレーベルを移し活動再開。その後EPICに再度移籍し’80年代後半から’90年代かけ第二次黄金期を迎えます。デレク・トラックスは’90年代の後半にディッキー・ベッツの相方としてバンドに加入。しかしながら、ずっとくすぶり続けていた、ディッキー・ベッツとバンドとの紛争が修復不可能な状況となり、ディッキー・ベッツがバンドから追われる形で脱退します。この項の最初で挙げた『Hittin’ The Note』(2003年)はバンドに残ったデレク・トラックスに加え、’80年代ALLMAN BROS.を支えたウォーレン・ヘインズを復帰させ心機一転、21世紀型ALLMAN BROS.を提示した作品だったわけです。
2003年以降のALLMAN BROS.は先にも述べたように、CDRではありますが、公演毎にパッケージ販売されていたため、2014年の最終公演までとてつもない数のライヴ音源が残されました。で、トラックス&ヘインズ時代のALLMAN BROS.における「Mountain Jam」演奏状況はどうだったかといいますと、大変アバウトな計算ですが大体、3公演に1回はセットリストに入り演奏されていました。立派な定番演奏曲です。トラックス&ヘインズのコンビネーションを強固なものしていく上でも重要なレパートリーだったと思います。
トラックス&ヘインズのギター・コンビがライヴ稼働を開始した2003年ツアーでの「Mountain Jam」はオリジナルを尊重しながらも、デレク・トラックスがデュエイン・オールマンと比較されることを尊敬と畏怖の念はあるけども、僕は僕みたいな意志を打ち出していたようで、意識的にオリジナルから離れていこうとするかのようなプレイが多かったように思います。
例として挙げれば2003年8月9日のVerizon Wireless Ampitheatre, Charlotte, NC公演における「Mountain Jam」
。この日の同曲はほぼ40分の長尺ヴァージョンで、ギターの爪弾きから入り徐々に「Mountain Jam」のメイン主題を形作っていったところでティンパニーが鳴り出すという変則的な導入から始まり、途中の展開部にWEATHER REPORTの「Birdland」が挿入され、それをきっかけにジャムの方向性が変わりそこからまた展開を見せるというパターンになっています。展開があって、一度は「Birdland」から離れていくのですが、ベースソロのパートでオテイル・バーブリッジが再び「Birdland」のメロディを持ち出したことでまたそっちへ流れていくという変則ヴァージョンを披露していました。
21世紀型ALLMAN BROS.の「Mountain Jam」は2005年あたりから独立した1曲ではなく、10〜15分程度のコンパクトなヴァージョンとなり、終盤別の曲にそのままなだれ込むというスタイルが多くなっていきます。そのまま別の曲になり終わるパターンと何曲か挟んで再びジャムに展開し、「Mountain Jam」のメイン主題に戻り終わるというパターンが混在する形になっていきます。ただ、面白いのは年を追うごとにオリジナルの「Mountain Jam」に近づいていくというか、あまりいじらず素直に演奏するようになっていくのです。デレク・トラックスが達観したというのでもないのでしょうけど、2005年から2011年あたりまでの「Mountain Jam」では背筋がゾクッとするような素晴らしいプレイを含んだものが多く存在します。
ALLMAN BROS.の最終公演となった2014年10月28日NY、ビーコン・シアター公演でも「Mountain Jam」は重要な役割を果たします。この日はギター2本によるオープニング「Little Martha」からいきなり「Mountain Jam」に突入。メイン主題のみの導入用ショート・ヴァージョンから最後の日ということもあり定番曲全部やりますセットリストにおける場面転換の役割を「Mountain Jam」に持たせたようです。ALLMAN BROS.のビーコン・シアター公演は2構成になっており、一部はオープニングのショート・ヴァージョンのみですが、2部後半に再び挿入され「Southbound」からメイン主題を演奏しない中間部のみの珍しいヴァージョンから更に「Will The Circle Be Unbroken」へ展開し再びジャムからメイン主題へ戻るエンディング・ヴァージョンに持っていくという感動的な演出がなされていました。冒頭に「Little Martha」が付いていましたがこの日は「Mountain Jam」に始まり「Mountain Jam」で本編を終わらせるという構成だったわけです。そしてアンコールとしてこれも定番の「Whipping Post」が演奏され、メンバーによる感動的なフェアウェル・スピーチがあり1stアルバム収録の「Trouble No More」でアメリカン・ロックの歴史に大きな足跡を残したTHE ALLMAN BROTHERS BANDは45年間におよぶ活動の幕を閉じました。

この時は、そんなこと言ったって、また2〜3年したらビーコン・シアターに戻ってくるんじゃないのとか呑気に思っていましたが、もうその日は永遠に来なくなってしまいました。「Mountain Jam」はデュエイン・オールマンを中心にひたすらリハーサル、ジャム・セッションに明け暮れたALLMAN BROS.のシンボルであり、この壮大なジャム・セッションをものにできたからこそ、バンドを45年も続けることができたと信じます。「俺たちは違うよ!」というミュージシャンとしての誇りが込められた名曲ですね。今回、何ヴァージョンも聴きましたが、すべて条件反射的にティンパニーが鳴り出すと心が躍りました。今年の山の日はいまから用意して一日中ノンストップ「Mountain Jam」をやろうかと思っています。
さて、ALLMAN BROS.をもう少し。僕が担当した『Hittin’ The Note』は実はあんまり売れませんでした。ALLMAN BROS.らしいサウンドを残しながらも、単にノスタルジックなサウンドではなく、時代に即した強固な骨格を持った音楽を提示した優れた作品で、21世紀版「Mountain Jam」ともいえる強力なインスト曲「Instrumental Illness」、グレッグ・オールマンが生涯追求してきたサザン・ソウル・スタイルのバラードの集大成と言っても過言ではないとことんディープな「Desdemona」。大体歌い出しがカッコよすぎ!「眠たい南部の街に雨が降る」だもの。またトラックス&ヘインズのギター・コンビの熱く燃え上がるギター・バトルに興奮する「Rockin’ Horse」を筆頭に良い曲満載!そしてこの『Hittin’ The Note』のツアーを記録した『One Way Out』(2004年)。これもまた良いんだ。前出のトラックス&ヘインズのギター・バトルが売りの「Rockin’ Horse」、ここではギタリストのガチのバトルが展開されます。鬼気迫る演奏なものでヴォーカル・パートに戻る瞬間に観客が一息つく雰囲気がモロに伝わってくるんですね。オフィシャル・ライヴ・アルバムであるのもかかわらず不人気な作品なのですがこれも強くお勧めします。
Rockin’ Horse(Studio ver.)
さて、今月の1枚です。最近、忙しかったものでショップほとんど覗いていなかったのですが、久しぶりに行って目に付いたのがこれ。アナログ時代からこれは超目立っていましたね。よりにもよってなんでこんなアートワークにしたのでしょうか? CDになって思い切り小さくなったにもかかわらず、恥ずかしさは未だ全開! THE YARDBIRDSのドラマーでキース・レルフとオリジナルRENAISSANCEを結成していたジム・マッカーティが中心となって結成したSHOOT、1973年の唯一作『On The Frontier』です。

レルフとマッカーティがレルフの妹ジェーン、ルイス・セナモらと結成したオリジナルRENAISSANCEはアルバムを2枚制作した後、活動が停滞。この後、かのアニー・ハズラムを中心としたRENAISSANCEが始まるのですが、レルフ&マッカーティはアルバムに彼らの楽曲を採用する条件をつけてバンド名貸しを行うという、なんかアパートの大家さんみたいなことをして、小銭を稼ごうとしたまではいいが、ここにマイルス・コープランドという一筋縄ではいかないマネージャーが登場。レルフ&マッカーティは権利まるまる引っ剥がされる羽目となり、一応楽曲採用条件は採用されたものの、それもすぐになかったことになってしまいます。妙に複雑な話を簡単にまとめると、こうなります。マッカーティにとってはなんだかなぁ、という状況の中、このSHOOTは結成されました。
相方に選ばれたのはデイヴ・グリーン。名前を言われてもすぐにはわからないかと思います。ありがちな名前だしね。VAN DER GRAAF並みのヘヴィなサウンドと2ndがRCAネオンから出ていたことからプログレ・ファンにもお馴染みのRAW MATERIALのギタリストだった人です。
1973年という年は、時代的にプログレ界は勝ち組の大物陣と中堅・小物の格差がつき始め若干落ち着き気味。音楽シーン全体を見渡すと、グラムも全盛期は過ぎ、クラブ・シーンをみるとファンクやエスニックが注目を集め、10CCに代表されるような新しい感性を持ったポップ・サウンドが登場みたいな感じでした。SHOOTはまさにこのシーンの動向を踏まえたサウンド指向を持ったバンドで、くくりとしてはプログレというよりポップに寄ったサウンドですが、出身がRENAISSANCEとRAW MATERIALだけにポップよりながら、そこかしこに、クラシカルな雰囲気を湛えた侮れないメロディが残っており、プログレからポップへ移行していく時代に出た作品の中ではかなりいい線いっていると昔から思っておりました。
後にオリジナルRENAISSANCEの再結成であるILLUSIONへ繋がっていく感性もこの作品にはしっかり記録されており、RENAISSANCE関連のレア・アイテムとしてもポイント高いかと思います。
アナログ市場でも2000年代の初めくらいに話題になり、それまではアートワークがこれですから大したプレミアは付いていなかったのが、RENAISSANCE+RAW MATERIALと紹介された瞬間に値段が一気につり上がったことをよく覚えています。
On The Frontier
関連カテゴリー
「音楽歳時記」 第三十回 再び山の日、さらばグレッグ・オールマン
-
ALLMAN BROTHERS BAND / EAT A PEACH
サザン・ロックの雄、デュアンの最後の参加作となった72年4th
急逝したデュアン・オールマンを含む布陣によるスタジオ音源と、フィルモア・イーストで収録されたライヴ音源で構成。トップ10ヒットとなった72年の出世作。
-
廃盤希少、特殊プラケース仕様、SACD/CDハイブリッド
盤質:傷あり
状態:良好
ケースに若干黄ばみあり
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!