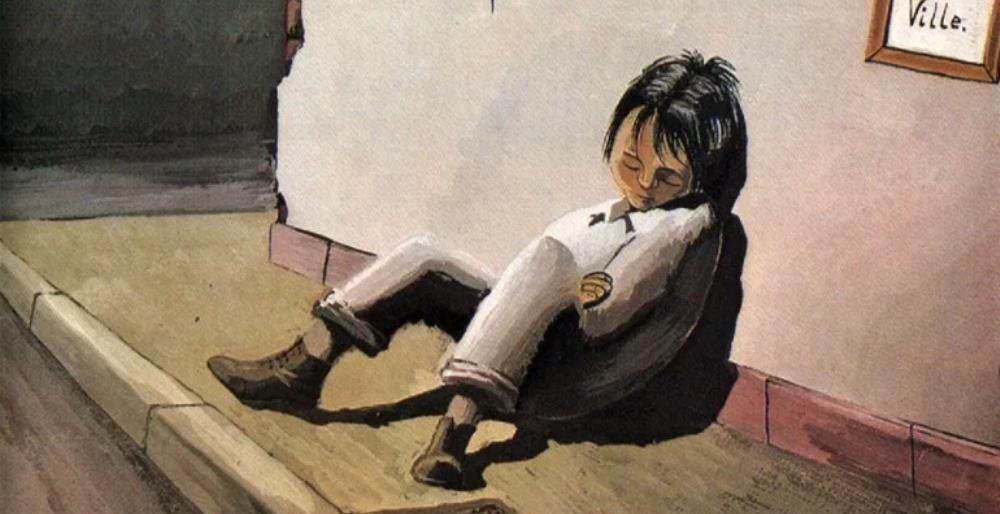COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹
2018年10月6日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム
タグ:

第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」
秋も徐々に深まってきた。さすがに木々が色づくのは少々遅い気もするが、あれだけ暑く、また台風等の災害に遇いながらも、ここに来てまた季節が巡ることはとてもありがたく感じている。と同時に不思議な気もする。間もなく寒さもやって来るが、過ごしやすさを感じられるこの時期。また音楽を聴きながら静かに落ち着いた時を持って、様々なことに考えを巡らせてみたいと思っている。


今回はこの季節にふさわしいと私が考える1枚のアルバムを紹介したい。
それは、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』(US Kama Sutra KSBS 2078 1973)だ。決して珍しくもない、皆さんよく目にするアルバムの1枚だろうと思う。昔からお勧めの1枚として機会ある度に人に伝えてきたのだが、その印象はどうにも芳しくないものが多かった。
周囲から最初に聞こえてくる声は、まずストーリーズってあの「ブラザー・ルイ」や「マミー・ブルー」のヒット曲を持ったポップバンドでしょうという声。(最初から聞いてみたいとは思っていない。) ちょっと詳しい人からは、バロック・ポップで知られるレフト・バンクにいたマイケル・ブラウンがその後に結成したバンドだよね。バンドがポップになったからストーリーズも2枚目までで脱退してしまったよね。(マイケル・ブラウンが辞めたのだからもう終わりだよね)
次に聞こえてくる声は、ストーリーズはつまんないよ。イアン・ロイドの声がもうひとつ好きになれない・・・といった按配。このように最初から否定されてしまうことが多かった。人が何と言おうと自分の好きな音楽は貫き通す。って、そんなに肩肘を張るものではないだろうが、私にとってはとても切なアルバムのひとつである。アルバムの内ジャケットに映った彼らの雄々しい姿(上図参照)もまた堂々としたポートレイトになっていて素晴らしい。同じ思いで聞いていてくれる人が多いと嬉しいな。
今では世界的に使われるようになったProg Rockという言葉。日本ではピンク・フロイドの『原子心母』の帯のコピーとして使われた「プログレッシヴ・ロック」が、次第に定着してひとつの音楽の形態を表す言葉となり、世界的にもかなり早い時期からカテゴライズされていた。
日本では、フロイドは早い段階から国内盤としても別格扱いだった。イエスは初期盤も米盤ジャケットで出されてはいた。EL&Pはデヴュー作から順に国内発売されたものの、クリムゾンはどうか。『宮殿』は輸入盤として大きな話題になり一部のマニアに騒がれていたが、意外なことに日本で最初に発表されたのは3作目の『リザード』だった。ジェネシスは『侵入』以下順次出ていたものの、注目を浴びるようになるまでには時を待たなければならなかった。国内でリリースされる洋楽のLP数は70年代に入ってそれまでより飛躍的に増えるものの、徐々に多くのリスナーの感応する力がひとつのジャンルとして広げていったことは間違いなかった。
私事ではあるが(私事ばかりで恐縮だが)、プログレとして音楽を認識する以前に最初に凄さを感じたのはブラッド、スウェット&ティアーズ(BS&T)とシカゴだった。特にBS&Tの2枚目のアルバムの冒頭は「エリック・サティの主題による変奏曲 第1楽章と第2楽章」。今でこそよく知られたピアノ曲だが、ギターとフルートで奏でられる美しいメロディーに夢中になった。エリック・サティその人が現代音楽の作曲家であることは後で知ったことだった。その後、最初のアルバム『子どもは人類の父である』を聞いて完全にその音楽の虜になった。デヴュー当時のアル・クーパーのアイディアに依るものであることは確かだが、在籍メンバーの確かな音楽的才能に裏付けられた名盤である。どちらかといえば、クラシック的なアレンジに魅力を感じていた。しかし、もっと驚いたのは当時新譜として聞いた『BS&T4』だった。1曲目の「ゴー・ダウン・ギャンブリン」は完全にハードなロックなのだが、そのダイナミックさの前にただただ平伏することになってしまった。
BS&Tよりやや遅れてデヴューしたシカゴは、ロック的なハードさをより強調しながらも実験的な音楽性をより消化した形で示し、さらには時代性を伴ったメッセージ性に日本中を席巻したと認識している。デヴューから3枚目までがどれも2枚組、さらに4枚目のカーネギーホールでのライヴに至っては4枚組という質量ともに圧倒的な存在だった。日本においての海外ロック・アーティストの本格的なコンサートもこのBS&Tとシカゴが最初と言っていいだろうし、この成功がその後続々とやって来るミュージシャンの足場となったことは間違いない。
私にとっては何よりもロックを足場としながらも、クラシックやジャズ等の要素も取り入れた複合音楽がある!という面白さに気づくきっかけになったことが大きい。
その後、AMラジオで聞いたイエスやクリムゾンに魅せられ、FMの番組にそれらしいバンドを次々にリクエストし、オンエアされる曲をエアチェックしていった。(この感覚は若い方々に伝わるだろうか?)
そんな中で学生時代の私が考えたことは、プログレッシヴ・ロックは英国アーティストが中心であるのに、BS&Tやシカゴは米国のバンドだ。音楽的には革新的だが、それはプログレッシヴとは呼ばれない。一大シーンをなすサイケデリックに関しては米国発祥なのに何故だろう・・・という問題だった。そこで、アメリカにもプログレッシヴ・ロックと呼ぶにふさわしいバンドがあるのではないかと、あれこれ間口を広げて聞くことになっていく。
そこでたどり着いた作品はたくさんあるのだが、その一例として今回紹介するのがストーリーズなのだ。冒頭にも書いたように一般にはヒットした「ブラザー・ルイ」や「マミー・ブルー」といったヒット曲を持ったポップ・グループと認識されているに違いない。それはそれで間違いはないのだが、しかし、彼らの73年発表の3枚目のアルバム『トラベリング・アンダーグラウンド』(特にLPのB面)を聞くと、それまでの価値観を覆す大きなメロディーの魅力にあふれたプログレッシヴ・ワールドを堪能することが出来るのである。私がそのアルバムを手に入れたのは、ジャケットの魅力だった。ジャケ買いである。見開きのデザインのダークな色調の中にメンバーが立ち、その背景に幻想的なコラージュがちりばめられている。その一つ一つに何かドラマが語られているように思えたのである。
その後私にとって本アルバムが重要な作品となるきっかけになった、B面の1曲目を聞いてもらおう。
Ian Lloyd & Stories / Stories Untold
この曲には一回聞いただけでノックアウトされた。4分間の中にそれまでのストーリーズとは違うドラマ、新たな物語を見せてくれている。イアン・ロイドのヴォーカルは、ロッド・スチュワートやロバート・プラントに比較されたこともある個性的なハイトーン・ヴォイスが特徴である。確かに好き嫌いは出てくるだろうが、この曲においては彼の声が見事に曲を引っ張っていく。そしてギターのスティーヴ・ラヴ、ベースのケニー・アーロンソン、キーボードのケネス・ビッチェル、ドラムスのブライアン・マーディのアンサンブルが一糸乱れぬ素晴らしさだ。途中に聞こえるコーラスも効果的であるし、完全にパワーアップしてハードになったバンドの姿を浮かび上がらせている。曲そのものも今日ではあまり聞かれなくなった(ように思える)タメの美学がここに息づいている。早急に展開を見せるのではなく、クライマックスをじらすように徐々に上り詰めていく。それまで私が持っていたストーリーズのイメージ、クラシックの要素はあるものの、迫力に欠けているという印象を見事に覆してしまった。
前作でイアンと並ぶバンドのもう一方の中心であったバンドのマイケル・ブラウンが抜け、新たにケニーとケネスの二人が参加した。そのことでまず、リズムがタイトになった。特にケニーは同じカーマ・ストラ・レーベルから2枚のアルバムを出しているダスト(Dust)から加入したこと。超絶ハード・サウンドを聴かせたトリオ編成のダストでのプレイが明らかに下敷きとなっている。同時に、彼の加入によってブライアンのドラムスも前作までとは別人のようにはじけた。メンバー交代が、いい相乗効果を生んだと考えられる。またキーボードのケネスの曲の解釈力と演奏そのものもバンドに若々しさを醸し出すことに成功したという印象がある。
それまでのストーリーズのアルバムにはソフトで室内楽的な雰囲気が支配的だったが、このアルバムでは一気に、ライヴを意識した開放的なサウンドに大転換している。
B面の3曲目を聞いていただこう。キーボードのケネスが持ち味であるその叙情性を武器にして、力量を存分に発揮した「Earthbound/Freefall」のメドレーも聞いてみよう。こちらも名曲に値する素晴らしさである。
Ian Lloyd & Stories / Earthbound~Free Fall
静かなピアノに導かれ8分を超える流麗でドラマチックな世界。途中のギターソロはまるでキャメルのアンディ・ラティーマーだ。今考えてみると本作はキャメルのデヴューの半年後の作品になるが、イアンやケネスは彼らのファースト・アルバムを聞いていたかも知れない。
キャメルのデヴューも、ストーリーズのこの大きな変化も1973年という同時期の活動だったことを考えると、(英米ともに)当時のシーンの面白さに思いを馳せてしまう。曲はイアンとケネスの手によるものだが、やはりリズムが強力だし、何といってもケネスの操る彩りを加えるメロトロン、そしてあくまでアコースティックなピアノを芯にして綴られる流麗なメロディーに心を打たれる。
前作までもマイケル・ブラウンはメロトロンを使用していたが、本作で新たに加わったケネスの各種キーボードが明確に当時のプログレを意識してこの曲をコンポーズしたことがわかる。
ここでもケニー・アーロンソンのベースの威力からリズムの強化が図られたことがよく分かる。ちなみにケニーが参加する前は、ストーリーズはイアン・ロイドがベースを担当していた。マイケル・ブラウンの脱退後、それまで双頭バンドの一方だったイアンが、アルバムのコンセプトと曲のアイディアづくりと、そして何よりもヴォーカルに専念するための措置だったと受けとめることが出来る。
アルバムのジャケット見開き(裏部分・・下図参照)を改めて眺めてみてほしい。表面には、アルバムのタイトル通りアンダーグラウンドの夢世界がコラージュに散りばめられて描かれている。収録された各曲の歌詞にはそのエピソードがうかがえる。それだけによりアルバム全体としてトータルな味わいを感じ取ることが出来る。

ここで少し、ストーリーズの歴史を簡単に振り返っておきたい。
ストーリーズは72年に米ブッダ系列のカーマ・ストラ・レーベルからデヴューしている。バンドの中心メンバーはキーボードのマイケル・ブラウンとヴォーカルのイアン・ロイド。
前身となるのはマイケル・ブラウンが率いた米国ソフト・ロックとかサイケデリックの括りの中で語られるレフト・バンクだ。レフト・バンクはマイケルのキーボード(ハープシコード)を中心に、曲調をバロックに据えた当時の時代性を象徴したバンドのひとつであった。マイケルは最初のアルバムのみで脱退してしまうが、バンドは66年初頭の活動開始から約2年間で2枚のアルバムをマーキュリーから出すと同時に「いとしのルネ」「プリティ・バレリーナ」といったシングル・ヒットも持っている。彼らの中で5枚目のシングルになった「デジレー(Desiree)」はとてもいい曲なのだがヒットしなかった。その後、マイケルはいくつかのセッションに参加するのだが、中でもモンタージュ(Montage)というバンドをプロデュースした時に再録させたのだが、これがまたなかなかの出来だ。(後年あのファイアーバレーが2枚目でカバーしている。悪評高いメンバーのバレージャケットだが内容はいい!)
マイケルは70年代に入って新たな活動を開始する段階では自分のソロアルバムを作成しようと考えていたという。しかし、そうした思いの一方で実際にはレフト・バンクの再編をもくろんで、オリジナルメンバーを呼び寄せ、意外にも映画音楽をレコーディングしていた。結果的にそのレコーディングはで、ヴォーカルのスティーヴ・ヤング名義のレコードとしてやはりカーマ・ストラ・レーベルから出されている。そのスタジオで、イアン・ロイドと出会うことから新たなバンドの結成を考えるようになる。その出会いは、マイケルとイアンの双方の父親が同じセッション・ヴァイオリニストだったことに由来する。同じセッションに参加していた二人の父親の息子同士が顔を合わせ、そのスタジオで意気投合したというのだから面白い。ファースト・アルバムの裏ジャケットには双方の親子4人が笑顔で並んだポートレイトを載せているのも微笑ましい。(余談だが、マイケルの父親の方は先ほど述べたBS&Tの「子どもは人類の父である」のストリング・アンサンブルの一員としてクレジットされている。)
また、出会った頃の様子は、マイケルが典型的なクラシック畑の出身を漂わせていたのに対して、イアンはロイド・ロンドンと呼ばれたほどに英国音楽に心酔したロック好きだった。60年代中期以降のことだからそこには間違いなくビートルズの存在があったことは想像に難くない。室内楽的なクラシカル・メロディーとハイトーン・ボーカルを武器にバンドはファースト・アルバム『ストーリーズ』を完成させる。その中に収録された「アイム・カミン・ホーム」が72年8月に米国で42位のヒットとなり、順調に滑り出す。セカンド・アルバム『アバウト・アス』はエディ・クラマーのプロデュースで発売された。録音は72年から73年の初頭にかけてのことだ。しかし録音を終えてすぐにマイケルは脱退してしまう。残ったイアンが率いるストーリーズはその後、「ブラザー・ルイ」をシングルとしてリリースするのだが、73年8月に全米ナンバーワン・ヒットになる。このヒットはプロデューサーのケニー・カナーとリッチー・ワイズの力による部分が大きい。このレコーディングに際し、このプロデューサー・チームが同じカーマ・ストラ・レーベルのダスト(Dust)にいたケニー・アーロンソンが加えたのはこの時点だからだ。オリジナル曲はホット・チョコレートというバンドが英国で73年4月に7位にランクさせている。米国でよりファンキーにヒットさせようというレコード会社の思惑がまんまと当たった格好になった。セカンド・アルバム『アバウト・アス』のオリジナルには「ブラザー・ルイ」は入っていないのだが、セカンド・プレスの際に追加収録されている。その結果、『アバウト・アス』はアルバム・チャート29位まであがり、ファーストの182位より上回る成果を収めた。マイケルにしては皮肉な事実であろう。
そのヒットの流れを受け、新たなキーボードとしてケネス・ビッチェルを加入させ、アルバム前に2匹目のドジョウを狙って今度は「マミー・ブルー」を用意した。「マミー・ブルー」が世界的に大競作としてたくさんのアーティストのバージョンが登場したのは71年のこと。(この時期のカバー合戦は本当にすごかったが、日本では (スペインの!) ポップ・トップスがダントツの人気盤となり、リッキー・シェイン、そして(イタリアの!)イヴァンナのバージョンがその次くらいに流行ったことを記憶している。)ただ、レコード会社が意気込んだ割にチャートアクションは今ひとつで、50位止まりだった。シングルのクレジットがストーリーズ名義になっているのはこれまでの流れをなぞっていたせいだ。
新たなアルバム制作に関して、バンド名もストーリーズからイアン・ロイド&ストーリーズと改め、イアン自身も意欲を持って本格的なバンド・サウンドを求めていったことは想像に難くない。しかし、アルバムの内容の良さとは裏腹に、チャート・インした事実がないのが残念だ。
私は、マイケル・ブラウンもレフト・バンクも大好きだし、ストーリーズの最初の2枚のアルバムも愛聴盤に数えているのだが、音楽を聴いたショック度としてやはり、『トラベリング・アンダークラウンド』の存在は別格と言えるほどにとにかく大きい。近年、この作品のLPのA面にあたる部分は、ハード・ロックやメタル・ファンに再評価されているという話をネットで拾った。
今回、このコラムではB面の2つの曲しか紹介していないのだが、この2つの曲のインパクトの強さ、尽きぬ魅力がもう40年以上私を縛り付けている。もちろん、他の曲もアルバムとして聴いても私的名盤として輝き続けている。CD、レコードともにいつでも取り出せる便利な場所に置いてあるくらいだが、新たに聞く方々についてもこの2曲が糸口になってくれることを願いたい。
この作品と出会ったのと同じ頃、やはりアメリカのタッチ(Touch)*Clossusやフィールズ(Fields)*Uni、フェイスダンサー(Facedancer)*Paramount、フライト*Capitol、フライイング・アイランド(Flying Island)*Vanguard等、けっこうな数のプログレに加えてもいいような魅力的なレコードに出会うことができた。また、カンサス(Kansas)やファイアーバレー(Fireballet)、スターキャッスル(Starcastle)、レヴィアサン(Leviathan)、シャドウファックス(Shadowfax)等が日本で紹介され始める頃とも重なってくる。表舞台には立たないが確かにニュー・ロックという旗印の前後に、同じ感性で複合的な音楽を目指す目というのは世界共通であると認識できたことを改めて思い返す。
この作品は今でもLPレコードで安価で結構見つけることが出来る。しかし、国内盤はシングルジャケットになっていて、歌詞カードはありがたいものの内部のメンバーの勇姿が拝めない。是非ともオリジナルのダブル・ジャケットの輸入盤で手に入れてその重みを実感してほしい。
再発CDは90年代にはいくつかあったのだが、2000年代に入ってからはブート的な物しか確認できなかった。
ファーストとセカンドの2イン1は2007年に豪Ravenから出ているが、これもあまり見かけない。編集ものは1989年に3枚のアルバムからのベスト盤“Walk Away From The Left Banke Plus”が英See Fo Milesから出ていたが、今回紹介した2曲は含まれていないし、何といっても古すぎるかな。
最新のアンソロジーは2014年、米Real Gone Musicからの19曲入りのベスト。これは件の2曲が収録されているし、珍しいシングルやイアン・ロイドのソロも入ったなかなか気の利いたCDだ。ただ何故なのか、このReal Gone Musicから出されているものはどれもなかなか入手しにくいのが困ったところ。
とりあえずyoutubeで聞けることが幸いだろうか。
ストーリーズとしては、この後のリリースはない。イアン・ロイドはその後、ソロとして独立し、ポリドール、スコッティ・ブラザーズといったレーベルからアルバムを発表する。フォリナーからヴォーカリストにという声もかかったという噂もあったが、結果的にルー・グラムに収まった。その後フォリナーは商業的にも大成功するバンドになっていくことは承知の通りだ。
2014年2月にイアン・ロイド・オブ・ストーリーズの名の下にAmerica Celebrates The Beatles All Star Benefitというコンサートで、「ブラザー・ルイ」を演奏した映像がある。イアンの高音がさすがにきついが、きっと彼の息子であろうデヴィッド・ロイドがキーボードを演奏している。さらに驚きは、元ストローブスのジョン・フォードが隣でアコースティック・ギターを弾いている。(この映像はジョン・フォード自身のチャンネルによるものだ)
歴史を振り返って考えたときに、イアン・ロイド&ストーリーズの唯一のアルバム(あえてそう表現するが)『トラベリング・アンダーグラウンド』は、パワーポップやアリーナ・ロックの先駆け的な位置にあったと言えるのではないだろうか。想像でしかないが、イアン・ロイドもケネス・ビッチェルも英国プログレをよく聞いていたように思える。
ケネスの方は、その後アレサ・フランクリンやビリー・ジョエルのバックも努めている。その他ジャズやフュージョン系のアーティストとの共演も多い。現在でも映画音楽や放送曲の仕事を含めソロとして活動を続けていて、彼のホームページもあり(kenbichel.com)、youtubeでも近年の演奏を聴くことが出来る。じつは彼はジュリアード音楽院の出身のピアニストでもある。実験的な取組みもあるが私はHPに添えられた彼の演奏は好きだ。ただ、HPのミニバイオには、ストーリーズのことは書かれていない。
ヒット曲の一つ二つを持ったがために、そのイメージが先行し成功に至らなかったミュージシャンは幾つも思い浮かべることが出来る。ただ、何のヒットも出すことなく消えていったアーティストは数え切れないほど存在するわけだ。そんな中で今も70年代のロック、ポップスシーンにおいて「ブラザー・ルイ」の一発屋、ストーリーズとしてその名を残していることは彼らにとってどう受け止められているのだろうか・・・。やはり一つの栄光だろうか。
「Stories Untold」(語られない物語)という彼らの運命をたどっているような曲名の皮肉さを感じながら、今後新たな再発の機会が訪れることを期待したい。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!