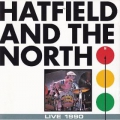COLUMN THE REFLECTION 第67回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ② ~ハットフィールド&ザ・ノース、ヘンリー・カウ、そして、ギルガメッシュ、ナショナル・ヘルス・・・アラン・ゴウェンの軌跡とともに~ 文・後藤秀樹
2023年11月28日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム
タグ:

第67回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ②
~ハットフィールド&ザ・ノース、ヘンリー・カウ、そして、ギルガメッシュ、ナショナル・ヘルス・・・アラン・ゴウェンの軌跡とともに~
前回はニュークリアスとソフト・マシーンを中心にジャズ・ロックを取り上げてきたが、今回はカンタベリー系の代表格としても知られるハットフィールド&ザ・ノースに始まる流れを追ってみたい。
日本コロンビアから75年にヴァージン・レーベルが発売になったことは、国内発売されたドイツ・ロックの流れの中で触れてきたが(本コラム第63回「ドイツ・ロックが日本において本格的に紹介され始め70年代を振り返る②」)、英国勢はマイク・オールドフィールドは別格として、ソフト・マシーン関連の作品に注目が集まった。
ひとつは不慮の事故後に復帰したロバート・ワイアットの『白日夢(Rock Bottom)』。これはファンが彼の回復具合がどうなのか、ドキドキしながら待った作品だった。また、デヴィッド・アレンのゴングも新たに『Angel’s Egg』と『You』がリリースされた。両者ともに期待通りの内容だったことは誰もが認めるところだろう。
そんな中で新たなラインナップとして、名うてのメンバーが結成したハットフィールド&ザ・ノース、そして当時はまだ新たな実力派ユニットだったヘンリー・カウへの期待感が高まっていた。
順番として日本ではヘンリー・カウの『伝説(Legend)』が5月に、ハットフィールドの方はファーストが6月、セカンド『The Rotter’s Club』が7月と続けざまに発売された。
その頃の私たちの期待はハットフィールド&ザ・ノース(以下ハットフィールズ)にあった訳だが、その理由はまずメンバーに元キャラバンのリチャード・シンクレア(Richard Sinclair)がいたことが一番大きかった。
さらには元エッグのデイヴ・スチュワート(Dave Stewart)を中心にマッチング・モールのフィル・ミラー(Phil Miller)、元ゴングのピップ・パイル(Pip Pyle)が並んでいるのだ。ただその頃(75年当時)は、エッグ(Egg)は日本では発売されておらず翌76年にキングの「ブリティッシュ・ロック秘蔵盤シリーズ」として最初の2作品が初めてリリースされることになる。しかし、そのデイヴ・スチュワートが凄いキーボード・プレイヤーであるという評判は伝わっていた。
§4 如何にも英国的なハットフィールド&ザ・ノースのクールな世界
◎画像1 Hatfield And The North / Same

英国で74年に発売された最初のアルバム(録音は73年)は、まずそのジャケット・デザインに驚かされた。陰鬱な英国の街に漂う空を覆い尽くすような雲・・・その雲に浮かび上がる殺戮の地獄絵図。古から続く人間の暗い歴史を風景に浮かび上がらせた見事な作品となっている。音楽も含めて総合的な芸術作品の一つと私は認識している。
最初に国内盤で買ったアルバムだが、英国盤のコーティング・ジャケットがどうしても欲しくなり後に入手した思い出深い作品の一つだ。
先にも書いたようにこのアルバムが日本で最初に出た時には、リチャード・シンクレアの名前で注目を集めた形になる。何といって彼が在籍したキャラバン最初のDecca/LondonとDeramからの3作品(本来のデヴュー作MGM盤レコードは日本未発)のインパクトが強かったからだ。
この作品は驚くことに15曲がクレジットされているのだが、作者を見ると1曲目がピップ・パイル、2曲目はリチャード・シンクレア、3曲目はデイヴ・スチュワート、4曲目はフィル・ミラーと4人のメンバーが順番に紹介されるような格好になっている。特に2曲目のシンクレアの『Big Jobs(Poo Poo Extract)』の歌詞は次のようになっている。「これは始まりを告げる歌/でたらめに並んだわずかな音符/だけど俺たちはベストを尽くしてよいサウンドを目指す/新しいLPを聴いて/君たちが夢中になれるように」
まさに新たなバンドに賭ける思いを歌っているわけだ。
続く5曲目「Son Of “There’s No Place Like Horseman」が10分を超える本領発揮の1曲と言える。彼らのサウンドはソフィティケイトされたジャズ・ロックという印象を受けるが、デイヴのオルガンを中心としたキーボード群の音色が彼らの個性を決定づけていた。
★音源資料A Hatfield And The North / Son Of “There’s No Place Like Horseman
このデヴュー作は内ジャケットもまた賑やかで、メンバーや客演陣(車椅子に乗ったワイアットが印象的)、女性バック・ヴォーカル(The Northettes)のバーバラ・ガスキンとアマンダ・パーソンズ、アン・ローゼンタールの3人、さらに若き日の俳優ジョン・ウェインと思われる姿も!
◎画像2 Hatfield And The North / The Rotter’s Club

そして、2作目の『The Rotter’s Club』が発売された。
ジャケットはレトロ調の色彩感覚で前作との大きな違いを感じたが、裏ジャケットのモノクロのコラージュが「現代に脈々と息づく宗教観と人間」といった前作に似た意匠も見られるものだった。
収録曲はA面こそ7曲だが、B面では1曲+20分近い組曲となっていて、彼らの長尺の演奏が聴けるという期待感を持った。
最初に聞いた時には1曲目の「Share It」に始まるA面は曲のつながりも意識させず一気に聞き通してしまった。もっと驚いたのはB面の組曲も傑作と呼べるほどに素晴らしかったこと。今でもCDでボーナス・トラックも含めてやはり一気に聴いてしまう。
★音源資料B Hatfield And The North / Share It
この作品は間違いなく名盤でその後の活躍を期待したのだが、アルバム発表後のプロモーショナル・ツアーを途中でキャンセルせざる終えない状況にバンド状態が追い込まれることになった。それは、所属するヴァージン・レコードの支援が得られなかったことが大きかったらしい。そして結局は75年6月に解散となる。
以前のコラムの「ドイツ・ロック」で触れたFaustも同様に厳しいツアーにメンバーが次々に脱退したエピソードを紹介した。ヴァージンは成功した大きな企業ではあったが、そこに所属するものにとっては厳しい実態に追い込まれていたということが言えるのだろう。時代の音楽状況もパンク前夜でニューウェイヴの足音が聞こえていた頃のこと。悲しい現実である。
◎画像3 V.A/ Over The Rainbow-The Last Concert Live+Afters+LIVE 1990+Hatwise Coice+ Hattitude

そんな中ではあったが、アルバム『レインボウ最後の日(Over The Rainbow-The Last Concert Live)』として1975年3月16日のコンサートでハットフィールド&ザ・ノースとして1曲「Halfway Between Heaven and Earth」が収録されている。
また、80年にはヴァージンから『Afters』(LP)という編集盤が出されていたし、93年にはハットフィールド&ザ・ノース名義で『LIVE 1990』(CD)が出ている。デイヴ・スチュワート抜きの3人が参加し、キーボードはフランス人の女性ジャズ・ピアニスト、ソフィア・ドマンチッチ(Sophia Domancich)を加えてのライヴ盤。さらには2005年には70年代中期のBBC音源をまとめた『Hatwise Coice』、そして『Hattitude』という2枚のCDも出ているのだが、通常流通の作品ではなかったので私も入手できないままだ。何とか今後どんな形でもいいから明らかにして欲しいものだ。
なお、2005年にはデイヴはいないもののオリジナル・メンバーの3人が参加して来日公演も行われた。
§5 そしてヘンリー・カウについても・・・
日本ではハットフィールズより1ヶ月早くリリースされたヘンリー・カウ(Henry Cow)。バンドはケンブリッジ大学在籍中に出会ったギター(マルチ・インストゥメンタリスト)のフレッド・フリス(Fred Frith)とクラリネットのティム・ホジキンソン(Tim Hodgkinson)が68年に音楽活動を開始。ドラムスのクリス・カトラー(Chris Cutler)、ベースのジョン・グリーヴス(John Greaves)、ファゴット・オーボエを演奏するジェフ・レイ(Geoff Leigh)を加え73年に最初のアルバム『Legend』を発表する。その後、ジェフがリンゼイ・クーパー(Lindsay Cooper)に交替する。
◎画像4 Virgin Sound + Henry Cow / Legend

彼らの音楽を最初に聴いたのは、日本でヴァージンがリリースされる際にプロモーション・レコードとして出された『Virgin Sound』というアルバムに収められた「ティーンビート」(実際にはTeenbeatとして3パターン収録されているうちのReprise部分)だった。これがカッコいい。ソリッドなロック・ギターにジャズ・ピアノ的な絡みがなかなか面白い。
★音源資料C Henry Cow / Teenbeat Reprise
これは「基本的にジャズ・ロック!!」と思ったのだが、アルバム解説を見て少し不安になった。
フリスはソフト・マシーン(特にワイアット)、とジョン・ケージに影響を受けてアヴァンギャルドな音楽に向かったとのこと。ホジキンソンはフリー・ジャズ・グループやハプニング・グループで活動・・・・うーん、これは前衛色が強いバンドということか。
注目したバンドだったのだが、いざ『伝説(Legend)』を聴いてみると不安が的中。ジャズ・ロック的な部分は間違いなくあるのだが、予想以上に前衛色が強い。ジャズも好きでけっこう聴いてはいたものの、その頃フリー・ジャズは苦手だった私には残念ながら全編通してというのは難しかった。
そんな私だが79年の『Western Culture』までは出る度にチェックして、当初感じた違和感は消えてきて現在に至っている。
◎画像5 Henry Cow 2、3 + Slapp Happy + Kew.Rhone.

彼らの初期のアルバムは靴下を置いた色違いジャケットだったのだが、その始まりがこのタイトル『Legend』→『Leg End』という言葉遊び的な発想であると気づいたときには「そうなのか」と妙に納得したことも思い出す。
そう言えば、ヘンリー・カウのジョン・グリーヴスがスラップ・ハッピー(Slapp Happy)のピーター・プレグヴァド(Peter Plegvad)と共にやはりヴァージンから77年に『Kew.Rhone.』というアルバムを出しているのだが、こちらも謎解きのような言葉遊びや、絵解きがあった。
この作品はリサ・ハーマン(Lisa Herman)という米国の女性ヴォーカルを加えた作品なのだが、他にもカーラ・ブレイやマイケル・マントラーといったジャズ・ミュージシャンを迎えている。前衛的ではありながらもコンテンポラリー・ジャズの良質な部分も感じられて興味深い作品になっている。
彼らは途中からスラップ・ハッピー(Slapp Happy)と活動するようになるのだが、私は当時ヴァージンから出たばかりのスラップ・ハッピーのアルバムを(ケヴィン・コイン(Kevin Coyne)の『Blame It On The Night』と一緒に)買った。その頃(高校時代)関わっていたミニコミにその感想を「ポップだが、コマーシャルな音楽ではない」と書いたのだが、アルバム自体はかなり楽しめたことはよく覚えていて、現在でも時々聴くほどに気に入っている。そのスラップ・ハッピーも活動歴は長いのだが、その姿勢が前衛的なことで知られるRecommended Records(通称レコメン)の流れにつながっていくことになるとは当時は考えてもいなかった。しかし、そのレコメンから出された一連の作品群を眺めたときに「なるほど」と理解することができる。
§6 ギルガメッシュとナショナル・ヘルス そしてアラン・ゴウェン
ハットフィールズが早々に消えてしまった残念な事情について当時は知る由もなかったが、75年にヴァージンの傘下レーベルCarolineから出たギルガメッシュ(Gilgamesh)のアルバムがジャズ・ロックだという情報が伝わった。
◎画像6 Gilgamesh

バビロニアの叙事詩から命名されたバンド名に比べ、ジャケットはかわいらしい双六的なイラストで俄にジャズ・ロック作品とは思われなかったが、裏のクレジットを見ると、まず目についたのがベーシストでニュークリアスのジェフ・クライン(Jeff Clyne)だった。さらにドラムがマイケル・トラヴィス(Michael Travis)は、Dawnレーベルに印象的なアルバムを残しているアトランティック・ブリッジ(Atlantic Bridge)のメンバーで、その後ツトム・ヤマシタのEast Windにも参加していた。さらにアマンダ・パーソンズはハットフィールズの女性ヴォーカル隊の一人で高音の美しい歌声の持ち主。
しかし、当時はバンドの中心であるキーボードのアラン・ゴウェン(Alan Gowen)もギターのフィル・リー(Phil Lee)も初めて目にする名前だった。
★音源資料D Gilgamesh / We Are All – Someone Else’s Food – Jamo And Other Boating Disasters
アラン・ゴウェンは70年代初頭にアフロ・ロックのアサガイ(Assagai)での演奏経験を持っていた。ジェイミー・ミューア(Jamie Muir)とSunshipというバンドを活動したが、72年にミューアがクリムゾンに加入することになり頓挫。ハットフィールズのオーディションを受けるものの落選。キーボードにはデイヴ・スチュワートが決まる。実力者ではあるもののなかなか運には恵まれないゴウェンの様子が伝わってくる。そこで自ら新たに結成したのがこのギルガメッシュとなるわけだ。
ギルガメッシュの結成は72年。しかし、メンバーの出入りが激しく安定しない状態が続いていた。そんな状況の中にあって73年11月にハットフィールズとダブル・カルテットの形でゴウェンが作曲した組曲を共演している。ギルガメッシュ自体はその後もメンバー交代が続き(特にベーシストが一定しなかった)、ようやく75年にアルバム『ギルガメッシュ』を録音、リリースにこぎつけたわけだ。
その75年8月にはゴウェンとリーはギルガメッシュと並行してナショナル・ヘルスを結成する。これは75年6月にハットフィールズが解散したことがきっかけではあるが、今述べたハットフィールズとギルガメッシュとのダブル・カルテットの経験が大きな転機となっていることは明らかだ。
当時のメンバーにはビル・ブラフォード(Bill Bruford)や元エッグ(Egg)のモント・キャンベル(Mont Campbell)も含まれていて、ライヴにはスティーヴ・ヒレッジ(Steve Hillage)も参加していた。
◎画像7 National Health

ナショナル・ヘルスの最初のアルバムは78年にリリースされるのだが、そのジャケット裏に記載されたパーソネルを見ると基本メンバーはデイヴ・スチュワート、フィル・ミラー、ニール・マレー(Neil Murray)、ピップ・パイルの4人なのだが、3人がハットフィールズからのメンバー。マレーはギルガメッシュの2代目ベーシストだった。ナショナル・ヘルスとは、結局ハットフィールズからシンクレアを抜いたラインナップになったわけだ。
アラン・ゴウェン自身は各曲の基本メンバークレジットの後に<with>として客演扱いとなっている。
じつはナショナル・ヘルスはメンバーの安定しない状態が続き、ゴウェン自身もフィル・リーと前後してアルバム録音前に脱退していた。それでもゴウェンはコンポーザーとして全4曲中2曲に関わっているのだが、あくまでゲストとしてアマンダ・パーソンズと共に全てのレコーディングに参加している。
これは想像でしかないが、周囲が「ハットフィールズの復活形をナショナル・ヘルスに期待した」ということが大きく働いていたように思えてならない。事実、当時の私も「ハットフィールズが戻ってきた」と喜んだことを思い出す。
ただ、本作がレコードとして出た時に「あれっ?」と思ったことは、Charlyレコード傘下のAffintyレーベルからのリリースだったこと。当時Charly、Affinityからリリースされるものは再発廉価盤という印象が強かっただけに私は「本当に新譜なの?」と戸惑ってしまった。やはり、ニュー・ウィヴ、パンク系が主流になった時期で、既にオールド・ウェイヴ扱いを受けているような気分にさせられた。
★音源資料E National Health / Tenemos Roads
同じ78年にはギルガメッシュ名義の2枚目となる『Another Fine Tune You’ve Got Me Into』がCharlyレーベル(CRL5009)から発売された。そして矢継ぎ早に、ナショナル・ヘルスの2枚目『Of Queues And Cures』も同じCharlyレーベル(CRL5010)から発売されたことになる。
◎画像8 Gilgamesh /Another Fine Tune You’ve Got Me Into + National Health/ Of Queues And Cures
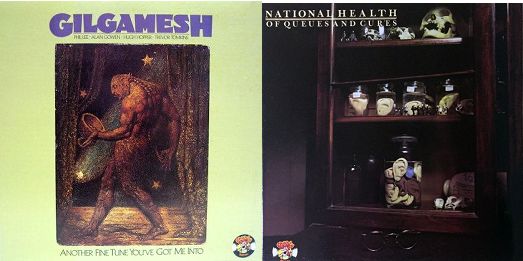
この2枚は時期を経て別々に見つけた。その都度「今回もCharlyレーベルからのリリースか」というため息交じりの言葉を呟いたが、レコード番号が続き番号になっていることからほぼ同時発売といってもいいだろう。その点ではじつに興味深いことだった。
日本盤が出るまではまだ時間がかかるが、この頃になると我が北の町にも輸入盤や中古店が既に複数存在しており、新譜で見つけることができるようになっていた。
先に見つけたギルガメッシュのセカンドは、ジャケットの絵画がウィリアム・ブレイクの「The Ghost Of A Flea」が不気味で、ファーストの可愛らしいイラストとは対照的。しかし、こちらの方がどこかバンド名との共通項が感じられる。入手した時点では先ほど書いたようにナショナル・ヘルスとの関連を知らなかったので、純粋にギルガメッシュの2作目として聞いた。
タイトルの「Another Fine Tune You’ve Got Me Into」は直訳すると「あなたが私を夢中にさせた別の素晴らしい曲」になるわけで、明らかに2作目を意識した作品と言える。
メンバーはゴウェンとリーは替わらないものの、ベースはお馴染みのヒュー・ホッパー(Hugh Hopper)、ドラムスはトレヴァー・トムキンス(Trevor Tomkins)に替わっていた。トレヴァーも英ジャズ方面作品に多数参加してきた名うてのミュージシャンだった。
ファーストではアンサンブルも見事で面白かったが、ゴウェンとリーが各々アコースティックなソロ曲を用意したところが魅力的だった。このセカンドではリーのアコースティック・ギター・ソロはあるものの、ゴウェンのピアノ・ソロがなくちょっと残念だった。代わりにホッパーのベース・ソロが何気なく収録されているのがミソかもしれない。
続いてはナショナル・ヘルスのセカンド。メンバーは前作と同じ・・・と言いたいところだが、やはりベーシストがヘンリー・カウのジョン・グリーヴスに交替していた。全体にリズムが強調されソリッド感が漂うと同時に、メロディアスでパワフルな曲が並んでいる。が、グリーヴスが入ったことで少しばかりフリー・ジャズ的な部分もある。また、ホーン・セクションを中心としたゲスト・メンバーを加えていることが特徴的。ここではそんな中から1曲「The Collapso」を聴いてみよう。ギターが奏でるメロディーがどこかVDGGの「Theme One」を思わせて仕方ないのだが・・・。
★音源資料F National Health / The Collapso
この「The Collapso」は90年に「The Apocalypso(黙示録)」として採録され、ナショナル・ヘルスの2枚組編集盤CD『National Health Complete』(ESD)に採録されていて、詳しい説明書きまで添えられているほどの重要曲(?)である。
**********************************************
◎画像9 National Health / D.S al.Coda
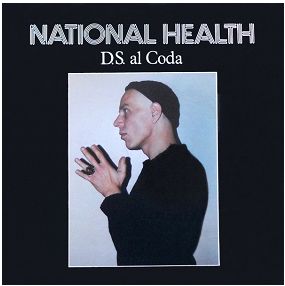
そして82年、前作から4年を経てナショナル・ヘルスの3作目『D.S.al.Coda』がリリースされた。これは事前の情報が何もないままに届いた作品。ジャケットの「祈りを捧げる男の姿」のポートレートが不思議だったが、裏ジャケの説明を読むと、何と「ゴウェンが81年5月17日に亡くなり、ここに収めた楽曲は彼が79年~81年までに書いた作品をまとめたもの」と書いてあった。ジャケットのポートレートはアラン・ゴウェンその人の姿だったわけだ。
メンバーは前作同様の4人。ゲストが3本の管に、フルートのジミー・ヘイスティングス、女性ヴォーカルにはアマンダとバーバラの2人、そしてリチャード・シンクレアもヴォーカルとして参加している。
しかし、追悼アルバムという湿っぽさはない。
アルバムの1曲目『Portrait of a Shrinking Man』を聞いて圧倒された。冒頭の3管のアンサンブルが鮮烈だった。
シンクレアのヴォーカルが入った『Black Hat』と合わせて聞いていただこう。
★音源資料G National Health / Portrait of a Shrinking Man
★音源資料H National Health / Black Hat
この2曲に限ることなく、収録されたどの曲もよく出来ているし演奏も文句の付けようもなく素晴らしい。当然のことながらゴウェン自身は演奏していないものの、改めて彼の持っていた音楽的資質の高さに凄みを感じさせる名盤と評価したい。
遅まきながらこのアルバムを聴いた後に彼の軌跡を改めてたどってみる作業を始めようとした。しかし、アルバムが出た時点ではなかなか資料が見つからなかった。CD化が進んだ頃になって少しずつわかってきた。彼は1947年8月生まれだから、34歳で亡くなったことになる。あまりにも早い死だった。
ゴウェンについて78年以降の音源をまとめると以下の作品が挙げられる。いずれもよく知られた英ジャズ的な作品だが、ジャズ・ロックを聴く耳にも楽しめるものだろう。
◎画像10 Soft Head + Soft Heap + w)H.Hopper + W)P.Miller ,R.Sinclar,T.Tomkins

*78年にヒュー・ホッパー、エルトン・ディーン、アラン・ゴウェン、デイヴ・シーンとSoft Headとして(4人の頭文字をとってHEAD) 『Rogue Element』*78・05録音
*79年にヒュー・ホッパー、エルトン・ディーン、アラン・ゴウェン、ピップ・パイルとSoft Heapとして(4人の頭文字をとってHEAP) 『Soft Heap』*79年
*80年にアラン・ゴウェン、ヒュー・ホッパーと 『Two Rainbows Daily』*80・06~07録音
*82年にアラン・ゴウェン、フィル・ミラー、リチャード・シンクレア、トレヴァー・トムキンスで 『Before A Word Is Said』*81・04/25~05/02録音
彼の最初期となる録音は、Dawnレーベルからの諸作で知られる英SSWのマイク・クーパー(Mike Cooper)の74年のアルバム『Life And Death In Paradise』(Fresh Air)のラスト・ナンバー「Critical Incidents」でのピアノ演奏だった。マイク・クーパーはジャズ・ミュージシャンをバックに唄うことで知られている。ゴウェンの素晴らしいピアノをここで聞いていただきたい。
★音源資料I Mike Cooper / Critical Incidents (piano・・・Alan Gowen)
1995年にナショナル・ヘルスの『Missing Pieces』(A)、2000年にはギルガメッシュの『Arriving Twice』(B)が、さらに翌2001年にはナショナル・ヘルスの『PlayTime』(C)が未発表音源集としてリリースされ、通して聴くと73年から79年までのゴウェンの各々との関わりが見えて興味深い。
◎画像11 National Health『Missing Pieces』+Gilgamesh『Arriving Twice』+National Health『Playtime』

(A)には、ハットフィールズ解散後のナショナル・ヘルスとの75年の「ダブル・カルテット」のデモも収録されている。キーボードはゴウェンとデイヴ、ギターもミラーとリーの二人のフィルが担当。ドラムスはブラッフォード、ベースがモント・キャンペルと基本的になっているが、時期によってリズム系のメンバーの交替が大きい様子も見えてくる。あとは76年のラジオ・セッションと79年のライヴが収録されている。
(C)に関してはナショナル・ヘルスとして79年8月と12月の録音で、デイヴ・スチュワートに替わってゴウェン一人がキーボードを担当し、バックの面目はそれまでと同じ。本来3枚目のアルバムになるはずの準備と思うと感慨深くなる。結果的にナショナル・ヘルスの最終メンバーにゴウェンが入っていることが確認できた。
(B)に関してはギルガメッシュの73-75年のスタジオ・レコーディング。
どれも、貴重な音源であることは間違いない。地道に発掘作業をしたスタッフに本当に頭が下がる。
今回のアウトロ・・・その他のジャズ・ロックについても
今回は、70年代中盤から後半にかけてハットフィールド&ザ・ノース、ギルガメッシュ、ナショナル・ヘルスが一本の流れのように英ロック・シーンを彩ってきたことを見てきました。改めて3つのバンドを並べて見たときに、浮かんできたのがアラン・ゴウェンの存在でした。長いことリチャード・シンクレアとデイヴ・スチュワートにばかり気がとられていましたが、じつは彼がいたからこそ、ハットフィールズ後の流れが出来上がったことを改めて実感します。ゴウェンは強く自己主張することなく、それでいて全体を見据えていたようなバランス感覚に優れていたことを私は信じています。
彼は白血病で亡くなったのですが、病気がわかって治療をしながら、それこそ命が消える直前までスタジオで演奏活動、レコーディングを続けたことが先ほどリスト・アップした作品の録音日の日付を見るとわかります。
**********************************************
前回、今回とジャズ・ロックをテーマに見てきましたが、この2回で取り上げた以外にも同様の音楽性を持ったバンドを幾つも思い出すことができます。
今回は取り上げなかったのですが、ソフト・マシーンを抜けたワイアットのソロ・アルバム『The End Of An Ear』と復活後の『Rock Bottom』、さらにはマッチング・モール(Matching Mole)の2作品、ゲイリー・ボイル(Gary Boyle)率いるアイソトープ(Isotope)、派生したジェフ・クライン(Jeff Clyne)とブライアン・ミラー(Brian Miller)が新たに組んだターニング・ポイント(Turning Point)、フィル・マンザネラ(Phil Manzanera)のクワイエット・サン(Quiet Sun)、パシフィック・イアドラム(Pacific Eardrum)、ビル・ブラフォードが自身の名を付けたブラフォード(Bruford)、フィル・コリンズを中心としたBrand X、英伊混合バンドのNova等々・・・・そして、ゴング(Gong)も徐々に音楽性を変えていき、ピエール・モエルラン(Pierre Moerlen)が中心になった時期からはずいぶんすっきりとした明快なジャズ・ロックを聴かせるようになりました。
それ以前に、グラハム・ボンド(Graham Bond)やブライアン・オーガー(Brian Auger)といった先達がいたことも、コラシアム(Colosseum)やマーク・アーモンド(Mark-Almond)等の存在も忘れることはできません。もちろん、ここに挙げきれないほどたくさんのアーティストがいます。
さらに、アルバムの中に収録された「曲」としてジャズ・ロックを感じさせるものを考えてみると、とんでもない数になってしまいます。
冷静に考えてみるとジャズ・ロックの最初は米国からの発信でした。60年代後期の若者のフラワー・パワー、サイケデリックの流れがそれまでのジャズ・シーンを揺さぶったのは確かでしょう。
当時のジャズ・ミュージシャンがエレクトリック・サウンドを取り入れたり、ロックのリズムを用いたりすることで新たな可能性を求めたわけです。当時のジャズ・ファンはロックを格下に見ていただけに、そうした世界観には眉をひそめたようですが、徐々に当時の文化状況の変化が世の中のものの見方を変えていったと言えるでしょう。
ジャズそのものはもちろん世界各国で広がっていたわけですが、特にヨーロッパでは独自なジャズ・スタイルが生まれたと言えます。それは米国にあった黒人音楽の影響を直接に受けていなかったということが大きいでしょう。ジャズは黒人文化の中で生まれたものといっていいくらいです。
それゆえに、70年代初頭を中心とした英ジャズは英国ロックを聴いてきた私にはじつに新鮮に映りました。アナログ時代には入手が難しかったものもCD化されたことで、マイク・ウェストブルックやマイク・ギブス、マイク・ギャリック、ヘンリー・ローザー等、数多くの作品に接することが出来て、そのシーンの大きさもわかってきました。いつか、その辺りも明らかにしたいものです。
たまたま手許に『ジャズ批評 2011No.9(通算No.163)』があり、「ジャズ・ロックって何だ?」が特集されていました。ロックの側から眺めるのではなく、ジャズ側から眺めると全く違った見方になるのが驚きであり、また面白くもありました。興味を持たれた方は探してみるといいでしょう。
私たちの本質に近づけて既に出版された参考となる書籍としてBNNからの『ブリティッシュ・ジャズ・ロック』(松井巧 1999)と青土社からの『ヨーロッパ・ジャズ黄金時代』(星野秋男 2009)を挙げておきたいと思います。
また、和久井光司さん監修の『カンタベリー・ロック完全版』も昨年(2022年)に河出書房新社から出されました。手に入れた方も多いと思いますが、これも「よくまとめたな」という労作です。(ただ、そこではアラン・ゴウェンのことがアラン・ガウエンと表記されていて、私にはちょっと違和感があったので、今回は昔ながらの呼び方のゴウェン表記にしました。)
前回のアウトロでも触れましたが、70年代後半から80年代にかけてフュージョンやクロス・オーバーとしてジャズ・ロックが新たな流れを受けた結果、その後は洗練された展開を見せるものが多くなったように思えます。
考えてみると、明確にジャズ・ロックの起点となったのは米国のウェザー・リポート(Weather Report)の登場が大きかったでしょうし、もう一つにはチック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴァー(Return To Forever)のカモメ盤がクロス・オーバーとして圧倒的な存在感で影響力を示したことは言うまでもないですね。どちらの音楽性も間違いなく画期的なことでした。
そんな中で、プログレ系ユーロ・ロックの多くのバンドに関してはかつてのジャズ・ロック路線を踏襲することが多いようです。ひとつには、ジャズやクラシックを学んだ後にプログレに向かったミュージシャンも多いということ、プログレの全盛期が70年代前半ということもあって、当然のようにその頃の複合的な音楽を意識し続けているということになるでしょうか。
人ごとではありませんね。私自身も21世紀になって23年も経っているのに、未だにこうして70年代の音楽にこだわり続けているのですから。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第62回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る① ~ Brain・BASFレーベルから ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」。氏にとってユーロ・ロックへの入り口となったジャーマン・ロックの中から、「ブレイン・ロック・シリーズ」として日本発売された作品群を見てまいります!
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第63回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る② ~ Brainに次いでVirginへ、全開のエレクトロニクス・サウンド ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はジャーマン・ロックをテーマに語る第2回。タンジェリン・ドリーム、クラスス・シュルツェ、マニュエル・ゲッチングという重鎮3アーティストを中心に見てまいります。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第64回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る③ ~ 70年代中期~後期、さらに広がるドイツのシーン テイチクBrainの大量リリース(77年~79年)を中心に ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はジャーマン・ロックをテーマに語る第3回。今回は、70年後期にテイチクより国内リリースされたBRAINレーベルの名盤群を取り上げます。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第65回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る④ ~ ドイツのロック・シーンのまとめ ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はAMON DUUL、CAN、NEKTAR、ANYONE’S DAUGHTERなどが登場、ジャーマン・ロックをテーマに語る第4回目をお届けいたします☆
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第66回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ➀ ~ニュークリアスに始まった私のジャズ・ロック体験~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は、ブリティッシュ・ジャズ・ロックをテーマに語る第1弾をお届け。
氏にとって最初のジャズ・ロック体験となったニュークリアスを中心に、ソフト・マシーンなどにもフォーカスしてまいります!
「Column The Reflection」バックナンバーはこちらからチェック!
HATFIELD & THE NORTHの在庫
-
HATFIELD & THE NORTH / HATTITUDE
ネット限定のアーカイヴ音源集、ライヴ&デモの全21曲を収録
「HATWISE CHOICE」に続く第二弾。内訳は、デモ音源1曲(「Big Jobs」)、73年〜74年のBBC音源7曲、73年〜75年のライヴ音源13曲。とにかく音質の素晴らしさにびっくり。特にBBC音源は、スタジオ盤以上と言っても過言ではありません。HATFIELDファンは必携!
-
HATCOCD737502(HATFIELD AND THE NORTH)
デジパック仕様
盤質:傷あり
状態:良好
ケース不良、トレーにヒビあり、軽微なスレ・若干角潰れあり
-
-
HATFIELD & THE NORTH / ROTTERS’ CLUB
Richard Sinclair/Dave Stewart/Phil Miller/Pip Pyleという鉄壁の布陣で録音された75年2nd、カンタベリー・ロックの最高峰に位置づけられる大傑作!
元CARAVANのRichard SinclairとSteve Miller、元MATCHING MOLEのPhil Miller、後にNATIONAL HEALTHで活躍するPip Pyleにより結成され、Steve Millerが脱退、KHANを経たDave Stewartが参加したカンタベリー・ジャズ・ロックバンドの代表格の75年2nd。カンタベリー・ジャズ・ロックの代表作である本作は、20分の大作「Mumps」を含め、 前作より全体的に整理、洗練された世界観をすっきりと聴かせる作風となっており、クロスオーバー・ジャズ・ロック色を強めた音楽性へと変化しながらも、彼ららしいポピュラリティーを持ったサウンドと、胸を打つメロディーが素晴らしい傑作です。
-
HENRY COWの在庫
-
-
HENRY COW / LEGEND(LEG END)
アヴァン/チェンバー・ロックの代表格、73年発表1st、緻密にして芳醇、問答無用の傑作!
FRED FRITH(G)、TIM HODGKINSON(Key)、JOHN GREAVES(B)、CHRIS CUTLER(Ds)、GEOFF LEIGH(Sax&Flt)の5人組。73年作の1st。ジャズ、現代音楽をベースにロック的なダイナミズムと英国的叙情がミックスされたサウンドはデビュー作とは思えない驚異の完成度。「Nirvana For Mice」での緻密かつ暴力的なアンサンブルは唯一無比。カンタベリー・ミュージックを代表する傑作。
-
HENRY COW / IN PRAISE OF LEARNING : ORIGINAL MIX
チェンバー/レコメンの始祖的グループ、75年作
SLAPP HAPPYのメンバー(DAGMAR KRAUSE、PETER BLEGVAD、ANTHONY MOORE)が加わり制作された3rd。75年作。狂気的なダグマーのヴォーカルに煽られるように、各楽器の攻撃性が増幅。よりフリーキーに、よりアヴァンギャルドに、圧巻のアンサンブルを聴かせる名作。
-
ORIGINAL MIX、直輸入盤(帯・解説付仕様)、定価2600+税
盤質:傷あり
状態:並
帯有
軽微なカビあり、その他は状態良好です
-
-
GILGAMESHの在庫
-
GILGAMESH / GILGAMESH
緻密かつメロウなアンサンブルが光るカンタベリー・ジャズ・ロックの名作、75年作
後にHATFIELD AND THE NORTHのメンバーと共にNATIONAL HEALTHを結成することになるカンタベリー・ジャズ・ロックグループの75年作。その内容はAlan Gowenのジャズ・フレーバーを散りばめたキーボードを中心にしたアンサンブルで聴かせる作風であり、テクニカルなインタープレイやユーモラスな質感が素晴らしい名盤です。NATIONAL HEALTHにも参加するAmanda Personsのスキャットはよりジャジーな色合いを楽曲に与え、Phil Leeのギターはへヴィーさと甘くマイルドなサウンドを行き来し、NUCLEUSのベーシストでもあったJeff Clyneと技巧的なMike Travisのリズム・セクションはスリリングなアプローチで迫ります。HATFIELD AND THE NORTH諸作と並んで名作と言えるでしょう。
NATIONAL HEALTHの在庫
-
NATIONAL HEALTH / NATIONAL HEALTH
カンタベリー・シーンの重要グループHATFIELD AND THE NORTHとGILGAMESHの中心メンバーが結成したジャズ・ロックバンド、78年作1st
カンタベリー・シーンの重要グループであるHATFIELD AND THE NORTHとGILGAMESHの中心メンバーが結成したジャズ・ロックバンドの78年作。Dave Stewart、Phil Miller、Neil Murray、Pip Pyleというキャリアのあるメンバーに加えてGILGAMESHのAlan Gowen、CARAVANやSOFT MACHINEとつながるJimmy Hastings、そしてGILGAMESHにも参加しているAmanda Parsonsなどゲスト人も強力。その内容はDave Stewartの存在感を感じさせる、HATFIELD AND THE NORTHの音楽性をよりジャジーにしたような作風であり、4曲の大作から成るカンタベリー・ジャズ・ロックの集大成といえる圧巻の傑作です。
-
NATIONAL HEALTH / OF QUEUES AND CURES
HF&Nから発展したグループ、78年2nd、メロディアスにして芳醇なアンサンブルが素晴らしすぎる、カンタベリー・ジャズ・ロックの大名盤!
Alan GowenとNeil Murrayが脱退し、元HENRY COWの奇才John Greaves(b)が参加した78年作2nd。Dave Stewart、Phil Miller、Pip Pyleとの4人編成になってまとまりが増したせいか、アンサンブルの強度はグッと増した印象。めまぐるしく切り替わるダイナミックな展開の中、一糸乱れぬ正確さで一気に駆け抜け、聴き手を置き去りにします。呆気にとられるほどのスピードとエネルギー。圧倒的なテンション!ジャズ・ロックのファンもアヴァン・ロックのファンも、またまたクリムゾンのファンも、知的でエネルギッシュなサウンドを好む方は大必聴の傑作。
-
NATIONAL HEALTH / MISSING PIECES
ビル・ブルフォード在籍時の貴重な音源も収録された好編集盤
ビル・ブラッフォード在籍時の貴重な音源など、驚きの音源が沢山つまった好編集盤。
MIKE COOPERの在庫
-
MIKE COOPER / PAPER AND SMOKE
「イギリスのライ・クーダー」とも称されるフォーク/ブルースSSW、00年ベスト
マイク・クーパーは、60年代終わりから70年代にかけて活躍したブリティッシュ・シンガーソングライター。ニュークリアスのメンバーとの交流など、ジャズ・セッション面の参加も多く、独特のアシッド感あるサウンドはかなり個性的。本作は、PYE/DAWN時代の佳作群から選曲された2枚組全30曲の豪華ベスト。
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!