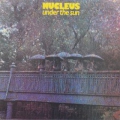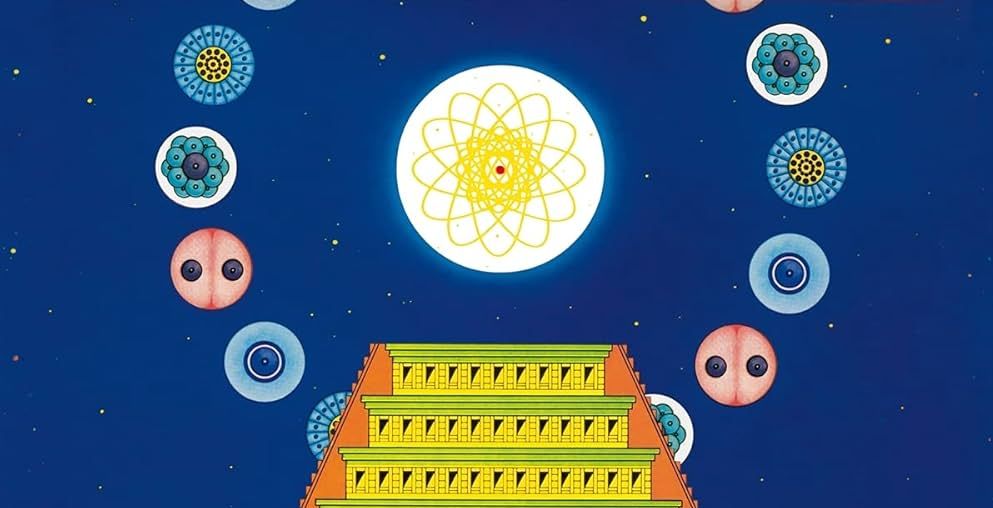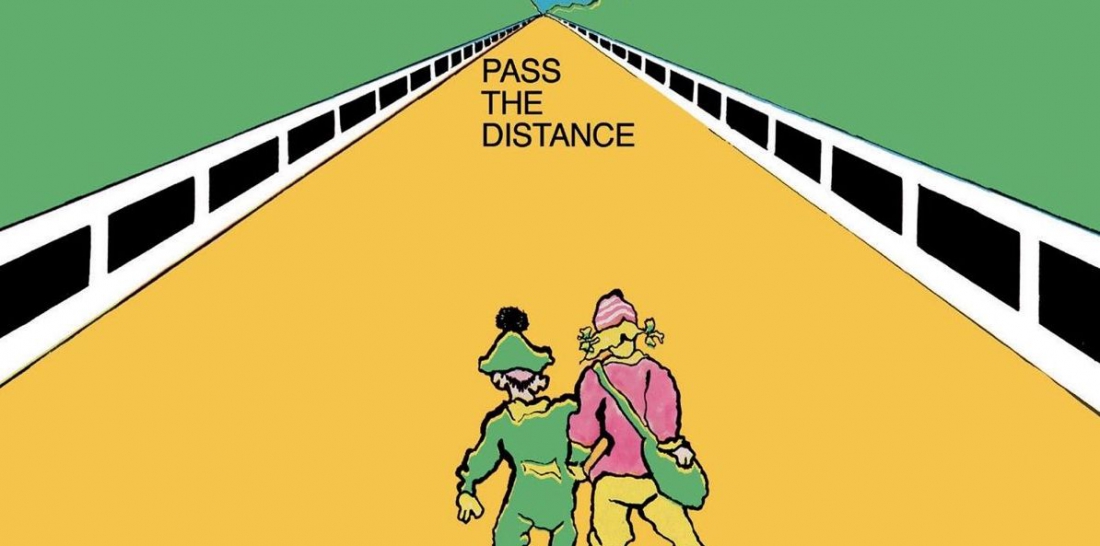COLUMN THE REFLECTION 第66回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ➀ ~ニュークリアスに始まった私のジャズ・ロック体験~ 文・後藤秀樹
2023年10月31日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム
タグ:

第66回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ➀
~ニュークリアスに始まった私のジャズ・ロック体験~
「音楽ジャンルというのは便利なのだが、時に邪魔するものになってはいないか?」ということは昔から今に至るまでずっと思っていることだ。
ポップスを聴いていた頃も、フォーク・ロックという言葉が出てきて何となくカッコよく魅力的に思えたのだが、「フォークっぽいロック」は単にアコースティック・ギターを使った曲で、アーティストとしてひとまとめにくくる言葉ではなく、単に曲の雰囲気を表す意味合いで使われていた。
ビートルズはあらゆるタイプの曲が次々とヒットし、彼らのことをロック・バンドと呼んでいいのかどうか真剣に悩んだこともあった。
時代が60年代後半からそれまでのポップ・ミュージックがシングル中心からアルバム単位の作品となり、ビートルズの『サージェント・ペッパーズ・・』以降のアルバムには、それまで以上にあらゆるタイプの音楽が収録されたことは驚異的なことだった。
中学時代のある日、友人の家に行ってご両親の壮大なクラシック・レコードのコレクションに驚かされたことがあった。そんな中にビートルズもあって、思わず「ロックもあるんだ !」と言うと、彼のお父さんに「これはロックではなく、ビートルズだよ。」と言われ、驚いた。後にビートルズの偉大さを表す表現として音楽雑誌で同じような発言を聞いたことがあるが、それもまたひとつ大きな意味のある言葉だったと思う。
プログレに出会ったときは「ジャンルを超えた音楽」と呼ばれ、その言葉は魅力的に映った。
ハード・ロックにしても、以前本コラムで取り上げたGFRもマウンテンも一筋縄ではいかないあらゆる音楽性を持っていることは今では誰もが認めるところだ。
ロックやフォーク、ジャズ、クラシックというと頭に浮かんでくるイメージは誰もが同じだと思われるが、今回取り上げるジャズ・ロックなんていうと仲間内には伝わるものの、今でも普通の人々にとっては「何のこっちゃ」となってしまうのだろう。
§1 ジャズ・ロックが意識され始めた頃 その萌芽
その昔、AMラジオで「VAN・ホリディ・イン・ロック」というロック番組があった。そのテーマ曲がじつにカッコよかった。
その頃はJUNとVANが流行の2大服飾メーカーがよく知られていた。JUNはユーロ・ファッション系、VANの方はアイヴィー・ファッションのアメリカン・トラディショナルという今も昔も私には関係ない世界なのだが、特にJUNのTV-CMが印象的で素晴らしくBGMにフォーカスの「Love Remembered」やEL&Pの「The Sage(賢人)」が使われていて、いつもそのCMを楽しみにしていたものだ。
そんな70年代初期のVANがラジオでロック番組の提供をしていたわけだ。しかし、そのカッコいいテーマ曲がニュークリアス(Nucleus)の「Song For A Bearded Lady」であるとわかったのは、ややしばらくたった頃になる。
★音源資料A Nucleus / Song For A Bearded Lady
ニュークリアスは今では伝説的なバンドとしてよく知られているが、当時の中坊にとっては初めて聞く刺激的な1曲だった。イントロのトランペットとサックスのユニゾンが周囲の空気を変えてしまうほどだった。当時からジャズ・ロックという言い方はされていたが、シカゴとBS&Tは聞いていたものの、本格的にジャズっぽい演奏を聞くのはこれが初めてで、まさに虜になってしまった。
収録アルバムは彼らの71年発表の2作目『We’ll Talk About It Later』(Vertigo)。メンバーはイアン・カー(Ian Carr)、ブライアン・スミス(Brian Smith)、カール・ジェンキンス(Karl Jenkins)、ジェフ・クライン(Jeff Clyne)、ジョン・マーシャル(John Marshall)、クリス・スペディング(Chris Spedding)の6人。その当時知っているのはギターのクリス・スペディングのみ、そのルックスのよさからかミュージック・ライフの表紙も飾っていた。中心となるイアン・カーは62年にEmcee5の一員として弟のピアニスト、マイクと共に2枚のシングルを出すことでレコード・デヴューを果たし、その後マイケル・ギャリックや、ドン・レンデルとの共演盤を発表、そしてニュー・ジャズ・オーケストラに加わりながら自分がリーダーとなってニュークリアスが誕生することになる。
◎画像1 Nucleus / We’ll Talk About It Later + Solar Plexus

幸運なことに、このアルバムはすぐに安価で国内盤(SFX-7349)を手に入れることが出来たのだが、70年のデヴュー作『Elastic Rock』(Vertigo)はなかなか見つからなかった。
しかし、不思議な縁があってイアン・カー・ウィズ・ニュークリアス名義の3作目『Solar Plexus』(Vertigo)の国内盤(SFX-7402)はその後すぐに見つかった。そちらもまた素晴らしい作品で最近でもよく聞く作品なのだが、入手以降国内盤は見かけたことがない。幸運だった。ここではその3作目から「Torso」を聞いていただく。幾分ラテン・ジャズともアフロ・ジャズとも言えるようなメロディアスな曲調とパーカッションがじつに心地よい。
★音源資料B Ian Carr With Nucleus / Torso
この作品では、上記ニュークリアスのメンバーに5人のゲストが加わっている。個人的には、その後参加作品を探すほどお気に入りミュージシャンになったハリー・ベケット(カーと同様にトランペッターなのだが)の参加が嬉しい。
これらを聞いた時に、確かにジャズ・トランペッターとしてそれ以前にもジャズ・アルバムを何枚も残しているイアン・カーなのだが、このニュークリアスが「ジャズ・ロック」と呼ばれ、その言葉が今も生き続けている理由のひとつには英Vertigoからのリリースだったことが挙げられるだろう。素晴らしいジャケットにも彩られた70年代初期の英国・マイナーレーベルの人気は50年以上経った今でも色褪せることなく今も魅力的な存在であり聞き続けられていることがその理由だ。さらに彼らの作品のほとんどがCDとして現在も聞き継がれていることは本当にありがたい。
◎画像2 その他のNucleus初期作品

ニュークリアスとしてはVertigoに9枚のアルバム(1枚は編集盤)を残している。特に人気が高いのはKeefのジャケット・デザインに包まれた74年の『Under The Sun』なのだが、彼らのアルバムは先に挙げた『Solar Plexus』以降、日本ではLPとして発売されなかった。
◎画像3 Bob Downes Open Music

同じVertigoから出されていたジャズ系の名盤ボブ・ダウンズ・オープン・ミュージック(Bob Downes Open Music)の70年の『Electric City』も忘れがたい。フルート奏者で、各種管楽器も演奏するボブ・ダウンズも当時のジャズ・ロック・シーンの重鎮の一人。このアルバムには、イアン・カー、ハリー・ベケット、クリス・スペディングらのニュークリアス関連メンバーをはじめ、ジャズ・シーンからケニー・ホィーラー、ハリー・ミラーら、そしてロック・シーンからはレイ・ラッセル、ハービー・フラワーズらが参加していることも興味深い。最初に聞いた時、ヴォーカルが入っていることからどうも普通にロックのように思えたのだが、演奏を聴くとやはりジャズを感じさせる部分が多く、またオープン・ミュージック名義としては唯一の作品でもあることから、時代の雰囲気の中で生まれたジャズ・ロックととらえられる。
★音源資料C Bob Downes Open Music / Dawn Until Dawn
こちらも日本盤が発売されていたが、Philips盤になっていたことが不思議に思えた。というよりも、当時の日本フィリップスからのリリースは海外アーティストが総じてPhilips扱いになっていた例が多く、逆にニュークリアスのVertigo盤の方が特別だったと言えるかも知れない。
(2000年代に入り、オープン・ミュージックの未発表だった当時の録音が発表されている。)
◎画像4 Rock Workshopの2作品

同様のタイプとしてロック・ワークショップ(Rock Workshop)の2枚の作品も思い出す。こちらもレイ・ラッセルを中心にした大編成ユニットになっているが、ボブ・ダウンズをはじめとしてオープン・ミュージックとメンバーがかなり重複している。アルバムは『Rock Workshop』(70年)、『最後の時(Very Last Time)』(71年)の2枚、ともにCBSからのリリース。日本でも発売されていた。
ジャズ・ロックとして認知され始めたこの時期は、ジャズ側からロックへのアプローチが感じられるもの、逆にロック側からジャズに接近したものがある。よく聞くと、その両者が混在していて作品によって味わいが違っていることを聞き分けてみるのも面白い。このロック・ワークショップはそのバンド名からもわかるが、ロックからジャズへのアプローチといった趣を感じる。
そのひとつの要素として、ブルースにルーツを持つアレックス・ハーヴェイ(Alex Harvey)がヴォーカルとして参加していることがバックの演奏以上に強烈な印象を与えているかも知れない。なお、彼はファーストのみの参加で、その後センセイショナル・アレックス・ハーヴェイ・バンド(SAHB)を結成する。もう一人のヴォーカリストだったAlan Greed(元Harsh Reality)がセカンド・アルバムでも続けて参加している。
★音源資料D Rock Workshop / Wade In The Water
改めて考えてみると、クリムゾンの『ポセイドンのめざめ』のキース・ティペット(Keith Tippet)をはじめとして、『リザード』『アイランズ』のアルバム・クレジットにジャズ畑の面々を見つけたことが、ロックの中にジャズを意識することになったと言えるかも知れない。
特にベーシストのハリー・ミラー(Harry Miller)、コルネットのマーク・チャリッグ(Marc Charig)、トロンボーンのニック・エヴァンス(Nick Evans)は、英国ジャズ界では有名で多数のアルバムでその名を見ることになるし、キース・ティペット(Keith Tippet)はそんな中でも特別な存在であることに気づいていくことになる。
◎画像5 Centipede / Septober Energy

英Neonからセンティピード(Centipede)が発表した2枚組『Septober Energy』は71年の作品だが、そうした英国ジャズのひとつの集大成とも言える大作だろう。キース・ティペットが中心となった50人を超える壮大な作品。ジャズ、ロック、さらにはオーケストラも導入された現代クラシック的な要素を持っている。ティペットの前衛的な感性にはついて行けないところもあるのだが、随所に「おっ!」と思う部分もあって、やはりその凄さは圧倒的だ。
§2 ジャズ・ロックにつながる英国ジャズの深みに魅せられ始めた頃のこと (1)
キング・クリムゾンやイエスを聞いていた私が、ジャズ・ロックを意識したのは、先に書いたようにニュークリアスが最初なのだが、その直後に聞いて強烈な印象を受けたいくつかの作品がある。
◎画像6 私の「ジャズ・ロック」体験の入口になった名盤群

それは、ジョン・サーマン(John Surman)を中心としたユニットの71年の『Where Fortune Smiles』(Dawn)、そしてジョン・マクローリン(John McLaughlin)の69年の『Extrapolation』(Marmalade)さらに、ジャック・ブルース(Jack Bruce)の70年の『Things We Like』(Polydor)。サーマンを中心とした「The Trio」(Dawn)の2枚組、
どれもジャズ・ロックというよりは、完全に英国ジャズなのだが、私の耳にはじつに刺激的に届いた。
そして、ブルースの作品にはコラシアム(Colosseum)のディック・へクストール-スミスとジョン・ハイズマンも加わっている。クリームにいたブルースが、これほどまでに本格的なジャズ・アルバムを創ったことは凄い驚きだった。ブルースの初期3枚のアルバムは、それぞれに素晴らしい作品だと思う。
マクローリンが本格的に立ち上げたマハヴィジュヌ・オーケストラの最初のアルバムで73年の『火の鳥(Birds Of Fire)』(Columbia)もすごかった。これは国内盤が発売されてすぐに買った思い出深い作品。とにかく圧倒的で、ジャケットの美しさと内容の荒々しさとのアンバランスな魅力に溢れていた。彼の端正な姿からは考えられないくらいの激しい演奏、そしてフロック(The Flock)のジェリー・グッドマン(Jerry Goodman)のバイオリンとドリームス(Dreams)にいたビリー・コブハム(Billy Cobham)のドラミングにも圧倒された。これはまさに「ジャズ・ロック」であると納得させられたものだ。
★音源資料E Mahavishunu Orchestra / Birds Of Fire
§3 ソフトマシーンに興味尽きなくなってしまった頃のこと
ソフト・マシーン(Soft Machine)についても本当は丁寧に語らなければならないのだが、それもまたなかなか難しい。メンバー・チェンジと音楽性の変化がめまぐるしいが、カンタベリーの砦を築き上げることになるワイルド・フラワーズ(Wild Flowers)を母体に、脈々とカンタベリー一派として枝葉を広げていくその中心にソフト・マシーンが位置しているということが一番重要なことだろう。
◎画像7 Soft Machine ➀②

凝ったジャケットの68年の最初のアルバムは、ケヴィン・エアーズ(Kevin Ayers)、ロバート・ワイアット(Robert Wyatt)、マイク・ラトリッジ(Mike Ratridge)の3人のクレジットだが、ソフト・マシーンの結成は66年で、その時にはデヴィッド・アレン(David Allen)が在籍していた。
67年にジョルジオ・ゴメルスキーのプロデュースの下でレコーディングしたのだが、お蔵入りとなり、その後ツアーで出かけたフランスでアレンはビザの関係で帰って来られなくなり、結局はバンドを抜けてしまうことになる。(アレンを含んだ67年のアルバムは72年に仏BYGから貴重音源シリーズ『Faces And Places』のVol.7としてリリースされ、何度もタイトルを変えながら発売され続けている。もちろん公式のファーストとは別物だ。)
その後アンディ・サマーズ(Andy Summers)に交替するのだが68年の7月に脱退し、結局残った3人でアルバムを制作することになり12月に米Probeからサイケ色も強い『Soft Machine』として発表する。
その後、ケヴィンが抜け、新たにヒュー・ホッパー(Hugh Hopper)が加わり69年4月に前作同様米Probeから『Soft Machine Two』が発売される。一気にジャズ・ロック色が強くなった感じだ。
★音源資料F Soft Machine / 10-30 Returns To The Bedroom
その後のツアーにはリン・ドブソン(Lyn Dobson)、ニック・エヴァンス、マーク・チャリッグ、エルトン・ディーン(Elton Dean)が参加していて、70年6月のアルバム『Third』のクレジットにもその名があるのだが、アルバム・ジャケット内側のメンバー写真でも分かるとおり参加ミュージシャン中、サックスのディーンのみが4番目のメンバーとして正式に加わった。(最初の日本盤は、そのメンバー写真が表ジャケとなり、何か収まりの悪い雰囲気になっていた。)
◎画像8 Soft Machine ③④⑤⑥

71年2月に『Fourth』、72年6月に『5』とサポート・メンバーを変えながらよりジャズに近い演奏を聞かせていくことになる。
その後ワイアットが『Fourth』を最後に脱退。彼はソフト・マシーンと並行してソロ・アルバム『The End Of An Ear』を70年に出していたが、今度は新たなバンド、マッチング・モウル(Matching Mole)を結成する。
次のドラマーはフィル・ハワード(Phil Howard)だったのだが、レコーディング途中でジョン・マーシャルに交替してしまう。結果的に『5』はA面がハワード、B面がマーシャルという2人のドラマーが変則的に参加するという不思議なアルバムに仕上がっている。
日本盤では、『5』が出された時に「ソフト・マシーンとその仲間達」という紹介で、『マッチング・モウル』(’72)と『エルトン・ディーン』(‘71)のアルバムにも共通ライナーが添付されていた。当時は情報が少ない時代だったので大変素晴らしい企画だったと今でも思っている。
しかし、当時CBSソニーの新品レコードはシュリンクで覆われていて、中を見ることも試聴することも出来なかった。というわけで、多くのリスナーは『5』を買って、あとの2枚は共通ライナーを見ながら思いを馳せることになるのではないだろうかと予測した。私は中古盤が出るまで待った!!!
『Six』は73年2月の発売だが、『Third』に続いて2枚組で1枚はライヴ盤だった。エルトン・ディーンの名前が消えていたが、驚きはカール・ジェンキンス(Karl Jenkins)が加わっていたこと。マーシャルとジェンキンスは冒頭に書いたように共にニュークリアスのメンバーだったわけだから、変幻自在の英ジャズ・ロック・シーンが展開されているという思いを強くした。
◎画像9 Soft Machine ⑦

前作から間もなく同じ73年『Seven』ではまた、音楽の方向性が少し変わって、よりエレクトリックの要素が強くなったように感じた。ここではヒュー・ホッパーに替わって、同じカンタベリー・シーンのキャロル・グライムス・アンド・デリヴァリー(Carol Grimes And Delivery)からロイ・バビントン(Roy Babbington)が加わっている。ホッパーに負けず音圧の強烈なベースという印象だ。この『Seven』は洗練されたエレクトリック・ジャズ・ロックを堪能できるだけに、非常に重要な作品と言える。
★音源資料G Soft Machine / Nettle Bed
その後、英CBSから英Harvestに移籍し8作目の『Bundles』(75年)を発表する。
a)最初に驚いたのはそのジャケット。まるで絵本の一コマのように牧歌的な雰囲気まで漂う優しいイラスト。それまでの彼らのクールで、時にバンド名通り機械的な雰囲気との違いを感じ取った。
◎画像10 Soft Machine ⑧

b)次に驚いたのはソフト・マシーンに専任のギタリストが参加したこと。それもあのアラン・ホールズワース(Allan Holdsworth)だっただけに期待は高まった。何といっても英ロック・ファンにとっては69年のイギンボトム(Igginbottom)の唯一作やテンペスト(Tempest)のファーストでのギター・プレイが忘れられない存在だ。
ホールズワースの参加もあってソフト・マシーンも新たなファンを獲得し、それまで以上に安定した人気を保った印象があった。もちろん、U.KやBrufordでの活躍以来、あと追いでこのアルバムにたどり着いたファンもたくさんいたことは当然のことだったように思う。
c)しかし、さらに驚いたのはその収録された曲。それこそひっくり返りそうになったのが1曲目の「Hazard Profile」と題された組曲の最初のパート。
何と、今回のコラムの冒頭で取り上げたあのニュークリアスの「Song For A Bearded Lady」のテーマリフが再現されていたのだ。これは嬉しかったが、それ以上にアルバム全体でやはり弾きまくるホールズワースのギターが凄い。まさにこれこそ私が理想とするジャズ・ロックのひとつの典型だった。
★音源資料H Soft Machine / Hazzard Profile
翌76年には9作目の『Softs』が出たのだが、今度のギターはジョン・エサリッジ(John Etheridge)のに替わっていた。ホールズワースが抜けたのは残念だが、彼はひとつのグループにとどまらないだろうという予感も頭のどこかにあった。
◎画像11 Soft Machine⑨⑩⑪

エサリッジも技巧派の素晴らしいギタリストで、73年からダリル・ウェイズ・ウルフ(Darryl Way’s Wolf)のメンバーだった。その3枚のアルバムでこれまた印象的なフレーズを次々と聴かせてくれていただけにまた期待感が膨らんだ。このアルバムでは期待通りの演奏とともに、ラスト曲で聞かせたアコースティック・ギターのソロも見事だった。
78年には『Alive And Well~Recorded In Paris』をリリースするのだが、そこにはマイク・ラトリッジの名前が見られなくなった。前作でもゲスト的な扱いになり、最後のオリジナル・メンバーが消えてしまったことになる。一抹の寂しさを感じたが、ソフト・マシーンの音楽は新しい姿で70年代後半に息づいていたという印象があった。
やや間が開いてリリースされた『Land Of Cockayne』(81年)は、カール・ジェンキンスが主導した作品。極めて良質な作品であるという認識は持っているものの、これはソフト・マシーン名義としては異質な部類に入るだろう。ジャック・ブルースや(何と)ホールズワースも参加、そして英国ジャズ・ミュージシャンも多く加わっているが、個人的にはアラン・パーソンズ・プロジェクトに近いものを思い浮かべてしまった。
ジェンキンスは、ニュークリアス時代にリンダ・ホイルの71年にソロ作『Pieces Of Me』(Vertigo)で素晴らしいアレンジと演奏を担当したことが印象に強く残っている。そうした彼の広汎な音楽的素養は見事だと思うし、リスペクトに値する。
ソフト・マシーンの歴史はこうした形で81年に終わるのだが、CDの時代に突入して過去の未発表ライヴを中心にかなりの数がリリースされている。同じ音源でもタイトル違いが多く、かなり複雑な状況だ。一度整理したいと思いながら、出来ないままでいる。
そんな中で2004年にはSoft Machine Legacyとして元のメンバー(エサリッジ、エルトン・ディーン、ヒュー・ホッパー、ジョン・マーシャル)で活動し、さらに2015年にはエサリッジが中心となって新たなメンバーを加えソフト・マシーンの名で再活動を続け、驚くべき生命力を持ったバンドとなっている。
「ジャズ・ロック」をキーワードに70年代のソフト・マシーンを聞き直してみるのも悪くないと思う。
今回のアウトロ
考えてみると、70年代中期頃から「ジャズ・ロック」に変わった形で、「クロス・オーバー」とか「フュージョン」とかいう言葉と新たな音楽が現れ、それまでの「ジャズ・ロック」が一緒に考えられてしまった時期もあって「ちょっと違うんだよな」と思っていたものでした。
単に言葉の問題じゃないか。と言われそうにも思えますが、様々な音楽ジャンルが生まれてきた中で、自分が大切にしておきたい音楽について、言葉を使って語りたいと思った者にとっては、そうした時代の流れを結構真正面からとらえていました。
多くの人にとってはどうでもいいことなのかもしれませんが、最近になって改めて考えるようになっています。
カケレコさんでは「ジャズ・ロック」という言葉がかなり使われていて、そこに入る音楽をたくさん紹介してくれているので、ありがたいなと思っています。勝手に連帯感というか仲間意識を感じます。
今回の原稿も骨が折れました。「ジャズ・ロック」の意味するものを再確認したいと考えて、いくつか項を立てたのですが、ハットフィールド・アンド・ザ・ノースとその周辺部まで行こうと思ったのにたどり着かず、次回に回します。何だか、最近こうした言い訳が多くなって申し訳ありません。では、また次回。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第61回 ~スーパートランプの名盤『Crime Of The Century』 ・・・そして『Breakfast In America』という現象に続く彼らの軌跡~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」。今回は70年代におけるスーパートランプの軌跡を辿ります!
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第62回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る① ~ Brain・BASFレーベルから ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」。氏にとってユーロ・ロックへの入り口となったジャーマン・ロックの中から、「ブレイン・ロック・シリーズ」として日本発売された作品群を見てまいります!
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第63回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る② ~ Brainに次いでVirginへ、全開のエレクトロニクス・サウンド ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はジャーマン・ロックをテーマに語る第2回。タンジェリン・ドリーム、クラスス・シュルツェ、マニュエル・ゲッチングという重鎮3アーティストを中心に見てまいります。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第64回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る③ ~ 70年代中期~後期、さらに広がるドイツのシーン テイチクBrainの大量リリース(77年~79年)を中心に ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はジャーマン・ロックをテーマに語る第3回。今回は、70年後期にテイチクより国内リリースされたBRAINレーベルの名盤群を取り上げます。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第65回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る④ ~ ドイツのロック・シーンのまとめ ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はAMON DUUL、CAN、NEKTAR、ANYONE’S DAUGHTERなどが登場、ジャーマン・ロックをテーマに語る第4回目をお届けいたします☆
「Column The Reflection」バックナンバーはこちらからチェック!
NUCLEUS(IAN CARR NUCLEUS)の在庫
-
NUCLEUS(IAN CARR NUCLEUS) / TORRID ZONE THE VERTIGO RECORDINGS 1970-1975
Ian Carr率いるブリティッシュ・ジャズ・ロックの名グループ、70年〜75年のVertigo在籍期9作品をまとめた6枚組ボックス
Ian Carrを中心とするブリティッシュ・ジャズ・ロックの代表的バンドNUCLEUS。彼らがVertigoよりリリースした71年作『ELASTIC ROCK』から75年作『ALLEY CAT』に至る8スタジオ作品(IAN CARR WITH NUCLEUS名義を含む)にIan Carrの72年ソロ作『BELLADONNA』を加えた9作品を収録。英国ジャズ・ロック・シーンに多大な影響を及ぼした彼らの軌跡を知るにはうってつけの一枚です。
-
6枚組ボックス、各CDはペーパーケース・ブックレット付仕様、19年デジタル・リマスター
盤質:傷あり
状態:良好
軽微なスレあり、軽微な汚れあり
-
NUCLEUS(IAN CARR NUCLEUS) / PRETTY REDHEAD
Ian Carr率いる英ジャズ・ロックの名グループ、71年のBBC音源と82年のBBC音源を収録したライヴ
Ian Carr率いる英ジャズ・ロック・グループ。Chris Spedding、Karl Jenkins、John Marshall等を擁する71年のBBC音源と82年のBBC音源を収録。しなやかさとシャープネス、叙情性と攻撃性。有機的に音が絡み合い、ぶつかりあう、ハイ・テンションの名演。これは素晴らしいです!初期NUCLEUSの魅力が真空パックされた名ライヴ!
-
NUCLEUS(IAN CARR NUCLEUS) / ROOTS
SOFT MACHINEと並び英国ジャズ・ロックを代表するバンド、ジャズ・ロックとして完成形を見た73年作6th
SOFT MACHINEと並び英国ジャズ・ロックを代表するバンド、73年作6th。従来のエレクトリック・マイルスを彷彿させるフリー・ジャズのエッセンスと、ギターとリズム隊を主役にロックのダイナミズムをより押し出したパワフルなアンサンブルが絶妙に調和したスタイルは、これぞジャズ・ロックと呼ぶべきもの。インプロビゼーションが炸裂するパートでもどこか陰りがあり、柔らかく優美なフレーズが光ります。女性シンガーJoy Yatesが妖艶に歌う2曲目「Images」の洗練されつつもどこかエキゾチックなサウンドも聴き所です。次作以降ジャズ・ファンク路線を邁進していく彼らの、ジャズ・ロック・バンドとしての完成形を提示した一枚と言えるのではないでしょうか。名作。
-
NUCLEUS(IAN CARR NUCLEUS) / ALLEY CAT
VERTIGOレーベルからの最終作となった75年9th、ジャズ・ファンク/フュージョン路線をさらに推し進めた逸品
SOFT MACHINEと並び英国ジャズ・ロックを代表するバンド、VERTIGOレーベルからの最終作となった75年6th。前2作『Under The Sun』『Snakehips Etcetera』からのファンク色を伴ったままクロスオーヴァー/フュージョンへと辿り着いた作品。どっしりと構えたドラム&地を這うようなベースに、艶やかなエレピ&Ian Carrのふくよかなサックスが絡み合うタイトル曲は必聴のナンバー。ハービー・ハンコックの『HEAD HUNTERS』から70年後期あたりまでのサウンドが好きな方にも推薦できるジャズ・ファンク/フュージョン秀作です。
-
-
NUCLEUS(IAN CARR NUCLEUS) / ELASTIC ROCK and WE’LL TALK ABOUT IT LATER
カール・ジェンキンス在籍、ソフツに並ぶ英ジャズ・ロックの実力派グループ、70年1st/71年2nd
イアン・カー、クリス・スペディング、カール・ジェンキンス等によって結成されたブリティッシュ・ジャズ・ロックを代表するバンド。70年作1stと71年作2ndをカップリングした2枚組。いかにも英国的な翳りに包まれた英ジャズ・ロックの名作。
-
NUCLEUS(IAN CARR NUCLEUS) / SNAKEHIPS ETCETERA
ソフト・マシーンと共に英国ジャズ・ロックを代表する名グループの75年作8th、前作に引き続きホーン・セクションを大々的にフィーチャーしたファンク・テイスト溢れるジャズ・ロック作!
60年代初頭より英ジャズ・シーンで活躍した重鎮トランぺッターIan Carrが率いた英国ジャズ・ロックの最高峰バンド、75年作8th。前作『UNDER THE SUN』で切り開いたジャズ・ファンク/ブラス・ロック路線をさらに推し進め、ファンキーに跳ねる軽快なアンサンブルの上を、ブラス・セクションが饒舌に鳴り響くサウンドはかなりのカッコ良さ。一聴ではアメリカのバンドだと言われても不思議に思わないグイグイと突き進むスタイルですが、熱気ある掛け合いが収まった瞬間、不意に見せる陰影ある表情はやはり英国のグループならではと言えます。名品です。
-
NUCLEUS(IAN CARR NUCLEUS) / UNDER THE SUN
英国ジャズ・ロックの最高峰グループ、彼ら流のジャズ・ファンクを追求した74年の意欲作!
60年代初頭より英ジャズ・シーンで活躍した重鎮トランぺッターIan Carrが率いた英国ジャズ・ロックの最高峰バンド、新たなメンバーとして後にAllan Holdsworthとの活動でも名を馳せるベテランkey奏者Gordon Beckを迎えた74年作7th。Carrのトランペットをリードに据えた彼ららしい知的でクールなアンサンブルを軸としつつも、ジャズ・ファンク的な跳ね感やブラス・ロック的な疾走感を随所に取り入れたサウンドが本作の魅力です。ドコドコとロック的ダイナミックが前に出た手数多いリズムに、饒舌なトランペットが乗り、エレピが流麗に舞い、鈍く光沢を放ついぶし銀ホーンが熱を加えます。とは言え痛快にぶっ飛ばす感じではなく、適度に抑制を効かせながらスリリングな緩急をつけるプレイがいかにもNUCLEUSでカッコいいです。もちろんフルートやクラリネットがデリケートに旋律を紡ぐブリティッシュな哀愁たっぷりの叙情ナンバーも素晴らしい。彼ら流ジャズ・ファンクを追求した意欲作!
BOB DOWNES OPEN MUSICの在庫
MAHAVISHNU ORCHESTRAの在庫
-
MAHAVISHNU ORCHESTRA / BIRDS OF FIRE
73年発表の2nd、『火の鳥』の邦題でも親しまれる、テンションみなぎる傑作!
マイルス・バンドで活躍した天才ギタリスト、ジョン・マクラフリンとドラマーのビリー・コブハムに加え、ヤン・ハマー(key)、リック・リアード(b)、ジェリー・グッドマン(vln)と、当時のジャズ界きってのテクニシャンによって結成されたフュージョン・シーンを代表するグループ。代表作と名高い73年の傑作2nd。ぶっといトーンでゴリゴリとフルピッキングで弾き倒すマクラフリンのギターと、鬼気迫るグッドマンのヴァイオリンとのユニゾンが放つ緊張感と迫力は唯一無比。ドラムも凄まじくって、ジャズドラマーらしい圧倒的な手数とシャープネス、さらにツェッペリンのジョン・ボーナムばりの重量感もあって、ただただ「超人的」。そこに流麗に切れ込むヤン・ハマーのエレピ、アグレッシヴに動くベースも超絶的だし、とにかく「テクニカルな緊張感」という点では、最高到達点と言えるアンサンブルを聴かせます。ジャンルを超えて音楽シーンに衝撃を与えた70年代屈指の大傑作!
-
MAHAVISHNU ORCHESTRA / APOCALYPSE
名手ジャン=リュック・ポンティの他、マイケル・ギブス、マイク・ウェストブルックら英ジャズの俊英たちも参加、ロンドン交響楽団と共演した74年作
-
SOFT MACHINEの在庫
-
-
-
-
SOFT MACHINE / THIRD
カンタベリー・ロックの最重要作であるだけでなく、英国ジャズ・ロックの代表作とも言える70年作3rd!
CARAVANと同じWILD FLOWERSを母体にRobert Wyattらによって結成されたグループであり、サイケデリック・ロックからその音楽性を変化させカンタベリー・ジャズ・ロックの代表的存在へと飛躍していったバンドによる70年3rd。Elton Deanに加えて、Nick Evans、Lyn Dobson、Rad Spail、Jimmy Hastingsという管弦奏者を充実させた8人体勢で録音された本作は、20分に迫る大曲4曲で聴かせる意欲作であり、初期のサイケデリック・ロックの音楽性を下地にしながらも、構築されたジャズ・ロック・アンサンブルと適度なアヴァンギャルド志向が融合した傑作です。
-
2枚組、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック3曲
盤質:傷あり
状態:良好
側面部に色褪せあり、小さいケースツメ跡あり
-
SOFT MACHINE / FIFTH
脱退したワイアットに代わり、フィル・ハワード/ジョン・マーシャルがドラマーで加入、渋く硬派なジャズ・ロックを披露する71年5th
CARAVANと同じWILD FLOWERSを母体にRobert Wyattらによって結成されたグループであり、サイケデリック・ロックからその音楽性を変化させカンタベリー・ジャズ・ロックの代表的存在へと飛躍していったバンドによる71年5th。ついにRobert Wyattが脱退しMATCHING MOLEを結成へと動く中、新ドラマーにPhil Howardを迎えるも収録中に脱退、アルバムの後半はNUCLEUSのJohn Marshallがドラムを担当しています。その内容は前作までの管弦楽器を撤廃、Elton Deanのサックスのみという最小限に抑えたアンサンブルで聴かせるフリー・フォームなジャズ・ロックとなっており、剥き出しになったバンド・アンサンブルの醍醐味が堪能できる傑作となっています。
-
SOFT MACHINE / FOURTH
71年発表、ワイアット在籍最後となる傑作4th
CARAVANと同じWILD FLOWERSを母体にRobert Wyattらによって結成されたグループであり、サイケデリック・ロックからその音楽性を変化させカンタベリー・ジャズ・ロックの代表的存在へと飛躍していったバンドによる71年4th。前作にも参加していたElton Deanが正式にメンバーとしてバンドに加入した本作は、前作よりもアヴァンギャルド志向と即興色を打ち出した作品であり、フリー・ジャズの音楽性の色濃いものとなりました。ジャズ色を急激に進化させたバンドと音楽性が合わなくなったRobert Wyattは本作を最後に脱退、MATCHING MOLEを結成することになります。
-
-
SOFT MACHINE / SIX
元ニュークリアスのカール・ジェンキンスを迎えて制作された73年作、オリジナルは2枚組の大作で、『Third』にも負けないイマジネーション溢れる傑作
カンタベリー・ミュージックのみならず、ブリティッシュ・ジャズ・ロックを代表する言わずと知れた名グループ。1枚目が新曲中心のライヴ作、2枚目がスタジオ作という2枚組でオリジナルはリリースされた73年作6thアルバム。前作でサックス奏者のエルトン・ディーンが脱退し、代わりにカール・ジェンキンス(オーボエ、Key)が加入。メンバーは、マイク・ラトリッジ(Key)、ヒュー・ホッパー(B)に、元ニュークリアス出身のカール・ジェンキンスとジョン・マーシャル(Dr)という4人となりました。ニュークリアスでも作曲センスを披露していたジェンキンスは、本作でも約半数の作曲を担っているのが特筆。ラトリッジのクールなエレピとホッパーのずしりと重いベースによるリフの反復を軸に、ジェンキンスのオーボエが涼やかなトーンで幻想的なリードを奏で、その後ろでは、マーシャルがウワモノとは対照的に手数多くシャープに疾走。『3rd』から『5th』で磨き上げた硬派でクールなフリー・ジャズ・ロックを軸に、初期ニュークリアスで聴けたミニマルな反復リフとたゆたうホーンとが織りなす幻想美が加わり、同じく1970年にリリースされた英ジャズ・ロック傑作、ソフツ『3rd』とニュークリアス『エラスティック・ロック』との融合とも言えるサウンドを聴かせています。ジェンキンスに負けじと、ラトリッジもジャズに収まりきらない独創的な楽曲を生み出していて、特に「Chloe And The Pirates」は、90年代以降のポスト・ロックと言えるような流麗かつ浮遊感たっぷりなキラメく名曲。『3rd』にも負けない、イマジネーションに満ちた英ジャズ・ロック・シーン屈指の傑作と言えるでしょう。
-
-
SOFT MACHINE / BUNDLES
75年リリース、Allan Holdsworth参加、圧巻のテクニカル・フュージョン/ジャズ・ロック傑作!
オリジナル・メンバーのKevin Ayers以来のギタリスト、Allan Holdsworthが加入し、『6』『7』と推し進めてきたフュージョン色をより強めた作品。75年作の8thアルバム。Karl JenkinsとMike Ratledgeによる叙情性と浮遊感のあるキーボード・ワーク、そしてその上をテクニカルに疾駆するHolldsworthの流麗なギター。John MarshallのドラムとRoy Babbingtonのベースによるロック的ダイナミズムに溢れたソリッドなリズム隊も特筆もの。圧巻のテクニカル・ジャズ・フュージョン・ロック!Holldsworthの唯一の参加作となった傑作。
-
デジパック仕様、2枚組、リマスター、DISC2には75年10月11日 のライヴ音源収録!
レーベル管理上、デジパック側面部に折れ線がある場合がございます。ご了承ください。
-
紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、内袋・ブックレット付仕様、定価2800+税
盤質:無傷/小傷
状態:良好
帯有
軽微なケースツメ跡あり
-
-
SOFT MACHINE / SOFTS
ホールズワースに代わり名手ジョン・エサリッジが加入した76年作、ギター入りソフツ第2弾!
最後のオリジナル・メンバーMike Ratledgeが脱退。新たに元Darryl Way’s WolfのギタリストJohn Etheridgeが加入。John Etheridge (G)、Karl Jenkins (Piano)、John Marshall (Dr)、 Roy Babbington (B)、 Alan Wakeman (Sax)という布陣で制作された76年作。シャープなリズム隊をバックにJohn Etheridgeの超絶ギターが炸裂するパートと、柔らかく広がるキーボード&ピアノとサックスによる優美なパートとがダイナミックに交差するアンサンブルが聴き所。圧倒的なテンションと浮遊感の間を超絶技巧とセンスで行き交う後期ソフト・マシーンの代表作。
-
SOFT MACHINE / LAND OF COCKAYNE
ソフト・マシーンの最終作となった通算11作目、再参加のホールズワースの他ジャック・ブルースも参加した81年作
英ジャズ・ロックを代表するグループ、SOFT MACHINEの最終作となった通算11作目。81年作。Karl Jenkinsがイニシアチブを取り、John Marshall、Jack Bruce、Alan Holdsworthらが参加して作られた作品。テクニカルなジャズ・ロックを期待して聴くと肩すかしですが、イージー・リスニング的な浮遊感のあるジャズ・ロックとして聴けばかなり完成度高いです。
-
SOFT MACHINE / LIVE AT THE PARADISO
2ndアルバム発表後の69年3月、アムステルダムはパラディソでのライヴ音源。ワイアット、ラトリッジ、ホッパーによる緊張感に満ちたアンサンブルが素晴らしい全13曲
2ndアルバム発表後の69年3月、アムステルダムはパラディソでのライヴ音源。ワイアット、ラトリッジ、ホッパーによる緊張感に満ちたアンサンブルが素晴らしい傑作。
収録曲は、1.Hulloder 2.Dada Was Here 3.Thank You Pierrot Lunaire 4.Have You Even Bean Green? 5.Pataphysical Introduction PtII 6.As Long As He Lies Perfectly Still 7.Fire Engine Passing With Bells Clanging 8.Hibou Anemone And Bear 9.Fire Engine Passing With Bells Clanging(Reprise) 10.Pig 11.Orange Skin Food 12.A Door Opens And Closes 13.10:30 Returns To The Bedroom
MAHAVISHNU ORCHESTRAの在庫
-
MAHAVISHNU ORCHESTRA / BIRDS OF FIRE
73年発表の2nd、『火の鳥』の邦題でも親しまれる、テンションみなぎる傑作!
マイルス・バンドで活躍した天才ギタリスト、ジョン・マクラフリンとドラマーのビリー・コブハムに加え、ヤン・ハマー(key)、リック・リアード(b)、ジェリー・グッドマン(vln)と、当時のジャズ界きってのテクニシャンによって結成されたフュージョン・シーンを代表するグループ。代表作と名高い73年の傑作2nd。ぶっといトーンでゴリゴリとフルピッキングで弾き倒すマクラフリンのギターと、鬼気迫るグッドマンのヴァイオリンとのユニゾンが放つ緊張感と迫力は唯一無比。ドラムも凄まじくって、ジャズドラマーらしい圧倒的な手数とシャープネス、さらにツェッペリンのジョン・ボーナムばりの重量感もあって、ただただ「超人的」。そこに流麗に切れ込むヤン・ハマーのエレピ、アグレッシヴに動くベースも超絶的だし、とにかく「テクニカルな緊張感」という点では、最高到達点と言えるアンサンブルを聴かせます。ジャンルを超えて音楽シーンに衝撃を与えた70年代屈指の大傑作!
-
MAHAVISHNU ORCHESTRA / APOCALYPSE
名手ジャン=リュック・ポンティの他、マイケル・ギブス、マイク・ウェストブルックら英ジャズの俊英たちも参加、ロンドン交響楽団と共演した74年作
-
SOFT MACHINEの在庫
-
-
-
-
SOFT MACHINE / THIRD
カンタベリー・ロックの最重要作であるだけでなく、英国ジャズ・ロックの代表作とも言える70年作3rd!
CARAVANと同じWILD FLOWERSを母体にRobert Wyattらによって結成されたグループであり、サイケデリック・ロックからその音楽性を変化させカンタベリー・ジャズ・ロックの代表的存在へと飛躍していったバンドによる70年3rd。Elton Deanに加えて、Nick Evans、Lyn Dobson、Rad Spail、Jimmy Hastingsという管弦奏者を充実させた8人体勢で録音された本作は、20分に迫る大曲4曲で聴かせる意欲作であり、初期のサイケデリック・ロックの音楽性を下地にしながらも、構築されたジャズ・ロック・アンサンブルと適度なアヴァンギャルド志向が融合した傑作です。
-
2枚組、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック3曲
盤質:傷あり
状態:良好
側面部に色褪せあり、小さいケースツメ跡あり
-
SOFT MACHINE / FIFTH
脱退したワイアットに代わり、フィル・ハワード/ジョン・マーシャルがドラマーで加入、渋く硬派なジャズ・ロックを披露する71年5th
CARAVANと同じWILD FLOWERSを母体にRobert Wyattらによって結成されたグループであり、サイケデリック・ロックからその音楽性を変化させカンタベリー・ジャズ・ロックの代表的存在へと飛躍していったバンドによる71年5th。ついにRobert Wyattが脱退しMATCHING MOLEを結成へと動く中、新ドラマーにPhil Howardを迎えるも収録中に脱退、アルバムの後半はNUCLEUSのJohn Marshallがドラムを担当しています。その内容は前作までの管弦楽器を撤廃、Elton Deanのサックスのみという最小限に抑えたアンサンブルで聴かせるフリー・フォームなジャズ・ロックとなっており、剥き出しになったバンド・アンサンブルの醍醐味が堪能できる傑作となっています。
-
SOFT MACHINE / FOURTH
71年発表、ワイアット在籍最後となる傑作4th
CARAVANと同じWILD FLOWERSを母体にRobert Wyattらによって結成されたグループであり、サイケデリック・ロックからその音楽性を変化させカンタベリー・ジャズ・ロックの代表的存在へと飛躍していったバンドによる71年4th。前作にも参加していたElton Deanが正式にメンバーとしてバンドに加入した本作は、前作よりもアヴァンギャルド志向と即興色を打ち出した作品であり、フリー・ジャズの音楽性の色濃いものとなりました。ジャズ色を急激に進化させたバンドと音楽性が合わなくなったRobert Wyattは本作を最後に脱退、MATCHING MOLEを結成することになります。
-
-
SOFT MACHINE / SIX
元ニュークリアスのカール・ジェンキンスを迎えて制作された73年作、オリジナルは2枚組の大作で、『Third』にも負けないイマジネーション溢れる傑作
カンタベリー・ミュージックのみならず、ブリティッシュ・ジャズ・ロックを代表する言わずと知れた名グループ。1枚目が新曲中心のライヴ作、2枚目がスタジオ作という2枚組でオリジナルはリリースされた73年作6thアルバム。前作でサックス奏者のエルトン・ディーンが脱退し、代わりにカール・ジェンキンス(オーボエ、Key)が加入。メンバーは、マイク・ラトリッジ(Key)、ヒュー・ホッパー(B)に、元ニュークリアス出身のカール・ジェンキンスとジョン・マーシャル(Dr)という4人となりました。ニュークリアスでも作曲センスを披露していたジェンキンスは、本作でも約半数の作曲を担っているのが特筆。ラトリッジのクールなエレピとホッパーのずしりと重いベースによるリフの反復を軸に、ジェンキンスのオーボエが涼やかなトーンで幻想的なリードを奏で、その後ろでは、マーシャルがウワモノとは対照的に手数多くシャープに疾走。『3rd』から『5th』で磨き上げた硬派でクールなフリー・ジャズ・ロックを軸に、初期ニュークリアスで聴けたミニマルな反復リフとたゆたうホーンとが織りなす幻想美が加わり、同じく1970年にリリースされた英ジャズ・ロック傑作、ソフツ『3rd』とニュークリアス『エラスティック・ロック』との融合とも言えるサウンドを聴かせています。ジェンキンスに負けじと、ラトリッジもジャズに収まりきらない独創的な楽曲を生み出していて、特に「Chloe And The Pirates」は、90年代以降のポスト・ロックと言えるような流麗かつ浮遊感たっぷりなキラメく名曲。『3rd』にも負けない、イマジネーションに満ちた英ジャズ・ロック・シーン屈指の傑作と言えるでしょう。
-
-
SOFT MACHINE / BUNDLES
75年リリース、Allan Holdsworth参加、圧巻のテクニカル・フュージョン/ジャズ・ロック傑作!
オリジナル・メンバーのKevin Ayers以来のギタリスト、Allan Holdsworthが加入し、『6』『7』と推し進めてきたフュージョン色をより強めた作品。75年作の8thアルバム。Karl JenkinsとMike Ratledgeによる叙情性と浮遊感のあるキーボード・ワーク、そしてその上をテクニカルに疾駆するHolldsworthの流麗なギター。John MarshallのドラムとRoy Babbingtonのベースによるロック的ダイナミズムに溢れたソリッドなリズム隊も特筆もの。圧巻のテクニカル・ジャズ・フュージョン・ロック!Holldsworthの唯一の参加作となった傑作。
-
デジパック仕様、2枚組、リマスター、DISC2には75年10月11日 のライヴ音源収録!
レーベル管理上、デジパック側面部に折れ線がある場合がございます。ご了承ください。
-
紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、内袋・ブックレット付仕様、定価2800+税
盤質:無傷/小傷
状態:良好
帯有
軽微なケースツメ跡あり
-
-
SOFT MACHINE / SOFTS
ホールズワースに代わり名手ジョン・エサリッジが加入した76年作、ギター入りソフツ第2弾!
最後のオリジナル・メンバーMike Ratledgeが脱退。新たに元Darryl Way’s WolfのギタリストJohn Etheridgeが加入。John Etheridge (G)、Karl Jenkins (Piano)、John Marshall (Dr)、 Roy Babbington (B)、 Alan Wakeman (Sax)という布陣で制作された76年作。シャープなリズム隊をバックにJohn Etheridgeの超絶ギターが炸裂するパートと、柔らかく広がるキーボード&ピアノとサックスによる優美なパートとがダイナミックに交差するアンサンブルが聴き所。圧倒的なテンションと浮遊感の間を超絶技巧とセンスで行き交う後期ソフト・マシーンの代表作。
-
SOFT MACHINE / LAND OF COCKAYNE
ソフト・マシーンの最終作となった通算11作目、再参加のホールズワースの他ジャック・ブルースも参加した81年作
英ジャズ・ロックを代表するグループ、SOFT MACHINEの最終作となった通算11作目。81年作。Karl Jenkinsがイニシアチブを取り、John Marshall、Jack Bruce、Alan Holdsworthらが参加して作られた作品。テクニカルなジャズ・ロックを期待して聴くと肩すかしですが、イージー・リスニング的な浮遊感のあるジャズ・ロックとして聴けばかなり完成度高いです。
-
SOFT MACHINE / LIVE AT THE PARADISO
2ndアルバム発表後の69年3月、アムステルダムはパラディソでのライヴ音源。ワイアット、ラトリッジ、ホッパーによる緊張感に満ちたアンサンブルが素晴らしい全13曲
2ndアルバム発表後の69年3月、アムステルダムはパラディソでのライヴ音源。ワイアット、ラトリッジ、ホッパーによる緊張感に満ちたアンサンブルが素晴らしい傑作。
収録曲は、1.Hulloder 2.Dada Was Here 3.Thank You Pierrot Lunaire 4.Have You Even Bean Green? 5.Pataphysical Introduction PtII 6.As Long As He Lies Perfectly Still 7.Fire Engine Passing With Bells Clanging 8.Hibou Anemone And Bear 9.Fire Engine Passing With Bells Clanging(Reprise) 10.Pig 11.Orange Skin Food 12.A Door Opens And Closes 13.10:30 Returns To The Bedroom
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!