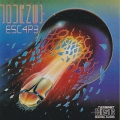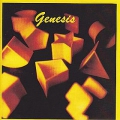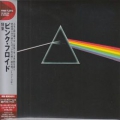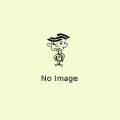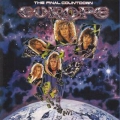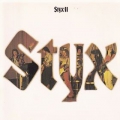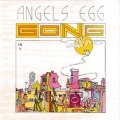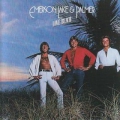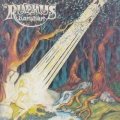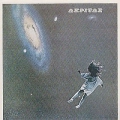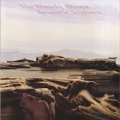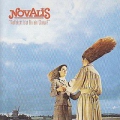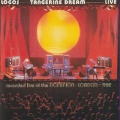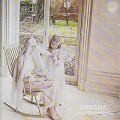プログレッシヴ・ロックの中古CD豊富!プログレ、世界のニッチ&ディープな60s/70sロック専門ネットCDショップ!
13時まで当日発送(土・日・祝は翌日)、6,000円(税抜)以上送料無料
-
カテゴリー
-
プログレ
- 60s/70s/80sプログレすべて
- ブリティッシュ・プログレ
- イタリアン・プログレ
- フレンチ・プログレ
- ジャーマン・プログレ
- 北欧プログレ
- 東欧・露プログレ
- その他ユーロ・プログレ
- 南米プログレ
- 北米プログレ
- ジャパニーズ・プログレ
プログレ新鋭
ロック&ポップス
ハード・ロック
ジャズ・ロック
-
- トップ
- 国内中古CD
- 輸入中古CD
- 新品CD
- 新品LP
- セール
- ベストセラー
- レコメンド
- ジュークボックス
-
ロック探求特集
- ロック潮流図鑑:黄金の60年代特集
- プログレッシヴ・ロック入門特集
- イタリアン・ロック特集
- プログレ新鋭特集「プログレ温故知新」
- アメリカン・ロック特集
- ブリティッシュ・ジャズ・ロック特集
- カンタベリー・ミュージック特集
- ブリティッシュ・ハード・ロック特集
- ブリティッシュ・フォーク特集
- スワンプ・ロック/ルーツ・ロック特集
- アメリカン・フォーキー・ミュージック特集
- アメリカン・ブルース・ロック特集
- サザン・ロック特集
- フュージョン・ロック特集
- 日本のニューロック特集
- サイケデリック・ロック特集
- ブラス・ロック特集
- グラム・ロック特集
- NYパンク・ロック特集
- イスラエル・ロック特集
- イタリアン・カンタウトーレ特集
- Webマガジン
waterbearerさんのレビュー
-
JOURNEY / ESCAPE

これぞ80sアメリカンハードの大名盤(2 拍手)
言わずもがなの大名盤。この一言で終わりにしたいくらい。
プロデューサーMike Stoneのお得意である「ハード&キャッチー」がはっきり現れた一枚。
楽器、ヴォーカルのチャンネルが絶妙に分離し、空間的な拡がりの中に放たれる…M1では印象的なCP80のイントロに導かれ、ギター、ヴォーカルと重層的に厚みを増していく。ベースの音に着目すると割と高い音程で行ったり来たりしているのが聞こえるが、これがたまらなく気持ちよい。
まぁ本作に捨て曲はないのはご存じの通り。どこを切り取っても「これぞJourney」な音。産業ロック?知ったこっちゃねぇ。プロなら売れてなんぼだ。
AOR Heaven、Escape、MTMなどのレーベルから量産されるメロディックハードAORの源流はここにある。 -
GENESIS / GENESIS
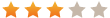
軽い、しかし巧い(2 拍手)
本作が彼らの15枚目のアルバムだったのか。
「Trespass」以後「No sons of mine」まで聴いていたのだが、彼らのアルバムを買った最後の1枚が本作。手が伸びなかったのはジャケットのせいだったんだんだけど。聴いてみて最初の感想は「うーん、軽い」だった。
作風は本作の前後「Abacab」や「Invisible Touch」よりも、さらにはPhilのソロより軽く感じてしまう印象だ。リズム隊に重みがなく、ロックの躍動感が希薄だと思う。一番ロックなのがVoのPhilだし。M7のシャウト加減はなかなかかっこいいんよ。インスト的にはゲートリバーブの利いたドラムサウンドで世界をあっと言わせたのは次作だから、なおさら軽さが気になると言えば気になる。でもこの布石は必要だったのかもしれない。
何だかんだ書いているが、楽曲の質は高い。印象的なメロディ、選び抜かれたKeyの音色はもうさすがというしかない。ヒットチャートを賑わす実力があるバンドになったんだなと思う。やっぱりねぇ、音楽は売れてなんぼのもんだと思うよ。メジャー所は特に。 -
ピンク・フロイド / 狂気

知らんがな(3 拍手)
まぁどんな名盤と崇められようが、ヒットチャートを賑わそうが、「自分の耳を信じる」のを信条としているので、本作が云々というのはもう語りつくされているので言及してもまぁ…ねぇ。
本作はピンクフロイドのアルバムで、プログレではなく「普通のロック」として公に認められた作品ということでいいのではないかと。
効果音、VCS3のシーケンサー(またはアルベジエーター)がギミックで入ってきてというのは1973年という時代においてはもう新鮮味はなかったと思う。YESやKCのようにテクニカルではなし、Genesisのようにクラシカルではなし、かといって初期のサイケデリックな部分も潜めてしまった。
本作の最大のウリは歌詞のメッセージ性、それに尽きる。これも多くの評論家が語りつくしたので言及はしないが、繰り返すけど「普通のロック」として歌詞が持つメッセージが公にフィットした、ということなのだ。別にプログレが云々ではない、ということを確認しておく。
個人的にはあまり興味がないアルバムだが、ロックの歴史を語る上では持っていていいのではないかと思う。それ以上ではないかなぁ。 -
ニュー・イングランド / 果てしなき冒険

甘美なメロディと適度なハードさ(2 拍手)
1980年、彼らの2ndである。InfinityからElektraに移籍し心機一転。前作でのハードロック風味は若干後退し、曲によってはベイシティローラーズ的のポップな曲もある。本作の注目するところはM4のような壮大なドラマとロマンを感じさせるようなタイトル曲にある。甘くて切ないメインVoのJ.Fannonだけではなく、ブリッジではDsのH.Gardnerの切れの良いハイトーンVoも実に魅力的だ。加えてメロトロンのクワイヤとストリングスで空間的広がりを作ったかと思うと、そこにシンセによるリードトーンが駆け抜ける…これだけでも満足ではある。だか彼らの魅力は「良質なポップソングが書ける」ことにある。しかも適度にハードでキャッチ−でヒット性も感じさせるのだ。M2、M3、M7〜M11はほんとどれもシングルカットできる出来と断言する。1980年といえばJourneyやStyxあるいはKansasといったアリーナロックバンドが隆盛していた頃。メジャーレーベルにいながらそこに食い込むことができなかったのが残念であった。
厳しいことを言えば、プログレでもなく、ハードロックでもなく、かといってポップなロックバンドにしては中途半端、というところでレーベル的には売りにくかったのかもしれない。
彼らのアルバム、初期3枚はアメリカンプログレ好きなら必聴・必携だ。 -
JAN HAMMER / FIRST SEVEN DAYS

これはプログレです(2 拍手)
発売が75年、ということなのでマハヴィシュヌを脱退した後に発表された1stソロアルバム。天地創造をテーマとした作風で、さぞかし壮大なんだろうと思いきや、マハヴィシュヌ風味も残しつつ、Keyによるオーケストレーションが見事なインストアルバムとなっている。
かといって華美にはならず、マハヴィシュヌ時代からのエレピ、モーグ、ピアノに加えてメロトロンが大々的にフィーチャーされている。彼がメロトロン?と思うが、これがなかなかいい使い方をしている。
リズム隊はクロスオーバー風だが、ギターレスでありながらロックの躍動感も十分。もうこれはただのプログレです。なんといえばいいのか…「ロックなリズム隊が活躍するTANGERINE DREAMのPhedoraもしくはRubyconへのオマージュ」といえばいいのだろうか。
ジャズロック好きな方も、マハヴィシュヌのファンの方も、メロトロンマニアの方も聴いて絶対損はない一枚。 -
SKY / SKY 2(VOL.2)

2ndは最もロック寄りの作風(2 拍手)
変わったバンドだ。クラッシック・ギターの名士とロックのセッション畑であちこちに名を見るエレキギター奏者が中心となったバンド。そこにCAMELのベース、H.FlowersやCURVED AIRのKey、F.Monkmanらが関わり、クロスオーバーなアルバムを連発する。
どのアルバムも全編インストなのだが、特にこの2ndはエレキギター使いのK.Peekが全面に出ている印象。そこに複雑なシンコペーションを叩くクラッシック畑のT.FlyのDsが絡んでくる。
聴きどころとしては、M4では珍しく、久しぶりにF.Monkmanもギターを弾いている。またM13はバッハのトッカータとフーガのアレンジによるシングルヒット曲。
面子がプログレ畑だというので、そっち方面のファンにも知られたバンドだった。本作を最後にF.Monkmanが脱退する。 -
SEMIRAMIS / LA FINE NON ESISTE

オリジナルメンバーはDsだけだが50年ぶりの2nd(4 拍手)
イタリアのプログレバンドって、「ん十年ぶりの再結成、新作、加えて来日」というパターンが多く感じる。もちろん全盛期のメンバーが全員揃わないパターンも少なくない。でも楽器の心得がある人ならわかると思うが、ライフスタイルが変わってもモチベーションとパッションがあるならプロじゃなくても趣味で続けることもできる。
オリジナルメンバーはDsだけになったが彼ら50年ぶりの2nd。ここはDsが奮起してプロの世界に戻ってたことに敬意を払うべきだろう。
どうしても1stと比べてしまうが、それはそれ。力強いメロディを表現力の高い新Voが高らかに歌い上げる。そこにギターがヘヴィーに絡んでくる。YESからの影響は1stよりも更に強く感じるが、静と動の使い分け、怪しげなKeyが空間を演出する。
別バンドと捉えてもいいし、やっぱり1stの良さを継承しているなと捉えてもいいし、とにかくプログレ大国イタリアからは目が離せない。良作です。 -
STRAWBS / DEADLINES

Strawbs流プログレポップ、ひとまずのラスト作(3 拍手)
78年の12thアルバム。そして85年の復活まで活動はひとまず止まってしまうラスト作。「Strawbs流」と言っても彼ら、というかD.カズンズが「ワイはプログレやってまっせ」とは言っていないと思うが、メロトロンの導入とR.ウェイクマンが参加したりとこれまでの遍歴からすればプログレの範疇なのだろう。なんか納得いかないところはバークレイ・ジェームス・ハーヴェストに対しても当てはまるんだが…まぁそれはさておき、フォーク色はさらに薄らぎ、ロック色が濃くなる。加えてそれがなかなか板についてきた感もある。曲によってはメロトロンわかりやすく導入され、「やっぱりええなぁ」と聴く者を魅了する(M4とM9)。哀愁度も十二分に感じられるし、ラストのM9なんかは重々しくてたまらん。ポップで味わい深い。そして軽くないのにキャッチー。デビュー当初からこの一本筋は揺るいでないと思う。
3枚組の内訳はBBCのSight&Soundのライブ音源(CD)と映像(DVD)が付いていくるというもの。オリジナルアルバムのほうにはアコースティック・デモ音源が10曲+未発表曲1曲という内容。米ARISTAのCutout盤LPもよく見た記憶があるなぁと懐かしく思う。 -
PINEFOREST CRUNCH / MAKE BELIEVE

Anglagardのメンバー参加の爽やか北欧ポップ(4 拍手)
1996年の1st。北欧でもスウェーデンというとABBAの存在が大きいが、その影響からか美しい旋律を奏でるポップグループを排出する土地柄。彼らもその1つ。
90年代というとカーディガンズが同郷の成功者(セールス的に)であるが、彼らはその後輩。本作は、セールス的には10万枚とまずまずだったが、内容は光るものがある。
A.Eklundの柔らかでナイーブな雰囲気のVoと、絡むコーラスが実に爽やか。
かと思えば、中盤にはフォーキーな曲がいくつかあり、アコギにメロトロンがたまらなくよい。
AnglagardのDs、M.Olsson(Ds)がメンバー。そして彼が本作(そして次作以降も)にメロトロンを導入している。おなじみのストリングスだけではなく、パイプオルガン、ヴィオラ、木管楽器など様々なサウンドがあちこちに入り込んでいる。これらの音を探しながら聴くのも一興か。
プログレな音を求めるならおすすめしないが、90年代北欧ポップのシーンを垣間見る一枚として、すばらしい内容なのでご紹介したい。 -
WIND / MORNING

ジャケットとメロトロンにお金を払おう(3 拍手)
1971(72?)年。ジャーマンシンフォではよく知られたバンド。こちらは2nd。
「よく知られた」の意味は、ジャケットの美しさとメロトロンの使用頻度の高さで、という意味だ。
音の方はジャケットから連想するようなファンタジーさよりも、ややダミ声のVoと時折ドタバタするドラムの音…これきっとProcol Harumの影響大でしょ? 楽曲は悪くないんだが、音作りとしては洗練度が低い。それでも冒頭の『The Morning Song』からメロトロンが登場。雰囲気はMatching Moleの「O Caroline」に似てなくもない。ダミ声Voを除けば(ちなみにG.ブルッカーには悪意はありません。ええ。)。
続く『The Princess And The Minstrel』そして、メロトロンのストリングスを大フィーチャーした『Dragon's Maid』は聞いて損はない。
いわゆる「ユーロロック(懐かしい!)」を紹介する雑誌なんかではよく取り上げられるほどの作品。プログレマニアを標榜するなら1枚お手元にどうぞ。 -
ブライアン・オーガー&ザ・トリニティ / ビフォア

Mel CollinsのCIRCUSと聴き比べるといいかも(4 拍手)
AugerがJulie Driscollとのアルバム発表後にJulie抜きで編成したのがTrinity。
この作品の目玉はG.Faure作曲のPavaneだ。「Pavane」そのものの意味は宮廷で男女ペアが威厳を持ってゆっくりと踊る音楽とのこと。しかしAugerのこのアレンジは疾走感あるロック。オルガン炸裂で威厳もへったくれもないほどカッコいい。あとこの曲だけメロトロン入りなのでその筋の方(?)にも満足してもらえそう。
そして本作のもう1つの目玉はHerbie Hancockの「処女航海」のカバーを収録。こちらは原曲のゆったりした雰囲気が生かされいる。リードを取るのはギターとオルガン。一聴する限りデパートの店内BGM然としてなくもない。ギターからオルガンにソロパートが移るところはまぁいいが、原曲と比べると若干緊張感が足りない。
名曲のカバー曲収録(しかもインスト)の作品というとMel Collis参加のCIRCUSを思い出すが、あちらほどヘヴィさはなく、ドラムもやかましくない。こちらもあちらも原曲からのアレンジはなかなかのものなので両方抑えたいところ。 -
ヴァンゲリス / 野生

映像を観てみたくなる一枚(3 拍手)
映像監督F.ロシフ監督と彼とのコラボ作は何枚かリリースされているけど、日本公開されなかったり、TVシリーズだったりで「一度は観てみたい」と思うんだが、叶わないんだろうか…RCAからポリドールに移籍後、70年台後半〜90年台頭までは映画のサウンドトラックを数多く担当し、中でも81年の「Chariots of Fire」はアカデミー賞受賞。それの前段に位置する本作は邦題が「野生」となっていても、曲のタイトルを見る限り人間にも焦点を当てているようだ。ますます映像が気になるじゃないか!
どの曲もCS80のアフタータッチやリボンコントローラーをフル活用しており、もはや彼の体の一部となって機能しているのではと思わせる。時には鍵盤楽器、時には弦楽器、そしてパーカッションとしても。いやはや「表現者」の鏡かと。
収録曲ラストでJ.アンダーソンがハープで参加しているが、まぁこのあたりは友情出演的なものであって、特段注目する点ではない。
本作と前作「China」は一組で必聴だ。RCA時代のロックな彼から、より多様な表現者となったポリドール時代の彼の魅力満載の一枚である。
-
イエス / ドラマ

プログレなYES、最終章(4 拍手)
90125以前のYES,最終章。DsがA.ホワイトになってからロックの躍動感が増し、R.ウェイクマンが出戻った「Going For The One」あたりからバンドとしてのまとまりが出てきたなと思ったら、主要な2人がBUGGLESと入れ替わった。
KeyのG.ダウンズは、YES歴代のKey奏者の中でも一番一台一台の特性を知っていて、かつ音色カラフルなアルバムは他にはないと思う。特にポリシンセそしてサンプリングキーボードの先駆けであるフェアライトの大胆な導入、これらとオルガンのレトロな音色との組み合わせは豪華な印象すらある。
T.ホーンのVoもJ.アンダーソンの物真似と言われたかもしれないが、いやいやどこか朴訥としていて、時折張り上げる感じは前任とは異なる魅力がある。
『Machine Messiah』ではクリスがリードをとるパートもあるし、S.ハウのギターはこれまで以上にヘヴィーな音を出すところもありながら、しっかりアコギやスティールギターを聴かせてくれる曲もある。これまでのYESの魅力も十分に発揮しているどころか、より磨きがかかったテクニックを披露していると思う。
この面子で唯一のアルバム、かつプログレ期最後のアルバムとなったが、個人的にはYES最高傑作なのではないかと思う。 -
ROXY MUSIC / COUNTRY LIFE

きゃー、のび太さんのエッチ!!(6 拍手)
と、しずかちゃんは言うのだろうか。個人的にはムフフで好きなジャケットだけど、本作を初めて買って聴いたときはUS盤のLPで、女性2人の姿がない、いわゆる「修正済盤」。木の枝とバンド名のみが書かれたジャケットは世知辛さを感じたけど、今となってはそれもまたいい思い出だ。
さて、本作。エディ・ジョブソン加入後2作めということで前作よりも居場所がある感を感じる。Out Of The Blueはその筆頭。ラストの長いヴァイオリンソロにうっとり。Bitter and Sweetではヒリヒリしたメロトロン。途中、道化師やサーカスを思わせる演出も面白い。他の楽曲でもそうだが、途中ちょこちょこ挟まるプログレ臭さとグラムロックのニヒルさがいい味わいなんだよなぁ、これが。
御大ブライアン・フェリーもいい買い物できましたね!最高 -
9:30 FLY / 9:30 FLY

グループ名の由来を知りたい(6 拍手)
ウェリントン夫妻による英国のバンドで、71年結成。翌年アルバムを1枚発表し、姿を消した謎の唯一作である。
あまりにもデータがないので相場から。個人売買で状態まずまずのもので4万円後半。日本の店頭売りがあれば8〜9万くらいか。その札束があれば他のをCDで買ったほうがいいし、本作のCDなら2000円でおつりがくるだろう。
女性Voでメロトロン入り、という触れ込みで連想されるのはSandroseやNarniaを想わせるだろうが、実際はマイケルとバーバラの夫妻によるデュオであり、妻であるバーバラの声がなかなかよいのが特徴。フォーク色も強いが、躍動感も十分に感じられる。ちなみにメロトロンは1曲のみに使用されている。ストリングスのあの音はマニアにはたまらないと思う
それにしてもこのバンド名とタイトル、どこからきたものか…教えてください。
-
EUROPE / FINAL COUNTDOWN

80年代末、北欧メタルと言えば(6 拍手)
これですかねぇ。スウェーデン出身。この3rd以前の作品どれも必聴なのだが、本格的にアメリカに攻める音作りをした結果大成功。WhitesnakeやJourneyでの仕事で知られるKevin Elsonのプロデュースは過剰だという批判も聞かれたが目標達成のためには必要だったのだ。
どの曲もシングルカットできるほど捨て曲なし。J.TempestのVoの若々しく情熱溢れる歌唱を際立たせるに十分だ。本作から元UniverseのKeyが参加。Keyの大々的なフィーチャーも成功要因だろう。80年代末HRの音を象徴するタイトル曲のイントロは誰もが聞き、驚いたに違いない。
この成功に味をしめた?のか、Columbiaは(世界デビューとして)後発に220V(スウェーデン)、Pretty Maids(デンマーク)をアメリカ市場に送り込む。他社も負けじとPolyGram傘下のMercuryはTNT(ノルウェー)をアメリカ市場に送り込み、成功を収めた。因みにPolyGram本体は先にYngwie Malmsteen(スウェーデン)である程度実績がある。
Rock Candy盤はリマスターが効果的に効いていて、実にクリアだ。ボーナストラックはライブ音源とシングルB面曲。これはありがたい。ライブは残念ながらスタジオ盤発表後に脱退したギタリスト、J.Norum在籍時のライブではなく、K.Marcelloに交代した後のライブのもの。確か24時間テレビで来日して演奏していた時はJ.Norumの時じゃなかったかな?そっちを使えばよかったのに、と星1コ減。 -
TANGERINE DREAM / ALPHA CENTAURI

ジャーマンロック黎明期の重要作(6 拍手)
2nd。Ohr時代の4枚はこの時代のドイツの地下音楽シーンの先駆的な存在を知らしめるには十分すぎるほど。サイケでコズミックで、かと思えばジャズや宗教音楽的な要素も盛り込まれている。ごった煮にならず、脱構築して彼らの解釈で再構築することにより、オリジナリティを生み出すことに成功している。
メインはオルガンであるのはこの時代なのだが、Moogを導入したり、トーンジェネレーター(発振器)やテープエコーで加工した身近なもの(非楽器)を用いたりと、工夫に工夫を重ねている様子がうかがえる。例えばM1で昇降機(エレベーター)の励起音を使っている。この技はDeep PurpleのFireballでも使われていて、リリース時期もともに近いことを考えれば、この手法はこの時代の最先端の手法だったと思われる。
本作のハイライトはM3ラスト。宇宙人からのメッセージなのか、神からの啓示なのか。ドラマティックにエンディングを迎える。
ジャーマンロック黎明期の重要作として位置づけられる名作。 -
STYX / STYX II

これぞアメリカンプログレ(5 拍手)
オペラチックなコーラス、キメキメの覚えやすいフレーズ、こういうの「アメリカンプログレ」の古典、お手本って言っていいと思う。
RCA/Wooden Nickel時代の4枚はどれも捨てがたいが、1stの路線をより整理した本作はぐっと聞きやすくなった感がある。大ヒットかつ今日でもM2はライブの定番曲は、徐々に盛り上がっていくドラマティックなバラード。
M5のドライブしたオルガンメインのインストに導かれ、M6につながる展開はいかにもアメリカンプログレのダイナミックさを味わえる。
個人的にはM3がアコースティックかつ微妙な緊張感があって、このアルバムの中では一番好きな楽曲。
Voは「ミスターStyx」D.D.ヤングがメイン。この人、若いころから声質が変わらないなぁ。すごい。 -
GONG / ANGEL'S EGG

GONG流、音のごった煮(5 拍手)
実は初期GONGは聴いたことがなくて、おっかなびっくりで入手。
初期…本作までの彼らは浮遊感あるサイケデリックな音を特徴としていたけど、本作ではジャズのエッセンスが前面に出たとのこと。聴いてみるとそれは間違いない。けど、それだけではなくロックのダイナミックさがベースにジャズやらサイケやらのごった煮状態。これがまた音のコラージュ的演出でいい。HAWKWIND風のサウンドジェネレーター(VCS3?)の導入も効果的だ。
部分的でもHillageのギターはAsh Ra TempelのManuelにも通じるなと思った。この経験が後々ソロ作品に繋がると考えるとまさに原点と言える。
入手してからスマホに入れてヘッドフォンで聴いているが、クスリなしで「飛べる音」だ。 -
WALLENSTEIN / BLITZKRIEG

ハードさと華麗さのシナジー(4 拍手)
Wallensteinの1stはアシッドフォーク系バンドを擁立するPilzレーベルからのリリースだった。それはさておき、M1の鋭角なKey、フランジャーを利かせたGtr、独特に変化するリズム隊が織りなすハードなインストで圧倒されてしまう。タイトルの「電撃戦」に相応しい激しさは本作の特徴を表していると思う。
翻ってM2になるとVoが入ってくるが、まぁそれほど大したことなない歌唱力。それをかき消すくらいの演奏力がこのバンドにはあるので全く気にならない。
M1が動ならM2は静、と簡単に二分化できないところは聴いてのお楽しみだ。
メロトロンも効果的だが、表現力豊かなリズム隊とピアノが実に華麗。
CD化されているのは1stから4thまでだったと思うが、アルバム全体の出来、まとまりは絶対1st。ジャーマンシンフォの名作、いや欧州プログレの中でも群を抜いての出来かと思う。おすすめです。 -
EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / LOVE BEACH

自分の耳を信じよう(8 拍手)
相変わらず評価低いんだけど…本当?ちゃんと聴いている??
ELPのラストアルバムとしてだけではなく、評価の低さも有名。そしてアルバムタイトルはメンバーの相違ではなく、本人たちは当然気に入っていない?へぇ…まぁ個人的な意見になるけど、凡長であくびが出る2枚組のライブアルバム「Welcome back my〜」、音源寄せ集め&やっつけ感しか感じない「Works Vol.1」と「同Vol.2」なんかより遥かに内容は良い。本作にまつわるゴタゴタを知ったとしても、よくもまぁ体裁を整えてリリースしたもんだと感心する。
M1、M2のキャッチーさは新しさを感じさせるも、これまでのELP的な力技感も十分に味わえる佳曲。本作の特徴はかのP.SinfieldがM6以外の歌詞を全て担当している。レコーディングにも立ち会ったそうだが、G.Lakeと険悪になったりと…まぁ大変でしたね。
M6はロドリーゴの曲のアレンジ。こういうインスト曲の入れ方はELP的でいいよね。そしてM7、LPだと片面全部を使った大作「将校と紳士の回顧録」は絶対対訳を読んで、涙してほしい。楽曲の内容も悪くない、むしろ「悪の教典」に迫る楽曲と言いたい。
評判(評論家、マニア、そして本人たち)はさておき、自分の耳で評価してほしい一枚。ジャケットも好きだけどね。私はLPとCD1枚ずつ持ってます。 -
RUPHUS / RANSHART

Voだけ肩の力が抜けたYESフォロワー、2nd(4 拍手)
ノルウェーのバンドの2ndとのこと。収録曲5曲中、4曲でメロトロン入りという。その筋の人にはこれだけでたまらんでしょう。生のフルートもいい感じで絡んでくるし、ギターの「駆け上がり」はかのYESを思わせる。そう、全体的にYESの香りがプンプンする。もしかしたらアメリカのSTARCASTLEよりもその香りが強いように思える。敢えて言うなら「And you and I」の雰囲気がアルバム全体に漂っているかのような作風だ。
ハイライトはPictures Of A DayとラストのBack Side。どちらも長めの曲だが、古き良き王道シンフォニックロックの味わい。今となっては新鮮味はもはやないのだが、安心して聴けてしまうのは魅力的。本作以降もアルバムをリリースしていくが、作風がいろいろ変わっているようなのでご注意。北欧色を感じるかどうかは別として、シンフォニック系のプログレとしては好盤。演奏はしっかりしているが、VoはJ.Andersonにはならず、肩の力が抜けていてそこがまたいいのかも。 -
マグナム / キングダム・オブ・マッドネス

大英帝国の誇りは磨かれたセンスの賜物(5 拍手)
「大英帝国の誇り・マグナム」っていう紹介されていたと思う彼らの1st。78年のアルバムデビュー、ギタリストT.クラーキンの作詞作曲のセンスは、おそらくアーサー王伝説とか指輪物語とかを下敷きにしたヒロイックファンタジーからの影響なんだろうなというくらいセンスがずば抜けていい。特に本作のドラマティックな展開はコンセプトアルバムかのような緩急のつけ具合が見事。この曲順もヘタなシンフォニックプログレバンドよりもはるかにスリリングで飽きさせないと思う。メタルの領域で括られる彼らだが、初期のJETからのリリース作はプログレファンは絶対聴いておいたほうがいい。特に本作はR.ベイリーがKeyとフルートを兼任するが、M4(超名曲!)の冒頭、アコギとフルートの絡みはA.フィリップスか?はたまたGenesisの「Trespass」っぽい!(雰囲気ね、雰囲気)と思ってしまうほど英国の香りがプンプンする。曲によってはメロトロンの影もチラチラする愛すべき一枚。ちなみにオリジナルLPとCD化再発版(と再発版LP)はジャケットデザインが違う。さらにFM Revolver版はR.マシューズによるイラストなのでマニア泣かせ…というのはトリビア
-
JON ANDERSON / IN THE CITY OF ANGELS

ベテラン歌手による良質なAORアルバム(5 拍手)
時期的には「Big Generator」発表の翌年、ということでまぁ稼ぐヴォーカリストだこと。当時の雑誌広告にも本作は紹介されていたのを思い出す。リアルタイムでは買わなかったけど。
90125期とはいえ、この頃のYESを期待しないほうがいい。JonのVoで80sAORを楽しめるという純粋に産業ロックが好きな人、聴ける人にはお勧めしたい一枚。
バックの面子がM.Landau、D.Huff、TOTOからはJeff、SteveそしてMikeのPorcaro兄弟、そしてD.Paich、S.Lukatherと錚々たる布陣(ほぼ全員)。プロデューサーはS.Levineって言ったらR&B、AORで名を馳せた名士。これで悪い作品ができるはずがない…んだが、まぁ売れなかった。
M1から軽やかなノリのいい楽曲。PVにはこっそり?C.Squireが登場しているので動画投稿サイトで確認してほしい。80s特有のDX7エレピがたまらんM8、M10だけは重厚な楽曲でYESっぽさがあると言えばある。
本作発表を前後する形でTOTOがアルバムを出しているがこっちにJonがゲストVoで参加。同じCBS/Columbiaというレコード会社からのリリースだったのでまぁ相互協力できたのでしょう。もちろんTOTOのほうが売上的には遥かに上だっだけど笑 ちなみに「Stop Loving You」のギターソロのパートでスキャット気味に入っているVoはJonだ。
本作がプログレファンにアピールするとしたら、「YESのJonのソロ」という一点に尽きる。普通にベテラン歌手による良質なAORアルバムとして聴いてくれたほうがJonも幸せなんじゃないかと。私は好きな一枚ですよ。ええ。 -
MARILLION / FUGAZI

Genesisクローンじゃないよ(5 拍手)
彼らに付けられたラベルは数知れず。「ネオプログレ」「ポンプロック」「Genesisクローン」…特に今更の話、彼らがGenesisクローンかというと「?」である。当時のVo、Fishがピーガブに成り切ろうとしたかどうかは別として、少なくてもGenesisの「眩惑の〜」からの影響はあったかもしれない。特にSF的な現代的ファンタジー観を盛り込んだと思われる歌詞の世界は、デビュー当時からMarillionの軸になっていたと思う。それは「月影の騎士」で童話や神話的世界に戻った(その中で現代的事象に対する比喩はあるけど)Genesisとは異なる。なので、Marillionを初めて聴く際に「Genesisクローン」という色眼鏡で入ると、肩透かしを喰らう。後々デビューする後輩達の作品と比べると素っ気なく、特徴が掴みとれない音に感じるかもしれない。ここは歌詞の意味世界を探求したり、動画投稿サイトでライブを観てGenesisとの「違い」を楽しんでほしい。
本作から元TRACEのI.モズレーがDsで加入。後年ライブの定番曲が盛りだくさんである。 -
MEN OF LAKE / MEN OF LAKE

「程よい雰囲気」を知っているバンド1st(6 拍手)
1991年の1st。当時のM紙でも広告やレビューが載っていたと思う。プッシュしていた割に売れたのかどうか・・・はさておき。
さて、イタリアのバンドで英語の歌詞。ネオ・プログレの範疇に入る。曲展開もノリを掴んで展開するので突拍子もないようなことにならない。しかも退屈しないのは、攻めるオルガンが全面に出ているからだと思う。まるで70s英国マイナーハードのようだ。オルガンの影に隠れて全体的に目立たないGtrはM6でカッコいい長めのソロを決めてくれるから安心していい。ドラムの刻みも巧み。Voは味わい深く、程よいクセがある。知らない人が聴いたら絶対70s英国のバンドの掘り出し物だと間違うと思う。M1のKeyはメロトロン?と思うほど。いや、メロトロンの音だ!と信じこんでもいいくらい、このメロディと雰囲気にドはまりのフレーズを聴かせてくれる。
とにかくどの曲もメロディがいい。そして渋いんだよね。どこかのプログレバンドを下敷きにしているというよりは、ブルース・ロックなんかをちゃんと聴いていて、そこから影響を受けていると思える。ネオ・プログレの一派にはない芯の強さを感じるのはそこかな。
ジャケットの雰囲気は完全にシンフォニックだけど、まったくそんなことはない。これはだまし討ちである。いやぁ、これは一度は聴いておいたほうがいいですよ。 -
AKRITAS / AKRITAS

「プログレ」の面白さに立ち返る一枚(6 拍手)
某M社により発掘されたと言ってよい唯一作。ギリシャのプログレは個人的に馴染みがないし、あの国はやはりVANGELISの国というイメージがある。
音的にはドカスカドラム、熱いギター、情熱のVoが近隣国、イタリアのプログレ風味を感じる。これだけでも聴く価値はある。華麗なピアノはPFMっぽさを感じつつ、M4のミュート気味のギターはジャズの風味。オルガンはK.エマーソンからの影響を受けたのが露骨にわかるのが素直でよろしい。ワイのハートをキャッチしたのはM1のオープニング、わざとチューニングをずらしたシンセ、そこに和太鼓風ドラムが絡むところ。これで名盤確定だ。至るところでモノマネ感がないわけではないが、自分たちのものに消化している印象がある。十分に楽曲のオリジナリティは感じるし、そもそもの作曲力はなかなかじゃない?
クラシカルな要素、ジャズ的要素をふんだんに盛り込んだ・・・これってプログレがプログレたる基本要素だったはず。それを思い出させてくれる一枚と言ったら言い過ぎ?おすすめ。 -
MOODY BLUES / SEVENTH SOJOURN

まぁ7日目は休んだらいいよ(7 拍手)
日本の中古LP市場を見るとムーディーズの「球数」の多さに驚く。特に国内盤はよく売れたのだろう。彼らの魅力はJ.ヘイワードとJ.ロッジという2大メロディメイカー&ヴォーカリストを擁し、ルーツをビートロックに持った甘美なメロディラインであろう。そこにコンセプチュアルな要素であるナレーションや劇的な音演出としてのメロトロン、T.タヴァーナーによるジャケットイラストも大きいかもしれない。
テクニカルではなく、ルックスも…まぁ彼らのスタイルは他のプログレ界隈とは異なり、今となっては古臭く、誰も真似しようとは思わないスタイルだ(ひどいね)。ゆえに長きにわたって活動できた唯一無二の存在だったのかもしれない。
さて、7日目の安息日はどうか。本作はメロトロンを用いず、チェンバリンを用いている。構造的には似ている(ほぼ同じ)楽器なのだが、音のテイストは結構違う。ストリングスはソリーナよりもストリングスらしく聞こえる。M3の冒頭、リコーダーの音色はメロトロンだと頭にクリック音が入るだろうが、こちらは入らない。こうした違いを過去の作品と比較して聴くのも楽しい。
全体的にはさらりとしている印象、そしてコンセプチュアルなメッセージ性は本作にはないに等しい。それでも「プログレ的なムーディーズ、最後のアルバム」としては良好な作品なのではないか。コンセプトのアイディアがなくなったわけではないだろうが、いったん仕切り直し的な作品…その仕切り直し後の作品が問題作(?)「Octave」なんだが。
このSeventh Sojurnの続編は、先述のJ.ヘイワード&J.ロッジ「ブルージェイズ」(1975年)を聴けば明らかだ。ともにお勧めしておく。 -
ヴィジターズ / ヴィジターズ

一筋縄でいかぬ宇宙交響楽団(4 拍手)
Jean-Pierre Massieraなる人物を中心とした1974年の作。Magma界隈のミュージシャンによるフレンチプログレの重要作として知られている。
Visitorsがセッションものなのか、プロジェクトものなのかわからない。オリジナルDECCA版LPが、状態まずまずで5〜6万が相場か。フランスのシンフォニック系はさらりとしていて、歌心あるもの、もしくはジャズロック系が多いような気がするんだがこれはその真逆。
粘っこいシンセ、コーラスも何だかソウルな雰囲気。収録曲Nous(「我々」)はDidier Lockwoodのヴァイオリンが冴えわたる。他の曲もゴリ押し気味で味付け濃いめなので、Boozの4枚目あたりが好みならどストライクで気に入るはずだ。
曲名も「地球」「神」「宇宙人」(地球人から見たらの「Visitors」の意味か)など、まぁあっちに行っちゃった感じでそそられる。裏ジャケットもどうかしているので注目だ。
本作1枚きりのリリースかと思ったら、1981年に2ndアルバムとシングル、1998年にもシングルが出ているんだが…なんなんだろうか。怖いもの見たさか、自分の耳を信じるか…ともあれ本作は一聴の価値あり。 -
キャラヴァン / 聖ダンスタン通りの盲犬

Pyeの声もいいよね(5 拍手)
CARAVANの声というと私の場合はR,Sinclair。朴訥として飄々としている声が私の中ではこのバンドのトレードマークなのだが、やや高めのPyeの声もいいよね。でもつい「Richardの声はまだかな…?」と登場を待ってしまう。逆にそれくらい今までの彼らのアルバムと遜色ない作品だと思う。
従来よりも管楽器とヴァイオリンのフィーチャー度合いが増えていて、さらにポップ度が上がったかな?と思いきや、1曲の中での緩急のつけ具合も見事。M4からM7は組曲風になっている。個人的には今までのファンも安心して聴ける一枚だ。
新しい収穫というと、コーラスがQueenとかELOっぽいエフェクトがかかっていてこれは今までの彼らにはなかったと思う。
あぁ、それから本作からJ.Schelhaasが参加。彼というとCAMELでの活躍を連想するが、ここでもCAMELとの関連が出てくる。プログレ界隈は世界が狭いね。一度は聴いてみたほうがいい一枚。
-
NOVALIS / VIELLEICHT BIST DU EIN CLOWN ?

はい、ピエロですがなにか?(10 拍手)
いかにも、のヒプノシスデザインのジャケットが目を引くノヴァーリスの作品。
ひんやりしたストリングスアンサンブルの活用は、フレンチ・シンフォニック系とも違う、どこか冬の曇り空を思わせる音作りに生かされているような気がする。
M5のインスト曲、City-Nordなんてまさにそれ。車を運転しながら北部ヨーロッパの景色と聴きたいものだ。
M1は前半が哀愁漂うスローな展開。そして後半はアップテンポになるという1粒で2度おいしい曲。この曲だけヴァイオリニストとしてWalter Quintus Wintherが参加。この人、そもそもジャズ畑の人だったはず。楽曲名も「ヴァイオリニスト」だしね。個人的にはアップテンポになる後半、そして終わり方もロックでいい。70年代末期、ジャーマン・シンフォの名作として称えるべき作品。
-
TANGERINE DREAM / LOGOS LIVE(LOGOS - TANGERINE DREAM - LIVE)

オリエンタルなエレクトロニカ(5 拍手)
1982年のロンドンでのライブ。MCのアナウンスに導かれて演奏が始まる。
TDは何枚かライブアルバムをリリース(Ricochet、Encoreなど)しているが、デジタルシンセを導入したライブアルバムは初だと思う。特にPPGのWaveシリーズの導入は80年代TDを象徴する音の要になっている。
この頃はHyperboreaのようにオリエンタルな音、音階を導入する傾向があったと思う。本作も妖艶でありながら悠久の時の流れを感じさせる…例えばシルクロードとかサハラ砂漠とか、何か自然と人が作り上げた歴史文化、そういうものを感じるのだ。喜多郎の影響なのだろうか…。
Part1の中盤、印象的なメロディが挟まる。これは2000年代のライブでも再現されていて、彼らの80年代以降、代表的なフレーズとしてファンに刻み込まれている。part1はゆったりめ、part2はラストに向けて躍動感を感じさせ、聴き飽きない。アンコール曲はポップなDominion。このライブ収録が行われたDominion Theatreのために書かれたのかな。明るくて分かりやすい素敵な楽曲で幕を閉じる。
C.フランケ、E.フローゼ、J.シュメーリングの3人体制時代の総決算的なライブアルバム。Ohr時代ともVirgin初期とも違うけど、魅力的な一枚。是非。 -
NIRVANA / LOCAL ANAESTHETIC

涅槃の局所麻酔(6 拍手)
ええ、もう言わずと知れた「ヴァーティゴ・レーベル一連のレア盤」の一枚。今もオリジナル盤の中古市場は10万円まではしないが、5万円以上か。わざわざLPを買い求めずとも1/100程度で買えるCDで十分だ。
さて、4thとのこと。ヘヴィ・サイケな一枚と認識している。プログレ派にはキーフのジャケットデザインが訴求するポイントだと思う。内容としては一言、Twinkの[Think Pink]を楽曲として成立させたかのような作風。Kaleidoscopeの[Faintly Blowing]から若干アクを抜いたようなというか。まぁ当時マイナーなロック界隈で聞かれたスタイルだ。生のフルートもVCS3?もハープシコードもいい味を加えているが、ジャケットのイメージとはかなり離れていることにご注意…まぁこの時期あるあるだがジャケ買いする前に視聴したほうがいい。
諸手を挙げてお勧めとは言い難いが、一度は耳にしておいてもよいと思う一枚。 -
マイク・オールドフィールド / アイランズ

爽やかで開放的な傑作(6 拍手)
南の島の物語をオーディオブックで聴いているかのような87年の作品。
空に舞う鳥の視点で捉える広大な海とそこに浮かぶ島、そんな風景が見えてくる壮大なオープニングで幕が開く。
そこへケチャやガムランの音がコラージュのように畳みかける。プログレでこれらの素材が扱われたことは過去にはなかっただろう。KeyがメインになるのだがマイクのGもしっかり前面に出ている。人間の営み、動物たち、風や砂浜や植物など様々な角度で島の風景が切り取られて再構成されていく様を耳から感じ取るような大作の余韻に浸ったあとは、どの曲もシングルカットできそうな小品曲が続く。
本作のテーマであるM3、メロディックな楽曲に力強いVo、B.タイラーをフィーチャーしたのは大正解だ。クレジットされてはいないがバックVoはM.ベーコン(GTR)で、ほぼデュエットだ。またK.エアーズのM4は木陰でハンモックを想わせる。肩の力が抜けるリゾート感を感じさせる。
南の島をテーマに扱ったプログレはおそらく唯一無二。プログレというジャンルを超えてもっと多くの人に評価されるべき作品だと思う。おすすめです。 -
IAN MCDONALD / DRIVERS EYES

Mr.Starrider(5 拍手)
プログレ畑には元キングクリムゾン、そしてマクドナルド&ジャイルズと傑作を生み出した重要人物のソロアルバムとしては初、そして最後のソロアルバムとなった。
M1は軽く疾走感のあるインストで、あとは歌もの。参加している面子の豪華さよ。久しぶりにM.ジャイルズがDs、VoにはJ,ウェットン、L.グラム、G.ブレッカー、そして本人も歌うのだが、どの曲もマイナーなメロディラインが実にたまらん。垢抜けしてなくて、肩の力が抜けている。ジャケットの写真のようになんとなく哀愁が感じられるのが実に魅力的だ。
私にとってI.マクドナルドといえばフルートなんだけど、Foreigner時代の名曲といえば1stに収録されていたStarrider、冒頭で聞けるフルートはKC時代からほとんど変わっていない。
速いパッセージでもクリアなトーンは一発でイアンのフルートだとわかる。
惜しくもこの世を去ってしまったが、Mr.Starriderの遺産として、我々の心に刻まれる一枚である。
-
KING CRIMSON / USA

KCのライブ盤、数あれど(7 拍手)
1973〜74年の4人(もしくはミューアたん含め5人)体制のライブ、公式もブートも数あれど、まぁこれ1枚あればお腹いっぱいにならずに済むかと思う。LP時代よりも局数は増えているし、音もよくなっているはず。
本作の目玉はなんだろなーと思うのだが、Asbury Parcなる即興演奏だろう、やっぱり。LPの時は突然かっこいいブルーフォードのドラムから始まった曲だ。CD化されて前半部分も収録されたと思う。
ほかの曲ではヒリヒリとしたメロトロンも堪能できる。この時期のKC、スタジオ盤(まぁ「暗黒の世界」はほとんどライブ録音だったけど)で聞けるこの「ヒリヒリ」としたメロトロン、いいよね。ストリングスとフルートくらいしか使っていないけど、それがいい。ワイにとってのKC、最後の1枚。 -
JASPER WRATH / JASPER WRATH

後々大化けするとは思えないほど牧歌的(4 拍手)
アメリカのプログレ界隈の懐の深さにはいつも畏怖の念を抱いているのだが、これもまたその一つ。
のちにプログレハードの名作、ARC ANGELをリリースするJeff CannataとMichael Soldanのコンビによるユニット。のちのちの音楽性とはかなり異なるフォーキーなシンフォニックロックを展開する。管楽器や古典的な鍵盤楽器も大活躍で、耳に優しさを感じてしまうほど。YESのこわれもの以前とか「And You And I」のフォーキーな雰囲気が好きな方は一度聴いていただきたい一枚。
個人的にはこれもあのARC ANGELに至るプロセスだったんだろうな、と思うけど、ずいぶん変わりすぎじゃね?と思う。メンバーにはH.HancockのバックバンドやC.Dionのプロデューサーとして華々しく活躍するJ.Bova、ANGELで華麗なKeyを奏でていたG.GiuffriaのバンドHouse Of LordsのVoになる、J.Christianなんかも参加していたと思う。まぁそれはそれでなかなかの作品よ。ぜひ。 -
RENAISSANCE / A SONG FOR ALL SEASONS

春待ち顔しながら耳を傾ける(9 拍手)
ルイス・クラーク指揮のRoyal Philharmonic Orchestraを贅沢にフィーチャーした本作。「四季」をテーマとし、コンパクトかつ分かりやすく練り上げた楽曲群は明るさを伴ってより洗練されたものとなる。
「Back Home Once Again」は1977年英国のTVドラマシリーズ「The Paper Lads」の主題歌。「She Is Love」はJohn CampのVoだが、ボーイソプラノ風の声質。個人的にはモネの睡蓮を観ているかのような夢心地な一曲で気に入っている。元々アニーが歌う予定の楽曲だったが、車の移動に疲れて声が出なくなってしまった彼女の代わりに3オクターブ低くアレンジをし直してJohnに歌わせたそうだ。
そして最大の聴き所はオーケストラではなくKeyを大々的にフィーチャーした「Northern Lights」。この曲はUKヒットチャート最高10位。1978年7月15日以来11週に渡りチャートイン。メロディメーカーのトップ30シングル1978年9月19日に第7位となる。壮大な雰囲気はそのままで洗練度を増した本作はアニーの美声も脂が乗り切ってまさに最高傑作といえる。
さて、これはボーナストラックが入ったESORTERIC盤なのだが、Northern Lightsのシングルエディットバージョン、そしてBBCの音楽番組出演時の生演奏バージョンも収録。そして1978年のフィラデルフィア公演のライブが10曲。難を言えばCD2枚目と3枚目で分割されており、通しで聴けないのが煩わしい。まぁそれはそれで気にしない人は気にしないのだろうが。
ヒプノシスによるジャケットも素敵だと思う。名作。 -
NIGHTRIDER / NIGHTRIDER

まぁダサかっこいいこと、この上ない(7 拍手)
1979年唯一の作。ジャケットは完全にハードロックだ。しかもレーベルはCBSと来たら、その筋のマニアには期待高まらないわけがない。
さて音のほうはというと、泣きのギターにKeyが絡むという王道パターン。M3やM4ではメロトロンらしき音も聞こえる。Voは英国人とのこと。フランス語の訛りがないので聞きやすいが、上手いとも言えない平均的である。メンバーに目を向けると、なんと元SKRYVANIAのギタリストや、元SOFT MACHINEのギタリストがメンバーとして名を連ねる。この2人のギタリストは割と奮闘している印象がある。Keyとよく絡むM5もなかなかの好ナンバーだ。
年代的には、アメリカでSTYXやTRILLION、はたまたTOTOやJOURNEYなどが活躍していた頃。フランスから「アメリカンプログレハード」への返答という感じもしなくはない。
適度にハード、適度にテクニカル、そこそこかっこいいが、アメリカのビッグネームには近くはない。それでも捨てがたい佳作なのではないか。聴いて損はないと思う。 -
U.K. / NIGHT AFTER NIGHT

最後か最高か、はたまたサイコか(14 拍手)
「ライブ・イン・ジャパン」を冠したアルバムは数あれど、プログレでは多分本作が最初なのではないだろうか…あれ?もしかしたらメジャーどころでは今もなお本作が唯一?まさかねぇ。さてさて、1979年中野サンプラザと厚生年金会館での収録をスタジオミックスした本作。後年、ブートCDやら正規で高音質盤での長編版が出回ったおかげで本作の音源の出元が明らかになった。当時、ライブに行った方の話を聞くと「とにかく音がデカいライブだった」と口をそろえて言っている。なるほど、当時のブートを聴くと確かに低音の響きがすごい。プログレとうよりもメタルバンドのライブかと思ってしまう。当然本作はライン録りでスタジオミックスしてるのでそれはわからないが、A.ホールズワースとB.ブルーフォード脱退、T.ボジオ加入後、UKは「ジャズロックバンド」から「アリーナロックバンド」になった証拠が本作なのではないだろうか。
M1では合いの手の拍手は入り、観客との一体感を感じさせる。M2のイントロが始まるや否や拍手、M3に入る直前に「ドウモ!コンバンハ!」。よく聞くとM3のイントロにも観客の歓声がミックスされている。そしてラストM9の前にあの名台詞「キミタチサイコダヨ」は界隈では物議を醸しだした。あれば「最後」か「最高」か、はたまた「サイコ」かと。本作の収録曲の順番からいうと「最後」だし、さしあたり本作で解散していたわけなので「最後」が正しいという人がいた。でもそれは後年出たブートやらで明らかになったとおり、実際ライブに行った人の証言からもそうではないのがはっきりしているので、これはX。
じゃあ「最高」か、というと、そりゃ最高でしょうや。タイトでコンパクトでビシビシ難解なフレーズを決めていく彼らのライブはいくら編集されているとはいえ、完成度は強烈に高い。これは間違いなく「最高」だ。
さて私の口の悪い友人は「いや、あれはサイコだったわ」と。エディはアイドル視され、会場内は黄色い歓声が飛び交っていたという。彼らも空港にファンの出迎えがって「我々はビートルズか何かになったのかと勘違いした」という証言がある。まぁジョンは狂乱的なファンに対して「キミタチサイコダヨ」と言ったのはあながち間違いじゃない、と。なるほどねぇ。
M9の「サヨナラ!」の後のアンコールを促す手拍子からわかるように、まぁ日本でのサイコな盛り上がりがわかる(編集をされた)ライブアルバムだ。最高だよ。