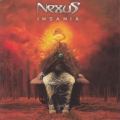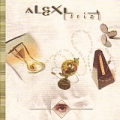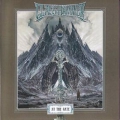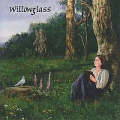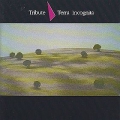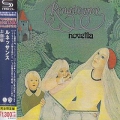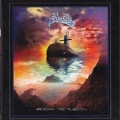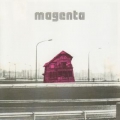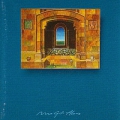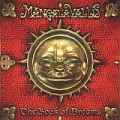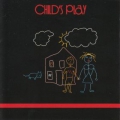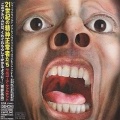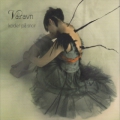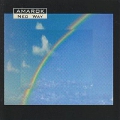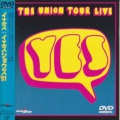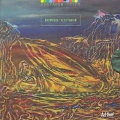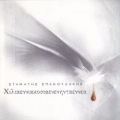プログレッシヴ・ロックの中古CD豊富!プログレ、世界のニッチ&ディープな60s/70sロック専門ネットCDショップ!
13時まで当日発送(土・日・祝は翌日)、6,000円(税抜)以上送料無料
-
カテゴリー
-
プログレ
- 60s/70s/80sプログレすべて
- ブリティッシュ・プログレ
- イタリアン・プログレ
- フレンチ・プログレ
- ジャーマン・プログレ
- 北欧プログレ
- 東欧・露プログレ
- その他ユーロ・プログレ
- 南米プログレ
- 北米プログレ
- ジャパニーズ・プログレ
プログレ新鋭
ロック&ポップス
ハード・ロック
ジャズ・ロック
-
- トップ
- 国内中古CD
- 輸入中古CD
- 新品CD
- 新品LP
- セール
- ベストセラー
- レコメンド
- ジュークボックス
-
ロック探求特集
- ロック潮流図鑑:黄金の60年代特集
- プログレッシヴ・ロック入門特集
- イタリアン・ロック特集
- プログレ新鋭特集「プログレ温故知新」
- アメリカン・ロック特集
- ブリティッシュ・ジャズ・ロック特集
- カンタベリー・ミュージック特集
- ブリティッシュ・ハード・ロック特集
- ブリティッシュ・フォーク特集
- スワンプ・ロック/ルーツ・ロック特集
- アメリカン・フォーキー・ミュージック特集
- アメリカン・ブルース・ロック特集
- サザン・ロック特集
- フュージョン・ロック特集
- 日本のニューロック特集
- サイケデリック・ロック特集
- ブラス・ロック特集
- グラム・ロック特集
- NYパンク・ロック特集
- イスラエル・ロック特集
- イタリアン・カンタウトーレ特集
- Webマガジン
yes_90125さんのレビュー
-
NEXUS / INSANIA

正統派シンフォと呼ぶに相応しい(0 拍手)
アルゼンチンを(南米を)代表するシンフォ・バンドNEXUSの6年ぶりとなる新作。
NEXUSはあまり聴いてこなかったのですが、これは良いです!
1曲は4〜5分でコンパクトにまとまっていますが、冒頭からドラマティックな始まり方で正統派シンフォと呼ぶに相応しい内容になっています。
インスト曲とヴォーカル曲のバランスも良く、すっと入って来るメロディに女性ヴォーカリストROXANA TRUCCOLOの伸びやかな美声。
そして、プログレ然としたシンセやオルガン、クラシカルな音色のピアノも印象に残ります。
ギターには少しスティーヴ・ハウぽさもあり、EL&PにYESのきらびやかさがプラスされたようなサウンドとでも表現すれば良いのでしょうか!?
きっと、女性ヴォーカル・ファン、キーボード・ファンにはど真ん中のストライクだと思います。 -
ALEXL / TRIZ

様々な要素が詰まっています(0 拍手)
全体的にはゆったりとした叙情的なサウンドでありながら、よく聴くと結構複雑な構成になっています。
ピアノとアコースティック・ギターを中心にフルート、チェロ、オーボエなども加わり、自国語のヴォーカルもクセがなくて聴きやすい。
コメントでGENTLE GIANTに例えていることも納得ですが、ギターに少しスティーブ・ハウっぽさもあり、コーラス・ワークも見事です。
女性Voによる上品な6曲目、チェンバー・ロックやジャズ・ロックの要素もある7曲目、「Siberian Khatru」が見え隠れする8曲目など聴きどころ満載。
シンフォ・ファンからジャズ・ロック・ファンまで幅広いファン層に受け入れられるであろう好作品。 -
GLASS HAMMER / AT THE GATE

JON DAVISONがゲスト参加しています♪(0 拍手)
Glass Hammerはメンバー・チェンジを繰り返しながら、毎年のようにアルバムを発表している多作なバンドですが、本作は前2作「Dreaming City」「Skallagrim-Into the Breach」と合わせた3部作の完結編という位置づけになっているようです。
地味目なジャケットとは異なり、厳かなパイプ・オルガンが鳴り響くドラマチックな始まりになっており、例えるならばやはりYES風のシンフォ・ロックということになるのでしょうか。
ハードなギターや重めのベースが近年のバンドらしさを持ち合わせていて、単なるYESフォロワーには収まっていませんし、過去作でも聴かれたようにオルガンの音色で少しだけEL&Pも加わります。
過去にバンドに在籍していたJON DAVISON(現YES)がゲスト参加している7曲目、ピアノが印象的な8曲目、幻想的なメロトロンやコーラスワークが冴えている13分超のラスト曲など終盤の展開が特に素晴らしいです。 -
LIZARD / SPAM

ヴァイオリンの存在感が増したクリムゾン・タイプのアルバム(0 拍手)
ポーランドのバンドLIZARDの4thアルバムで、「SPAM#1」から「SPAM#6」の6曲が収録されています。
この人たちは曲名に対するこだわりがないのかこういうパターンが多いのでわかりませんが、コンセプトを持ったアルバムなのかもしれません。
LIZARDのサウンドはクリムゾンに例えられることが多いですが、本作もその傾向は変わりません。
しかし、前作までと比較すると華麗なヴァイオリンが主旋律を取る場面も多く、その存在感が高まっています。
彼らの特徴のひとつであるヘヴィなギターとの掛け合いもカッコ良く、かと思えば一転して穏やかな曲調のポーランドらしいメロディも聴かれます。
これまでのLIZARDファンには新たな一面を見せてくれると思いますし、ヘヴィ・シンフォの一言では語り切れない魅力を持ったアルバムだと思います。 -
WILLOWGLASS / WILLOWGLASS

英国らしい正統派シンフォ・ロック作品(0 拍手)
マルチ・プレイヤーであるANDREW MARSHALLとドラムのDAVE BRIGHTMANによるユニットながら、完全にバンド・スタイルのサウンドになっているWILLOWGLASSのデビュー・アルバム。
最初に聴いた時のバンド・イメージはキャメルでしたが、改めて聴いてみるとジェネシス・ファンにこそ聴いて欲しい作品だと思います。
キーボード好きにとっては全編に亘って使用されているメロトロンやオルガンはもちろんピアノの印象も強いのですが、アコースティック・ギターやフルートの音色も欠かすことが出来ない魅力のひとつになっています。
9曲目の「Waking the Angels」ではイエスのようなきらびやかさもあり、まさに英国らしい正統派シンフォ・ロック作品です。 -
TRIBUTE / TERRA INCOGNITA

北欧を代表するシンフォ作品(0 拍手)
北欧を代表するシンフォ・バンドTRIBUTEの4作目。
同傾向の作品として、ISILDURS BANEの「CHEVAL」やFUGATO ORCHESTRAの「Neander Variaciok」あたりが思い浮かびますが、こちらの方がより多彩な要素を含んでいるように思います。
チェロ、ヴァイオリン、フルート、オーボエなどの管弦楽器によるクラシカルな演奏に、トラッド、ニューエイジ、ケルト、エスニック色も加わります。
北欧のバンドを評する時よく使われる「透明感」「清涼感」という表現がぴったりなサウンドで、ピアノやギターのアコースティックな演奏、美声女性ヴォーカルをフィーチャーした曲のポイントも高い!
ラストのタイトル曲は20分超えの大作。
弦楽器による哀愁のメロディから始まり、打楽器の使い方が印象的なエスニック調、ピアノと弦楽器によるクラシック風の展開を経て、少しオールドフィールドを思わせるギターがリードする終盤を迎えます。
全体的には上品で大人しめな印象ですが、決してイージーリスニングにはならず、やはりシンフォ・ロックと呼ぶのが相応しい作品だと思います。 -
FLEUR / PRIKOSNOVENIE

クラシカルな趣のあるウクライナの女性Vo作品(0 拍手)
ウクライナの女性Voグループ。
ピアノのOLGAとギターのELENAが作詞・作曲を手掛けており、2人の曲が交互に並んでいます。
グループ・メンバは、ベース、パーカッション、フルート、チェロを加えた6人編成。
何曲かでゲストも加わっているようですが、楽器構成からもわかるようにクラシカルな趣のあるアコースティックなサウンドで、哀愁を帯びたメロディーがウクライナらしいと思います。
OLGAとELENAはヴォーカルも担当していて(タイプは異なるけれど)ふたりとも美声で、ささやくような繊細な歌声が切ないのです。
私が初めてFLEURを聴いたのは確かにこのアルバムなのですが、デビュー作だとは知りませんでした。
絶対的な信頼を置いている「ウクライナの女性Vo物」という理由だけで購入したのかもしれませんが、デビュー作からしっかりチェックしている自分を褒めてあげたい!
全ての女性Voファンにおススメです。 -
アラン・パーソンズ・プロジェクト / アンモニア・アヴェニュー

PVも話題になったAPPの代表作(0 拍手)
初期のコンセプト重視の創作からポップ路線に移行して成功した前作「Eye In The Sky」に続く80年代らしい華やかさと上品さを併せ持った7thアルバム。
エンジニアであるアラン・パーソンズと、バンドのコンセプトを支えるエリック・ウルフソンによるプロジェクトがひとつの到達点に至った作品ではないかと思います。
エリック・ウルフソンのヴォーカルが印象的でメル・コリンズ(サックス)が参加しているファースト・シングル「Don't Answer Me」をはじめ、シングル曲「You Don't Believe」、「Prime Time」も収録されており、まさに代表作と呼ぶにふさわしい。
メル・コリンズは唯一のインスト曲である「Pipeline」にも参加しており、シングル・カットされていないと思いますがタイトル曲もAPPらしい良曲。
アメリカン・コミック風のPVも話題になりました。 -
アトール / ロック・パズル

少しポップになったけれどカッコいい!(1 拍手)
ATOLLの代表作を問われたら2ndか3rdを選ぶファンが多いのではないかと思います。
個人的にはATOLLを初めて聴くのであれば、メロディ重視で聴きやすい3rdだと思っていたのですが、実は一般受けするのは、この「ROCK PUZZLE」なのかもしれません。
私は3rdが大好きなので、このアルバムを聴いた時には「ポップになったなぁ」と感じましたが、管弦楽入りで華やかさを加えつつ、演奏やコーラスなどATOLLらしさも失われてはいません。
そして、あらためてAndre Balzerのヴォーカルの魅力に気づいたりもします。
ボーナス・トラックはアルバム収録曲の別ヴァージョンや、当時加入が噂されていたJohn Wettonが参加しているデモなど6曲。
John Wettonも好きなのでとても興味深いけれど、Wettonがメインヴォーカルを取ってしまったら、最早ATOLLではない感じがします。
後にASIAのアルバムに収録される「Here Comes The Feeling」の聴き比べは面白いかもしれないけどね!?
ということで、ボーナス・トラックはあくまでオマケとして楽しむのが正解だと思います。 -
LIZARD / PSYCHOPULS

クリムゾン・ファンには無条件におススメ!(0 拍手)
ポーランドのバンドLIZARDの2nd。
バンド名からもわかるようにクリムゾンを継承するサウンドで、96年発表のデビュー・アルバムから8年の歳月をかけて作成されたアルバムはかなり緻密に計算された構成になっている。
全体的にはヘヴィーな印象ながら、短いインスト曲やバラード調の曲も含まれており、メリハリがあるのも好印象。
「レッド」を例えに挙げるのはとてもわかりやすく(少しだけ「ディシプリン」も入っている)、クリムゾン・ファンには無条件におススメ!
特に、ヴァイオリンが効果的でクリムゾンのアルバムに入れても違和感はないであろう2曲目や、テクニカルな演奏で11分越えのラスト曲あたりは、なかなかの衝撃。 -
ルネッサンス / お伽噺

RENAISSANCEの代表作(0 拍手)
シンフォニック・ロック・ファンが美声女性Voを問われて、誰もが最初に思い浮かべるのがAnnie Haslamだと思います。
バンド・イメージの例えとして挙げられることも多いRENAISSANCEですが、彼らの作品の中でも名盤中の名盤が「NOVELLA」です。
女性Voファンはストリングスや合唱が印象的な1曲目「Can You Hear Me?」で虜になってしまうことは間違いありません。
Annie Haslamの伸びやかな美声と合わせて、所々で聴かれるピアノやアコースティック・ギターもポイントで、すっと入って来るメロディが美しい。
私が初めて聴いたRENAISSANCEのアルバムなのでそれなりに思い入れもありますが、それを除いたとしても、やはり聴き逃すことが出来ないアルバムの1枚だと思います。
名曲揃いで、何度聴いても飽きることはありません。 -
TRIUMVIRAT / OLD LOVES DIE HARD

ジャケットのネズミが小さくなった(0 拍手)
大作志向の2nd「ILLUSIONS ON A DOUBLE DIMPLE」、完全にELP化していた3rd「SPARTACUS」に続く4thアルバム。
TRIUMVIRATのアルバムとしては前2作の評判が高いと思うのですが、ジャケットのネズミが小さくなったこちらも捨てがたい良作です。
前作までと比較するならば、若干ヴォーカル・パートが増えている点とピアノが奏でる旋律が特徴的です。
バンドとしての独自路線に踏み出した時期だと思いますが、「ドイツのELP」と評されるサウンドは変わらず、より洗練されてきた印象があります。
新たに加わったヴォーカルはレイクより高音で線が細いのですが、どうしてもELPを追い求めてしまうファンの方には6曲目の「PANIC ON 5TH AVENUE」がおススメです。
ボーナス・トラックは同時期に発表されたアルバム未収録のシングル曲で、こちらもピアノが印象的です。 -
SILHOUETTE / ACROSS THE RUBICON

オランダのバンドらしい正統派シンフォ作品(0 拍手)
最初聴いた時に「SILHOUETTEって、こんなに良かったっけ!?」と思った3rdアルバム。
バンド構成が変わったわけでも、メンバー・チェンジがあったわけでもないのにここまで劇的に進化するものでしょうか?
もしかしたら過去作の聴き込みが足らなかったのかもしれません。
すでに手放してしまったのですが・・・。
如何にもオランダのバンドらしいタイトル曲から始まり、ヴィンテージ感のあるオルガンや美しい音色のピアノも操るキーボードと力強いギターによるドラマティックな曲が続きます。
キャメルを思わせる泣きのメロディも好感度が高く、メンバー4人のうちの3人が代わる代わるリード・ヴォーカルを取っていることが曲の印象の変化をもたらしています。
それが、繰り返し聴いていても飽きが来ない要因のひとつなのかもしれません。
厚みのある演奏で10分超えの長尺曲とコンパクトな曲がバランス良く配された正統派シンフォ作品だと思います。 -
MAGENTA / MAGENTA

具体的には語れない良さというものもあります(0 拍手)
イギリスのMAGENTAのアルバムなのかと思ってコメントを読んだらベルギーのポップ・バンドとのこと。
74年発売かぁ・・・とは思いましたが、FISH ON FRIDAYを知ってからベルギーのポップ・シーンは侮れないとも感じているので聴いてみました。
ヴォーカル・パートが多い歌物で、「イタリアのカンタゥトーレ作品にも通じる」という例えは的を射ていると思います。
自国語のヴォーカルも思っていたほどクセはなく、メロディアスな曲調に合っています。
演奏に関してはあまり派手さはないのですが、クラシカル志向のオルガンと、アコースティック&ハードを使い分けるギターの組み合わせが、なんか微妙に良いです。
オルガンが前面に出てくる7曲目や12曲目にはプログレ・ファンも捕らえられてしまうかもしれません。
2〜3分程度の曲が並び、アルバム全体で40分程度なので若干物足りなさを感じますが、発表年を考えればこんなものでしょう。
アコースティックな曲や少しコミカルな印象の曲もあり、なかなか楽しめました。
リマスターで音も良いのです。 -
AFTER CRYING / OVERGROUND MUSIC

繊細で美しいアルバム(0 拍手)
AFTER CRYINGが90年に発表した1stアルバムということで聴いてみました。
CSABA VEDRESのピアノを中心にチェロ、フルート、オーボエ、ヴィオラ、トランペットなどを加えた演奏で、3rd「FOLD ES EG」以降のロック色が強い作品に比べるとクラシカル寄りですが、ジャズ、チェンバー要素も包含している佳作だと思います。
曲によってリード・ヴォーカルを取っているメンバーが異なりますが、ラストの10分超えの曲ではJUDIT ANDREJSZKIがリード・ヴォーカルを取っていて、女性Voの歌声とシリアスな演奏が相俟ってROBERTO CACCIAPAGLIAの「GENERAZIONI DEL CIELO」を思い起こしました。
あまりに繊細で美しい。 -
トレース / ホワイト・レディース

大作志向のコンセプト・アルバム(0 拍手)
前作からメンバー交代があり、トリオ編成からサックス/フルート、キーボード、専任ヴォーカリストなどを加えた7人体制に代わった最終作。
TRACEが残した3枚のアルバムはどれも素晴らしいですが、少しずつ作風が異なっているように思います。
その中でこのアルバムをひとことで言い表すならば、大作志向のコンセプト・アルバム。
ストリングス・オーケストラを加え、途切れ目なく紡がれていく曲はリストを意識しなければ1曲の中で展開が変わっていくように聞こえます。
「悲愴」のフレーズを取り込んだ曲などピアノの音色も印象的ですし、サックスも過去作にはない新たな効果を生み出しています。
クラシカル・ロックを体現したような前作から、優美さを前面に押し出したシンフォ・ロックに変化していることもあり評価は分かれると思いますが、このアルバムを彼らの最高傑作とするファンも多いのではないでしょうか。
トレースのみならず、オランダの音楽シーンを語る上でも欠かせない1枚だと思います。 -
MR.GIL / ALONE

COLLAGEサウンドを継承(0 拍手)
昨年復活したCOLLAGEのギタリストMirek Gil(最新作には参加していませんが)のソロ・・・というより彼が新たに立ち上げたバンドと言うのが正しいかもしれません。
その後のBELIEVEやSATELLITEへの参加もあり別プロジェクトで動き出したのかと思っていましたが、メンバーや作風を変化させつつMR.GILとしての活動も続いています。
本作について言えば、メンバとして参加しているベースとキーボードが元COLLAGEですし(音楽性の相違で解散したはずなのに・・・!?)、彼のギターもバンドの魅力のひとつだったので、発売当時は「COLLAGEの新作」的な紹介のされ方もしていました。
COLLAGEを継承しつつコンパクトで聴きやすくなり、ヴォーカリストの声質もあって、よりメロディアスで叙情性が高くなった印象ですが、その分壮大さは影を潜めたと言えなくもありません。
しかし、COLLAGEファンには無条件に受け入れられるはずですし、「叙情」とか「哀愁」という言葉に反応してしまう人はきっと好きになるアルバムだと思います。 -
PANIC ROOM / VISIONARY POSITION

幅広いファン層におススメできる女性Voシンフォ・アルバム(0 拍手)
KARNATAKAのメンバーを中心に結成されたPANIC ROOMのデビューアルバム。
当時のKARNATAKAの作風からすると異なるアプローチの作品のように思えましたが、その後シンフォ路線に舵を切ったバンドの方向性には近いかもしれません。
個人的にはバンドではハーモニーの役割に回ることが多かったANNE-MARIE HELDERの美声を十二分に聴けることがうれしいです。
英国らしい美しくメロディアスなサウンドで、JONATHAN EDWARDSの漂うような穏やかなキーボードとピアノの音色との対比や、ゲスト参加しているLizzie Prendergastのエレクトリック・ヴァイオリンも効果的です。
KARNATAKAやIONAを思わせるケルト色も聴かれ、アルバムのクライマックスを迎えるラストは19分弱のシンフォ曲。
KARNATAKAファンはもちろんのこと、シンフォ・ファン、女性Voファンなどに幅広くおススメ出来るアルバムだと思います。 -
MANGALA VALLIS / BOOK OF DREAMS

デビュー作にして最高傑作(0 拍手)
大袈裟な言い方をすれば、プログレはジャケットも含めた総合芸術だったわけですが、MANGALA VALLSのこのジャケットはあまりにもイケていません。。。
今のように情報が多くはなく、ジャケット・イメージと自分の勘だけを信じてアルバムを購入していた時代であれば手を出すことはなかったのではないかと・・・。
何が言いたいかというと、ジャケット・イメージに惑わされてはいけませんよということです。
メロトロン、ハモンドオルガンなどヴィンテージ感があり、キーボード好きな人にはおススメ。
00年代に発表されたとは思えないほどに70年代への憧憬が詰まっていて、きれいなコーラスワークやギターの音色はサードアルバムあたりのYESファンにも訴えかけるのではないかと思います。
イタリアのバンドのアクの強さに魅了されている方にはおススメしないのですが、すっと入ってくるメロディアスなサウンドは好き嫌いは分かれないのではないかと思います。
2nd以降のアルバムも良いですが、個人的な感想としてはきれいにまとまり過ぎていると思うので、今のところデビュー作にしてMANGALA VALLISの最高傑作です! -
CHILD'S PLAY / CHILD'S PLAY

ジャズ・ファンにもおすすめです(2 拍手)
このCDは気になるリストに入れておいたけれどなかなか再入荷しませんでした。
しかし、CDショップで子供の落書きのようなこの可愛らしいジャケットを見つけ、これは千載一遇のチャンスと購入・・・大正解でした。
メンバーのテクニックは申し分なく、ピアノとベースは明らかにジャズ寄り。
ドラムを加えてピアノ・トリオのジャズ・バンドと言っても良いくらいですが、ギターが参加するとジャズ・ロック色が強くなります。
ピアノも流麗なメロディを奏でている時にはジャズ風なのですが、打楽器よろしく力強く、高速で弾き込むところではロックしています。
何気なく裏ジャケットを眺めていたらSTANLEY CLARKEの名前も並んでいます。
やはり、ジャズ畑の人たちなのでしょうね。
ロック・ファンのみならず、ジャズ・ファンにもおすすめできると思います。 -
KHARMINA BURANNA / SERES HUMANOS

ペルーのバンドに対する認識が少し変わった(0 拍手)
ペルーのバンドと言えば情熱的で泥臭いという個人的なイメージがありました。
少しハードなギターなどは正にそのイメージに近いのですが、きれいな音のピアノや、ハモンド・オルガンなどを駆使するキーボードにシンフォ色があり、まとまりの良い曲構成で取っつきやすい作品となっています。
全体的にはインスト曲が中心ですが2曲だけ女性Voが入っていて、歌心のある美声を聞かせています。
アコースティック・ギターで始まる「Sublime Muerte」やピアノ・ロック的な「10:27」も良いですが、プログレ・ファンにはやはりラストの大曲「Lenguas De Trapo」がおすすめでしょうか。
ペルーのバンドに対する認識が少し変わりました。 -
COLOR / COLOR

一聴するとポップな印象がありますが完成度は高いです(0 拍手)
「ハンガリーのシンフォ・バンド」という紹介コメントを見て購入した記憶があります。
当然のことながら78年のリリース時ではなく、この再発盤です。
そこまで演奏テクニックを前面に押し出しているわけではなく、ヴォーカル・パートも多いので一聴するとポップな印象があります。
しかし、キーボードは東欧のバンドらしい哀愁を漂わせ、弦楽器が奏でるメロディにはハンガリーのバンドが持つクラシカルな一面も顔を出します。
聴き返してみれば、リズム隊もテクニカルで安定しています。
そして、アルバム・ラストは14分超えの組曲「Panoptikum」。
変化が激しくドラマティックな展開の曲で「いきなり、どうした!?」というくらいにプログレ・バンドの本領を発揮するのです。
ほぼ無名のグループということですが、発掘した人もすごいと思います。 -
モルゴーア・クァルテット / 21世紀の精神正常者たち

くれぐれも心してかかるように!(0 拍手)
東京フィルハーモニー交響楽団に所属していた荒井英治さんを中心に、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、NHK交響楽団という名立たるオーケストラに所属する実力者が揃っているモルゴーア・クァルテット。
弦楽四重奏でロックをやろうと思うこと自体が尋常じゃないけれど、そのカバー曲がプログレ大御所バンドの曲ともなればさらにハードルは上がります。
プログレ・ファンは厳しいから・・・。
しかし、そんな心配は無用。
ライナーノーツに寄稿している荒井さんの「ロックを弦楽四重奏でカバーすること自体に無理がある(中略)でも、できる!」という強い決意のもとに演奏された楽曲はどれも素晴らしい!
コンサート・マスタ・レベルのメンバーが集まっているので、その演奏力はお墨付きですし・・・。
これも引用になってしまうのですが、「弦楽四重奏というものは、書き過ぎると音が濁るので避けるのが書法の基本」らしいですが、あえて「濁らせるために詰めるだけ詰めた」そうです。
オーケストラによるロック曲のカバー・アルバムも発売されていますが、どうしてもイージー・リスニング調に無難にまとまっているものが多いのではないでしょうか?
でも、モルゴーア・クァルテットはロック・バンド(と言い切ってしまう!)です。
取り上げられているのは、クリムゾン、ジェネシス、イエス、EL&P、フロイド、メタリカ。
メタリカは聴いたことがありませんでしたが、荒井さんによれば「プログレの遺伝子を受け継いでいる」とのことです。
とは言いつつも、ジャケット・イメージからも分かるように、このアルバムの聴きどころはやはりクリムゾンなんでしょうね。
「クリムゾン・キングの宮殿」は原曲と比べても全く見劣りしませんし、ラストを飾る「スターレス」は、ここにウェットンのヴォーカルが重なったら・・・などと思いを馳せてしまいます。
最後に荒井さんからの「このアルバムは、くれぐれも心してかかるように!」という一言を添えておきます。 -
スティング / ナッシング・ライク・ザ・サン

スティングを聴こうと思ったならばまずはコレです!(0 拍手)
STINGのアルバムの中でも一般的な評価が高く、個人的にも大好きなアルバムです。
前作「ブルー・タートルの夢」のジャズ・テイストを引き継ぎつつ、ポリス・ファンも納得のいく作品ではないかと思います。
エリック・クラプトン、アンディ・サマーズ、マーク・ノップラーなど豪華な参加アーティストも注目されますが、演奏面ではそこまで主張していない感じがします。
モノクロのPVも印象的な名曲「Englishman in New York」、CM(確か本人も出演していた)に使われていた「We'll Be Together」、ジミ・ヘンドリックスの「Little Wing」、そして絶対に外せない「Fragile」。
どの曲がシングル・カットされてもおかしくない良曲揃い。
STINGを聴こうと思ったならば、まずはこれだと思います。
-
ラレ・ラーセンズ・ウィーヴワールド / ナイトスケープ

プログレ・ファンは聴き逃してはいけない(0 拍手)
KARMAKANICのメンバーでAGENTS OF MERCYのアルバムにも参加しているLALLE LARSSONが率いるシンフォ・バンド。
バンド名に自身の名前を冠するだけあって、彼が全ての曲を書き、アレンジも担当している。
冒頭からメンバーのテクニックがぶつかり合うインプロヴィゼーションを展開。
テンションが高い掛け合いで聴かせるギターに圧倒されるけれど、それを支えるリズム隊がまたスゴイ。
疾走感のあるロック・ナンバーで一気に押し切るのかと思えば、ピアノとアコースティック・ギターのみの「Nocturne」では繊細で物悲しいメロディを奏で、24分超えのタイトル曲では緩急の効いた緻密な構成で長尺の曲を飽きさせずに聴かせる。
テクニカルなメンバーが揃っているので曲によってはジャズ・ロック的な要素もあり、重厚な演奏は下手なハード・プログレなど一蹴してしまう。
それでいながら、北欧のバンドらしい叙情性を失っていないところも魅力。
メンバーの演奏のバランスが良いアルバムで、LALLE LARSSONのひとりバンドになっていないところも好感が持てる。 -
ジェイムズ・ブラント / バック・トゥ・ベッドラム

色褪せることはない美しく切ないメロディ(0 拍手)
James Bluntを知ったきっかけは覚えていないのですが、初めて聴いた曲は間違いなく「You're Beautiful」だったと思います。
全英チャートNO.1のヒット曲なので・・・!
帯の紹介文によればシングルとともに「6週連続同時全英NO.1という快挙」を達成したのがこのデビューアルバム。
ライナーノーツには、キャンペーンなどを大々的に行うなどレコード会社が仕掛けて売れたのではなく、発売から9か月かけてチャート1位に上り詰めたということが書かれていて、これは純粋に曲の良さが聴く人の心に響いた証しだと思います。
アコースティック・ギターやピアノをメインにしたバックの演奏に派手さはありません。
しかし、そのシンプルさがJames Bluntの歌声に合っていて、曲の魅力をさらに高めていると思います。
美しく切ないメロディ。
2004年発売なのですでに20年近く経っていますが、今聴いても全く色褪せることはありません。 -
VALRAVN / KODER PA SNOR

ビョーク・ファンは聴いてみて下さい(1 拍手)
これもジャケ買いだったような気がします。
輸入盤で購入した時には全く知らなかったので「見つけた」感がありましたが、実は国内盤も発売されているのでメジャーなアーティストなのかもしれません。
知識不足でラジカル・トラッドとはどのような音楽を指し示すものなのか理解できていませんが、このアルバムの印象としては女性Voエレクトリック・ロックです。
ジャケットのしっとりした印象とは異なり意外とダンサブルな曲が並んでいるのですが、ヴォーカルのAnna Katrin Egilstrodはビョークを思わせる浮遊感のある美声で女性Voファンにもおススメ出来るのではないかと・・・。
フルートや弦楽器、アコギが奏でるメロディが効果的でケルト色も感じられ、厳かなコーラスに彩られたラストの「Farin Uttan At Veroa Vekk」はシンフォ・ファンも捕らえる佳曲だと思います。 -
AMAROK / NEO WAY

キャメル色が加わった2ndアルバム(0 拍手)
デビュー作もフロイド+オールドフィールドという印象でしたが、この2ndアルバムではオールドフィールド色が強くなったように思います。
ゲストでCOLIN BASSが参加していることもありキャメル色が感じられることも確かです。
2曲目のメロディアスな曲はキャメル・ファンにおススメ(この曲良いです!)。
3曲目はアコースティック・ギターのソロによる小曲。
4曲目ではラティマー風のギターが聴かれ、そうかと思えば5曲目、9曲目あたりはオールドフィールド節全開で、6曲目のピアノソロはとてもピュア。
7曲目はオールドフィールド+キャメルにフロイド的なアレンジを盛り込んだ感じでしょうか。
前作でも聴くことが出来たポーランドのバンドらしい美しい女性Voコーラスも加わり、多彩な曲が揃っています。
AMAROKはアルバムごとに作風が少し異なります。
1stはインスト作品と言っても良い内容でしたが、本作ではCOLIN BASSの参加もありヴォーカル・パートが増えています。
Michal Wojtasは作曲やアレンジはもちろん演奏もほぼひとりでこなしおり、シンフォ・ファンの琴線に触れるこのメロディ・センスは見事です。 -
HORIZONT / PORTRAIT OF A BOY

好き嫌いは分かれそうですが・・・(0 拍手)
20分近い1曲目を聴いて「何これ?」状態になるHORIZONTの2ndアルバム。
とにかくぶっ飛んでいて、実験的、即興的な一面もあるので好き嫌いが分かれそうですが、キラキラしたキーボードが少しウェイクマンを思わせる音色なので個人的にはそこもお気に入りのポイント(しかし、YESサウンドではありません)。
重量感のあるサウンドの中にクラシックっぽいフレーズが聴こえてきて、メンバーはそういう素養を持った人たちなのではないかと思います。
何々風とか他のバンドに例えようもなく、この音を表現する語彙力もないので、聴いて判断してもらうしかないのです。 -
AVIVA OMNIBUS / NUTCRACKER IN FURY

バンド構成でプログレ度は高まっています(0 拍手)
前作ではゲストにヴォーカリストを迎えながらも演奏に関しては Dimitri A. Loukianenkoのマルチプレイによるアルバムでしたが、AVIVA OMNIBUS名義でリリースされた本作ではキーボードに専念し、バンド体制で制作されています。
その効果もあってヘヴィで重厚感のある曲は、よく比較されるLITTLE TRAGEDIESに接近していますが、逆にキーボードの演奏が控えめになっているような気がしなくもありません。
1曲がコンパクトにまとまっているので、前作のどこに連れて行かれるかわからないような展開の面白味は薄れていますが、プログレ度は高まっています。
キーボード好きな人には前作、プログレ・ファンには本作という評価で良いかと思います。
ロシアにはエマーソン?な人が多いのですが、キーボード・ファンはそれなりに楽しめるのではないかと思います。 -
エア・サプライ / グレイテスト・ヒッツ

エア・サプライを聴いて暑い夏を乗り切ろう!(0 拍手)
プログレ・ファンにはセバスチャン・ハーディーで知られているオーストラリアですが、一般的な音楽ファンにはあまり注目されていなかった国なのではないかと思います。
有名どころではオリビア・ニュートン=ジョンやビージーズがオーストラリアのアーティストとして紹介されていますが、活動拠点は英米でその認識は薄いと思います。
そんな中、80年代初頭に登場したのがエア・サプライ。
「ロスト・イン・ラブ」、「シーサイド・ラブ」、「さよならロンリー・ラブ」などがヒットし、80年代前半のチャートを席捲しました。
80年代を通過してきた人にとっては懐かしくもあり、「ペパーミント・サウンド」というキャッチフレーズそのままに爽やかで親しみやすいメロディは猛暑の夏を乗り切るのに最適です。 -
イエス / ショウズ’91

8人YESによる貴重なライブ映像(1 拍手)
ABWHと本家YESが合流した8人YESによるライブ。
ツアーに合わせてリリースされたアルバム「結晶」の評価は良くなかったけれど、世界一周80日間ツアーの方は成功だったと言われています。
アンダーソンは夢見人なので、YES結成の何十周年かの時にも「過去にYESに在籍したメンバーを全員集めてライブをやりたい」というようなことを言っていました。
全員ではないにせよ主だったメンバーが揃った8人YESは夢が叶った瞬間でもあり、ライブでも活き活きしています。
それに反して淡々としているのがブルーフォード(この表記はなかなか馴染めない・・・)。
元々、YESやクリムゾンへの参加は自分が好きな音楽をやるための資金稼ぎみたいなものだと公言しているくらいだし、この強引な合体劇には思うところもあったのでしょうが、来日公演前には脱退の噂も飛び交いました。
そして、8人体制での来日公演は実現したものの、それは現実のものとなってしまいます。
その後、ハウとウェイクマンも脱退し、気がつけば90125YESに戻っていたという幻のようなひと時のライブです。
来日公演も観に行きましたが、アルバム同様にふたチームに分かれていて、70年代の曲はABWHメンバーが中心、80年代の曲は本家YESメンバー中心に演奏されている感じは否めませんでした。
そんな中で、ツアーに出たくて合体劇に賛同したラビンはとても楽しそうで、ウェイクマンとの掛け合いなど「やっぱり、ラビン上手いんだな!」と思いました。
ふたりの仲が良いことは知られていて、それが後々のARWに繋がるのでしょう。
収録時間は120分なのでほぼライブ1本まるごと収録されているのだと思います。
YESのライブ定番曲とメンバーのソロで構成されていて見所満載ですが、何といってもメインディッシュは「悟りの境地(Awaken)」。
最近のライブではわかりませんが、当時「究極」の曲がセットリストに載ることはあまりなかったので、とてもうれしかったことを覚えていますし、期待を裏切ることはないパフォーマンスでした。
このメンバーの「危機」が聴きたかったなと思うのはファンの贅沢な望み。
スクワイアーのソロカッコいいなぁ・・・ホワイトのドラムの安定感は見事だなぁと思いながら観ていますが、もう8人揃うことはない現実も再認識されて少し寂しいです。 -
BARBARA RUBIN / UNDER THE ICE

イタリア色は弱いが、良質なポップ作品(0 拍手)
BARBARA RUBINのソロ・デビュー・アルバム。
全曲英語で歌われている洗練されたポップ作品でイタリア色は弱いのですが、その分幅広い女性Voファンにおススメ出来ます。
彼女自身が作詞・作曲を手掛け、ピアノやシンセも演奏しています。
バックにはギターやべースの他にチェロやフルートも参加していて、ストリングスが配された曲などはシンフォ・ファンにもおススメ。
もう少し膨らませて欲しいなと思う小曲はあるものの、全編メロディアスで美しい旋律に満たされていて、大きく好き嫌いが分かれない作品だと思います。 -
KOSTAREV GROUP / KOSMOBOB: VEGETARIAN

超絶的なジャズロック♪(1 拍手)
ロシアのバンドKOSTAREV GROUPのデビューアルバム(らしい)。
相変わらずこのあたりのバンドの詳細情報はわからないのですが、スリップケース内のジャケ写やクレジットを確認する限りメンバーは3人。
ギターを中心にキーボードとドラムがそれを支える圧巻のジャズ・ロックを繰り広げています。
ロシアにはテクニカルなバンドが多いので、ちょっとやそっとじゃ驚きませんが、ここまで来るとさすがに凄みを感じます。
若干、クリムゾンとUKが入っているような気がしますがフォロワーではなく、しっかりと独自の色を持っているバンド。
トータル43分程度ながら聴きごたえがあるアルバムです。
ボーナスとしてアルバム収録曲「HOOP」のライブ映像が入っていて、こちらではゲストとしてヴァイオリンやサックスが加わった6人編成。
ギターの人の指の動きが凄まじく、ヴァイオリンの人は海老反り状態で演奏している。
アルバムで聴ける超絶的な演奏力を目の当たりに確認することが出来ます。 -
STAMATIS SPANOUDAKIS(STAMATIS) / CHILIAENNIAKOSIAENENINTAENNEA

ヒーリング効果があるかも・・・?(0 拍手)
ギリシャの音楽事情について詳しくはないけれど、STAMATIS SPANOUDAKISは発表作品が多いアーティストなのではないかと思います。
音楽的にはプログレとかシンフォ・ロックの枠組みで語るよりも寧ろクラシック寄りなのですが、「プログレ・ファンからも支持される」ことは理解できます。
このアルバムもオーケストラとの共演が多い彼らしい作品で、繊細な美声女性Voや優美な合唱団を配して荘厳な音世界が広がります。
美しいピアノやアコースティックギターにストリングスが重なり、全編通してゆったりとした曲調なので聴いているととても落ち着いた気分になります。
ヒーリング・ミュージックではありませんが、そうした効果はあるかもしれません。 -
ROBERTO CACCIAPAGLIA / TEMPUS FUGIT

イタリアという国の奥深さを知る(0 拍手)
1曲目の(他のいくつかの曲でも聴かれる)プログラミングによる軽快なリズムが印象に残るが、そこにROBERTO CACCIAPAGLIAのピアノや2本のチェロが加わり、女性Voが幻想的な雰囲気を醸し出す。
エレクトリックなリズムと生楽器によるクラシカルな演奏との対比が見事で、チェロが奏でる物悲しいメロディにも心打たれる。
これまで聴いてきた彼の作品の中では珍しいが、spoken voiceとクレジットされている「語り」のような男性Voもアルバム全体の流れの中でとても効果的。
オペラチックな女性Voの繊細さは名作「GENERAZIONI DEL CIELO」を思わせ、情熱的な演奏で魅了するたくさんのバンドを輩出しながら、一方でこのようなシリアスな作品も産み出すイタリアという国の奥深さをあらためて感じさせられる。 -
I POOH / DOVE COMINCIA IL SOLE

バンドの良さを残りながら力強くドラマティックなサウンドが魅力(1 拍手)
正直なところ、私の中でのI POOHは70年代の誰もが知っているアルバム(例えば「パルシファル」や「ロマン組曲」)で止まっていました。
ところが、評判が良いと聞いて購入した「Ascolta」で再び動き出したのです。
そんなわけでI POOHのメンバーについても詳しくはありませんが、このアルバムは前作からメンバーが脱退し、トリオ編成になって初めてのアルバムとのことです。
まず驚くのが、しっかりとした厚紙仕様の観音開き変形ジャケット!
さらに透明スリップケースに納められているという手の凝りようで、気合の入り方が違います。
久しぶりに聴いた前作ではメロディーやコーラスなど私が知っているI POOHの良さは残しつつアップデートされたサウンドに感動したものですが、本作ではさらに力強さが加わりました。
何と言っても2つのパートに分かれたタイトル曲が素晴らしく、これを冒頭に持ってきたことこそがバンドの意思表示だと思います。
全編をとおして泣きのメロディを奏でるギターと美しいコーラス、そしてドラマティックな曲、その合間に挿入されるI POOHらしい歌心に溢れたポップで穏やかな曲。
もちろん捨て曲なし、文句なしの満点! -
イエス / 結晶
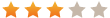
良い曲もあるが、アルバムとしてのまとまりは今ひとつ(2 拍手)
YESとABWHが合流したいわゆる「8人YES」による唯一のアルバム。
一時はYESという名前の使用権などを争い裁判沙汰にまでなりながら、あっさり「一緒にやろうよ」となってしまうところは常人には理解し難いが、双方の商業的な思惑もあって実現した(もはや)プロジェクト。
ジョンが再結成に乗り気で、ABWHメンバーはその流れに巻き込まれた形。
ファンにとっては、黄金期と言われる過去のメンバーと「ロンリーハート」のヒットを生み出したメンバーが一体になりどのようなサウンドを作り上げるのかと心躍る出来事ではあったが、アルバとしては成功とは言えず、メンバーの評価もかなり低い。
制作側が発売を急いだことによって、じっくりと時間をかけられなかったこともあってか小粒の曲が並んでいる。
しかし、「Shock To The System」はシングル・カットされても良かったんじゃないかと思うし、ハウらしいソロ曲「Masquerade」、90125YESっぽいサウンドの「Miracle Of Life」、スクワイアーのソロ・アルバムに入っていそうな「The More We Live-Let Go」(「未知への飛翔」が好きな人におススメ!)など良い曲もある。
8人が集まって演奏することがないまま制作され、「両者が作成していた曲を持ち寄って、YES名義で1枚にまとめました」というアルバムなので、全体的なまとまりとしては今ひとつ。
個人的にも通して聴くより、好きな曲をつまみ食いで聴く作品になっている。 -
TRESPASS / MORNING LIGHTS

TRACEやGRYPHONのファンにおススメ(1 拍手)
イスラエルは音楽的には辺境扱いなのかもしれませんが、素晴らしいバンドがたくさん存在していて、TRESPASSもプログレ・ファン、シンフォ・ファンにはよく知られているバンドだと思います。
1stも好作品ですが、この2ndアルバムはよりシンフォ色が強くなっているように感じます。
グループの詳細情報はよくわかりませんが、キーボード、ギター、リコーダーを演奏し、ヴォーカルも担当しているGil Steinのワンマンバンドなのかも・・・!?
しかし、ゆったりとしていてメロディアスなヴォーカル・パートとの対比で、インスト・パートの疾走感を支えるリズム隊も見事だと思います。
大曲2曲(タイトル曲は20分超え!)を含み、4曲目「Vivaldish」はそのタイトルどおりヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲をベースとした曲。
紹介コメントに書かれているとおりTRACEファンは必聴なのではないかと思いますし、少しだけGRYPHONファンにもおススメです。
イスラエル恐るべし! -
ODIN DRAGONFLY / OFFERINGS

これは、MOSTLY AUTUMNファンだけのものじゃない!(2 拍手)
MOSTLY AUTUMNの女性ヴォーカリストHEATHER FINDLAYとANGELA GORDONによるプロジェクトとして発表されたアルバム。
現在のバンドの音楽性とは異なりますが初期のアルバムで聴かれたようなケルト色もありますし、彼女たちのルーツとか方向性を窺い知ることが出来ます。
ピアノ、フルート、アコースティック・ギターなどによる演奏はシンプルですが、ふたりの美声ハーモニーにあっていて「フォーク作品」の一言で語ることは出来ません。
JETHRO TULL「WITCHES PROMISE」やMOSTLY AUTUMN「CAUGHT IN A FOLD」のカヴァーも収録されています。
それも聴きどころなのかも・・・。。
しばらく音沙汰がなかったので単発プロジェクトで終わってしまったのかと思っていたら、昨年15年ぶりの2ndアルバム「Sirens」が発表されました。
こちらもまた美品。
この1stアルバムが気に入った方や、女性Voファンにはおススメです♪