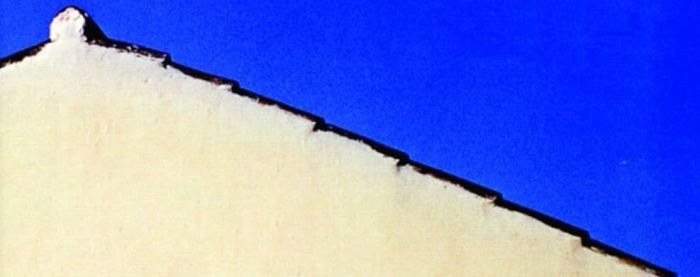COLUMN THE REFLECTION 第70回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 その① ~ KansasとStyxを中心に、プログレとしての浸透度の検証~ 文・後藤秀樹
2024年2月29日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム
タグ:

第70回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 その①
~ KansasとStyxを中心に、プログレとしての浸透度の検証 ~
プログレの全盛期が73年にあったことは多くの人が認めるところだろう。
5大バンドで振り返ると、ピンク・フロイド『狂気』、EL&P『恐怖の頭脳改革』イエス『イエスソングス』、キング・クリムゾン『太陽と戦慄』、ジェネシス『月影の騎士』がその年の作品ということになる。
しかし、それらの作品をピークに各バンドともにその勢いが徐々に失速したり、方向性が変わったりしたことも時代は見事に物語っている。
その一方で、英国ではグリーンスレイド、ダリル・ウェイズ・ウルフ、グリフォン、カルメンといった新たなバンドが登場し、タイ・フーン(Tai Phong)やPFMをはじめとした多くのプログレ・バンドがヨーロッパにも存在することが知られるようになった。
◎画像1 Kansas + Styx

そんな時期、かつてはプログレ不毛の地(?)とされていた米国のバンドが注目されるようになった。それこそ、多くのバンドが登場したのだが、今回はまず一躍全米で有名になり、ついには世界的にメジャーな存在となったカンサス(Kansas)とスティックス(Styx)の70年代のアルバムについて、当時の日本でのLP発売時の状況を振り返り、アメリカン・プログレとして認知されていった様子を振り返っておきたい。
§1 70年代のカンサス(Kansas)
カンサスの国内盤はCBS/Sonyから3作目の③『仮面劇(Masque)』が発売されたのが最初だった。本国発売と同じ75年のことだ。帯には『聴け!体のすべてを耳と化せ! 宙を引き裂き心臓をえぐるツイン・シンセサイザー&ツイン・ギター 偉大なる先導者カンサスによってアメリカン・プログレッシヴの火蓋は切って落された!』とある。もう、カンサスが日本で紹介された途端に、アメリカン・プログレッシヴと呼ばれたことは興味深い。
メンバーは6人、その編成がツイン・ギターにヴァイオリンに厚みのあるツイン・キーボード、そしてヴォーカル・ハーモニーも見事という評判もあったことから、期待が高まった。
◎画像2 Kansas / ③Masque + ④Leftoverture

そのジャケットが衝撃的だった。タイトルにもなっている仮面が全て魚や甲殻類で形作られた顔。でも、どこかで見たことがあると思って調べてみると、16世紀イタリアの画家アルチンボルドの『水』という作品だった(4連作「四大元素」と呼ばれる作品のひとつ)。アルチンボルドは奇想の画家と呼ばれ肖像画が花や果物で形作られた絵画を多数残しているのでお馴染みだろう。バンド自体は、何のエンターテインメント的な要素が感じられないメンバーの集合体に思えたのだが、アルバム裏のライヴ時の演奏ポートレート写真はカッコよかった。
最初にアルバムA面を聴いてみたのだが、1~2曲目で肝心の音楽の方は特別な面白さを感じず、そこで聴くのをやめてしまった。しかし、この3作目はB面が圧倒的に素晴らしかった。それに気づいたのは後になってのことだった。特に凄さを感じたのが「Child Of Innocence」だった。
★音源資料A Kansas / Child Of Innocence
日本で次に出されたのは、今でも最高傑作といわれる4作目、76年の④『永遠の序曲(Leftoverture)』だ。日本盤帯の言葉は『ロックは遂にここまできてしまった!知的な感性と、驚異のテクニックが、クラシックをベースに織りなす衝撃のサウンド!』ときた。
冒頭の力強い無伴奏のコーラスで幕を開ける「伝承(Carry On Wayward Son)」。間違いなくアメリカン・プログレッシヴ・ロックを代表する名曲のひとつだろう。続く2曲目「壁(The Wall)」もやはり名曲。ただ、帯に書かれていたようなクラシックがベースという感じは受けなかった。アルバム・タイトルからの「Overture」や曲構成からの判断と思われるが、じつは『Leftoverture』という言葉の意味自体が難しく、『Left Over(残り物)』を基に「序曲(Overture)」の造語としてクラシック的なものに変えたということなのだろう。彼らはラストに収録された「超大作(Magnum Opus)」の6つの小曲のことを、後に「これまでに作った作品の寄せ集め」と語っていたこともあり、遊び心からつけられたタイトルと受け取るのが正解のようだ。
じつはそれまでの3枚のアルバムの売り上げと、チャート・アクションが今ひとつだったこともあり、カンサスはレコード会社との関係も上手くいってはいなかったらしい。しかし、自分たちの音楽には自信を持っていただけに、勝負を賭けてかなり挑戦的な部分を出すことになったのだろうと想像できる。
結果的に「伝承(Carry On Wayward Son)」は全米11位となり大ヒット、アルバム④『永遠の序曲(Leftoverture)』は76年12月に最高位5位を記録した。それでも、レコード会社との契約の見直しは次のアルバムの成功後ということになった。
私は、このアルバムを77年にほぼ新品状態の中古を安く入手した。試聴済みアルバムとして売られていた輸入盤なのだが、A面は必ず通して、そして1日に何度も繰り返し聴いてしまうほどに気に入ってしまった。その頃、アルバムを聴く時は「まずA面を聴き、ちょっと間を置いてB面に針を落とす」ということが儀式のようなものだった。CDを聴くようになった当初は、それまであったA面とB面の間が上手くとれず戸惑ったものだ。ここでは、アルバム冒頭の2曲を続けて聞いていただこう。
★音源資料B Kansas / Carry On Wayward Son
★音源資料C Kansas / The Wall
カンサスの音楽はプログレといいながらも、キーボードにシンセ系を多用するのではなく、ピアノ、オルガンを上手く使っていて、あくまでもメロディーを大切にし、ツイン・ギターも重視。ヴァイオリンも要所で効果的に導入しているところに好感を持てたし、何より凄く自然に素直に彼らの音楽を心から楽しめたことが嬉しい。その歌詞も、それまでイメージしていたアメリカン・ロックのものではなく、純粋に含蓄の深い詩が多かった。確かにプログレッシヴ・ロックとカテゴライズされておかしくないと思ったものだ。
それにしても、ロビー・スタインハートとスティーヴ・ウォルシュの二人のリード・ヴォーカリストを中心としたコーラスのインパクトは鳥肌もの。さらにウォルシュに関してはヴォーカルに加え、キーボードとパーカッションも1曲の中で次々と担当していることにも驚かされた。
曲作りは一部メンバーとの共作はあるものの、ケリー・リヴグレン(Kerry Livgren)が手がけている。彼もギターとキーボードを縦横無尽に演奏することを考えると、カンサスというバンドの凄さをこのアルバムで見せつけられたような気がした。
◎画像3 ➀Kansas(’74) + ②Song For America(‘75)

ところで、カンサスの最初のアルバムは74年の➀『KANSAS』で、私は輸入盤店でLPを新譜として手に取っていた。しかし、裏ジャケットに写ったメンバー写真の6人の姿を見て、いわゆる普通の(?) アメリカン・ロック・・・と判断してしまい、シュリンクに包まれたまま棚に戻してしまった。
表のイラストは南北戦争を表したものだが、カンサス州、ネブラスカ州は19世紀に奴隷制を巡る微妙な立場に置かれた時期があったことはよく知られている。さらに、裏の写真もじつは暗雲漂う中にメンバーが立っているわけで、そこにバンド名の意味を見いださなかった自分自身に「見る目がなかったね」と呟いた。
さらに、75年には②『Song For America』も店でジャケットは覚えがあるものの、それがカンサスのアルバムであることさえも気づかずにスルーしてしまっていた。
もちろん、4作目のヒットを受けて最初の2枚も78年に国内盤LPが発売された。しかし、ファーストの帯に(72年作!)なんて間違って記載しているのと、その帯がCBSソニー「ミュージック・ライフ選定ロック・ベスト100」という再発シリーズの全く魅力のないものだったので私は中古輸入盤を買った。新品の輸入盤の方も国内盤よりずっと安く手に入る時代があったことを改めて思い出す。
その2枚を聞いた時に、彼らが最初から新しい音楽を目指していたことを認識させられた。本当に驚きだった。ファーストに収録されていた1曲目の「Can I Tell You」は、カンサスがドン・カーシュナーという超大物プロデューサーの元に最初に送り認められるきっかけとなったデモ曲として知られる。(そのデモの方は、94年の2枚組ベスト冒頭に収録、2022年の50周年3枚組アルバムには新録としてやはり冒頭に収録されていて、よほど思い入れの強い1曲なのだろう。)スピーディーな曲展開の中に、ヴァイオリン、キーボード、ハーモニー、リズムが一体となった世界観に新しさが感じられた。続く「Bringing It Back」はJ.J.Caleのカバー曲で純粋にアメリカン・ロックといえる曲なのだがそれも面白い。続いてオリジナル曲が続くのだがどれも聞き物。特にA面最後の「Journey From Mariabronn」は8分の大曲だが、全くスキを見せることなくその素晴らしさを見せつけられた格好になった。4作目同様にA面のみで脱帽だった。
②『Song For America』も言うまでもなく圧倒された。8分を超える3曲の大作を中心にシンフォニックな側面を一気に強めた印象の作品だった。
こうした、英国プログレを意識するようになったのは実質的なリーダーであるドラムスのエハートの考えにあったことも今ではよく知られている。72年のプログレ全盛期に渡英し3ヶ月ほど滞在、かなりの数のライヴに触れたようで、それらに触発されたことは明らかだ。
そんな中で、EL&P、Moody Blues、Procol Harumらがオーケストラと共演している様子に衝撃を受け、いつか米国でも挑戦してみたいと考えていた。その夢も98年のアルバム『Always Never The Same』でロンドン・シンフォニー・オーケストラと共演することで叶えられたことになる。
★音源資料D Kansas / Journey From Mariabronn
★音源資料E Kansas / Song for America
◎画像4 Kansas / ⑤Point Of Know Return(’77) + ⑥Tow For The Show(’78)

④『永遠の序曲(Leftoverture)』を聞き続け、その余韻が続いていた中で翌77年には⑤『暗黒への曳航(Point Of Know Return)』が届いた。『伝説と未来が交錯する、幻夢の音宇宙(サウンド・マクロポリス)!カンサス激情のヘヴィー・スリル!』と国内盤帯に記され、さらに「暗黒の狂宴か?伝説の黄昏か? 今や、ピンク・フロイド、イエス、EL&P、と肩を並べるアメリカン・プログレッシヴの最高峰、カンサス宿命の音黙示録!燦然と輝く前作「永遠の序曲」に続いて放つ、一大巨弾!」という言葉が並んでいた。
ついに、英国のプログレ5大バンドの名が引き合いとして出されたことになる。
当時、アルバムを見て驚いたのは収録曲が10曲もあったこと。曲のクオリティーは不変なので安心できたのだが、シングル・ヒットを狙うことも視野に入れたのだろうか・・・という思いがよぎった。
ジャケットの「海の果て(?)」伝説のイラストを見ながら、アルバム・タイトルも(ア)『Point Of No Return』と思っていたら、(イ)『Point Of Know Return』となっていた。そう思うと(ア)のような「目的地不明の帰還不能」ではなく、「(知っている場所だから)また戻ってくることができる」ととらえることも出来た。謎を秘めながらも音楽的には充実した感じがうかがえて安心したことを思い出す。
シングル・カットされた「すべては風の中に(Dust In The Wind)」は米チャートで全米6位となり、始めてトップ10内に入るヒットなった。「伝承(Carry On Wayward Son)」と「すべては風の中に(Dust in the Wind)」は、それぞれ100万枚以上を売り上げた。その後、CDの時代、デジタルの時代になってもアルバムも聞かれ続けRIAA公認の様々な栄誉を受けている。永遠のスタンダードとして認められたようでとても誇らしい気分になる。
★音源資料F Kansas / Dust In The Wind
70年代のカンサスを追ってきたが、78年には2枚組のライヴ・アルバム⑥「Two For The Show」、79年には「Monolith」、80年には「Audio-Visions」を出している。ライヴは圧倒的な内容で今もよく聞く。
カンサスのメンバーはドラムスのフィル・エハート(Phil Ehart)、ベースのデイヴ・ホープ(Dave Hope)、ギター+キーボードのケリー・リヴグレン(Kerry Livgren)、ヴァイオリン+リード・ヴォーカルのロビー・スタインハート(Robby Steinhart)、キーボード+リード・ヴォーカルのスティーヴ・ウォルシュ(Steve Walsh)、ギターのリッチ・ウィリアムス(Rich Williams)。この6人がデビュー作(’74)から8作目の『Audio-Vision』(’80)までを創りあげた不動のメンバーとなる。
80年代に入るとスティーヴ・ウォルシュが抜け、スタインハートも『Vinyl Cofessions』(’82)を最後に脱退(98年『Always Never The Same』~2002年『Device-Voice-Drum』まで復帰。)。リヴグレンとホープも『Drastic Measures』(‘83)で脱退する。84年にはバンドは一度休止状態になる。
ウォルシュは『Power』(’85)で復帰するが、その間、ジョン・エレファンテ(John Elephante)、スティーヴ・モーズ(Steve Morse)ら多くの交代メンバーが参加している。しかし、やはり昔から聴いたものにとっては、オリジナル6人の姿が忘れられない。
バンドの歴史が長くなることで、メンバーの変遷は仕方ないところだが、2000年のアルバム『Somewhere to Elsewhere』では全盛期メンバーが揃った。しかし、ウォルシュの歌声にかつての精彩がなくなってきたことは仕方ないとは言え、時間の流れを感じやはり寂しく思えた。
スタインハートは2021年に亡くなっている。
2024年、現在もカンサスはオリジナル・メンバーのエハートとウィリアムスが中心となって活動を続けている。
§2 70年代のスティクス(Styx)
◎画像5 Styx 初期の4枚 (A~D)

続いてはスティクス(Styx)の70年代を見ていこう。
やはり、日本で初めて紹介されたアルバムから見ていこう。日本で最初のリリースはWooden Nickelからのファーストが73年に日本ビクター(RCA)から出たのだが、全く話題にはのぼらなかった。次に出たのがセカンド『黄泉(よみ)の国より(Styx II)』で、日本では75年にやはりRCAからの発売だった。
帯には「<憧れのレディ>の異常なまでのヒットによって遂に陽の目を見た幻のアルバム。シンセサイザーやジャズ的手法を駆使した幻想のプログレッシヴ・ロック」と書かれていた。
米本国ではWooden Nickelから73年に出されていたものだ。
帯にある<憧れのレディ>の異常なまでのヒットとは、どういうことだったのかが気になるところだ。
スティクスは72年に最初のアルバムA)『Styx』を出し、73年にB)『Styx II』、C)『The Serpent Is Rising』、74年にD)『Man Of Miracles』を米Wooden Nickelから出している。最初のアルバム冒頭から13分を超える大曲を聴かせ、そのハード・サウンドには注目できるものがあった。コーラスやツイン・ギターも決まっているし、シンセも導入し構成にも凝った本格的なロック・バンドだ。今聴いてみても、その後のヒット作と変わらないクオリティーを持っていたと思う。
73年のB)「II」からの「憧れのレディ(Lady)」というシングルは、地元シカゴでは注目を集めたが、その人気が全米に伝わらないというジレンマにメンバーはA&Mへの移籍を考えることになる。となると、これまでのWooden Nickel側が面白くない。改めてそのシングルを74年になって再発したところ、巻き返しを図るような感じで全米チャートに火が付いた。75年3月には全米で6位に達する大ヒットとなり、アルバムB)『II』も20位を記録した。
もちろん曲のよさはあった。この曲を作曲したメンバーのデニス・デヤング(Dennis DeYoung)はこのヒット曲によって全米では「パワー・バラード」の父とまで呼ばれるようになったわけで、まさに伝説的なヒット曲となったわけだ。この事実が日本盤の帯の「異常なまでのヒット」ということになるのだろうが、「異常」という言葉を使うのはどうだったのかなと考えてしまう。
先ほど紹介したように日本では75年にRCAからB)『II』が発売された。私はFM番組で紹介されたのを聴いたのだが、全く知らない名のバンドだったもののかなり面白かったことを覚えている。もちろん「Lady」も良かったのだが、個人的にはバッハの「小フーガ(Little Fugue In “G”)」と続く「Father O.S.A」に驚くと同時に歓喜した。
特に「小フーガ」は、私の思い出のフェイバリット・ヒットソング、フェアリーダスト(Tinkerbell’s Fairydust)の『誓いのフーガ(Twenty-Ten)』のメロディーそのままだったし、続く「Father O.S.A」は荘厳なクラシカル・モチーフのプログレに思えたことで、スティクスに注目するきっかけになった。
それにしても「三途の川」の意味を持つ「Styx」というバンド名がじつに印象的。神話や寓話にインスパイアされたバンドも幾つか思い浮かぶが、どれもが主題を文学に求めたり、哲学的な歌詞を持っていたりして興味深い。音楽的にも凝っているものが多かっただけに、プログレ的な感性を思い浮かべたことに間違いはなかった。
◎画像6 Styx 初期4作のコンピレーション

初期4作品はレコード時代にはなかなか入手困難だったが、A&M移籍後に再発され、その後CD化もされている。さらに今では4作をまとめた『The Complete Wooden Nickel Recordings』という2枚組CDが比較的入手しやすく便利だ。
★音源資料G Styx / Lady/Little Fugue In”G”/Father O.S.A
◎画像7 Styx / E) Equinix(’75) + F)Crystal Balls(’76)

その後、5枚目にあたる75年のA&MからのE)『分岐点(Equinox)』が日本ではキングからのリリースだった。レコード・デビュー時から不動のメンバーで、リード・ヴォーカルとキーボードのデニス・デヤング、ギターのジェイムス・ヤング(James Young)とジョン・クルリュスキー(John Curulewski)、ドラムのジョン・パノッツオ(John Panozzo)、ベースのチャック・パノッツオ(Chuck Panozzo)の5人。2人のパノッツオは双子の兄弟で、同じバンドのリズムセクションとして在籍しているというのも珍しい。
デニスのハイ・トーンのヴォーカルとそれに絡むやはり高音域のコーラスが鮮烈。曲調もメロディアスで、メリハリが効いていてどの曲もよく出来ていた。この作品の帯には宣伝文はなかった。
76年の6枚目のF)『クリスタル・ボール(Crystal Ball)』は、クルリュスキーに替わってトミー・ショウ(Tommy Shaw)が参加。彼はリード・ヴォーカルも担当し、またギター演奏の幅も広く新たな戦力としてバンドに大きな貢献をすることになる。ストレートなロック・ナンバーが増えた印象もあるのだが、そのことが逆にアルバムの中のプログレを感じさせる曲を際立たせる結果となったようにも思えるし、リード・ヴォーカルもとれるトミーの参加で、コーラスの幅もさらに広がった。
この作品帯には、「アメリカン・プログレッシヴ・ロックのゆくえは.”ボストン”と、この”スティクス“に聞こう 抜群のコーラス・ハーモニーとエレクトリック・インストゥルメンツを駆使した、アメリカン・プログレ最高のバンド、スティクスのA&M2枚目のアルバム。A面2曲目「マドモワゼル」は目下ヒット・チャート上昇中!! その実力は高く評価されている。」とある。
同じ「アメリカン・プログレッシヴ・ロック」としてボストン(Boston)の名が挙がっているのは面白いところだ。ボストンの最初のアルバム『幻想飛行(Bostn)』も76年発売で、まずその中からカットされた「宇宙の彼方へ(More Than A Feeling)」が全米で大ヒットしていた。カンサスのアルバム『永遠の序曲』も日本ではボストンのすぐ後に出ているのだが、日本で広く知られるようになるのは少し先なので仕方ないことだろうと思われる。
心機一転で取り組んだA&Mからの最初の2作品は音楽的な充実にもかかわらず、E)『分岐点』からシングル・カットした2枚のうち「ローレライ」が全米27位、F)『クリスタル・ボール』からは3枚のシングルの中で「マドモワゼル(Mademoiselle)」が唯一36位と営業的には物足りない成績だった。
ここでは、2枚のアルバムの中から現在でも聞き継がれる印象深い曲を聞いていただこう。「Suite Madam Blue」はデニスのヴォーカルだが、「Chrystal Ball」の方はトミー・ショウのヴォーカルとなる。
どちらもコーラスの素晴らしさが際立った名曲と言える。
★音源資料H Styx / Suite Madam Blue
★音源資料I Styx / Crystal Ball
◎画像8 Styx / G)The Grand Illusion(’77) + H)Pieces Of Eight(’78)

通算7枚目となるアルバム、77年G)『大いなる幻影(The Grand Illusion)』はとにかく一際目立つ明るい色彩のジャケット・デザインが印象的だった。エッシャーの有名な騙し絵をモチーフにしたものだが、化粧品の広告のような女性の表情が浮かび上がっていることが強烈なイメージを伝えている。
本作の国内盤帯には「時にはシンフォニックで、ときにはロマンチックで、またときには痛快なロックンロール―圧巻のハード・ドライヴィング・サウンド。アメリカン・プログレッシヴの最成長株スティクス待望のA&M第3弾」と書かれていた。先ほど紹介したカンサスの『暗黒への曳航』の国内盤帯と同様に77年「アメリカン・プログレッシヴ」と記されていたことになる。
ちょっと77年という年を振り返ってみると、フォリナー(Foreigner)の最初のアルバムが出た年でもある。イアン・マクドナルドとミック・ジョーンズが参加した新たなバンドということで期待されたことを思い出すが、フォリナーは英米混合メンバーの参加ということもあり、その国内盤帯には「全米ヒット・チャートを爆走するフォリナー戦慄のデビュー・アルバム! ブリティッシュ・ロックの伝統とアメリカン・ロックの若い力が見事に融合して誕生した最新のロック・パフォーマンス」とあった。
よく考えると、アメリカン・プログレの台頭と時期を同じくして、英米の区別の意味があまりなくなってきたような気がするのだがどうだろう。その辺りからメロディアス・ハードとかアリーナ・ロックという名の下にライヴも巨大化してロック自体が大きな転換期を迎えたことになったと言えそうだ。
**********************************************
その当時、イーグルスの『ホテル・カリフォルニア』が76年12月に発表され、77年に特大のヒット作品となったが、表題曲の歌詞解釈について大きな議論を呼んだ。それは、「69年以来、ここでは酒(スピリット)は品切れのままです。」という部分。 69年という年は、あくまでもひとつの時代解釈で社会的にもいろいろあったわけだが、音楽的に言えばウッドストックという巨大なフェスティバルが開催され、ロックが多様化を見せるようになった年でもある。それ以後もロックの歴史は続くのだが、その中で持っていた「魂」が失われたのではないのかという主張・提言としても受けとめられた。
その当時、大学に通っていた私も友人と熱く語り合った思い出がある。
**********************************************
ちょっと脇道にそれてしまったが、『大いなる幻影』はスティクスの大ブレイク・アルバムとなった。それまでと音楽性が変わったわけではないが、当時の社会に対して懐疑的な歌詞が多く思えた。と同時に自分たちが何故大きな成功を手に出来ないのかという不満も込められていたように思える。アルバムの構成として表題曲にはじまり、「The Grand Final」で幕を閉じるという、ちょっとしたミュージカル的なトータル・アルバムになっているところも特筆すべきところ。
そんな中で2曲目の「Fooling Yourself (The Angry Young Man)」を国内盤では「怒れ!若者」という邦題にしたことに関して、ちょっと違うのではないだろうか?・・・と邦題擁護派の私でも感じたことだ。
そんなことをあれこれ考えた中で、「永遠の航海(Come Sail Away)」は素晴らしかった。デニスの得意な、ピアノの柔らかいオープニングから歌い始め、途中から華々しくロックになる感じなのだが、中間部のまさに航海を思わせる柔らかいシンセの演奏も雰囲気が素晴らしい。タイトルをコーラスにしてフェードアウトするまで夢を見させてもらった。実際、この曲はシングル・カットされ翌全米8位を記録し、アルバムも6位という過去最高位を記録し大ヒット作となった。最終的に300万枚の売り上げを記録し、トリプル・プラチナを獲得することになったのは大きな驚きだった。
★音源資料J Styx / Come Sail Away
まさに快進撃のようにスティクスのリリースは続き、78年には8枚目のH)『ピーシズ・オブ・エイト~古代への追想(Pieces Of Eight)』が登場する。そのジャケットを見て多くの人がすぐに気づいたと思われるヒプノシス(Hipgnosis)の手によるデザイン。まずそこに当時の彼らの勢いを感じることが出来た。(日本ではA&Mの発売権がそれまでのキング・レコードからAlfaに移って、私にとっては結構な違和感を覚えてしまった。)
この時の国内盤帯には「アメリカ・プログレ・ハード・ロックの過去・現在・未来を担う第一人者スティクスが壮大な構想の上に描き上げた荘厳、華麗なサウンド絵巻。ポップ感覚がキラリと光る圧巻のコンセプト・アルバム」という文言、今度は「アメリカン・プログレ・ハード・ロック」とさらに拡大された表現になっていた。今考えると面白い。
その勢いは、よりストレートなロックとして現れ、その中核となったトミー・ショウの人気が一段と高まった時期でもあった。シングル・カットされた3曲「逃亡者(Renegade)」(16位)「Blue Collar Man(Long Nights)」(21位)「この一瞬のために(Sing For The Day)」(41位)は、すべてトミーの作品だった。アルバムの方は全米2位を記録する大ヒットとなった。
◎画像9 Styx / I)Cornerstone(’79) + J)Paradise Theatre(’80)

79年は9枚目I)『Cornerstone』の発表となるが、ここで前作を上回る新たなピークを迎える。シングル『Babe』が遂に全米1位を記録。アルバムも最高位2位となり、名実ともに全米のトップ・グループとなった。これまでのスティクスの音楽性に比べると、メロウな面が強調されたかなり甘い曲だが、新たなファン層を獲得した結果だったのだろう。個人的にはこうした曲も嫌いではないが、スティクスには甘すぎると思った。
ここでも国内盤帯の文言を・・・「かつて、これまでにロマン溢れるサウンドを作り得たハード・ロック・バンドがあっただろうか?『ピーシズ・エイト』に続く待望の最新アルバム! 全編漲る叙情性と、パワフルなポップ感覚でスティクスは遂に頂点に立った。」
ここでは「ロマン溢れる・・ハード・ロック」という表現になっている。「ポップ感覚」は前作と同様。
この作品もジャケットが凝った作りになっていて、米盤は裏面が観音開きになっていた。ただし、前作からのAlfa国内盤は二つ折りジャケットにはなっていたものの、オリジナルの意匠ではなかった。残念。
それまでのファンにとって好意的に迎えられたのは、意外な音楽性の『Boat On The River』だった。トミーの弾くマンドリンと、デニスのアコーディオンの響きが中心となった民謡調で印象的な1曲。日本はもちろん、世界的でシングル発売された人気曲だが、意外なことに米本国ではシングルとして発売されなかった。
★音源資料K Styx / Blue Collar Man
★音源資料L Styx / Boat On The River
『Babe』の大ヒットにデニスはよりメインストリーム指向の音楽性をバンド内で提案したが、よりロック的な方向性を求めたトミーとジョンと対立することになる。そのエピソードを聞いたときに思い出したのは69年に社会派のメッセージを持って硬派としてデビューしたシカゴが70年代半ばから後半にかけて徐々にポップな方向に向かっていったことだった。70年代後半から80年代にかけては、パンク~ニュー・ウェイヴやディスコ等が全盛となった時期だが、それまで活動を続けてきたバンドの多くが苦難を抱えていた時期と言える。それは、英プログレ5大バンドにしても同じだったわけで、私たちリスナーにとっても複雑な思いでシーンを眺めていた覚えがある。
そして81年、10作目となるJ)『パラダイス・シアター(Paradise Theatre)』が出されたが、驚くことにはアルバムがトータル仕立のコンセプト・アルバムになっていたこと。題材は1928年から58年代に実在した劇場の盛衰だった。ジャケットには表裏でその明と暗を表現していた。内容的には、デニスとジョン、トミーの思いを折衷した内容で、想像した以上に落ち着いた素晴らしい内容だった。
懐古的な意味合いもあってか、アルバム内の演奏も冒頭の「A.D.1928」と「A.D.1958」は同じメロディーを持ちながら、ピアノの響きが違っていて少しばかり印象が違っているし、ビッグ・バンド風の演奏もすっと出てくる。ジャケットの看板下のタイトル文字も表と裏ではスペルが異なっていて、30年の時代の変化を大きく考えさせられるものになるだろう。前作以上にかなりジャケットも音作りにも気を遣って構成されたことを感じられる。
ここでも当時の国内盤の帯から引いてみると、「パラダイス・シアターへようこそ !! さあ、はじまるぜ!華麗なるスティクス・グラフィティ! 既に4枚のプラチナディスクを獲得し、王者の風格を感じさせるスティクスがグループ結成10年の記念すべきアルバムとして完成させた入魂の力作。」だ。
さらに特筆すべきこととして、初回のレコード盤面はレーザー・エッチングが施された仕様で、光を当てると虹色に輝く絵柄が浮かび上がるというものだった。残念ながら当時私はその効果を明確に理解できたとは言えなかった。
スティクスはこのアルバムで遂に全米1位を記録している。シングル・カットされた2曲「The Best Of Times」は9位、「Too Much Time on My Hands」は30位だったものの、アルバムとしての質の高さが際立っていたからだったとも言えそうだ。ただ、プログレからは離れていった印象も否めなかった。
「そうか、もう80年代に入ったのだ」ということを実感させられたアルバムでもあった。
★音源資料M Styx / Rockin’ The Paradise (Live Version)
83年には『ミスター・ロボット(Kilroy Was Here)』が出て前作以上にロック・オペラを意識したコンセプト・アルバムになっていた。これも全米トリプル・アルバムとなり大ヒットしたのだが、これがひとつのピーク点だった。日本語を取り入れた「Mr.Robot」はなんとも言えない思いで聞いた。
ブルー・オイスター・カルト(Blue Oyster Cult)が77年にリリースした『Spectres』に収録されていた「Godzilla」中、日本語で「リンジニュースヲモウシアゲマス・・・」と収録された時と同様に、今回の「ドモアリガト、ミスター・ロボット」もそれほど好意的には受けとめられなかった。
この後、大規模なライヴを続ける内に再びバンド内は分裂した格好になり、トミーが脱退する。そのトミーも、そしてデニスもソロ・アルバムを出すことで、スティクスの実体は怪しくなってしまった。
80年代以降もバンドも活動休止、再活動、再結成といったことを近年に至るまで繰り返すのだが、彼らに対する私の興味は徐々に薄れていった。しかし、彼らのそれまでの作品群は輝きを失わないことも事実だ。
§ 今回のアウトロ
今回は多くの方になじみ深いカンサスとスティクスに焦点を当てたのですが、今振り返ってみても凄い勢いのあった時代だと思います。
英国以外にもあるはずだ・・・と、プログレ的な音楽を探していた70年代中期からの大学時代、他にもToto、Bostonといった大物級を含め、たくさんのものに出会い新たな面白さを発見した時期でした。もちろん、他にも多くの単発アーティストもいたわけですが、それらについては次回以降触れていこうと思います。
さらにその後の時代背景を考えると、81年にMTVが生まれ、日本でも『ベストヒットUSA』もスタートし、ロックが映像とともにあるようになりましたし、日本では「レンタル・レコード(貸しレコード)店」が生まれ、安価でレコードが聞けるようになり身近なものとして認識されたものでした。
私にとっては、友人同士で貸し借りを互いにしていたので、お金を払ってレコードを借りるというのは考えられないことでしたが、そんな時代があったことも事実でした。しばらくしてCDが一派的になり、当時貸し出されたレコードが中古品となりレンタル・シールがついたまま大量に出回った時期もありました。スティクスの『ミスター・ロボット』なんて、どれだけ目にしたことか・・・
ロックが巨大化するということで、中心となるファン層が私たちよりもっと若い世代に移った印象もありました。私自身は79年に始まったキングからのユーロ・ロック・コレクションのシリーズを追いかけることになったこと、70年代初頭の廃盤系LPを探して入手するという生活だったような気がします。
そんな流れもあって、21世紀の今も相変わらず70年代を聞き続けている毎日なのだろうと思います。
同時代を通ってきた方々であれば同じような思いで今に至っている方がいたのではないだろうかと想像するのですがいかがでしょう。そして、今の方々に当時あった熱気と、現在も価値を持ち続けるそれらの音楽を伝えていきたいと考えています。
今回の最後に、1996年に亡くなったStyxのドラマーだったジョン・パノッツオに捧げる形でトミー・ショウが歌う「Dear John」を聞いていただきます。翌1997年の「リターン・トゥ・パラダイス(Return To Paradise)」のラストに収録された美しい曲です。
★音源資料N Styx / Dear John
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第65回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る④ ~ ドイツのロック・シーンのまとめ ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はAMON DUUL、CAN、NEKTAR、ANYONE’S DAUGHTERなどが登場、ジャーマン・ロックをテーマに語る第4回目をお届けいたします☆
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第66回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ➀ ~ニュークリアスに始まった私のジャズ・ロック体験~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は、ブリティッシュ・ジャズ・ロックをテーマに語る第1弾をお届け。
氏にとって最初のジャズ・ロック体験となったニュークリアスを中心に、ソフト・マシーンなどにもフォーカスしてまいります!
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第67回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ② ~ハットフィールド&ザ・ノース、ヘンリー・カウ、そして、ギルガメッシュ、ナショナル・ヘルス・・・アラン・ゴウェンの軌跡とともに~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!ブリティッシュ・ジャズ・ロックをテーマに語る第2弾をお届け。今回はカンタベリー・ロックを語ってまいります♪
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第68回 ~ 今年も過ぎ行き冬の到来、そして新たな年に向かう今 「マイ・プレイ・リスト~冬の歌~」セレクション ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は、氏が好きな「冬の歌」14選をお届けいたします。どうぞお楽しみくさだい☆
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第69回 ロックのヴォーカル・アンサンブルに驚かされた日々の想い出 ~ ヴォーカル・ハーモニー、コーラスの魅力 ~ 不定期連載 ➀ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は、ヴォーカル・ハーモニー、コーラスに注目して、有名アーティストからニッチなアーティストまで取り上げます。どうぞお楽しみくさだい☆
「Column The Reflection」バックナンバーはこちらからチェック!
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!