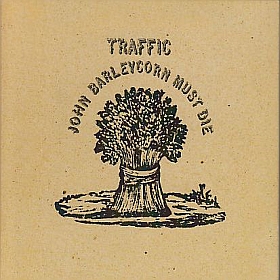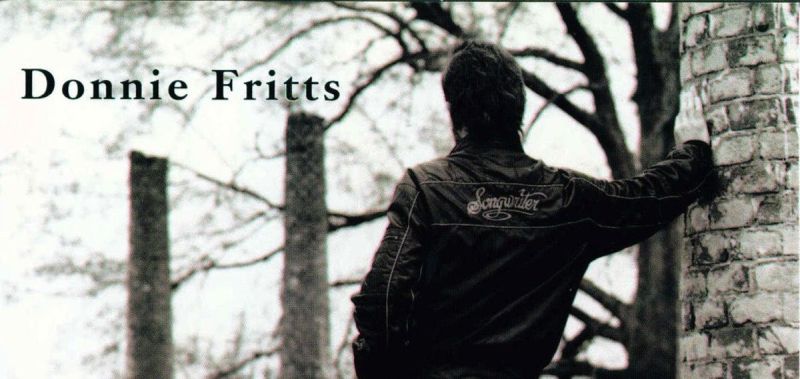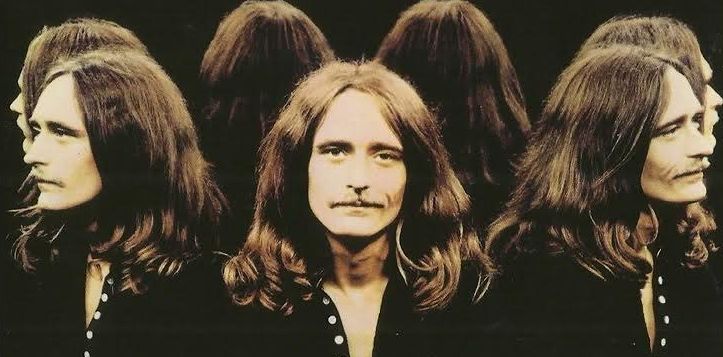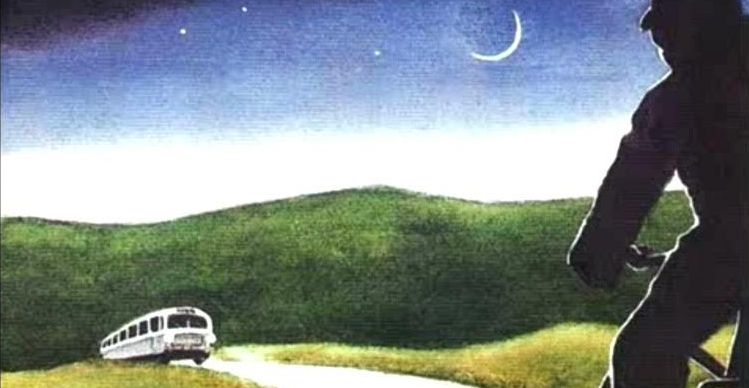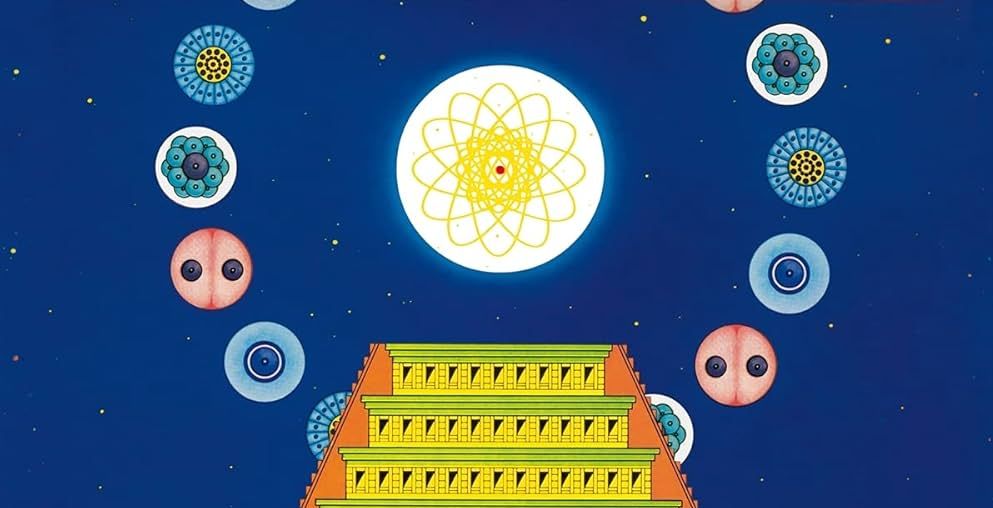トラフィックの1970年作『JOHN BARLEYCORN MUST DIE』- MEET THE SONGS 第172回
2020年4月26日 | カテゴリー:MEET THE SONGS,世界のロック探求ナビ
タグ: ブリティッシュ・ロック

今から50年前にリリースされたTRAFFICの名作『JOHN BARLEYCORN MUST DIE』をピックアップいたしましょう。
弱冠10代半ばでスペンサー・デイヴィス・グループのリード・シンガーを務め、その英国人離れしたソウルフルな歌声で「天才少年」として名を轟かせたスティーヴ・ウィンウッド。
そんな彼がより自由で実験的な音楽を求め、3人の才気あふれるミュージシャンたちと18歳の時に結成したのがこのTRAFFICというバンドです。
彼らの音楽性というと、なかなか掴み所がないという印象が強いかもしれません。
初期にはジャズやR&Bなど黒人音楽に惹かれるウィンウッドと、ポップ志向のデイヴ・メイスンという方向性の異なる二人のソングライターの才能がぶつかり合い、複雑で多様性に富んだサウンドを展開。
やがてメイスンがバンドを離れ一旦の解散を迎えますが、翌年ウィンウッドを主導として再び再始動。この後期TRAFFICにおいてもジャズやR&B、フォークやスワンプといった様々な要素を取り入れ、ジャンルに囚われない自由なサウンドを打ち出していきます。
そんな後期TRAFFICの第1作目がこの70年作『JOHN BARLEYCORN MUST DIE』。まずはアルバムの背景からご紹介いたしましょう。
前述の通り、音楽性の相違から67年デビュー作『MR.FANTASY』リリース後に早くもバンドを脱退したメイスン。その後メンバーの説得で何とか68年2nd『TRAFFIC』を同じ4人で録音するも、メイスンはソロでの活動に移行。やがてウィンウッドも新たな活動のためにバンドを離れ、TRAFFICは一時の解散を迎えます。
TRAFFICを離れたウィンウッドが向かった先は、CREAMを解散した友人エリック・クラプトンの元。ともに米国音楽に強く惹かれていた二人はクラプトンの地下室にこもり、理想の音楽追求のためにセッションを行います。そこに同じく元CREAMのジンジャー・ベイカー、そして元FAMILYのベーシスト=リック・グレッチが加わり結成されたのが、ビッグネーム揃いの「スーパーグループ」BLIND FAITH。
彼らのデビュー・ステージとなった69年6月のフリー・コンサートは当時最高といわれる10万人を動員、翌月リリースされたアルバム『BLIND FAITH』もなんと英米両方のチャートで1位を獲得。「何があっても成功するだろう」という皮肉を込めてクラプトンが付けたバンド名(BLIND FAITH=盲目的信頼)通り、彼らの存在に世間は大いに賑わいます。
ところがバンド内では活動に不満を感じるクラプトンの孤立が目立ち始め、わずか半年のうちに解散が決定。クラプトンは米国の夫婦デュオ、デラニー&ボニーとの活動に移行し、一方ウィンウッドとグレッチはベイカー主導のジャズ/アフロ色濃厚なバンドGINGER BAKER’S AIRFORCEに短期間参加。なお、彼らはライヴ演奏を収録した70年のアルバム『GINGER BAKER’S AIRFORCE』にも名を連ねています。
こうしてクラプトン、ベイカーなど名だたるミュージシャンと経験を積んだウィンウッド。1970年、21歳の彼は初のソロ・アルバム、それも一人でほぼ全ての楽器を担当しての制作を決意します。
彼はMOTT THE HOOPLEなどを手掛けていたアイランド・レーベルのプロデューサー、ガイ・スティーヴンスの助けを借り、まず最初のナンバー「Stranger to Himself」に着手。
しかし次第に『志を同じくする盟友』の存在が恋しくなり、TRAFFIC時代のドラマー、ジム・キャパルディを呼び寄せ「Every Mother’s Son」を録音。結局サックス/フルート奏者のクリス・ウッドも加わることになり、ウィンウッドのソロ・アルバムは1年越しのTRAFFIC再結成作としてリリースされることになったのでした。

そんな経緯もあって、ほぼウィンウッド主導で制作されたこの『JOHN BARLEYCORN MUST DIE』。過去作との大きな違いは、やはりデイヴ・メイスンの不在でしょう。それまではソウルフル&グルーヴィーな演奏の中にもメイスンの親しみあるポップ・センスが交わる作風が特色でしたが、メイスン抜きとなった本作はウィンウッドの趣向がより露わなサウンドに変化していると言えます。
もう一つ過去作と異なる本作の特色が「曲の長尺化」。1曲目の「Glad」と最終曲の「Every Mother’s Son」は約7分、2曲目「Freedom Rider」も6分越え。ライヴ録音を除いて長くても5分程度だった過去作と比べると、かなり演奏時間が伸びています。
1969年、KING CRIMSONなどのプログレッシヴ・ロックの台頭により、商業主義におもねらないより自由な演奏が可能になったロック・ミュージック。それを経た本作は、「ポップ」を捨てて「芸術的表現」により比重を置いた『TRAFFIC流プログレ・アルバム』と呼ぶことができるかもしれません。
♪Glad & Freedom Rider
ウィンウッドといえばあのソウルフルな歌声が印象的ですが、本作の冒頭を飾るのはインストゥルメンタル・ナンバー「Glad」。ピアノにオルガン、パーカッションにサックスと多彩な音色が重なり、重厚でダイナミズム溢れるアンサンブルが展開されていきますが、これがたった3人で制作されたというのだから驚きです。
軽快に転がるピアノやブイブイとむせぶサックスのメロディが印象的な冒頭を抜けると、ウッド奏でるエレクトリック・サックスの長尺ソロ・パートに突入。4分を超えるとガラリと表情が変わり、ウィンウッドのピアノがクラシカルな趣を帯び始めます。やがて徐々にオルガンやパーカッションが不規則に鳴り始め、実験的な雰囲気が濃厚に・・・と思うと急に2曲目の「Freedom Rider」に突入。
2曲目の「Freedom Rider」もまた3人とは思えない濃密なサウンドが見事。ウィンウッドのピアノやオルガン、ソウルフルなシャウトがアーシーな米国色を醸し出す一方、JETHRO TULLを彷彿とさせるウッドの唾吹きフルートと枯れた味わいのサックスの音色は非常に英国的。ピアノとオルガン、グルーヴィーなベースらが奔流のように絡み合い、クライマックスに向かって上り詰めていく様が見事です。
「Glad」のソロ・パートなどが特に顕著ですが、全体的にセッション的というか、カッチリとしていない演奏はBLIND FAITHに通ずる所も。ただその中でも「Glad」終盤のプログレッシヴな展開は新境地と言ってよく、新たな試みに挑戦しようというウィンウッドの意気込みが伝わってきます。
♪Empty Pages
ヴォーカルやキーボードはもちろんのこと、本作で聴けるウィンウッドのベースもとても魅力的。個人的な感覚なのですが、ギタリストやキーボーディストなどいつも旋律を奏でているミュージシャンが弾くベースは非常にメロディアスでリズミカルなんですよね。この「Empty Pages」を聴くと特にそれを感じます。
♪John Barleycorn (Must Die)
TRAFFICでは過去にもフォーキー・テイストのナンバーがありましたが、アルバムのタイトルにもなっているこの「John Barleycorn (Must Die)」はもろに英国のトラディショナル・フォークをカヴァーした楽曲。
英トラッド・フォークの代表格FAIRPORT CONVENTIONが米フォーク・ロックからの影響を出発点としていたように、英国のミュージシャンが米国音楽に魅了されるうち、自国のルーツ・ミュージックにも目を向けるようになるのは珍しい事ではなかったのかもしれません。
歌詞は大麦の擬人化である「ジョン・バーレイコーン」が一度死に、酒となって復活する様を描いた内容。冒頭に出てくる「3人の男」など、バンドの復活にも重なる一曲です。
♪Every Mother’s Son
アルバムの最後を飾る賛美歌風の「Every Mother’s Son」は、先ほど述べた通りウィンウッドとキャパルディの2人のみで録音された楽曲。
ウィンウッドの操るダイナミズムいっぱいのピアノと荘厳なオルガン、そして生き生きとした巧みなギターが緻密に絡み合うアンサンブルは惚れ惚れするほどの完成度で、ウィンウッドの類稀なる音楽的才能を感じます。
ちなみに彼は幼少の頃、聖歌隊に入り教会のオルガンを弾いていた経験もあるとか。中盤の格調高いオルガン・ソロはそんな教会音楽の影響が伺えますね。
軽快なジャズ、アーシーでソウルフルなR&B、クラプトンと共に培ったブルース、そして教会音楽や英国トラディショナル・フォーク。
複雑な要素が絡み合ったTRAFFICのサウンドは、ウィンウッドがこれまでに触れ、愛してきた音楽の結晶と言えるかもしれません。
彼らが次に発表する『LOW SPARK OF HIGH HEELED BOYS』やマッスル・ショールズの面々と共に制作した『SHOOT OUT AT THE FANTASY FACTORY』では多数のゲストが参加し、さらに多彩になったサウンドを楽しむことができますが、ウィンウッドの才能を濃密に味わうならばやはり本作。
ジム・キャパルディ、クリス・ウッドという気の合う少人数の仲間とともに丁寧に作り上げた、当時のウィンウッドの理想形と呼べる作品がこの『JOHN BARLEYCORN MUST DIE』なのです。
【関連記事】
トラフィック2ndからスタートする世界のR&B/サイケ・フィーリング溢れるロック探求
トラフィックの2ndからスタートし、R&Bフレイヴァーとサイケフィーリングがまじりあう、レイト60s〜70年代初期ならではの世界のロックをピックアップ。
関連カテゴリー
関連在庫
-
TRAFFIC / JOHN BARLEYCORN MUST DIE
TRAFFIC再結集、グルーヴィーで瀟洒な通算70年発表4作目!
STEVE WINWOOD、DAVE MASONという両雄並び立たずな、関係の中でその摩擦力を音楽の原動力に変えて来た彼らの名盤の誉れ高い70年発表、通産4作目。表題曲「JOHN BARLEYCORN MUST DIE」は擬人化された大麦について歌われる英国のトラッド・ソング。ジョン・バーリコーン(大麦)は一度刈り取られなければならない。その後、美酒となって人々に幸福をもたらすと歌われるこの歌こそが、一度は解散しながらも再び相見えた、新生TRAFFICの姿勢を象徴しているかのようです。オルガン、サックス、パーカッションと月並みなロック編成を大きく離脱し、むしろジャズ・コンボのような柔軟さで、インストから幕を開ける今作は、来るべき80年代以降のジャンル混淆時代の突入を予見しているかのようです。
-
紙ジャケット仕様、99年マスター採用、ボーナス・トラック4曲、定価2039+税
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
帯中央部分に若干色褪せあり
-
-
BLIND FAITH / BLIND FAITH
エリック・クラプトン/ジンジャー・ベイカー/スティーヴ・ウィンウッドらビッグネームが集結するも半年という短命に終わったスーパーグループ、69年唯一作
大物ロック・ミュージシャンが大集結したスーパー・グループ、Blind Faithがたった半年という一瞬の活動期間に放った、大輪の華。Eric Clapton(g、元Yardbirds、Cream)、Ginger Baker(ds、元Cream)、Steve Winwood(vo、key、g、元Spencer Davis Group、Traffic)、Rick Gretch(b、元Family)という錚々たる顔ぶれもさることながら、Claptonの音楽的欲求がコンテンポラリー・ブルースへと向かっていたこの時期に、志を同じくしたTrafficのSteve Winwoodとその追求を目指したことが窺える作品と言えるでしょう。とは言え、互いに激しく火花を散らすような作風には程遠く、肩肘を張らない、ナチュラルなセッション・ユニットと言った風情のアルバム。「盲目的な信頼」と名付けられたこの皮肉めいたスーパー・グループは、69年6月、ロンドンのハイドパークにおよそ10万人!の観客を集め、アルバムはミリオン・セラー。その後の米国ツアーを経て、バンドはあっという間に解散。Eric Claptonはこの流れのまま、Delaney & Bonnieたちとの共作に続いて行きます。
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!