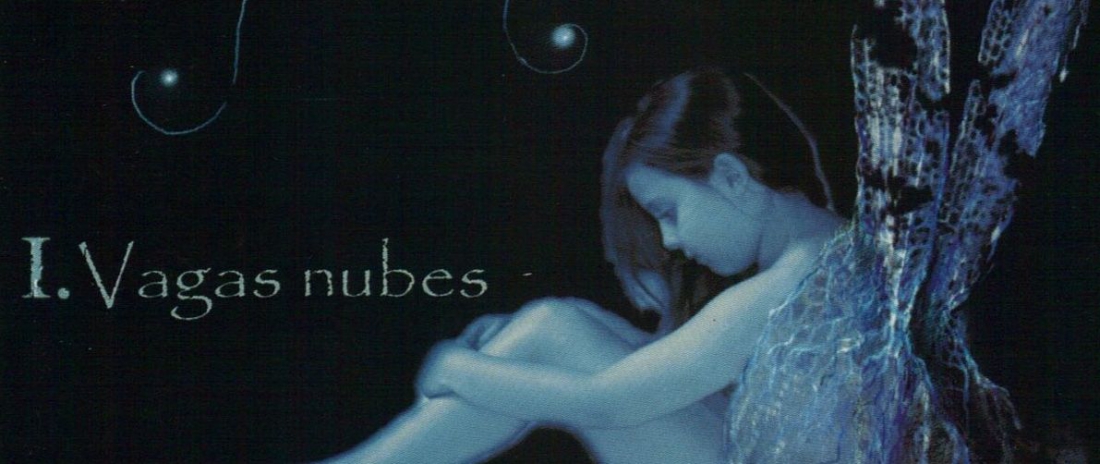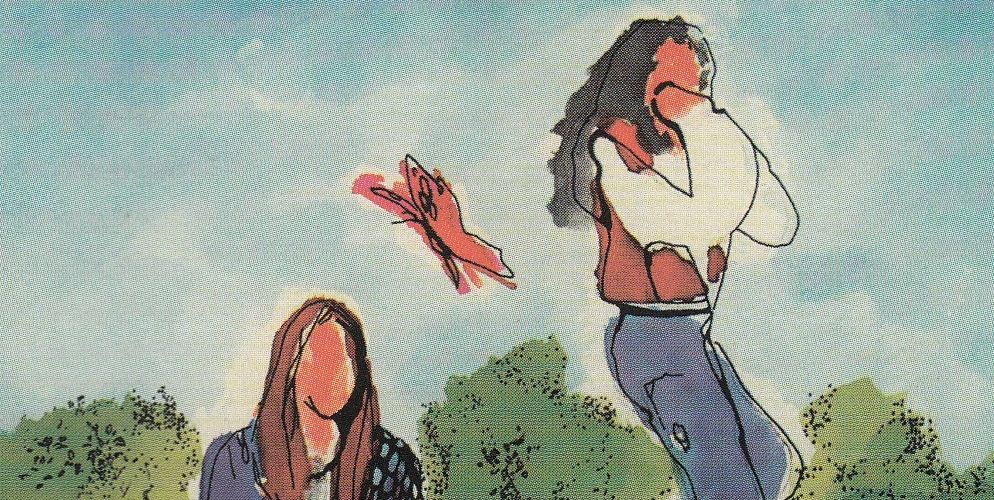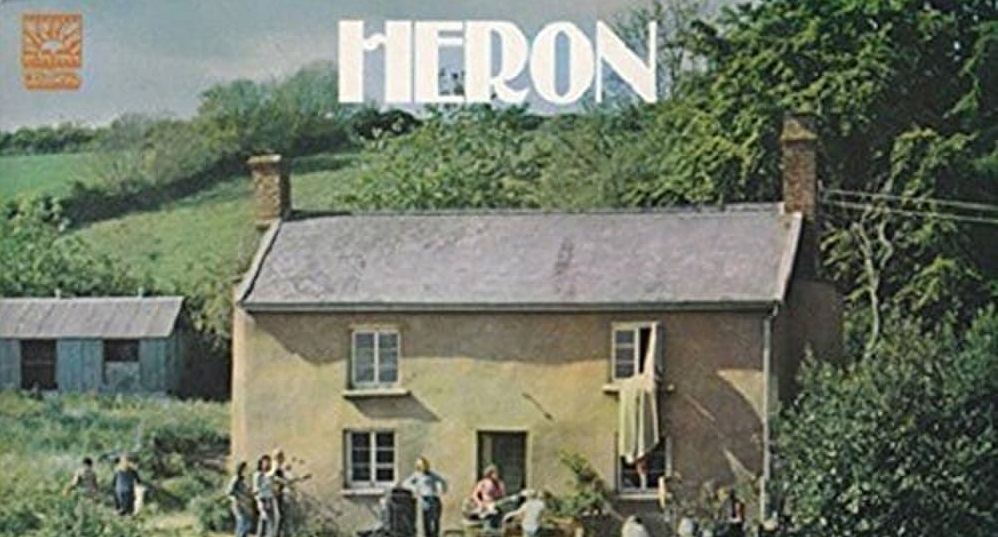「音楽歳時記」 第八十四回 1月19日のど自慢の日 文・深民淳

年明けとともにオミクロン、大変なことになっております。昨年までは大変な騒ぎだけど周りでコロナになっちゃった人いる?みたいな話でしたが、オミクロンの登場でいよいよ要注意レベルになった雰囲気でさらに気分はどよ〜んとなってきました。
年末は結構出歩き、CD中古盤市場観察やっておりましたが、市中在庫の総量ますます減ってきている印象を受けました。ここ10年くらいのCDの総生産量の落ち込みを考えれば、中古盤市場の在庫が減るというのはさもありなんの話ですが、実際に減ってきている現実を目の当たりにするとちょっと不安になってきます。まぁ深く考えても仕方ないので軽く受け流して参りましょう。
先月はネタが面倒なものだったこともあり、文字数が大変なことになってしまいましたので、今月は軽く流していきたいと思います。
まずは去年の終わりからよく聞かれる質問に対する回答です。ディシプリン・グローバル・モービルとWOWOWエンタテインメントのレーベル契約は2021年12月末をもって終了しました。契約解除の理由はDGMが日本市場もその他のエリアに合わせるという形を取りたいという意向によるものです。
どういうことかと申しますと、現在、DGMはヨーロッパ、北米ともにインディーズ・レーベルとして商品を販売しています。日本のみ特例でWOWエンタと販売契約を交わしていたのですが、日本においても海外同様、独立した形のインディーズ・レーベルとして2022年4月1日よりスタート。ただいま準備中です。
新しいホームページのアドレス等は3月後半に発表させていただきます。
というわけで今月のネタにまいりましょう。あ、その前に今年最初の原稿である今回からルールを変更します。これまではこの1月公開の原稿ですと2月の記念日を取り上げてきましたが、今年から1月の原稿なら1月の記念日とさせていただきます。通常毎月第3金曜日更新ですので、更新される時には既に終わっている記念日が出てきますが、書いているうちに10月から11月前半にかけてクリスマス・アルバムをしゃかりきになって聴いたり、様々前倒しで聴いているのにちょっと違和感プラス疲れを感じちゃうことが多く季節合わせをしたいということで変更させていただきます。
というわけで1月。さる1月19日は「のど自慢の日」でした。1946(昭和21)年のこの日、NHKラジオで「のど自慢素人音楽会」が開始され、それを記念してNHKが制定したそうです。
第1回の応募者は900人で予選通過者は30人、実に競争率30倍の超難関だったそうです。敗戦国となってから5カ月あまりでスタートしたこの番組はTV時代になるとNHK総合チャンネルでも放送されるようになり、現在も日曜の昼に放映されています。戦後の混乱、食料・物資の不足で日々の暮らしにも苦労した時期に新聞とともに情報伝達の要となっていたラジオは、また庶民の数少ない娯楽を提供するメディアでもあり、人々は歌に飢えていた時代でもあったことから評判を呼び、瞬く間に人気番組となりました。
またこの「のど自慢」放送開始の約3週間前、終戦の年1945年の12月31日には大晦日恒例の紅白歌合戦の前身となる「紅白音楽試合」が同じNHKラジオで放送されました。もともとは「紅白音楽合戦」という番組名で企画されるもGHQから「敗戦国が合戦とは何事か」と咎められ、「試合」に変更されたという経緯もあったそうです。この特番は大きな反響を呼びますが、翌年以降は放送されず、5年後の1951年に大晦日ではなく正月特番として復活。以降3年間は正月特番として放送され第4回から大晦日の放送となり現在に至っているそうです。なるほどねぇ・・・。今年の12月のネタは紅白だな、多分。
ま、それはさておき今回は自分の記憶に残る声をピックアップしていこうかと思います。まずはレオン・ラッセル。結構ダミ声系で南部の人の特徴である空気漏れっぽい語尾のはっきりしない発声がかなり特徴的。かなりアクの強い声質および歌い方の上、入れ歯がずれちゃったジィちゃんみたいな不明瞭な歌詞回しが随所で発生することもあり、作った曲は好きだけどこの人の声は苦手という方も多いアーティストです。
普段ですと迷いなくシェルター・レーベルからの2nd『Leon Russell And The Shelter People』をひっぱり出しますが今回は、彼自身のシングルとしては日本で一番売れた「Tight Rope」からスタートする『Carney』を聴きます。持ってはいますがほとんど聴きません。どちらかというと苦手な作品です。苦手な理由は書いている本人もよく分かっていません。その辺の解明も含め聴いてみたいと思います。
楽曲面は作曲家として最も脂がのっていた時期の作品だけあり、粒ぞろい。『Leon Russell And The Shelter People』と比べても遜色はほとんどなし。逆にオリジナル発売当時、日本のラジオでもかかりまくっていた「Tight Rope」やThe Carpenters等のカヴァーでお馴染みの人気曲「This Masquerade」などが収録されており、ゴージャス感は高いのですが、やはり人気急上昇期、スケジュールがめちゃタイトな中で作られた感が強く、『The Shelter People』の持つ一気通貫の熱気みたいなものがなくなちゃったのが惜しいですね。それでもオープニングの「Tight Rope」から「Roller Derby」までのアナログA面にあたるパートはアーティストとして全盛期を迎えていた時期だけあって充実しています。
Tight Rope
個人的に苦手だった理由は整合感に欠けるB面パートから受ける印象だったように思います。この作品のテーマであるドサ廻りの大衆演芸の世界を再現したインストのタイトル曲からマーク・ベノと組んでいたAsylum Choir時代にもどったかのようなサイケデリック感漂うサウンドコラージュ「Acid Annapolis」を挟みひなびたアコースティック・ナンバー「If The Shoe Fits」への流れが、実はこの『Carney』のキモなんだろうと思うのですが、この部分とこの後に収録されている、みんなが聴きたがっているから収録せざるをえなかった「This Masquerade」がもろに水と油みたいな関係になってしまっているのがちょっと痛い気がします。
If The Shoe Fits
前にも書いたようにレオン・ラッセルは声が苦手という人が多いのですが、そのラッセルがこれまた地味目のマーク・ベノと組んでいたAsylum Choirに至っては組み合わせだけでパスって感じかもしれませんが、これがサイケに寄った時のThe Beatlesとボブ・ディランの『Blonde On Blonde』を衝突させて飛び散った破片を集めて作ったかのような質の高いサイケデリック・ポップ作品だったりします。2作品とも英国系のフリーク・ビートやソフトタッチのサイケ好きにも推奨の名作。先入観だけで判断できない隠れた銘品です。
いや、もっとクセが強くてもOKという場合は70年代当時結婚していたマリー・マククレーリィ(Sly & The Family Stoneのバック・ヴォーカルなどやってました)とのデュエット作2作目『Make Love To The Music』(1977年)どうでしょう。レオン・ラッセルの全作品中でも最高に歌っていて空気抜けまくっています。シュー、シューと空気が抜ける音が聞こえてきそうなくらいサザーンな歌いっぷりと収録曲の出来が久々に良いのが売りかと。極上サザーン・メロー・グルーヴ炸裂のタイトル曲、カリプソのりの「Say You Will」は間違いなしの上出来。ちなみにこの2曲は腰砕けの揺れ声が魅力のマリア・マルダーが1978年発表の『Southern Winds』でカヴァー。タイトルのとおりサザーン寄りの作風のアルバムですが、彼女の緩さが魅力の揺れ声とは若干ミスマッチといった雰囲気。ただ、妙にジャズっぽくなったり、アメリカーナ風になっちゃうのが苦手な向きには安心のロック寄り作品です。
同じく「Say You Will」を自信たっぷり力強く朗々と歌ったのがニコレッタ・ラーソン。4作目でワーナー最終作『 All Dressed Up And No Place To Go』に収録。オリジナルとは異なる視界良好のヴォーカル・パフォーマンスは強く記憶に残っています。
Say You Will(Nicolette Larson)
曲は好きだけど声がちょっと、の線でもうひとり。Paul Williams。この人の声もクセ強いですね。あくまで個人の感想ですが、この人の歌声、焼けたゴムの臭いがうっすら混じったような感じがします。何言っているか分からない、って感じですが、ま、そういう声です。ソングライターとしてはこの人無しでは初期The Carpentersは成り立たなかったし、Three Dog Nightはヒットメーカーには成りえなかったといっても過言ではない70年代アメリカを代表するコンポーザーのひとりです。
A&M時代の作品には特にその傾向が強く、1971年発表の『Just An Old Fashioned Love Song』のタイトル曲はThree Dog Nightの大ヒットとなり、アルバム収録曲「We’ve Only Just Begun」と「Let Me Be The One」はThe Carpenters。続く1972年作『Life Goes On』にはThree Dog Night『It Ain’t Easy』収録の「Out In The Country」、The Carpenters『A Song For You』収録の「I Won’t Last A Day Without You」など、どの作品にも知っている曲満載ながら、オリジナル・コンポーザーのプライドか、チャートを上がった他人のカヴァーとはどれもきっちりアレンジ違いで収録されています。カテゴライズするとAORに入るサウンドながら、流麗さとは無縁でどれも素材の良さを活かした朴訥なアレンジが施されているのが魅力的です。
イギリスに目を向けるとやはりこの人がでてきます。ロジャー・チャップマン。まずはこのコラムでは鉄板推奨盤指定となっているFamily『Bandstand』。ジョン・コッシュ・デザインの古いTVを模した変形ジャケットがまず秀逸。サウンドは英国産ヘヴィ・ファンク・ロックの頂点を極める極上もの。重く沈み込むジョン・ウェットンのベース、バタバタ感Maxのロブ・タウンゼントのリズム・セクションでファンクをやろうという着想自体が既に神発想。結果、このメンバー時のみ有効の超重量級引き摺りファンク・サウンドが完成。埃をまきあげ邁進するリズムセクションの上でチャーリー・ホイットニーのいぶし銀のカッティングが踊り、新し物好きポリ・パーマーの妙に浮ついたシンセサイザーが空気を読まずに投げ込まれ、そこで地獄のダミ声ロジャー・チャップマンが吠える。もうとてつもない世界が作り出されています。
アルバム制作の裏でウェットンはロバート・フリップとKing Crimson加入の話し合いをしており、エンジニアーは『太陽と戦慄』も担当することになるジョージ・チキアンツであった偶然。その裏歴史も含めて名作といったところでしょうか。本作完成と同時にウェットンは脱退。ポリ・パーマーはサウンドチェック時のシンセのセッティングに時間がかかりすぎると疎まれクビになりブリティッシュ・ロック史に残る超弩級ファンク・ロック・ユニットは幻となってしまうのであります。
また、その怒涛のファンク・ナンバーの中にひっそりと置かれていたはずのどこまでもくすんだ色合いのアコースティック・ナンバー「My Friend The Sun」はバンドを支えてきたファンに見出され、労働階級のロック・アンセムとして定着。そしてこの曲がロック・アンセムであったことを証明したのがStreetwalkers1977年発表の『Live』でした。
『Bandstand』をスタート地点としてロジャー・チャップマンとチャーリー・ホイットニーのデュオ・アルバム『Streetwalkers』(1974年)を経て結成されたStreetwalkersは結成当初のドラマーは現Iron Maidenのニコ・マクブレインでしたがこのライヴ・アルバムでは元ブライアン・オーガーのOblivion Express、後にマギー・ベルが在籍したMidnight Flyer、Runnerで活躍するデイヴ・ドウルに交代。またチャーリー・ホイットニーの相方として元Gass、Jeff Beck Group、Hummingbirdのボブ・テンチがギター、ヴォーカルで参加。再現不可能なウェットン在籍時のヘヴィ・ファンクとはグルーヴ感が異なるものの剛性体質はそのまま受け継いだアップグレード・ヴァージョンのファンク・サウンドを完成させ、その集大成となったアルバムが『Live』だったわけです。
まぁ、騒々しいライヴ・アルバムです。1曲目の「Chili Con Carne」(オリジナルのスタジオ・ヴァージョンはビザール系エロジャケでお馴染み3rdアルバム『Vicious But Fair 』収録)からテンションMax。鋼のヘヴィ・ファンク・サウンドにのってチャップマンのビブラート入りダミ声シャウトが炸裂。このStreetwalkersライヴで代表曲と共に演奏されるのが『Bandstand』のキモともいえる「Burlesque」と「My Friend The Sun」。「Burlesque」は後半の最も盛り上がるパートで演奏され、「My Friend The Sun」は中盤で演奏されるのですが観客の大合唱となるわけです。今となっては単体の中古か2016年にMadfish/Snapperから出たボックス・セット『I’m Walking – Complete Streetwalkers 1974-1977』を探すしかないのが残念ですがかなり感動的なシーンです。
くせ者ヴォーカリストは他にも多数いますがここでは3人取り上げました。最後に今月の1枚ですが、男性ばかりだったので女性ヴォーカリストを取り上げます。あまりにクセが強すぎて一生忘れられません。大学時代にバイトしていた輸入盤店で輸入業者だった本社の倉庫にあったデッドストックで誰も買わないので店員割引で買いました。普通のジャズ・ヴォーカル・アルバムだと思って買いました。その前の週に買った同じレーベルから出ていたチャーリー・パーカーのアルバムを買って音はあまり良くなかったけど演奏はかなり良かったので、きっとヴォーカルものも良いのだろうと思い何も考えずに買いました。
レーベルはESP。Pearls Before SwineやThe Fuggsを出していたレーベルなのは知っていましたがジャズ系はまともなんだろうと思っていました。それが超怖かったんだよ。
パティ・ウォーターズ『カレッジ・ツアー』です。まぁ、フリー・ジャズでアヴァンギャルドって言っちゃったらそれまでなんですが、小学生に聴かせたら間違いなくトラウマになります。そんなものですが、世の中、怪作としてカルト化し、しっかりCDにもなっています。もちろんCD持ってません。欲しくないです。大学の時買ったレコードのままです。40数年ぶりに聴きました。結論としましては還暦過ぎても怖いものは怖いです。しかも原稿書いている今は夜中の2時過ぎです。やめればよかったと後悔しています。天井から「し〜〜ん〜〜ぶ〜〜ん」とか声がして恐怖新聞がパサっと落ちてきそうな雰囲気です。ではさようなら。
Song of Life/Hush Little Baby
「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!
関連CD在庫
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!