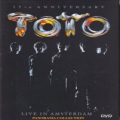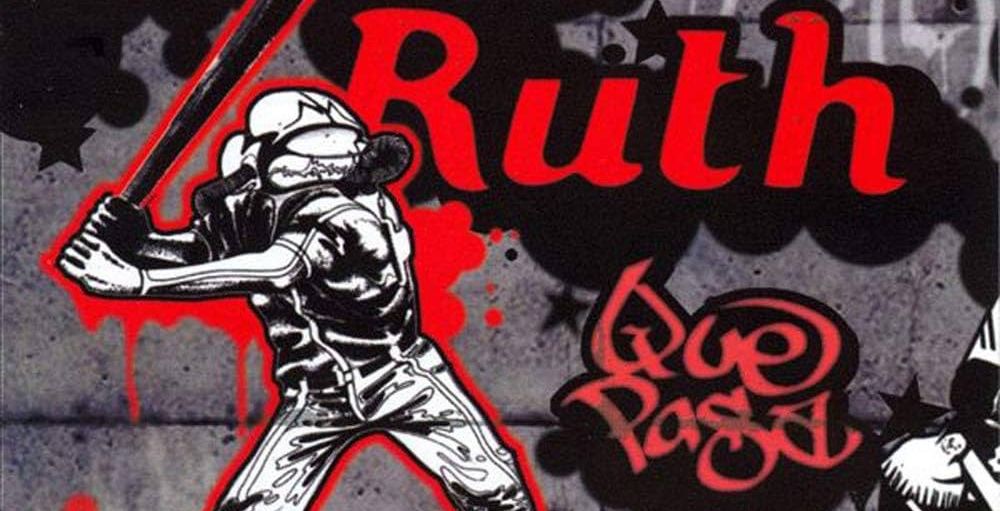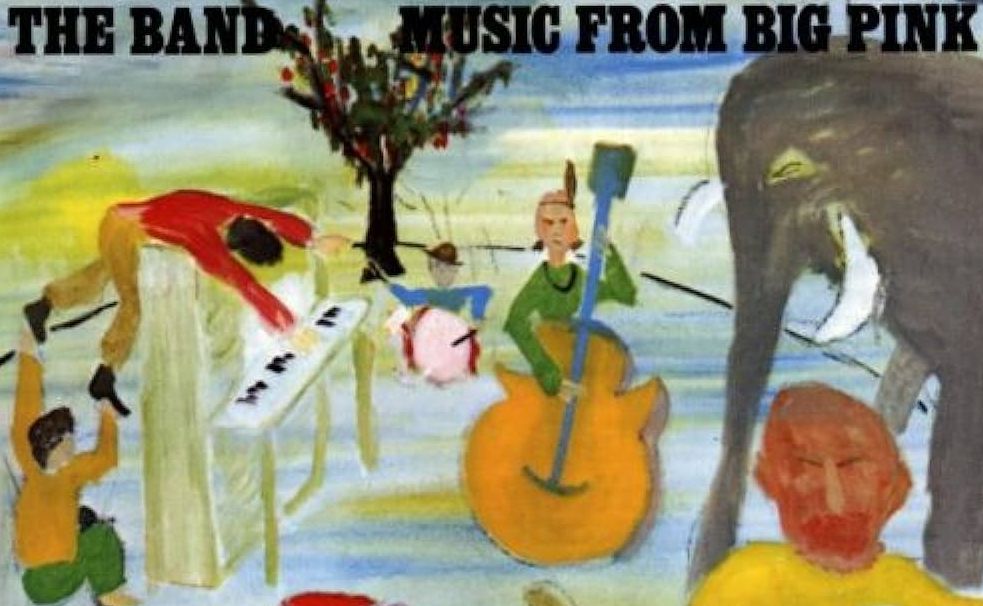COLUMN THE REFLECTION 第71回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 その② ~ BostonやTotoもあったけれど、Fireballet、Starcastle、Pavlov’s Dog、Ethos等が次々と紹介され、勢いのあった70年後半の米国プログレ系バンドを振り返る ~ 文・後藤秀樹
2024年3月29日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム
タグ:

第71回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 その②
~ BostonやTotoもあったけれど、Fireballet、Starcastle、Pavlov’s Dog、Ethos等が
次々と紹介され、勢いのあった70年後半の米国プログレ系バンドを振り返る ~
前回取り上げたカンサスやスティックスをはじめとして、70年代中盤以降のロックの勢いは凄かったと改めて感じる。その理由は多々挙げられるだろうが、何よりも「ロック」自体が世の中で一般化して社会現象の一面として認知され、馴染み深いものになったということが出来るのだろう。
媒体としてのラジオもそれまでのAM放送から音楽番組中心のFM放送が広く浸透し、若者にとっては自分専用のラジカセの時代にもなった。加えて、新たなFM雑誌が音楽雑誌に混じって並ぶようになり、それまで以上に多くの情報を伝えることになった状況とも重なる。
同時期から少し後に、パンク・ロックが出てきたが、如何にも不良っぽいヴィジュアルに反体制的な姿勢を見せたパンク系のバンドに対しても世の中は寛容に受けとめていたような気がした。
また振り子の揺れのように、激しい音楽の一方でMOR/AORと呼ばれた音楽もかつてのポップ・ミュージックの復権のように大きな流れとなり、音楽文化の受け止め方が大きく変わった時期でもある。
今回は、70年代中盤から後半をひとつの区切りと考え、前回と同様に「米プログレ」として私自身が同時代的に見聞きしたものを中心に取り上げることにした。当時発表されながら日本で紹介されず、ずっと後になってCD化されたものは基本的に除外してある。それでも、「米プログレ」が一般に受け入れられるようになった時期と、その経緯・状況が少しでも伝わっていくといいのだが・・・。
§1 登場自体が衝撃的だった・・・・・ボストン
◎画像1 Boston 『Boston』 + 『Don’t Look Back』

ボストンは米・日ともに76年に登場したが、これは衝撃的だった。例によってそのファースト・アルバムの国内盤帯を紹介すると「22世紀に向けて飛び立て! エレクトロニクスを駆使したハード・ロックとアコースティック・サウンドの見事な融合。限りなく鮮明なギターはうねり宙を舞う。ズシッと確かな手応えに火を吹く謎の飛行物体。21世紀最大のニュー・バンド!」そして、「全米チャート驚異の急上昇!」とある。
ちょっと待て、76年は未だ20世紀ではないか・・・と今になって考えると思うが、当時は時代先取り的な表現も多々あったことを思い出す。それはともかく、大きな期待を持って迎えられたボストンだった。
78年に同アルバムは再発されているのだが、その時の新たな帯には「76年、このアルバムによってボストン神話は生まれた!」と幾分シンプルになったが、「全世界で1000万枚を超える驚異の大ヒット!」したという事実に触れている。
ファースト・アルバム冒頭に収録された「宇宙の彼方へ(More Than A Feeling)」も確かに凄かったが、私が当時もっと夢中になったのは3曲目の「Foreplay/Long Time」。前半のインスト「Foreplay」の圧倒的迫力には脱帽だった。
★音源資料A Boston – Foreplay / Long Time
バンドはトム・ショルツ(Tom Sholtz)、ブラッド・デルプ(Brad Delp)、バリー・グードリュー(Barry Goudreau)、フラン・シーハン(Fran Sheehan)、ジム・マスデア(Jim Masdea)の5人組で各メンバーの力量の凄さは伝わったのだが、何よりもトム・ショルツの存在が際だっていた。というより、実際にはショルツがヴォーカル以外の多くの演奏を手がけていたということはその後伝わってきた話だ。
当時は既にシンセサイザーや新たなキーボード、エフェクターが比較的手軽に使用できるようになった頃でもあった。
そんな中、78年の2枚目のアルバム『Don’t Look Back』には「No Synthesizers Used. No Computers Used」と記されていた。「そんなものを使わなくても,こんな音が出せるんだぜ。」というメッセージのように受けとめられたが、確かにボストンの音の衝撃は新鮮だった。
ショルツはマサチューセッツ工科大学出身の技術職人だったことから、音作りにかなりのこだわりを持っていたことは想像できる。「Foreplay」は在学中の69年に作曲していたという事実には驚かされた。ただ、その後デビューに至るまで何度もデモを作りながらも、レコード会社から拒否され続けていたという。そして、最初のアルバムの巨大ヒット後もレコード会社(Epic)とはかなりのトラブルを抱えていた。意外なことに彼らは94年までに4枚のアルバムしか残していない。(当初のEpicからは2枚のみ)その後、さらに2枚のアルバムを発表はしている。ボストンは現在も演奏活動をしていると伝えられるのだが、残した作品量としてはあまりに寡作なことも意外な事実ではある。
§2 技巧派の集団だった・・・・・TOTO
◎画像2 TOTO 『TOTO』 + 『Hydra』

続いてはTOTO。最初は「トト」という名前に「何じゃこりゃ?」と思ったものの、今では卓越した音楽職人集団として世界中に認知された誰もが知っている超有名バンド。彼らの78年のデビューも衝撃的だった。それは、ファースト・アルバム冒頭のやはりインスト曲である「子供の凱歌(Child’s Anthem)」に始まった。
★音源資料B TOTO / Child’s Anthem
この作品の国内盤タイトルは『宇宙の騎士/TOTOデビュー』で、帯には「ロスから超大型スーパーグループ登場! LAの熱い香りを君のハートにたたき込む凄腕の6人。」 これは、既にAOR作品で使われたコピーに似ていて、決してプログレを意識したものではなかった。実際、キャッチーな味わいの名曲も多数収録されていることは事実だが、やはり演奏力が高いと何をやってもサマになる作品だった。
今考えても凄いメンバーが揃っていたのだが、当時はボズ・スキャッグスのアルバムのバックで演奏していたジェフ・ポルカロ(Jeff Porcaro)とデヴィッド・ハンゲイト(David Hungate)、スティーヴ・ルカサー(Steve Lukather)、デヴィッド・ペイチ(David Paich)が中心となり、ジェフの弟でキーボードのスティーヴ・ポルカロ(Steve Porcaro)、そしてヴォーカルのボビー・キンボール(Bobby Kimball)の6人編成だった。すべてのメンバーが数多くのアーティストのレコーディングのサポートに参加しているミュージシャンでもあったわけで、TOTO結成後もそのスタンスは変えていなかったことが凄い。
TOTOとしての2枚目『Hydra』も映画のワンシーンのような印象的な「青色の風景」の中に、ファーストのジャケットに描かれた『剣』が表現され、トータル・イメージとしてワクワクして聞いた覚えがある。今ではもちろんアルバム全体をよく聞くのだが、発表された当初は神話・伝説を思い起こさせる1曲目のタイトル・ナンバーに魅せられ繰り返し聞いた。それは、やはりプログレ的だった。帯のコピーは『衝撃のデビュー・アルバムから1年、果てしない夢とロマンをのせてTOTOのセカンドは若き剣士と神獣ハイドラのスペクタクルファンタジー』だった。
★音源資料C TOTO / Hydra
ご存じのように80年代以降も彼らは順調に活動を続ける。81年の3作目『Turn Back』のジャケットには唖然とさせられた。ユーモラスと言えばそうなのだが、私はその時点で一歩引いてしまった。ただ、その作品が日本では前2作を上回る最大のヒット作になったということが意外だった。
ただ82年の4作目『聖なる剣(IV)』では邦題にも使われたように『剣』のモチーフが帰ってきたことと、日本では『来日記念盤』LPとして通常より安く2000円で発売されたことが大きなポイントだった。シングル・カットされた「ロザーナ(Rosanna)」と「アフリカ(Africa)」もよくラジオでオン・エアされていた。プログレではなくとも心地よく聞くことができた。
84年の5作目『Isolation』は日本でLPと同時にCDも発売された最初のアルバムだった。この辺りから徐々にメンバーの交替も行われていくようになる。ヴォーカルがジョセフ・ウィリアムス(Joseph Williams)になったことは大きな変化だった。さらに、ベースもマイク・ポルカロ(Mike Porcaro)となり、バンド内にポルカロ3兄弟が並んだことになる。しかし、88年の『第7の剣(The Seventh One)』では、久々にジャケットに『剣』が描かれたものの、ジェフ・ポルカロが抜けていた。ただ、多数のゲストが迎えられ、その中にイエスのジョン・アンダーソンが含まれていたことは意表を突かれた感じだった。その後、休止もあったものの、現在に至るまで堂々たる音楽性を持って活動を続けていることはリスペクトに値する。
§3 英国プログレの影響が直接感じられた・・・・・ファイアーバレー
◎画像3 Fireballet 『Night Of Bald Mountain』 + 『Two,Too』

時は70年代中盤に戻る。そして76年、ファイアーバレーの『はげ山の一夜(Night Of Bald Mountain)』が国内盤として突然登場し驚かされた。75年に米Passportレーベルから出されていたものが、日本では翌76年にフィリップスからリリースされていた。
国内盤帯には、「あの元クリムゾンのイアン・マクドナルドが発見し、自らプロデュースをかってでたイエスのハーモニー、ELP以上のクラシック・センス、ジェネシスのサウンドをそなえたアメリカが生んだプログレッシブ・グループ驚異のファイアーバレー日本初登場!」
まず、そのジャケットのイラストにもプログレ的な雰囲気があったのは事実。さらに、プロデューサーがあのクリムゾンのイアン・マクドナルド(Ian McDonald)だ。
彼は、クリムゾン後も様々なアーティストのアルバムに参加していたが、忘れられない名盤のひとつが70年の『McDonald & Giles』がある。これはセルフ・プロデュースした作品だった。その後、73年にダリル・ウェイの新たなバンド『Daryl Way’s Wolf』のプロデュースを手がけたことでクリムゾンのファンにとって再びその名前が思い出された頃だった。同作には「McDonald Lament」という彼の名を関した”泣き“の名曲があっただけに、ファイアーバレーがどんなグループなのかも知らなくても、マクドナルドの存在そのものに期待が高まったのは確かだった。
ファイアーバレーは米ノースジャージー出身で、71年からThe Fireball Kidsとして活動していたという経歴を持っていた。最初のアルバムというのに、何よりも内容が凄かった。どの曲も構成も見事で、各メンバーの演奏も素晴らしく、今聞き直してもやはり名盤と断言できる。面白いのは有名プログレ・バンドのメロディーがところどころで顔をのぞかせるところ。さらにB面1曲目はそのままジェネシスを思い起こさせる。彼ら自身が、英プログレを聞き込んでリスペクトの上、それらの音楽性を目指したバンドの作品ということが間違いなく理解できた。
★音源資料D Fireballet / Les Catedrales
この1曲目のタイトルが何故フランス語なのか? というのは最初から疑問だったが、リーダーのジム・コモ(Jim Como)の経歴を見るとフランスでの活動歴があるからなのだ・・・とdiscosの紹介をみて思ったのだが、ファイアーバレーに至るまでの時期と重ならない部分があって未だに謎のままだ。(EURO ROCK PRESS 62号にコモ自身のインタヴューが掲載されていたというのだが、申し訳ないことに私はよく覚えていない。)ただメンバーの素性は分からなくても、彼らの凄さはこのアルバムで十分に伝わってくる。他のメンバーはブライアン・ハウ(Brian Howe)、リッチー・クランダ(Riche Clanda)、フランク・ペトゥ(Frank Petto)、マーティン・ビグリン(Martyn Biglin)で、計5人。
B面の20分近い組曲がまた素晴らしい。アルバム・タイトル通りムソルグスキーの交響詩『はげ山の一夜』をモチーフにした5部構成の曲だが、中間部ではドビュッシーの『沈める寺』が聞かれる(ルネッサンスの『港にて』でお馴染み)。それをはさんだ形で彼らのオリジナル曲も見事。当時のプログレ・ファンにとって曲の構成も演奏もまさに理想的なものだった。本当に米プログレ・バンドが登場したのだと嬉しくなった。アルバム中では、イアン・マクドナルドもプロデュースと共に演奏にも加わり、彼らしい音を聞かせてくれていた。
その後すぐに76年のセカンド・アルバム『Two Too』を輸入盤新譜として見つけたのだが、何度も「本当にあのファイアーバレーか?」とバンド名とクレジットを確かめてしまった。メンバー5人がバレーの衣装をまとい、踊っている姿というジャケットなものだから、ただただ、唖然とした。そして、さらに裏ジャケには、ご丁寧にもそのバリエーションが・・・。一抹の不安を抱えながらも、家に帰って聞いた。
ファーストとは印象は異なるものの、やはりプログレとして素晴らしいアルバムだった。前作でも見事なコーラスを聴かせていたが、ここではさらに磨きをかけた完全なアレンジのヴォーカル・アンサンブルになっていたことに舌を巻いた。そして、大胆にストリングスを導入したことが大きな変化だった。
それにしても意表を突いたジャケットはかなり損をしていると今も思う。結局日本ではレコードとして発売されなかった。しかし、ファイアーバレーの名前は「米プログレの代表格」として今も認知されているのは間違いない。
ファイアーバレーの紙ジャケがマーキーから2014年に発売された際に、ボーナス・トラックで74年のライヴからクリムゾンの「ポセイドン」時代の「Pictures Of A City」、「Mars」が収録されており、彼らはクリムゾンの硬質な部分も合わせ持っていたことが分かり興味深かった。
一方、イアン・マクドナルドは73年のウルフに関わった後、75年にはファイアーバレーともう一つ、アイルランドのフループ(Fruupp)の『当世仮面舞踏会(Modern Masquerade)』もプロデュースしていることを付け加えておきたい。その後76年にフォリナーの結成時のメンバーとなった。しかし、3枚目の『Head Games』までの参加となってしまったのは残念だった。
§4 イエスの影響下にあると言われた・・・・・スター・キャッスル(Starcastle)
76年という時期には、輸入盤でスター・キャッスル(Starcastle)、パヴロフズ・ドック(Pavlov’s Dog)、イーソス(Ethos)、といった米プログレ系(と思われた)バンドのアルバム・リリースが続いた。
この頃は、当時の音楽雑誌の記事以上に、輸入盤店の広告で紹介されるものが興味深かく、どちらもそんな中で知ったものだ。そして、友人間で「スター・キャッスルがイエス・タイプのサウンドであること」と、「パブロフズ・ドッグは高音のリード・ヴォーカリストが凄く、メロトロンも多用している」ということで注目することになる。よく考えると、広告に載せること自体プログレ系ロックが商売になるという事実で、それだけ新たなバンドを探す者が増えていたということの証明となりそうだ。
◎画像4 Starcastle album 1~4

スター・キャッスルのファースト・アルバムは76年1月に出ている。最初は、「イエスのコーラスをより明るくした感じ」と思って聞いていた。そのコーラスの印象はイエスの3枚目『The Yes Album』を思い浮かべた。キーボードやギターの幾重にも重なる旋律や、ベースの音にはその影響を感じたものの、曲構成に関してはイエスの持っている緊張感とはちょっと違うとも思った。
彼らは6人組で、メンバーはギターがマシュー・スチュワート(Matthew Stewart)とスティーヴン・ハグラー(Stephen Hagler)の2人、キーボードはハーブ・スキルト(Herb Schildt)、ベースはゲイリー・ストレイター(Gary Strater)、ドラムはスティーヴン・タスラー(Stephen Tassler)、リード・ヴォーカルはテリー・ラトレル(Terry Luttrell)という編成。アルバム・クレジットを見るとスキルト以外がヴォーカルも担当していることが記されている。
彼らはイリノイ州のシャンペーン出身。早くから活動をはじめメンバーも音楽性も変わってきたのだが、73年にファースト・アルバムのメンバーが固まり74年米国Epicと契約を結んでいる。が、その年に交通事故でハグラーが重傷を負い、機材も駄目になるという不運に見舞われ、活動停止の期間もあった。75年のアルバム制作から完成までは大きな苦労している。
テリー・ラトレル(Terry Luttrell)の声質はジョン・アンダーソンとは違うのだが、確かに意識して歌っている様子は微笑ましい感じだった。彼はREOスピードワゴンのファーストでリード・ヴォーカルだったということは後で知った。何度も聞いていくうちに、確かに各楽器が幾重にも重なる演奏には構築されたイエスの影響はあるとは思いながらも、コーラス自体は米バンドらしい爽やかな雰囲気が強いと感じるようになった。
この最初のアルバムは、日本では国内盤としては発売されなかった。
★音源資料E Starcastle / Lady Of The Lake
彼らの77年の米での2作目『神秘の妖精(Fountains Of Light)』がボストンの大ヒットの余勢を駆ってか? ここではじめて日本デビューとなった。ファーストに比べジャケットの色合いが暗く地味に思えるのが気になったのだが・・・。
国内盤の帯には「華麗なるロマンとファンタジーの世界~神秘の静寂に包まれた泉に浮かぶ城。透明な世界にまさに翔美他党とする謎の妖精・・・・・・アメリカのイエスと呼び声の高いスター・キャッスルが創り上げた壮麗なる世界。待望の本邦デビュー!」とあるのだが、「アメリカのイエス・・・・・・」の部分は本来のファーストを発売してつけていたらもっと話題になっただろうと今も思う。また,本作と次作はロイ・トーマス・ベイカー(Roy Thomas Baker)がプロデュースを手がけている。
米3作目は同じ77年『星の要塞(Cutadel)』として発売される。ジャケットが美しくプログレらしく感じられるイラストで、今もこの作品が一番人気であるようだ。「アメリカの夜空にキラリ輝く冷めた星!スター・キャッスル第2弾!★ボストン、カンサスに次ぐ、アメリカン・ニュー・ウェイヴ、第3の星!」と帯に書かれている。さらに解説書には「“第2のイエス”・・・もはや、彼らにはこの名はいらない。スター・キャッスルの決定打ついに登場!」と付け加えられていた。
4作目の78年『リアル・トゥ・リール(Ral To Reel)』はメンバーが前面に出たモノクロのポートレイトがジャケットになっている。それまでのプログレ路線から脱却しストレートなロックを打ち出した作品。ここでの帯の言葉が象徴的だった。「ボストン、カンサス、ジャーニーの一群から抜け出し、チューン・アップしたロックンロールでアメリカン・ロック本道に躍り出したスター・キャッスル、軽快なる第3弾!」 これは、ボストン、カンサスを引き合いに出した前作の帯からさらにジャーニーまで加えたところが面白い。それはボストンも、カンサスもさらにジャーニーも抱えるCBSソニー/Epicレコードの当時の勢いを感じさせるものになっていた。
なお、スター・キャッスルの活動もこの4枚で終わりだったが、バンドとしては87年まで継続している。そこで一度解散したのだが、その後も97年に復活し活動も続けていた。しかし、2000年代に入ってから出されていたアルバムは、ライヴとアーカイヴ、ハグラーやタスラーのソロといったものだったが、2007年の『Song Of Times』はバンドとしての新作(通算4作目!)となっていた。ただし、2004年に亡くなったベーシストのストレイターも加わっていることから、それ以前の録音ということが考えられた。
§5 音の背景に映像が浮かんでくる・・・・・パブロフズ・ロック
◎画像5 Pavlov’s Dog 『Pampered Menial』 2種 + 『At The Sound Of Bell』

パブロフズ・ドッグ(Pavlov’s Dog)はミズーリ州セントルイスのバンド。75年にデビュー・アルバム『Pampered Menial』を発表する。デヴィッド・サーカンプ(David Surcamp)のビブラートのかかった高音ヴォーカルが特徴で、彼の歌声がバンド・イメージを決定するほどだ。収録曲は9曲、どれも美しく叙情的な雰囲気が感じられ、間違いなくプログレ的な組み立てが感じられる。
メンバーにはキーボード奏者が二人いて、一人はデヴィッド・ハミルトン(David Hamilton)、もう一人のダグ・レイバーン(Doug Rayburn)はメロトロン、フルートの専任のクレジット。さらに、バイオリン、ビオラ担当のジーグフリード・カーバー(Siegfried Carver)もいて随所で効果を上げている。アルバム中のインスト・ナンバー『Preludin』はその編成も手伝ってか、カンサスを彷彿とさせる部分もある。あとのメンバーは、ギターのスティーヴ・スコーフィナ(Steve Scorfina) (*彼もスター・キャッスルのテリー・ラトレル同様、REOスピードワゴン結成時のメンバーだった。)ベースのリック・ストックトン(Rick Stockton)、パーカッションのマイク・サフロン(Mike Safron)の7人編成だ。
また、ブルー・オイスター・カルト(Blue Oyster Cult-BOC)のプロデューサーのマレイ・クラグマンとサンディー・パールマンが担当していることも印象的。BOCもオカルトをテーマにした個性派ハード・ロック・バンドとして知られていたが、徹底したハードな部分がありながらも一筋縄ではいかない音楽性も持っていただけに、パブロフズ・ドッグにも共通した個性を感じ取っていたのだろうと思えた。
★音源資料F Pavlov’s Dog / Late November
そのデビュー作『Pampered Menial』は2種類のジャケットが存在し混乱したことが思い出される。
私が買ったのは米ABC盤で白地の真ん中に犬の版画が配置されたもの。しかし、間もなくその版画が全面に施されたデザインのレコードも見つけた。はじめは他国盤なのだろうと思ったが、じつは途中で彼らの契約がABCからColumbiaへと変更になったようで、ジャケットの体裁も変わったことを知った。ダブル・ジャケットの内ジャケットのメンバーも当初イラストだったものが、Columbia盤では各人が犬を抱いたポートレイトになっていた。
このファースト・アルバム『Pampered Menial』は日本では発売されなかった。しかし、注目度は大きかったと見えて、輸入盤にもかかわらずラジオでオン・エアされたことも思い出される。
日本盤としては76年のセカンド・アルバム『条件反射(At The Sound Of Bell)』がデビュー作ということになる。(レコード時代はこれが唯一のリリースだった。)ここでも、レコード会社とのトラブルもあり、前アルバムから2人が脱退し(バイオリン等担当のカーバー、パーカッションのサフロン)、新たなメンバー、トーマス・ニッケソン(Thomas Nickeson)をアコースティック・ギター担当として参加させた。しかし、それ以上にゲストとして多数のミュージシャン、さらに少年合唱団、オーケストラが加わり音楽性の追求を見せていたことが印象的だった。
この作品のジャケットがまた奇妙だった。表は大きなベルにぶら下がる男、裏にはその男の疲れた姿。まるで、『ノートルダムのせむし男』のような物語性は感じるものの、どう見ても地味だ。この作品の日本盤帯には『キャッシュ・ボックス紙最優秀新人グループ‘76』の後に『76年、ニューヨークを大センセーションの渦に巻き込んだ噂のパブロフズ・ドッグ。かつてのロック概念を打ち破る、新しい世代のための新しいロック・アイドルの台頭。秘密のベールを脱いでパブロフ、遂に日本上陸!』とあった。「サーカンプをアイドルに仕立てようとしたのか?」 「秘密のベールを被せたのはレコード会社のせいだったのではないか?」等々、突っ込みどころがたくさんあるのだが、とにかく日本で発売されたことは意味があった。が、そのままではあまり売れなかっただろう。じつは、サフランが脱退した替りには(何と)ビル・ブラッフォードが参加しているのだが、そのことについて帯には触れていないことも不思議だった。しかし、結果的に日本でも彼の参加情報が知られるようになり、何とか売れたようだ。ブラッフォードの参加はともかく、この作品も聞くところは多く、忘れられない作品のひとつだ。
★音源資料G Pavlov‘s Dog / Valkerie
当時出たアルバムはこの2枚のみなのだが、77年にサード・アルバム用にレコーディングしたものはお蔵入りとなった。しかし、88年にその音源はThe St.Louis名義で『HOUNDS』がリリースされ(92年以降、パブロフズ・ドッグ名義で幾つものバリエーションがCD化され分かりにくい状態だ)、90年にはサーカンプとレイバーンを中心に新たなメンバーで『Lost In America』を出している。2000年以降も時折新たな活動をしてCD化してきているがその全貌が複雑だが、2018年に出た『Prodigal Dreamer』はちょっと注目してほしい作品だ。
§6 硬質な演奏の中に柔らかさも感じられた・・・・・イーソス
◎画像6 Ethos 『Ardaour』 + 『Open Up』 + Relics(CD)

イーソス(Ethos)に関しても当時話題にはなったが、76年の『Ardour』のレコード現物は当時見たことがなく、翌77年のセカンド『Open Up』を輸入盤レコードで聞いたのが最初だった。今考えてみると、『Ardour』の方はジャケットの良さもあり、すぐ売れてしまったのだろうと思う。大手の米キャピトルからのリリースだったが、2作品共に日本では発売されなかった。2009年に紙ジャケットの国内盤CDが出るまで半ば幻のアルバムでもあったと言える。
やはりサウンドの特徴はまずキーボードにあった。イーソスもマイケル・ポンチェック(Michael Ponczek)とL.ダンカン・ハモンド(L.Duncan Hammond)という2人のキーボード・プレイヤーがいた。
他のメンバーは、ギターにウィル・シャープ(Wil Sharp)、パーカッションにマーク・リチャーズ(Mark Richards)、ベースにブラッド・ステファンソン(Brad Stephenson)という計5人の布陣だった。
各楽器の最新機能を存分に使った技巧派のバンドという印象があり、クリムゾンやジェントル・ジャイアントのようなギミックを伴った部分も感じられる。しかし、そう思わせながら曲作りはじつに丁寧で「歌心」が各曲に感じられるところにかれらの信条があったように感じる。「もうロックンロールに酔っているばかりの音楽じゃあないぜ!」といった主張が『Open Up』の1曲目「Pimp City」の歌詞に見ることが出来て興味深い。
★音源資料H Ethos / Atlanteans
彼らはインディアナ州のフォート・ウェインの出身。中心人物はギターのシャープで、67年頃から音楽活動を開始している。当初付けたバンド名が「The Herd」や「Atlantis」だったのだが、同じグループ名を持つバンドが既に存在することがわかり、何度も変えたというエピソードが妙におかしい。
ただ、彼らも残念ながら大きなヒットを飛ばすことも出来ず、3作目を制作し始めたもののキャピトルから契約を打ち切られてしまった。しかし、2000年にその3作目の音源をもとにした『Relics』がCD化されている。
§7 ロバート・プラントとメロトロン・・・・・レヴィアサン(Leviathan)
◎画像7 Leviathan 『Leviathan』

レヴィアサンの唯一のアルバムは、メロトロンを大々的に扱ったアルバムとして有名だろう。ヴォーカリストの声がロバート・プラントに似ていると話題になったことも大きなポイントだった。最初にメンバーを紹介しておくと、ドラムス、パーカッションのシェフ・ビーヴァーズ(Shof Beavers)、ベース、リード・ヴォーカルのウェイン・ブラッドリー(Wain Bradley)、オルガン、リード・ヴォーカルのピーター・リチャードソン(Peter Richardson)、メロトロン、ヴォーカルのジョン・サドラー(John Sadler)、ピアノ、ヴォーカルのドン・スウェアリンゲン(Don Swearingen)、ギターのグラディ・トリンブル(Grady Trimble)という6人。
キーボードが3人いて、1人はメロトロン専任だ。ちょっとした驚きだったし、プログレ好きにとっては期待してしまうのは当然だろう。しかし、2人いるリード・ヴォーカルのうち、どちらがプラント的な声の持ち主なのかは分からないままだ。
このアルバムは「ニューミュージック・マガジン」74年12月号で福田一郎さんが輸入盤をレヴューしていた。それを読んで興味を持ったが、Machという知らないレーベルから出ているので入手は難しいだろうな・・・と何となく考えていた。
そんな中、2年後の1976年日本でキング/Londonから国内盤がリリースされたのだ。しかも未だレコードの時代なのに、シングルで出ていた2曲が追加されていてCDのボーナス・トラックのようで妙に嬉しかったことを思い出す。後で調べてみると、MachレーベルはLondonレコードの傘下だった。それゆえ、日本でも発売権に問題がなかったようだ。しかし、シングルは10枚程度出ているものの、アルバムのリリースはレヴィアサンのみという不思議なレーベルだった。
CD化は、2000年イタリアのAkarmaが例の厚紙ジャケットで出したことにも驚かされた。
彼らは米メンフィスで活動していたバンドなのだが、全くサザン・ロックなんて感じは受けず驚きだった。ただ、元々持っていただろう泥臭さは、特にリズム面に感じられるのだが・・・。彼らのバイオグラフィーがないのでどういう経緯でこのような音楽性を身につけたのか分からないが、ヴォーカリストの声も含めて考えるとやはりまずはレッド・ツェッペリンが原点だったと言えるのかもしれない。
★音源資料I Leviathan / Arabesque
国内盤LP帯には『ロバート・プラント(レッド・ツェッペリン)顔負けの驚異的な二人のヴォーカリストをフューチャーし、ヘヴィー&リリカルなサウンドをクリエイトするアメリカン・ニュー・ウェイヴの旗手レヴィアサン遂に登場!』と記されていた。スター・キャッスルの『星の要塞』の帯にも見られた「アメリカン・ニュー・ウェイヴ」という同じ呼び方が使われている。音楽雑誌の特集でも、そのようなくくりで前回、今回と取り上げたバンドが取り上げられていたのは確かだった。しかし、その呼び方は定着しなかった。というのも、パンク・ロックの流れから生まれた70年代後半の一連のロックをニュー・ウェイブと呼ぶようになったことで、プログレ系の音を表すにはふさわしくないと思われたからだろう。ただ、短期間ではあるものの一連の音楽をそう読んでいた時期が確かにあった。まあ、その言葉にときめいたことはないのだけれど・・・
今回のアウトロ
当時を思い出しながら綴ってみましたが、ちょっと欲張りすぎたかな・・・とも思います。その一方で「もっと紹介しておきたいグループもあった」という考えは今回も残っています。次回は、カナダ編といきたいと思っていますが、少し残った米プログレ系も幾つか取り上げようと考えています。
レコードからCDになって改めて集め、紙ジャケットになってやはり買い求め、迷いながらも関連Boxが出るとやはり触手が動き・・・と一体、どれだけつぎ込んだことになるでしょうか。
同じような方は多いと思うのですが、そんな中で音楽仲間がいて、情報交換をしながら熱く語ったことは懐かしく嬉しい思い出でもあります。当時のそうした仲間には今も感謝したい気持ちを持っています。私同様に、皆同じように聞いているのかなあ。
今回の原稿に向かいながらそんなことを考えてしまいました。
そう思い出すたびに「プログレ」は既に懐かしく過去のものになっていることも最近は特に実感します。
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第66回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ➀ ~ニュークリアスに始まった私のジャズ・ロック体験~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は、ブリティッシュ・ジャズ・ロックをテーマに語る第1弾をお届け。
氏にとって最初のジャズ・ロック体験となったニュークリアスを中心に、ソフト・マシーンなどにもフォーカスしてまいります!
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第67回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ② ~ハットフィールド&ザ・ノース、ヘンリー・カウ、そして、ギルガメッシュ、ナショナル・ヘルス・・・アラン・ゴウェンの軌跡とともに~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!ブリティッシュ・ジャズ・ロックをテーマに語る第2弾をお届け。今回はカンタベリー・ロックを語ってまいります♪
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第68回 ~ 今年も過ぎ行き冬の到来、そして新たな年に向かう今 「マイ・プレイ・リスト~冬の歌~」セレクション ~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は、氏が好きな「冬の歌」14選をお届けいたします。どうぞお楽しみくさだい☆
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第69回 ロックのヴォーカル・アンサンブルに驚かされた日々の想い出 ~ ヴォーカル・ハーモニー、コーラスの魅力 ~ 不定期連載 ➀ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は、ヴォーカル・ハーモニー、コーラスに注目して、有名アーティストからニッチなアーティストまで取り上げます。どうぞお楽しみくさだい☆
【関連記事】
COLUMN THE REFLECTION 第70回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 その① ~ KansasとStyxを中心に、プログレとしての浸透度の検証~ 文・後藤秀樹
音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はアメリカのプログレ・シーンより、その代表格である2バンドKANSASとSTYXの軌跡を辿ります。どうぞお楽しみくさだい☆
「Column The Reflection」バックナンバーはこちらからチェック!
BOSTONの在庫
TOTOの在庫
STARCASTLEの在庫
-
STARCASTLE / CHRONOS I
「アメリカのYES」と評される米プログレ・グループ、01年リリース、未発表曲&アザーテイク集
-
直輸入盤(帯・解説付仕様)、解説の規格はMAR01630です、定価2857+税、全11曲
盤質:傷あり
状態:良好
帯有
帯に軽微な圧痕あり
-
-
STARCASTLE / STARCASTLE
「アメリカのYES」として知られる人気グループ、76年デビュー作
プログレッシブ・ロックの歴史においてYESフォロワーは数知れず各国から乱立していますが、その中でも最も有名なYESフォロワーとなったアメリカのシンフォニック・ロックグループの76年作。時代がコンパクトなロックへと向かっていた時期に、アメリカ独特のポップセンスを感じさせながら70年代プログレッシブ・ロックにこだわった長尺主義などを積極的に採用しており、その演奏は本家と間違えるほどの徹底したクローン・サウンドとなっています。特にきらびやかなキーボード・サウンドにはRick Wakemanの影を感じ、ハイトーンのボーカリストはまさにJon Anderson風。ここまで徹底したサウンドを追求すればそれ自体が個性になり得るという名盤です。
-
紙ジャケット仕様、Blu-spec CD2、ボーナス・トラック1曲、内袋付仕様、定価2100+税
盤質:無傷/小傷
状態:良好
帯有
-
-
PAVLOV’S DOGの在庫
ETHOSの在庫
-
ETHOS / ARDOUR
アメリカン・シンフォ屈指の名盤、76年デビュー作!
KANSASに代表される抜けの良いキャッチーなアメリカン・プログレ・ハードとは全く違い、YESやGENESISなどからの影響をベースにし、英国然とした湿り気と気品を持ったファンタジックなサウンドを聴かせるアメリカを代表するシンフォニック・ロック・グループの75年デビュー作。どこをとっても英国的なサウンドで統一された作風であり、メロトロンやチェンバリンを駆使した儚げなサウンドとアコースティック・ギターによるGENESISのような御伽噺の世界、そしてバタバタと展開するKING CRIMSONのようなアプローチなど、こだわり抜かれた名盤でしょう。
-
ETHOS / OPEN UP
アメリカン・シンフォの代表格、77年作2ndアルバム
KANSASに代表される抜けの良いキャッチーなアメリカン・プログレ・ハードとは全く違い、YESやGENESISなどからの影響をベースにし、英国然とした湿り気と気品を持ったファンタジックなサウンドを聴かせるアメリカを代表するシンフォニック・ロックグループの77年2nd。キーボーディストの1人が脱退してしまうものの、基本的な路線は前作からの流れを持った英国然としたシンフォニック・ロックであり、前作より多少ポップ・テイストと、楽曲によってはフュージョン的なアプローチも見せています。やはりテクニカルで構築的なサウンドとファンタジックな質感が素晴らしい1枚。
LEVIATHANの在庫
-
LEVIATHAN / LEVIATHAN
メロトロンを豪快にフィーチャーした米ハード・ロック・グループ、74年唯一作
メロトロンを豪快にフィーチャーした米ハード・ロック・グループ、74年唯一作。ツェッペリンやユーライア・ヒープからの影響が感じられる陰影に富んだヘヴィネスとドアーズなどアート・ロック的な佇まいとがブレンドしたスケールの大きなアンサンブル、そこにクリムゾンの1stばりに豪快に溢れ出すメロトロン!ハードなセクションでは壮大さを演出し、バラードセクションでは独特の冷ややかさとファンタジックさを見せます。ブリティッシュ・ハードのファンには是非ともオススメした米ハードの名作!
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!