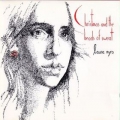「音楽歳時記」 第七十五回 5月2日 えんぴつ記念日 文・深民淳

先月は象でまとめちゃったわけですが、準備しておいたにも関わらず、すっかり忘れて置き去りにしちゃった1枚がありましたので、先月からの続きで紹介させていただきます。
THE ALLMAN BROTHERS BAND 2003年発表作品『Hittin’ The Note』です。1994年発表の『Where It All Begins』以来のスタジオ・アルバムでデレク・トラックスがメンバーとしてレコーディングした唯一のスタジオ・アルバムになります。見事に象だらけ。チラッと象が見えますなんてレベルではありません。象だらけです。しかも、当時日本ではワン・ショット契約でユニバーサルから発売されたのですが、担当ディレクターは僕でした。置き去りにして申し訳ない。
THE ALLMAN BROTHERS BANDは、今や神格化されているギタリスト、デュエイン・オールマンとディッキー・ベッツのツイン・リードがロック界のレガシーとなっており、『Hittin’ The Note』発表前からグレッグ・オールマンの死去でその歴史の幕を閉じるまで不動(と言ってもライヴでは何回か代役が立っているのですが・・・)のギター・コンビだったデレク・トラックス&ウォーレン・ヘインズはその陰に隠れがちですが、このアルバムは時代の流れを何となく気にしていた80年代、90年代のALLMANS作品と比べると遥かに初期ALLMANSに近いサウンドですし、このアルバム発表以降その歴史を閉じるまでの11年間のライヴで初期の代表曲「Statesboro Blues」、「Whipping Post」、「In Memory Of Elizabeth Reed」、「Mountain Jam」、「Jessica」、「Midnight Rider」とともにライヴで演奏され続けた人気曲目白押し!
2000年代の「Whipping Post」といったパワー・トラック「Rockin’ Horse」、元祖ジャム・バンドALLMANSの本領発揮の場面となった「In Memory Of Elizabeth Reed」、「Mountain Jam」の遺伝子を持った「Instrumental Illness」、ブルース・ロック寄りの名曲「Woman Across The River」など聴きどころは満載ですが、ここではサザン・ロックのバラードは何故か演歌に聴こえてしまう僕が自信を持ってオススメする演歌ロック至高の一品「Desdemona」をイチオシさせていただきます。
Desdemona
このアルバム、ギター2人の音が左ウォーレン、右デレクと完全に振り分けられているのですが、思い切り粘っこいウォーレンのリードからグレッグ・オールマンのヴォーカルが入ってくる瞬間が痺れます。歌い出しの歌詞がもう演歌の世界ね。ジョージア州アトランタも北区赤羽も世界はひとつ!「眠たい南部の街に雨が降る・・・」最高のつかみかと思います。この続きは是非ご自身でお確かめください。以上、象さん番外編でした。
ま、そういう訳で象の続きがありましたが、それでは5月の記念日に移りたいと思います。どうも最近、語呂合わせ記念日に偏りがちだったこともあり、今月は脱・語呂合わせ、王道の記念日を探してみようと思います。
5月2日に『えんぴつ記念日』というのがあります。えんぴつねぇ・・・我々のような年寄りは子供の頃、鉛筆削り器は高級品、ましてや電動鉛筆削り器は金持ちのボンボンの持つもの。えんぴつは自分で切り出し刀で削るという今日のガキにはほぼ不可能に近い特殊技術をほとんどのはなたれ小僧が体得していた世代の終わりの方におった訳です。今ではえんぴつはおろかシャープ・ペンシルだって使わないことが多くなっていますし、カッターナイフでえんぴつ削るのも怪我の危険性があるからと止められる世の中になっちゃいました。今、こうして原稿を入力していて、机の上のペン立てに目をやれば、シャープ・ペンシルはかろうじて1本あったけど、えんぴつなし。最後にえんぴつ持ったのいつだろうと考えてみると、だいたいそんなこといちいち意識なんかしない訳だけれど、今年に入って使った記憶がない。ま、そんな時代なわけです。
『えんぴつ記念日』は三菱鉛筆の前身の眞崎エンピツ製造所が1886年(明治19年)に新宿区に工場を設立、製造販売を開始したのが5月2日だったのを記念したものなのだそうな。
という訳でえんぴつで描かれたアートワークを探し始める訳ですが、えんぴつデッサンものとかそれなりにあるだろうと思ったものの、意外に思い浮かばない・・・。フランク・ザッパの『Fillmore East – June 1971』は元はえんぴつだと思われるし、ゲイリー・ライトの最初のソロ・アルバム『Gary Wright’s Extraction』(1970年)えんぴつデッサンのように見える。THE HOLLIES『Would You Believe』(1966年)も素の絵はえんぴつデッサンぽい。
ローラ・ニーロ『Christmas And The Beads Of Sweat』(1970年)は一瞬、お!っとなりましたがこれは多分インク使用の点描でしょうね。NEW TROLLS『Searching For A Land』も線が柔らかな感じでえんぴつ画のように見えるけど、う〜ん、これもペンかな・・・。ロバート・ワイアット『Rock Bottom』もそれっぽく見えるけどなぁ・・・。すぐに見つかりそうと思いましたがいざとなると意外に出てこないものですね。クラシックの方まで見ていくと結構いっぱいあるんですけどね。
というわけで、これはどうでしょう。バート・ヤンシュ『A Rare Conundrum』(1977年)はフロント・アートワークに部分使用といった感じです。アートワーク見てもどんなアルバムだったか思い出せなかったので聴いてみました。iTuneに入っているMP3音源で聴いたのですが、ギターの音がMP3で聴いてもかなり深みがあり、弦の鳴り、共鳴ともに申し分なし。天下のバート・ヤンシュなんだからというのもあるのでしょうが、それにしても思わず口開けて聴き惚れてしまいました。
元々は1976年にデンマークのEx Librisレーベルから『Poor Mouth』というタイトルでリリースされたものの一部楽曲を差し替えてタイトル、アートワークを一新した作品で、クレジットを見るとロンドン、AIRスタジオ、モーガン・スタジオ、ノヴァ・サウンドでレコーディングされており、1曲だけパリのC.B.E.スタジオ録音となっています。C.B.E.は1974年発表、カリスマ・レーベル移籍第一弾となった『L.A. Turnaround』で使用しており、C.B.E.録音の「Doctor Doctor」は『L.A. Turnaround』のアウトテイクの流用のようです。
プロデュース、ベースはLINDISFARNE、JACK THE LADのロッド・クレメンツ、微妙にタイミングをずらし良い味出しているドラムにはDIRE STRAITSのピック・ウィザース。アナログ盤で集めていた頃には『L.A. Turnaround』の方はよく聴きましたが、この『A Rare Conundrum』の方は印象が薄かったのですが、このアコースティック・ギター・サウンドはなかなか得難いものがありました。2009年版リマスターCDは『Poor Mouth』の方にだけ収められていたトラック3曲を追加した17曲編成になっています。
さて、『A Rare Conundrum』というアルバムをもう少し近くから見て見ましょう。バート・ヤンシュが在籍していたPENTANGLEはトランスアトランティックからワーナー系のリプリーズ・レーベルに移籍して発表した『Solomon’s Seal』を最後に活動停止。PENTANGLEでの活動と並行してソロとしても英国トラッド・フォーク史に残る名作を残してきたヤンシュですが、ソロ活動一本で活動を続ける上での新たな方向性を示した作品が先に挙げた74年発表の『L.A. Turnaround』でした。元MONKEES、脱退後はソロ、THE FIRST NATIONAL BANDを率いたマイケル・ネスミスをプロデューサーに迎えロニー・レーンのモービル・スタジオ・ユニットを使用してレコーディングした素材をLAのサウンド・シティ・スタジオで仕上げものをメインに2曲だけパリのC.B.E.スタジオで録音し、ダニー・トンプソンがプロデュースしたものを加え発表された作品で、従来からのアコースティック弾き語りスタイルとジェシ・エド・デイヴィスやペダル・スティール・ギター奏者レッド・ローズらを迎えたバンドを従えカントリー・ロック・スタイルのナンバーにも挑戦した作品です。意欲的な作品でしたが発表当時は賛否両論だった記憶があります。この『L.A. Turnaround』に続き翌75年に発表された『Santa Barbara Honeymoon』では弾き語りとバンド・スタイルのバランスがバンド側に大きく傾きしかもAORマーケットを強く意識したフォーク・ロック路線。フォーク系のアーティスト、例えばイアン・マシューズがAORマーケットに接近していったり、リチャード・トンプソンがギタリスト、シンガーとしてレイドバック路線に踏み出していったり転機の時代だったのは確かでしょうが、ヤンシュの変貌に対しては否定的な論調がほとんどでした。バート・ヤンシュの全キャリアを通じて最もポップな作風なのですが、AOR寄りのフォーク・ロックとしてもフォーク・アルバムとして中途半端な感は拭えない作品だったと思います。
『A Rare Conundrum』はやっては見たけれども向いていなかったフォーク・ロック路線に見切りをつけ原点に戻ってきた作品です。弾き語りとベース&ドラムにフィドルが加わるくらいの最小限のバンド編成で、バート・ヤンシュ自身のセールス・ポイントはその卓越したギターの調べと朴訥な声で伸びやかに歌い上げるフォーク・スタイルであることを宣言した作品であり、キャリア後期のスタイルの基本形を示した作品であったと思います。えんぴつ記念日がなければ僕自身、完全に忘れていたアルバムでしたし、極めて地味なアートワークなんですが、今回聴き直して心引かれました。そのふくよかなギターの調べは正に宝です。
Three Dreamers and Dragonfly
僕のイマジネーションが貧困なせいもあるのでしょうし、引っかかったのがバート・ヤンシュの作品だったこともあるのですが、えんぴつ由来はロックよりもフォークっぽいイメージということになり、フォーク系であれこれ探していたら、伝統派の重鎮というべきバート・ヤンシュの反対側に生きる改革派の重鎮にもえんぴつ由来のアートワークものがありました。ロイ・ハーパーです。
ロイ・ハーパー『Valentine』はかなりそれっぽい雰囲気。通算8作目に当たるスタジオ・レコーディング作で、ここに至るまでに書きためてきたラヴ・ソングを中心に収録した作品です。因みに『Valentine』はアートワークが3種類あってオリジナルのアナログ盤に使われたもの、1989年にAwarenessレーベルからでたCDに使われたもの、1994年Science Frictonからの再発CDとそれぞれデッサン画の絵柄が異なっていてどれもえんぴつデッサンぽいタッチです。最初のHarvestからのアナログ盤とScience FrictionのCDは正面を向いて軽く握った右手をかざしたポーズは同じで絵が違いますが、Awareness盤は斜め左からのポーズで3つの中では一番リアルなデッサンとなっています。このAwareness盤のポートレートは彼の当時の奥さんが描いたものだそうです。

ロイ・ハーパーはPINK FLOYD『Wish You Were Here』への参加やLED ZEPPELINのメンバーとの親交が深かったことでも知られていますが、アルバムのバックで参加したメンツはなかなか豪華です。まず1970年発表の『Flat Baroque and Berserk』収録の「Hell’s Angels」のバックはTHE NICE。続く初期の代表作『Stormcock』にはジミー・ペイジが変名で参加。アコースティック・ギターを弾いていますし、1973年発表の『Lifemask』にもジミー・ペイジ、EDGAR BROUGHTON BANDのスティーヴ・ブロートン、THE NICE解散後のブライアン・ダヴィソンらが参加しています。こうしたロック人脈との繋がり、LED ZEPPELINのツアーに参加したことが影響したのでしょう、この『Valentine』が発表された1974年はロイ・ハーパーのサウンドがよりロックにシフトしていく転換期の始まりだったのではないかと思います。
『Valentine』には3度目の参加になるジミー・ペイジを始めTHE WHOからキース・ムーン、FACESのロニー・レーン、スティーヴ・ブロートン、マックス・ミドルトンら参加。また、このアルバム発売に合わせ同年の2月14日ヴァレンタイン・デイにはロンドン、レインボー・シアターでジミー・ペイジ、ジョン・ボーナム、ロニー・レーン、キース・ムーン、マックス・ミドルトンらで構成されたバンドをバックにライヴを行い、この音源の他いくつかの会場で録音されたライヴ・トラックを集めスタジオ録音の新曲「Home」(フルートでイアン・アンダーソンが参加)を含むLP2枚組コンピレーション・ライヴ・アルバム『Flashes From The Archives Of Oblivion』を発表します。
『Flashes From The Archives Of Oblivion』は新曲「Home」スタジオ版からスタートし、ラストにレインボー・シアターに於けるヴァレンタイン・コンサートでのライヴ・ヴァージョンの「ホーム」で終わる構成になっていましたが、Awareness、Science Frictionから発売されたCDではこの構成が変わっています。
『Flashes From The Archives Of Oblivion』はLP2枚組でその全容をCD1枚に収めることができなかったため、スタジオ版「Home」、ヴァレンタイン・コンサートのオールスター・バンドをバックに従えた「Too Many Movies」とライヴ版「Home」が同じくCD版『Valentine』のボーナス・トラックとなっています。
Home
バート・ヤンシュはえんぴつデッサン画をフロント・アートワークに配した『A Rare Conundrum』で本来あるべき姿に戻ってきますが、ロイ・ハーパーは逆に『Valentine』を起点にロックのフィールドに急接近していきます。74年の2作品『Valentine』と『Flashes From The Archives Of Oblivion』に続くアルバムは1975年3月にロンドン、アビー・ロード・スタジオで制作された『HQ』。このアルバム制作のためにギターにクリス・スペディング、ドラムにビル・ブルフォード、ベースにデイヴ・コクランからなるTRIGGERを結成。アルバム制作だけではなくライヴも行なっています。
ハーパーが『HQ』制作のためアビー・ロード・スタジオに入った時、同スタジオでアルバムを制作していたのがPINK FLOYD。いうまでもなく『Wish You Were Here』のレコーディングでした。これが縁となりハーパーは『Wish You Were Here』へ参加となり、PINK FLOYDからはデイヴ・ギルモアがハーパーのセッションに参加。『HQ』のオープニングを飾った13分超えのハード・ロック・トラック「The Game (Parts 1-5)」にリード・ギターで参加。ベースもLED ZEPPELINからジョン・ポール・ジョーンズが参加しています。
アルバム『HQ』はギルモアとJPJが参加した「The Game (Parts 1-5)」を筆頭にソリッドなロック・トラックがメインの作品ですが、もうひとつハーパーの代表曲と言っても過言ではない英国臭全開、哀愁のメロディラインに聴いていて思わず居ずまいを正す「When An Old Cricketer Leaves The Crease」も収録されています。発売当時、英国盤、日本盤などはヒプノシス・デザインによる波間を悠然と渡ってくるロック・アーティスト然としたハーパーのフォト・コラージュを使用したアートワークが使われていましたが、アメリカでの発売権を持っていたクリサリスはアルバム・タイトルを『When An Old Cricketer Leaves The Crease』に変更。アートワークもクリケットのユニフォームを着ているものの何故か上半身裸のハーパーの写真が使われていました。
When An Old Cricketer Leaves The Crease
CD版にはボーナス・トラックとしてその名曲「When An Old Cricketer Leaves The Crease」の1977年10月31日エクセター公演からのライヴも収録されています。このエクセター公演のバックを務めたのがCHIPS(BLACK SHEEPと名乗った時期もあるようです)。メンバーはこの時期ハーパーと親交が深かったアンディ・ロバーツ、ヘンリー・マカロック、GREENSLADE解散後のデイヴ・ローソン、元PATTOのドラマー、ジョン・ハルセイ、TRIGGERから残留したデイヴ・コクラン。『HQ』に続くアルバム『Bullinamingvase』のレコーディングに参加したメンバーによるバンドでした。
『Bullinamingvase』のレコーディングは『HQ』以上に多彩なゲストが名を連ねており、アルヴィン・リー、ポール&リンダ・マッカートニー夫妻、パーシー・ジョーンズ、BJコール、ハービー・フラワーズらの他、古くからのお友達筋スティーヴ・ブロートン、ロニー・レーン、マックス・ミドルトンが名を連ねています。
『HQ』がソリッドでハード・ロック寄りのサウンドであったのに対し、この『Bullinamingvase』はアンディ・ロバーツをパートナーとして、ヘンリー・マカロックが加わり、そこにデイヴ・ローソンが乗っかったものですからなんとも滋味深い田園系プログレ・フォークが展開されるのです。アルバムはパート1を独立したナンバーとした「One Of Those Days In England」と組曲構成に仕立てた「One Of Those Days In England (Parts 2-10)」を中心としており、パストラル感満載のスライド・ギターの後ろでメロトロンが鳴っているたおやかなパートがあったり壮大なスペース・ロック展開へと発展する場面あったり奇想天外なサウンドが楽しめます。アナログ盤で発売されていた当時は初回盤のA面ラストに収録されていた「Watford Gap」がその後「Breakfast With You」に変更になりましたがCDではどちらも収録されています。
One Of Those Days In England (Parts 2-10)
バート・ヤンシュとロイ・ハーパー。どちらも英国フォーク・シーンを代表する重鎮ですが、えんぴつデッサン風アートワークの作品が片方は収束、片方は拡散に繋がっていったのが興味深く取り上げてみました。
さて、今月の1枚ですが、これもえんぴつ繋がりです。実は『えんぴつ記念日』で最初に頭に浮かんだのはこのアルバムです。しかしながらこれを最初に出してしまうとドッと疲れてそれだけで終わってしまいそうでしたので最後に持ってきました。僕の守備範囲ではありませんが何故かアナログ盤で持ってました。30年以上聴いていません! 後は寝るだけの状態で聞きたいと思います。THE DICKIES『The Incredible Shrinking Dickies』(1979年)です。

Xと並びLA最古のパンク・バンドとして知られるバンドのメジャー・デビュー作。5年くらい前にネットのニュースでまだ活動中っていうのを読んだ記憶がありますので、まだやっているかもしれません。ほとんどパンク・ゾンビですね。引っかかりネタとしてはBLACK SABBATHの「Paranoid」のカヴァーをやっていること。ただでさえ騒々しいこの曲がよりスピードアップして騒々しくなっております。ついでに西海岸のバンドなのにシングル・カットした「Banana Splits」は何故かイギリスでヒットし、チャート・インも果たしました。「Banana Splits」なんだそりゃ、と思う方多いと思いますがこれ曲聴くと「あ!これ知ってる」となると思います。ライヴ写真とか見ると着ぐるみ着て演奏しているメンバーもいて音聴けば一発でわかるようにコミック系パンク・バンドなわけですが、実はこのアルバム、パワー・ポップのアルバムとしては結構優れている作品だったりします。
ま、騒々しいったらありゃしないんですけどね。それでは37分50秒聴き通しましたのでもう寝ます。
Paranoid
Banana Splits
「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!
LAURA NYROの在庫
BERT JANSCHの在庫
-
BERT JANSCH / JACK ORION
英国トラッド・フォーク界の最重要ミュージシャン、66年3rd
-
盤質:傷あり
状態:良好
スリップケースなし、若干スレ・軽微な汚れあり、若干ケースツメ跡あり
-
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!