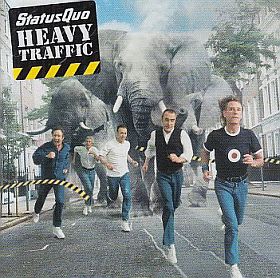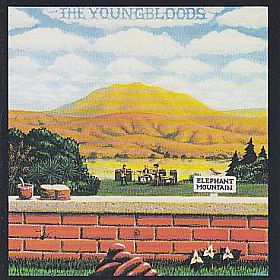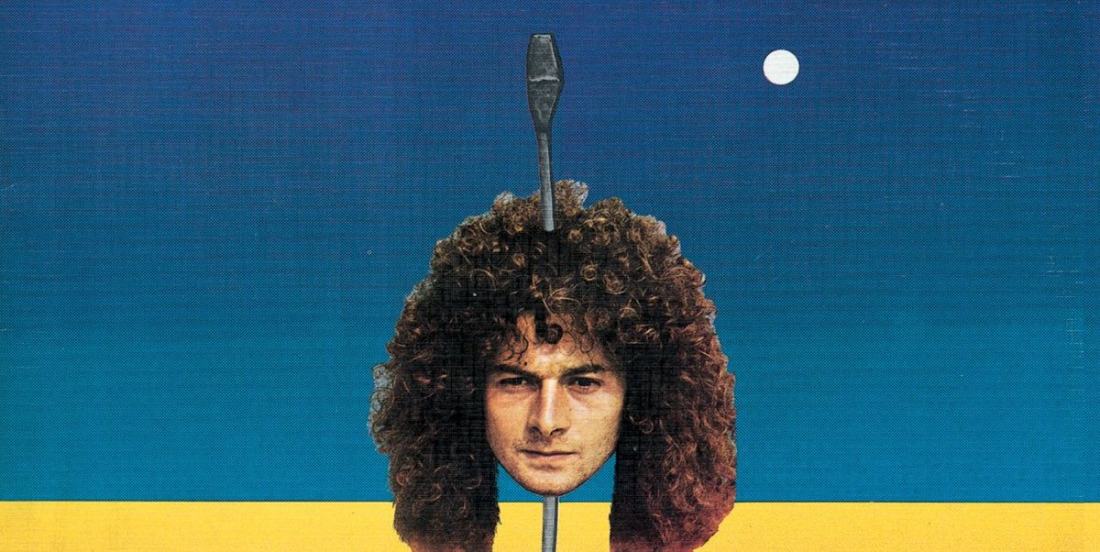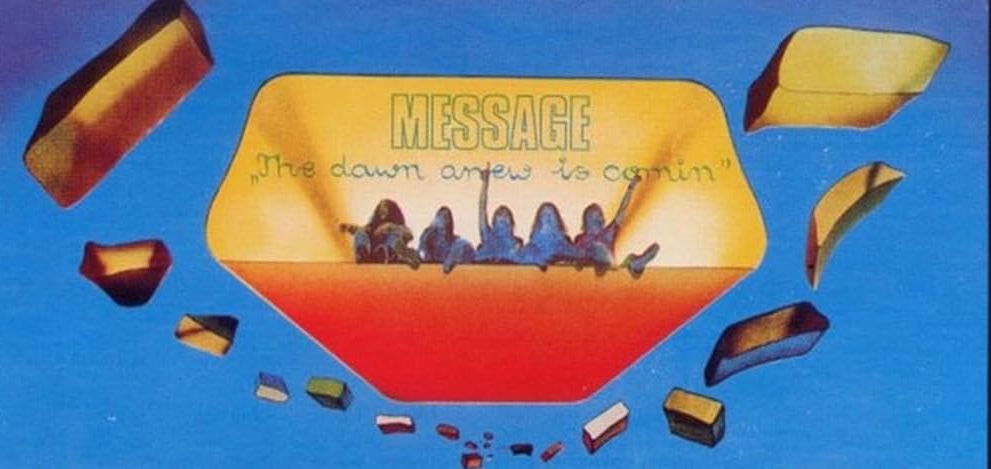「音楽歳時記」 第七十四回 4月28日 象の日 文・深民淳

最近はTVのクイズ番組でも語呂合わせの記念日を当てるクイズが出題されていますが、象印マホービンが4月10日に制定した記念日はかなり強引かつ脱力系で思わずヘラヘラしてしまいました。「ステンレスボトルの日」なのだそうです。中国語の四の「スー」と英語の10の「テン」で「ステン」と読ませる荒技系記念日です。発案者は間違いなく麻雀好きでしょう。雀荘で卓を囲み、「リーチ一発、四暗刻、ドラドラ」とか言った瞬間、記念日の神が降りてきた。または誰かにデカい振込みをやっちまい「今日はスッテンテン」としょんぼりした瞬間に「スッテンテン…ん?スー、テンテン…スー、テンレス!」ここにも記念日の神は降りてまいります。
これを記念日に制定するための社内会議を想像しても、思わず頬が緩みます。提案した方も承認した方もかなりパンチが効いています。というわけで、携帯用のステンレスボトル1本買っても良いかなと思っていたので、僕は象印のヤツを購入しようと思います。
話変わりまして、4月28日は「象の日」となっています。1729年(享保14年)、ベトナムからの献上品として清の商人により初めて象が日本にやってきたのに因んだ記念日だそうです。最初に中御門天皇の御前で披露され、その後江戸に運ばれ、5月27日に将軍徳川吉宗に送られたそうです
象関係も色々ありますね。FLOWER KINGS 2019年発表の『Waiting For Miracles』。
バランスを取る象にはMR. BIG 2017年発表の『Defying Gravity』というのもありました。STATUS QUO 2002年作品『Heavy Traffic』ではメンバーが象に追いかけられているという設定なのですが、リアルでやったわけではないので、そのジャケット写真は顔やポーズに緊張感が今ひとつ。後ろに合成された象がいなければ普段着でジョギングといった印象です。
1968年発表THE BANDの名作『Music From Big Pink』にはボブ・ディラン画伯が描くところの象がおりますし、エルヴィス・コステロがElvis Costello & The Attractions名義で発表した『Armed Forces』は荒ぶるアフリカ象の一群を描いたイラストでした。このイラストで謎なのはKhaliq Al-Rouf & Salaamというジャズ・ファンク系のユニットが1979年に発表した『The Elephant Trot Dance』のアートワークが『Armed Forces』のイラストのセンターの象とよく似ていること。Khaliq Al-Roufの方はOgundipeというおそらくナイジェリアあたりのアフリカ人アーティストが描いた絵画が使われています。ふたつを並べた画像を用意しました。左がエルヴィス・コステロのアートワーク、右がKhaliq Al-Roufです。このふたつ似てますよね?

あれ?そうだっけ、という感じのものではMOODY BLUES『Question Of Balance』にも象がいます。ちょうど見開きアートワークの背の部分にかかるあたりにいるのでちょっと分かりにくいのですが。故ジョン・ロードのソロ・アルバム『Before I Forget』は鼻が結ばれてしまった象のイラストでした。ジョン・ロードのアルバムのように赤バックに象のイラストというパターンはWHITE STRIPESの『Custom Elephant Singles Box』(2014年)というのもありました。2003年のアルバム『Elephant』からのシングルを集めたボックスみたいですね。僕は持っていません。ブライアン・アダムス 1998年作『On A Day Like Today』も象がらみですね。

バンド名、タイトルの方に目を移してもたくさんあります。まずは皆さん思い浮かべるELEPAHNT MEMORY。1972年にアップル・レーベルから発表した『Elephant Memory』(1969年にブッダ・レーベルから発表した1stアルバムも『Elephant Memory』でしたが・・・)象の墓場のモノクロ・アートワークがショッキングな1枚。日本にはTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTがありましたし、60年代末に活躍したアメリカ産バブルガム・ポップのCRAZY ELEPHANT、ズバリELEPAHNTを名乗るバンドもいくつかあります。タイトルの方に行くとNEKTAR『Down To Earth』には「Nelly The Elephant」なる曲が収録されていますし、スペル違いの「Nellie The Elephant」はTOY DALLSのヒット曲。放題「ネリーさんだ象!」でお馴染みのあれです。1969年発表のYOUNGBLOODSの3rdアルバムのタイトルは『Elephant Mountain』。YOUNGBLOODというと最大のヒット曲「Get Together」収録の1stアルバムが人気ですが、フォーク色、サイケデリック・ポップ色、ジャズ・テイストが渾然一体となった『Elephant Mountain』もまた彼らの名作と言って良いかと思います。ジェシ・コリン・ヤングがソロになった後にセルフ・カヴァーし、ライヴの定番演奏曲となっていた名曲「Sunlight」のオリジナルも収録されています。
Sunlight
さて、空飛ぶ象といえばウォルト・ディズニーのアニメでお馴染みのダンボです。体が大きく体重も重い象が耳をパタパタさせて飛ぶところに映像的面白さがあるのでしょうが、ロック系にも空飛ぶ象はおります。ロジャー・ディーンが描く空飛ぶ象はOSIBISAの1st『Osibisa』と2nd『Woyaya』に登場します。また3rdアルバム『Heads』は人面象のイラストですし、2009年の『Osee Yee』では昆虫の頭が象になっており、2015年に出たコンピレーション・アルバム『Singles A’s & B’s & 12 Inches』では象の頭の部分が戦車の砲台になったイラストが使われ流など象モチーフ登場率の高いバンドです。
OSIBISA現在もバリバリ活動中です。リーダーでサックス担当のテディ・オセイを中心に現在もコンスタントにライヴ活動を行っており、2021年4月には『New Dawn』なるタイトルのニュー・アルバムが発売になるそうです。
今回はこのOSIBISAに代表される70年代初頭にアフロ・ロックという呼び名で括られていたバンドを取り上げたいと思います。歯切れの悪い書き方していますが、当時の括り方って、純粋にアフリカ出身の黒人バンドだけではなく西インド諸島、パナマ出身バンドも一緒の括りに入っていましたし、実際、アフロ・ロックのシンボルと言っても過言ではないOSIBISAもアフリカ出身者とカリブ出身者によって構成されていたわけですしね。ただ、アメリカのジャズ・シーンからロックに寄って来たものまで入れちゃうと収拾がつかなかくなってしまいますので、ここでは主にイギリスで活躍したバンドを中心に取り上げて行きます。
まず最初はMANDRILL。イギリス中心と言いながら初っ端からニューヨークはブルックリンのバンドです。パナマ出身のカルロス、リック、ウィルフレドからなるウイルソン兄弟が中心となって結成されたバンドで1971年にポリドールからデビューし、現在も活動しています。イギリスで活躍したOSIBISAやASSAGAIなどと比較すると取り上げられる頻度は高くなく、名前は知っているけど音の方は馴染みがないという方が多いと思います。でも、彼らがオリジナルの楽曲、絶対に一度は聞いたことあると思います。アントニオ猪木のテーマとなっている「炎のファイター 〜Inoki Bom-Ba-Ye」の元曲「Ali Bombaye」です。作曲はダイアナ・ロスの「Do You Know Where You’re Going To (Theme from Mahogany)」やホイットニー・ヒューストンへの楽曲提供で知られるマイケル・マッサーですが、1977年に公開されたモハメド・アリの伝記映画『Muhammad Ali In “The Greatest”(邦題:アリ/ザ・グレーテスト)』の挿入歌としてMANDRILLが演奏しています。同曲はアリが1976年の猪木と格闘技世界一決定戦で対戦した後にアリから猪木に寄贈されたそうです。
Ali Bombaye
この「Ali Bombaye」を制作するあたりではかなり洗練されたファンク・ロック・サウンドになっていましたが、初期3作はアフロ・ロックという名称から想起されるイメージそのものの熱いファンク系ジャズ・ロック・サウンドが堪能できます。特に1971年のデビュー作『Mandrill』はしなる・うねる・疾走する変幻自在の重力感溢れるリズム・セクションの上をホーン、オルガン、ギターが乱舞する驚異的なジャズ・ロック。特に後半に置かれた組曲「Peace and Love (Amani Na Mapenzi)」はイギリスのプログレ系ジャズ・ロック好きにもアピールする高品質楽曲。パート4の「Peace and Love (Amani Na Mapenzi): Movement IV (Encounter)」なんかはジャズ・ロック版URIAH HEEP「July Morning」といった趣です。
Peace and Love (Amani Na Mapenzi): Movement IV (Encounter)
イギリスの方に目を向けるとOSIBISA、ASSAGAIの他にもDAWNレーベルから1970年に出たDEMON FUZZ。所属プロダクションがMUNGO JERRY、TITUS GROAN、MIKE COOPERらが所属していたレッド・バスだったためプロダクションと強いコネクションがあったPYEレーベル系DAWNからデビューとなった次第。このDEMON FUZZはアフロ・ロックというより、ギターがジミ・ヘンドリックスから影響を受け、サウンド全体はTRAFFIC等イギリスのジャズ・ロック系バンドに近いです。ホーンもパーカッションも入っているのですがトライバル系のテイストは薄い作品です。
Disillusioned Man
同じくDAWNレーベルから1971年に出たNOIRもブラスやパーカッションがドカドカ入るタイプではなく全体的にダウナー系。ミックスを少し変えるとヘヴィ・ロックとしても十分通用しそうなどんよりした重さを持ったサウンド。サウンドだけの印象は個人的にはBLACK WIDOWとかと思い浮かべましたね。ただそこにトライバル系のチャントのようなヴォーカル・パートが乗ることで様相は一変。ソロのチャントだけではなくコール&レスポンスも多用しており、これがアフロ・ロック的色付けになっています。
Rain
RCAネオンからにはCHRIS McGREGOR’S BROTHERHOOD Of BREATHがいました。南アフリカの白人ピアニストであるクリス・マクグレガーを中心とした白人・黒人混成バンドでした。
The Bride
それでは像つながりのOSIBISAに戻ります。まずその前にアフロ・ロック系バンドがイギリスに多かった背景にあるイギリスの植民地をざっとさらっておきましょう。アフリカではウガンダ、エジプト、ガーナ、ガンビア、ケニア、ザンビア、シエラレオネ、ジプティ、ジンバブエ、スワジランド、スーダン、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、ブルンディ、ボツワナ、マラウィ、ルワンダ、レソト。今回のアフロ・ロックとも関連があるカリブ海地域はアンティグア・バーブーダ、グレナダ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネイビス連邦、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、バルバドス、バハマを植民地としていました。
OSIBISAのリーダーであるテディ・オセイはガーナ出身で1950年代から本国で音楽活動を行っていました。ガーナは1957年3月6日にイギリスの支配下から独立していますので、オセイが音楽活動を開始したのは丁度、自国が独立する時期だったわけです。当時オセイはガーナでSTAR GAZERSなるハイライフ・バンドを組んでいたそうです。ハイライフはガーナの音楽ジャンルでガーナの伝統的な旋律を持つ音楽を植民地化で入ってきた西洋の楽器で演奏するハイブリッド・ミュージックでした。
1962年オセイはガーナ政府からの奨学金を得てロンドンに留学。1964年にOSIBISAの母体となるCAT’S POWを結成。その活動を通じてOSIBISAの中心メンバーとなるソル・アマルフィオ(ds)、マック・トント(トランペット他)と出会い1969年にOSIBISAは結成されます。多様化するブリティッシュ・ロックの大きな波の中、ロックとジャズの融合や50、60年代に労働力としてアフリカやカリブ海地域からの移民がイギリスに増えたことを追い風としてOSIBISAは1971年にMCAからデビューします。
ロジャー・ディーンの描いた昆虫の羽を持った空飛ぶ像のアートワークのインパクトもあり、OSIBISAのデビュー・アルバムはイギリスをはじめとするヨーロッパ各国のみならずアメリカでも注目を集めます。日本でも話題となりOSIBISAのアップサイドを象徴する人気曲「Music For Gong Gong」は「熱狂のゴンゴン」と邦題でシングルも発売されました。
デビュー・アルバム『Osibisa』は個人的には彼らの全作品の中で最高の一枚かと思います。2nd『Woyaya』(正確には二つ目の”O”の左側が空いており”C”が逆になったような表記が正しいそうです)以降では失われる素朴さに引かれるのです。まずドラムの音色。『Woyaya』以降はロック・バンド然としたドラム・サウンドになっていきますが、この1stでのドラム・サウンドはドラムというよりほとんど太鼓。それも音楽のための太鼓ではなく生活の中の伝達手段であった太鼓の響きを感じます。またアフリカの夜明けを表したドラマティックなオープニング・ナンバー「Dawn」におけるウェンデル・リチャードソンのギター・ソロもロック・バンド的ギター・ソロを強く意識するあまり妙にたどたどしく、聴いている方が心配になってくるぎこちなさ。でもそのぎこちなさが味になっていたのですが、2nd以降は淀みないソロになってしまいます。全体を通してレコーディングに慣れていなかったというのが根底にあるのでしょうが、経験値とテクニックはまだまだでもそれを補っても余りある高揚感と演奏することの喜びが全編に溢れかえっており、爽快この上ない作品に仕上がっているのです。
極めつけはやはり「熱狂のゴンゴン」でしょう。トライバル・リズムというのは万国共通の何かがあるのでしょうかね? ドラムのリズム・パターンはどこか盆踊りを思わせ、スタジオ録音ということで何度も合わすリハーサルを行ったに違いないホーン・セクションが叩き出すメイン・メロディはどこか日本の民謡のメロディを思わせる素朴な味わい。遠くアフリカのリズムと旋律が日本人が親しんできたリズムと旋律に近いものを感じるというのも不思議です。
OSIBISA、演奏力はアルバムを重ねるごとにどんどん向上していくのですが、このデビュー作だけが持つ晴天ロックの魅力は何ものにも代えがたい魅力を持っていると思います。
Music For Gong Gong
このOSIBISAと並びアフロ・ロックの代表格みたいな位置付けにあるのが、ASSAGAI。南アフリカとナイジェリア出身のメンバーによるバンドでした。今も活動を続けるOSIBISAと異なり、2枚のアルバムを残したのみにも関わらず、今も語られている背景にはデビュー作がVERTIGOのSwirlレーベルで出ていたというのが大きいのでしょう。ドラムのルイス・モホロやサックスのドュドュ・プクワナらはASSAGAI以降も英ジャズ・シーンで活躍してきたプレイヤーではありますがやはり、その名を残す最大要因はやはりVERTIGOから出ていたというのが大きいと思います。2ndアルバム『Zimbabwe』もVERTIGOから発売される予定で6360 058と番号まで決まっていましたが、結局、VERTIGOからの発売は見送られ、同じくPHONOGRAM系のPHILLIPS 6308 079として発売されます。1stはレゲェにも通じる後ろノリの脱力系サウンドが魅力でしたが、2ndアルバム『Zimbabwe』はかなりジャズ・ロック度がアップ。ブラスとパーカッションが活躍するアップ・テンポのナンバーとキーボード、フルートが霧がかったミステリアスなムードを醸し出すスロー・ナンバー、ジャズ寄りのミッドテンポ・ナンバーとのバランスが良くブリティッシュ系ジャズ・ロック・マニアには侮れない内容の作品となっています。
アップ・テンポ系ではオープニングの「Barazinbar」のホーン・セクションのメロディが後のHAIRCUT 100「Favourite Shirts (Boy Meets Girl)」ホーンのメロディっぽかったり、ラストの「Kinzambi」は逆にメロディが思い切りLED ZEPPELIN「Whole Lotta Love」(CCSかよ!)だったりと結構引き込まれますが、やはりこのアルバムの聴きどころはミステリアス・ムードのスロー&ミッドテンポ・ナンバーにあるように思います。スローの「La La」は叙情的なフルートのメロディが美しく、それだけ聴くとCAMELみたいなんだけれどもそこにトライバル音階でハイトーンのヴォーカル・パートが被ってくるため不思議な魅力を醸し出しています。またミッドテンポの「Sanga」はヒンヤリとしたサックスとフルートのソロをフィーチュアしたジャズ・ロック然としたナンバーでそこに思い切り被せたパーカッションがなければNUCLEUS風だったりします。演奏力に関しては今回ピックアップしたバンドの中ではMANDRILLと並びかなりのテクニック。因みにアートワークはみなさん何となくお判りかと思いますがこれもロジャー・ディーンの手によるものです。
Barazinbar
Kinzambi
今月の1枚は先月の続きとなります。vocalionのマルチ・チャンネルSACDシリーズまとめ買いしてみました。SACDフォーマットは対応プレイヤーがないと再生できませんが、SACD再生環境・マルチ・チャンネル環境がなくてもとりあえずはCDプレイヤーで2ch再生は可能なCDコンパチブル仕様になっています。この手のディスクは気がついたら製造終了となっていることが多いので、気になるものは後回しにせず入手しておくのが吉ですが、世の中そううまくはいかないもの。そういう時に役立つのがここカケレコ。毎度お世話になっております。
さて、発表当時からその存在は知っていたものの、4ch再生装置がなかったので聴いたことがなかったMOTT THE HOOPLE『The Hoople』。2chステレオ・ミックスはギターやホーンがかなりギチっと詰まった音の壁状態のサウンドでしたが、4chミックスの方はレイアウトに余裕があるため、聴き慣れたステレオ・ミックスとはだいぶ違った印象を受ける内容でした。僕は普段のセッティングが2台のサブウーファー強めでメイン・スピーカーのウーファー再生域と被りめのクロスオーヴァー設定にしているのですが、そのまま再生したら低音域が出過ぎでボコボコしたサウンドになってしまいました。それくらい低音再生に関しては強めです。またギミック多めの「Marionette」、「Crash Street Kids」などはステレオ・ミックスには無い定位をいじった遊びなどがあり楽しめました。また後半のバラード「Trudi’s Song」、「Through the Looking Glass」などもステレオ・ミックス以上にドラマティックな音像が展開されます。
今回買ったものの中で最も楽しめたのは、バディ・マイルスの『Booger Bear』とカルロス・サンタナとの共演ライヴ『Carlos Santana & Buddy Miles! Live!』のカップリング。なかでも『Carlos Santana & Buddy Miles! Live!』の4chミックスはかなりのめり込むグルーヴ感と押しの強い低音が魅力的です。2chステレオ・ミックスは元々ポストプロダクションに問題が多く、後から被せたとってつけたかのような観客の拍手の雑な扱いやベタッとしたミックスから内容イマイチみたいな風評が付いて回っていた作品ですが、2chでは雑な感じのミックスが4chになると逆にリハスタできっちりと作り上げたものではなく、有名ミュージシャン同士の最低限の打ち合わせから展開されていくセッションの熱いグルーヴ感を際立たせる形に変化しています。相変わらずよく意味がわからない突然の拍手は4chになると更に白々しい雰囲気になってしまいますが、演奏オンリーの部分はサラウンド・スピーカー部分もメインと同じくらい強く鳴らす荒っぽいミックスが演奏のグルーヴ感を際立たせ、うるさい・暑い・圧迫感ハンパなしのファンク空間を創出しています。同梱の1974作『Booger Bear』もR&B寄りのファンク・ロック・サウンドが熱いアルバムなのですが、『Carlos Santana & Buddy Miles! Live!』のど迫力の前には涼しく感じるほど。4chミックス版『Carlos Santana & Buddy Miles! Live!』濃いめのファンク・ロックにどっぷりと浸かりたい方には強くお薦めします。文字通り浸かれます。
「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!
OSIBISAの在庫
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!