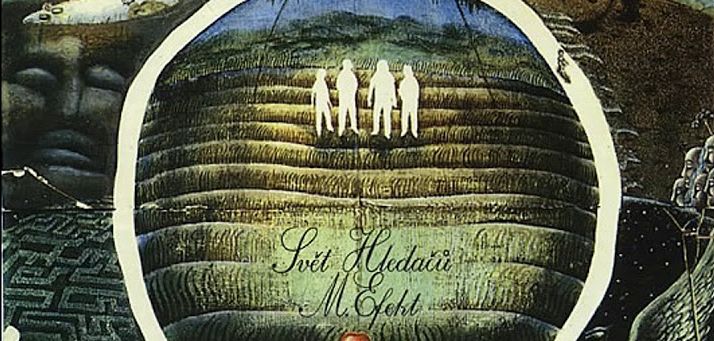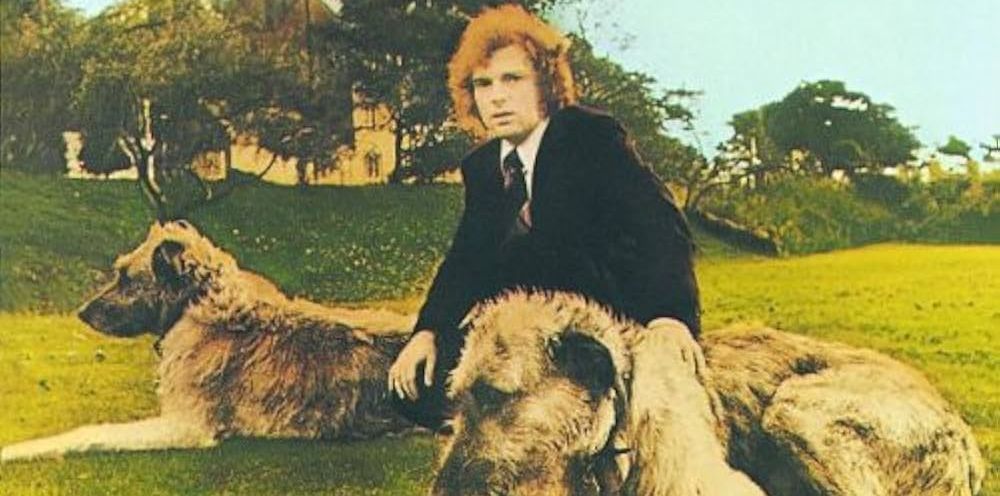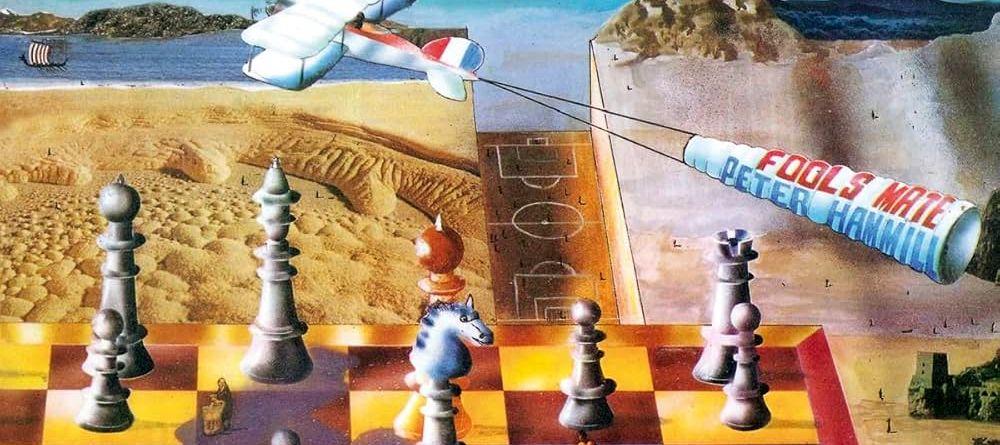<ロック黄金時代回想企画>1969年デビュー・アルバム特集Vol.9 ー THIRD EAR BAND『Alchemy(錬金術)』
2019年7月29日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ
タグ:
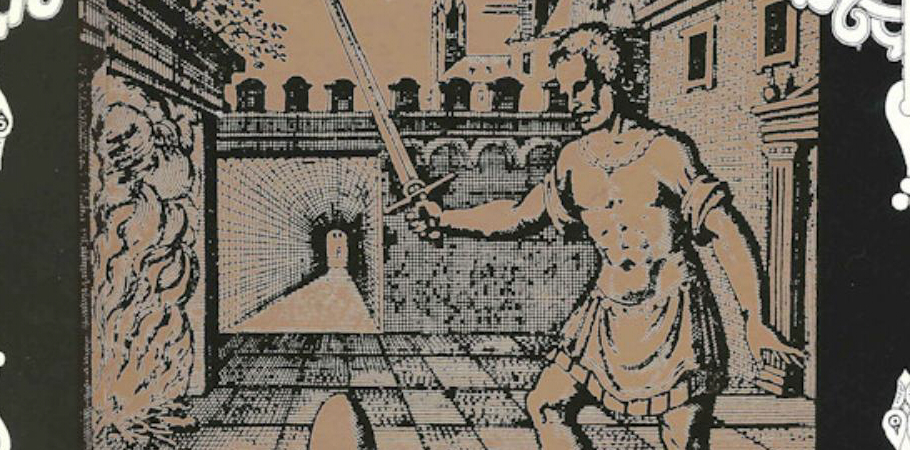
こんにちは。スタッフ佐藤です。
3月より連載中の特集「ロック黄金時代回想企画【1969】」。
ちょうど今から50年前、ロックが多様なスタイルへと細分化していく転換期と言えた1969年に着目し、ロック史に名を残す重要アーティスト達による69年デビューアルバムを連載形式で取り上げていきます。
今回は、異端のブリティッシュ・プログレ・バンドTHIRD EAR BAND(サード・イヤー・バンド)によるデビュー・アルバム『Alchemy(錬金術)』を取り上げます!
“チェンバー・ロックの創始者”サード・イヤー・バンド
サード・イヤー・バンドについて語る際にキーワードとなるのが「チェンバー・ロック」。
クラシックの中でも少人数編成の重奏「室内楽」(チェンバー・ミュージック)の要素を取り入れたプログレの一スタイルで、サウンドの性質上、ヴァイオリンやチェロといった弦楽器の奏者を編成に含みます。加えてオーボエやサックスなど管楽器奏者を含む場合も多いです。
さてチェンバー・ロックと言えば、73年にデビューしたヘンリー・カウが代表的存在として知られますが、その4年も前にすでにチェンバー・ロック作品が生まれていたとなると、なかなか驚きですよね。
百聞は一見に如かず。ということで、まずはアルバムの中から冒頭を飾るこの曲をお聴きください。
Mosaic
原始的なリズムが絶え間なく刻まれ、ヴァイオリンとオーボエが即興で不穏なフレーズを応酬し続ける、魔女の住む森で鳴らされているような一種呪術的なサウンドが印象的です。
HENRY COWの技巧的で知性みなぎるサウンドからすると印象はだいぶ違いますが、間違いなく「チェンバー・ロック」の起点がここにはあります。
それでは、いかにしてこの孤高のサウンドが生まれるに至ったのか、彼らの経歴を辿りながら見てみましょう。
アルバムデビューまでの経緯
サード・イヤー・バンドの中心メンバーとなるのがドラマーのGlen Sweeney。
彼は、詩の朗読を交えてフリー・ジャズを演奏していた自身のバンドSOUNDS NOVAを経て、66年~67年頃には3人組グループGIANT SUN TROLLEYとして、当時オープンしたばかりだったUFOクラブなどでピンク・フロイドらと共に出演するなど実績を重ねていきます。
3人のうちの一人は、早逝の名ジャズ・ピアニストMike Taylorのリーダー作品『Pendulum』でJohn Hisemanらと共にプレイした管弦奏者Dave Tomlinでした。
67年にそのTomlinがグループを離脱することになりGIANT SUN TROLLEYは解散。Sweeneyはフリー・ジャズ的なアプローチを改め、よりポップでエレクトリックなサウンドを取り入れた新バンドの結成に動きます。そうして同年に始動したのがサード・イヤー・バンドです。
発足後しばらくは、エレキギターを中心に据えインド音楽エッセンスも漂わせたパフォーマンスを行なっていましたが、ここでバンドの方向性を大きく変える事態が起きます。
ある日のコンサート後にエレキギターなどの楽器や機材が何者かに盗まれてしまい、これまでのスタイルでの演奏が不可能になってしまったのです。
これを機にギタリストもバンドを去り、メンバーはドラムのSweeney、オーボエのPaul Minns、ヴァイオリンのRichard Coff、ヴィオラのBenjamin Cartlandという、奇しくもチェンバー・ミュージックの基本編成で活動を続けることになりました。結果として、リード楽器にオーボエとヴァイオリンがフィーチャーされる形となり、自然な形でチェンバー・ミュージック的アプローチが完成されていったと云われます。
盗難事件が起きなければ、彼らがこの作風に目覚めることもなかったかもしれないと思うと、運命のいたずらというものを信じずにはいられません。
やがてBBCの名物DJジョン・ピールの目に留まった彼らは、69年に彼のラジオ番組で数曲をプレイし、知名度を上げます。そうして同年2月、アビー・ロード・スタジオで1stアルバムの制作に乗り出すのです。
69年デビュー作『ALCHEMY』
一曲目はすでに聴いていただきましたので、他の注目すべきナンバーも取り上げてみましょう。
Ghetto Raga
不気味な緊張感を漂わせていた1曲目から一転して、比較的外へと向いた中世トラッド調のアンサンブルが美しい2曲目。まるでバグパイプのようなオーボエのプレイが印象的で、ケルト/アイリッシュ・フォーク的な神秘性を帯びています。
Egyptian Book Of The Dead
本作中、最も「チェンバー・ロックらしい」と言えるのがこの曲かもしれません。不協和音スレスレの弦楽とアヴァンギャルドに即興し続けるオーボエによる不気味さ極まる演奏から否応なく思い浮かぶのは、UNIVERS ZEROの1stや2nd。彼らから遡る事8年も前にこの場所に達していたとは。
Dragon Lines
グワングワンと旋回するフィドル、これまでになく変化に富んだパーカッション、即興ならではの予想のつかないフレージングを繰り出すオーボエらが溶け合い混ざり合って、強烈なトリップ感覚を引き起こします。69年と言うとシーンはまだサイケデリック・ムーブメントの影響が色濃かった時期ですが、この曲はそれとはまったくの別アプローチによってサイケデリック・ミュージックが目指さんとする地平に立ってしまった感すらあります。
こうして各曲を注意深く聴いていくと気づくのは、決して本作は「チェンバー・ロック・アルバム」ではないということです。しいて言えば、チェンバー・ミュージック的編成によって、アイリッシュ・トラッド、即興音楽、フリージャズ、そしてもしかするとサイケデリック・ミュージックまでを演奏した「実験音楽」。チェンバー・ロックは彼らの恐ろしく広範な音楽性においては、一側面でしかないように感じられます。
とは言え、本作がチェンバー・ロックの原点であることには変わりありません。それは5曲目「Egyptian Book Of The Dead」がそのサウンドをもって如実に物語っているところでしょう。
チェンバー・ロックの源流であると同時に、それだけでは到底片づけられない底知れなさを秘めたまさしく「怪作」という呼び方が相応しい作品です。
【関連記事】
ロック黄金時代回想企画【1969】
コメントをシェアしよう!
あわせて読みたい記事
カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!