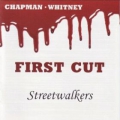プログレッシヴ・ロックの中古CD豊富!プログレ、世界のニッチ&ディープな60s/70sロック専門ネットCDショップ!
13時まで当日発送(土・日・祝は翌日)、6,000円(税抜)以上送料無料
-
カテゴリー
-
プログレ
- 60s/70s/80sプログレすべて
- ブリティッシュ・プログレ
- イタリアン・プログレ
- フレンチ・プログレ
- ジャーマン・プログレ
- 北欧プログレ
- 東欧・露プログレ
- その他ユーロ・プログレ
- 南米プログレ
- 北米プログレ
- ジャパニーズ・プログレ
プログレ新鋭
ロック&ポップス
ハード・ロック
ジャズ・ロック
-
- トップ
- 国内中古CD
- 輸入中古CD
- 新品CD
- 新品LP
- セール
- ベストセラー
- レコメンド
- ジュークボックス
-
ロック探求特集
- ロック潮流図鑑:黄金の60年代特集
- プログレッシヴ・ロック入門特集
- イタリアン・ロック特集
- プログレ新鋭特集「プログレ温故知新」
- アメリカン・ロック特集
- ブリティッシュ・ジャズ・ロック特集
- カンタベリー・ミュージック特集
- ブリティッシュ・ハード・ロック特集
- ブリティッシュ・フォーク特集
- スワンプ・ロック/ルーツ・ロック特集
- アメリカン・フォーキー・ミュージック特集
- アメリカン・ブルース・ロック特集
- サザン・ロック特集
- フュージョン・ロック特集
- 日本のニューロック特集
- サイケデリック・ロック特集
- ブラス・ロック特集
- グラム・ロック特集
- NYパンク・ロック特集
- イスラエル・ロック特集
- イタリアン・カンタウトーレ特集
- Webマガジン
Humanflyさんのレビュー
-
CHAPMAN WHITNEY / FIRST CUT - STREETWALKERS
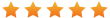
文字通りの意味でミッシングリンク(1 拍手)
告白しますと、私は人生で一回だけ権利関係の怪しげなロシア製のリプロダクション版CDを買ったことがあります。このアルバムのCDがそうでした。ファミリー関連のブツで、これだけが正規でCD化されていなかったもので。
ロジャー・チャップマンとチャーリー・ホイットニーにとっては、ファミリーとストリートウォーカーズの狭間に発表した一枚であり、オリジナルとしてはチャップマン―ホイットニーというデュオ名義による、Streetwalkersというタイトルのアルバムでした。この初CD化に当たるミスティック盤は、タイトルがFirst Cutと替えられ、ジャケットもえらく地味なものに変更されています(がっかりしたという人も多いでしょう)。おかげで、私は音質的にはだいぶ劣るロシア製CDをまだ処分出来ていません。
「ストリートウォーカーズ」というだけだとバンド名なのかアルバム名なのか分かりにくい、というのは多くのファンが思ったことではないでしょうか。ミスティック盤CDのライナーでのチャップマンの発言やDowntown FlyersのBGO版CDライナーでのホイットニーの発言によると、本作発表時にもギグを行ったが、メンバーがまだ固定していなかったということですが(ホイットニーは、デュオとしてではなくバンドとして活動したかった、とも言っています)。
この辺の事情からチャップマン―ホイットニーからバンドとしてのストリートウォーカーズへの連続性は曖昧でありつつ、ゆったりと繋がってもいるということなのでしょうが、ロシア製CDで本作を初めて聴いた時に驚いたのは、これがファミリー最終作であるIt’s Only a MovieからDowntown Flyersに始まるバンド名義としてストリートウォーカーズを名乗ってからの作品群へと、緩やかに音楽性を変化させながら橋渡しを務めているということでした。
色々な要素が独特に複合していて、その音楽的特徴が非常に語りにくいバンドとされがちなファミリーですが、今まであまり語られてこなかった見方として、七作あるファミリーのアルバムは、ある作品とその次作では音楽性が緩やかに変化しつつ、以前の作品との連続性も感じられるのに対し、二作離れると、もう別のバンドのようになっている、という傾向がある、と思っています。一作ごとに、確実に、だが緩やかに変化しており、結果、七作のどれもが他と交換不可能な聞かせどころを持っているし、一作ずつの価値・存在感もかなり対等、という点でファミリーのようなバンドは実はなかなかいない、というのがファンである私の持論です。
ファミリー七作目で最終作であるIt’s Only a Movieは、六作目までと比べると散漫な出来、という声が時折囁かれますし、私はそうは思わないのですが、それでもストリングスやディキシーランド風のホーンが入ったり、フォーク〜カントリー風の要素も混じってきた音楽性がロック的なパンチの強さに欠ける、という印象はあったりします。
それがこのStreetwalkers=First Cutでは、〜Movieでのそうしたアイディアとアレンジが引き続き織り込まれつつ、Downtown Flyers以降の、泥臭いスライドギターとファンク的粘り気を加えたハードロック曲もある、という音楽性がこの時点で芽生えつつあり、まさに“アルバム一作ごとの緩やか且つ確実な音楽性の変化”が確認出来るのです。その意味で、このアルバムがずっとCD化されなかったことはファミリーからストリートウォーカーズへの連続性を見えなくするものであった、と痛感すると同時に、ファミリー名義ではなくなった本作が、逆説的に“一作ごとの音楽性の緩やかな変化”というファミリーの特徴を改めて裏付ける結果になった、とも思っています。
ミスティック盤は曲順も大幅に変更されているので、分かり易く並べて書いておきます。
オリジナル
1) Parisienne High Heels
2) Roxianna
3) Systematic Stealth
4) Call Ya
5) Creature Feature
6) Sue and Betty Jean
7) Showbiz Joe
8) Just Four Men
9) Tokyo Rose
10) Hangman
ミスティック盤再発CD
1) Hangman
2) Roxianna
3) Sue and Betty Jean
4) Call Ya
5) Just Four Men
6) Tokyo Rose
7) Creature Feature
8) Parisienne High Heel
9) Systematic Stealth
10) Showbiz Joe
何といっても、オリジナル一曲目、スライドギターも強烈なイントロで始まるParisienne High Heelが後半に回され、オリジナルでは曲間なしでひと続きだったラスト三曲が、ラストの盛り上がりを担うHangman(それも、よりにもよってアルバムど頭に回される形で)とそれ以外に引き離されている点がかなり気になります。おかげで、私は音質的にはだいぶ劣るロシア製CDをまだ処分出来ていません(しつこい)。
Parisienne High HeelやHangmanのような痛快なロックナンバーもあれば、素朴で真摯なソウルバラードのCall YaやSystematic Stealth、It’s Only a Movieの路線を受け継ぐディキシー風路線のRoxiannaやShowbiz Joe、そのどちらの要素も含まれているSue and Betty Jean、ファンキー路線の萌芽が見られるCreature Featureと、Downtown Flyer以降へ繋がるソウルフルでファンキーな音楽性が徐々に形作られているのが分かります。
ジャケットに話を戻すと、ミスティック盤First Cutでジャケットデザインが変更されたのは、ライナーでのチャップマンの発言によると、「オリジナルのアートワークはDoll’s Houseから逃げ出していくような感じが後ろ向きな感じがして好きになれなかった」からだそうですが、ディスクユニオンから出ていたミスティック盤の国内盤は(深民さんの尽力だと思いますが)オリジナルのジャケットを再現したものでお見事。
そして、ここに来て、五十周年記念のエクスパンデッドエディションが出ることになり、ようやくオリジナルのアートワーク&曲順でのCD化が全世界で叶うこととなる2024年夏、というところなのであります。
五十年目の快挙というか、今まで再発の機会に恵まれてこなかったこんな作品にも五十周年記念エクスパンデッド規格という陽が当たるような昨今というか、ようやくこれで私もロシア製リプロ盤を処分出来るというか…… -
JACKIE LEVEN(JOHN ST.FIELD) / CONTROL
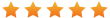
唯一無二の味(1 拍手)
『英国ロックの深い森』によると、”本作は'71年に録音されながら発表は'75年になってから、しかもスペインのレーベルから”という何らかの事情があったらしいことをうかがわせつつ、”その頃レヴンはロンドンのローカルシーンでR&Bテイストのバンドを率いていたらしい”とも付け加えています。
'70年代後半のレヴンは、ややニューウェイヴ寄りのパブロックであるドール・バイ・ドールに歩を進めるので、以上の字面だけ見ると音楽性の変化が屈折しているように感じられるかもしれませんが、この'71年録音のデビュー作の時点でそれなりにR&Bっぽさが出ていたように思います。
タメを効かせてコーラスが入ってくる楽曲が多く、また、そういう手法としてはR&Bなことをしてもゴスペルやドゥーワップっぽくならない、つまり黒っぽくならないところは特異な個性といえると思います。
英国のアーティストで、フォークとR&B/ソウルに跨る個性というと、ミラー・アンダースンやゲイリー・ファー、アーニー・グレアム、より黒っぽいところでフランキー・ミラーのような人を思い浮かべますが、ジャッキー・レヴンはというと、あまりソウル的なエッジやざらつきは感じさせず、ひたすら滑らかなのが特徴。米国黒人っぽさと非常に微妙な距離があるのが面白いです。
一方で英国フォーキーとして見ると、そこまでアコースティックでなく、モーグシンセが出てきたりして(マンやピート・ブラウンとのコラボで知られるフィル・ライアンが弾いています)既にニューウェイヴに繋がるような色も見えますし、R&B的にシャウトするのでトラッドっぽさもあまりなく、アシッドフォーク扱いされることが多いものの、声の滑らかさ故にどろどろはしない、というこれまた所謂英国フォークとも距離がある、という非常に分類が難しい音楽です。
是非一度ご賞味ください。 -
ヴィネガー・ジョー / ヴィネガー・ジョー
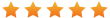
英国スワンプの極み(1 拍手)
ヴィネガー・ジョーのアルバム三作の中で、一番人気があるのはどれなんでしょうか?私はこれを推します。彼らが目指したゴスペルっぽさが一番良く出ていると思います。
ロバート・パーマーはまだ魅力全開といきませんが、というか、VG時代はエルキー・ブルックスの方が圧倒的に目立っていて、彼女が主役といっても過言ではないでしょう。Early Monday Morningの力強さ、See the Worldの解放感、Live a Little, Get Somewhereの詩情、どれもとても良いです。
パーマーに関しては、Circlesのような洗練方向での歌唱・楽曲に個性が発揮されています。レアグルーヴ寄りというか、アコースティックでフォーキーな方向性で、ソロになってからの洗練され具合とはまた毛色が違うのが面白いです。キーフ・ハートリーのアルバムでジェス・ローデンが歌ったヴァージョンと聴き比べも一興かと。Getting’ Outになると、かなりソロになってからの路線を思い起こさせる曲であり、歌唱です。
あと、Never Met a Dayが最高に良いです。ストーンズっぽい曲をやろうとしたバンド・曲はいくらもあるでしょうが、それと同時にストーンズも目指した黒っぽさ、南部っぽさも達成した上で成功した曲となるとこれの他にはハンブル・パイくらいしか思いつきません。
まるでキースな冒頭のリフ、ストーンズフォロワーの曲/バンドには意外にないビル・ワイマン心を理解したスティーヴ・ヨークのベース(ストーンズと違って、ベースの音量がめちゃ大きいところは正反対ですが)、ミック・テイラー寄りのトーンでロン・ウッド寄りのフレーズを弾いているスライドギター、思いっきり『ブラウン・シュガー』風のサックスソロ、とストーンズフォローの曲としては満点をあげていい出来だと思います。
しかしアルバム全体としては、ゴスペル・ソウル的なものとアコースティックな部分でのカントリー的なものが同居していて、そういう南部音楽の気持ちの掴み方という点こそがストーンズと共通するとこで、大事なのは、ストーンズの物まね的楽曲の出来がいいというのではなく、アメリカ南部的な音を求めた結果、ストーンズ風の曲も一曲混ざった、ということだと思います。 -
ザ・バンド / アイランド
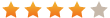
人生は幻(2 拍手)
……ロビー・ロバートスン追悼のために引っ張り出して聴いたのがこれ、という辺りが筆者の性格の悪さを物語っていますが。
長年、「契約証化のために急ごしらえされた中身のない一枚」的な扱いをされている本作を、判官贔屓ではないですが、昔から妙に好きだったので、この機会に聴き直してみました。
でどうだったかというと、いや、あんまり良くないよ、四十年以上前から諸先輩方が言われてきた通り中身薄いわ、やっぱ、という結論に達すると同時に、じゃあ、何故自分はこのアルバムが妙に好きだったのかも分かったのでした。
一曲目Right As Rainの分かり易すぎる曲調(メジャーセヴンスを使っている時点でザ・バンドじゃないと言われたそうですが)に、甘口のシンセとサックス、これだけでもう土臭く奥深いザ・バンドではないことが分かりますが、こういったサウンド上の特徴は既に前作Northern Lights - Southern Crossで顕著になっていたので、やはり急ごしらえの曲ということに原因があるのでしょう(一方で、ゼロ年代に入った辺りから、後期ザ・バンドの最高傑作とされてきたNL - SCは少しずつ評価が下がって来た感があると思うのですが、それはそちらが本作の地位に近づいてきたということでもあると思う)。
では、このアルバムのどこが好きだったかというと、常にザ・バンドを目標にしてきたが、あのオーガニックで自然体な土臭さ、先鋭的で深遠なのに常に柔らかさを失わないドラマ性には到底到達出来ない英国パブロックと同じ地平で聴けるザ・バンドのアルバムだったから、ということに今回気が付きました。
曲調はザ・バンド節ですが、歌詞はSFないしファンタジーしちゃうSaga of Pepote Rougeなんか、プログレでもあります。
小尾隆氏が、再結成ザ・バンドのことを「ザ・バンドがパブロックと同じ市井の目線まで降りてきた」と書かれていましたが、ロビー抜きの再結成後より、ロビー入りでこれ、な本作には、やはり妙な愛着を感じます。
……と書いてみたものの、Georgia on My Mindで泣かされ、最初から二曲目のTo Kingdom Come以来歌わないで来たロビーが、最後からの二曲目になって歌ったKnockin' Lost John、シメのLivin' in a Dreamというラスト3曲は心に染みるものがありますし、ロビー亡き今、この三曲の意味合いが自分の中で答え合わせのように響いています。
リチャードも、リックも、レヴォンも、彼らとは袂を分かったロビーも、いずれも彼らを見送るのに相応しい曲は、I Shall Be releasedでもThe WaitでもAcadian DriftwoodでもThe Last Waltz Themeでも、増してや増してや増してや絶対にロビーのソロに入っていたFallen Angelなどではなく、Livin' in a Dream、というのが筆者の辿り着いた答えです。 -
BOB DYLAN / STREET LEGAL
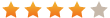
素朴な質問:アレンジャーって何する人?(2 拍手)
偏見と決めつけ込みの物言いですが、ディランの作品の中で最も「音楽的」な作品でしょう(音楽を捕まえて「音楽的」ということがそもそも偏見と決めつけに溢れた物言いでありますが)。
サックスやパーカッション、女性コーラスを加えた華やかなサウンドは、従来のぶっきらぼうなサウンドと歌唱の一本鎗でアルバムを仕上げてきたディランとは一線を画しており、一方でコーラスを用いた分厚いサウンドは自作以降のゴスペル路線への伏線……と言われることもありますが、こうした素直で分かり易いメロディの曲は受け継がれていません。
従来からすれば異例の分厚い編成のフルバンドを率いての(初来日を含む)ツアー、そのツアーメンバーを動員してスタジオ作を一枚作った訳ですが、旧作もフルバンド用に華やかなアレンジを施したあのツアーの音が、そのままここでは新曲を彩っており、ツアーでの音がそのままアルバムでの音に反映された意外と少ない(実は同じことがストーンズにもクラプトンにも何よりB・B・キングにも言えるんですが)ディランのアルバムになっているところがポイントです。
ツアーの音を刻み込んだアルバムが欲しかった、あるいはアルバムの音をそのままツアーで再現したかった、と言えば話は簡単なのですが、それでも”じゃ、なんでこんな音になったのか”という疑問は残ります。
これ以前のローリング・サンダー・レヴューでも、ディランは大所帯フルバンドでのツアーを試みましたが、そこでの荒削りな演奏と歌唱(これはこれで大変魅力的)は明らかに従来のディランのそれの延長線上です。それに比べると、こちらのサウンドは明らかにアレンジされプロデュースされた音です。一曲目Changing of the Guardがフェイドインで始まる、という時点で、他のディランのアルバムとは異なる作為を感じさせます。
つまり、「作為」と「音楽的」は同じものの言いかえであり、この辺りがファンの間でも評価が一定してこなかった原因なんでしょう。個人的にここでの「音楽的」なディランにもとても魅力を感じますが、一方で、荒削りなディランこそ本道、という思いも強くありますし、何より”なんでこんな音になったのか”という疑問が立ちはだかります。大編成のバンド用のアレンジを、ディランが譜面に書いて指示した、などということは考えにくく(この辺、キャリアの似ているヴァン・モリソンは、毎回ではないけど音楽監督的なメンバーを抱えている)、この時期以前も以後もこうした大規模で多彩で整理の行き届いたサウンドのディランは聴けないことを考えると、このアルバムだけ”なんでこんな音になったのか”に加え、”誰がこんな音にしたのか”という疑問も持ち上がります。
例えば、中山康樹氏がこのアルバムを妙に高評価していたのは、そういう部分にひっかっ狩りを感じたからなんでしょうが、同じく引っかかりを感じる者として、別の方向の引っかかり・疑問のために私はこの結構好きなアルバムを無条件に評価出来ないでいます。
なんかこのアルバムのレビューでなくなってしまいますが、この問題は'60年代後半から'70年代までのロックのアルバムのどれだけが、アレンジによって「ロック」として成立しているのか、という問題とも重なってきます。スタジオレコーディングに於ける作業という面とも重なるでしょうが、一応は既に書きあがった楽曲をアレンジの段階でどう完成させるか、という最終過程で、バンド/アーティストのキャラクターに合った、その楽曲のキャラクターが決定される、と考えると、ハードロックもプログレもフォークロックも要はアレンジの問題、ということが見えてくると思います。
(マルチトラック上での切り貼りや即興演奏という部分を除けば)骨組みとして出来上がっている楽曲にアレンジによりキャラクター/フレーヴァーを与える、という見方からして、私は本作を「ボブ・ディランのプログレアルバム」と勝手に認定しております。お後がよろしいようで…… -
JOHN MAYALL / BACK TO THE ROOTS
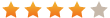
豪華ゲストということが話題になりますが(1 拍手)
最近よく聴いている盤なので、ちょっとレビューさせてもらいます。
クラプトン、ミック・テイラー、ハーヴィー・マンデル、ジェリー・マギー(ちょっとだけだけど)といったギタープレイヤー勢が曲によって入れ代わり立ち代わり弾いていることが有名なアルバムですが、実は一番美味しいフレーズを弾いているのはドン・シュガーケイン・ハリスのヴァイオリンです。味が濃いです。
曲によってメンバーや楽器の組み合わせが異なるのですが、ギター、ハリスのヴァイオリン、メイオールのオルガンかハーモニカが主導権を取り合うように絡み合うところは、ブルース一辺倒とは異なる情報量が感じられ、なかなか良いです。どちらかと言えば、色々試行錯誤してメンバーの組み合わせを決めたのではなく、その場の成り行きでこの組み合わせになった部分の方が大きいように感じますが、こうした行き方も、スタープレイヤーのソロに比重が傾きがちだった'60年代のブルースブレイカーズとは違うことをしたい、というメイオールの意気込みを感じます。
'80年代にリズムセクションを差し替えたリミックスヴァージョンもボーナストラックとして追加されていますが、整理が行き届いたそちらの音では、上記のような雑然としたニュアンスがほぼ消し飛んでしまっているので、是非聞き比べてみてください。
楽曲としては、「ジミ・ヘンドリックスについて言っておきたいことが二、三ある」と歌い出すアンチドラッグソングAccidental Suicideの出だしにドキッとします。 -
MICHAEL CHAPMAN / NAVIGATION
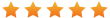
一時期は結構入手困難だった一枚(2 拍手)
'80-90年代のチャップマンは、レコード契約を取れなかったのかアルバムの間隔が空きがちで、散発的に出たアルバムの中でも、これは前後のそれと比べて格段に入手が難しかった記憶があります。なので、ネット上のショップやオークションで見かけると、ついお薦めしたくなってしまいます。
チャップマンのだみ声の歌唱は、明らかにボブ・ディランの影響下にある/あったのでしょうが、この人のミュージシャンとしての資質はポール・サイモンに近いと思います。フォークからスタートし、音響系へと歩を進めていくという点が共通しています。ロックにもフォークにも縁の薄いニューエイジめいたアルバムも出しているところに、そういう要素を感じますが、この一作前"Still Making Rain"でRoad To Senegalというアフリカを向こうに置いた曲なんかがあると、サイモンとの共通点や相違点も何となく見えてきます。
このアルバムでは、静かにギターをつま弾くThe Mallardが、Road to Senegalからアフリカ色を取り除いたような曲……というか、アレンジを剥ぎ取って本来の曲の骨格に戻したような印象を受けます。It Ain't Soも、ある種のファンキーさが魅力的です。
The North Will Riseは、アメリカ南部白人の常套句のパロディのようなタイトルですが、変拍子ではないものの聴いていて癖になる変則リズムで叩くドラムが印象に残ります。 -
MICHAEL CHAPMAN / FULLY QUALIFIED SURVIVOR
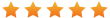
このほの暗さが英国(1 拍手)
チャップマンが昨年亡くなっていたことを、かなり後になって知り、ショックを受けました。日本ではあまりいないファンの一人を勝手に自任していたのに、リアルタイムで気づかなかったなんて。
元から知名度が低いだけの話なのか、とっつきにくいからなのか、日本での人気・認知の低さは話にならないものがあるチャップマンですが、相当にアルバム数がある中で、初期四作くらいはどれも英国フォークに関心がある人は聴いて損がない名盤ばかりです。
また、初期数作は本人とは別に、リードギターを置いているのが特徴ですが、この二作目は、二曲ほどしかリードギタリスト(クレム・クレムスン)が参加していなかった一作目と異なり、よりリードギターが前に出て、チャップマンの押し寄せる波のようなアコギと丁々発止を演じています。Stranger in the Roomで冒頭から響くリードギターはミック・ロンスン。曲によってはストリングも加わり、この二者、三者のせめぎ合いが、あまり他のフォークロックにはない聴きどころの一つになっています。
エレキのリードギターが目立つ曲では、Soulful Ladyも名曲ですが、英国フォークだというのにある種のファンク要素もあり、タイトル負けしていません。アルバムタイトルは、この曲の歌詞の一節から取られていますが、意味が取りにくいこの言葉は、「(その証言が)十分に信頼出来る生存者」ということのようです。
アルバムジャケットは、波に翻弄される小舟の果ての島の向こうからギターを手にしたチャップマンが浮かんでいるというアートですが、裏ジャケ・内ジャケは波間にチャップマンのでっかい顔がコラージュされていて、船をひっくり返しそうになっています。よって筆者は「海坊主」アルバムと呼んでいますが、難破した船の生存者は何を語ったのでしょうか。 -
SOFT MACHINE / NOISETTE
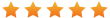
もしこれからソフトを聴く方がいれば(1 拍手)
これを含め、今はサード期だけでも本当にたくさんの発掘ライヴ盤が出ているんですね。
その全部を聴いている訳ではないのにこんなことを書くのもナンなんですが。
これからソフト・マシーンを聴くという方がいらっしゃったら、セカンドとサードの間でこれ、という順番で聴くことをお薦めします。松井巧氏だったかな? 「思いのほかセカンドとサードが緩やかに繋がっていることが確認出来る」というようなことを書かれていたと思いますが、セカンドB面の世界観がライヴで聴け、且つそれがサードの緊張感を既に達成していることに驚きます。
もちろんサードのSlightly All the Timeの音源がここから取られているから当然のことなんですが、一方で、ライヴならではの音の強度と説得力はきちんとスタジオで構成されたサードとは異なる顔も見せている、といった感じです。
個人的には(音の強度とか言った割りには、抒情性に寄り過ぎた聴き方だと思いますが)冒頭二曲の激しい応酬がふっと途切れ、Backwardsのテーマが出てきた時の浮遊感が何にも替え難く好きです。
ハンブル・パイのキングビスケットアワー盤辺りと並ぶ、「実質的にレギュラー盤と同格の価値/必聴度を持つ発掘ライヴ盤」だと思います。